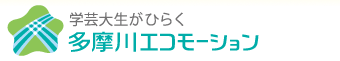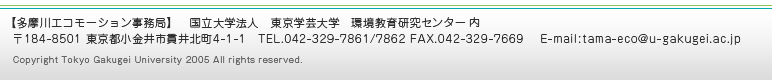|
多摩川バイオリージョンにおける
エコミュージアムの展開を考える |
「多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開を考える」をテーマに、エコミュージアムを研究されている2名の講師による講演会が行われました。
講演「海外のエコミュージアムの事例から考える」においては、エコミュージアムの語源と、現状、そこでの地域住民のあり方の解説がされました。また、海外のエコミュージアムの事例の紹介と、エコミュージアムの機能としての地域の一体感の創造が提示されました。
講演「日本のエコミュージアムの事例と展開課題」においては、日本のエコミュージアムのあり方について、環境と経済の好循環を生み出すサテライトによる地域づくりが提言されました。
パネルディスカッション「多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開」では、本講演会を振り返りつつ、参加者からエコミュージアムに関する様々な質疑応答がされました。
本講演会を通じて、多摩川バイオリージョンを展開してゆく際に参考となる話題が提供され、参加者からは課題を含めエコミュージアムのあり方についての意見を聞くことができました。
【予告ページ】
講演記録
 講演「海外のエコミュージアムの事例から考える」(pdf:3593.0KB) 講演「海外のエコミュージアムの事例から考える」(pdf:3593.0KB)
 講演「日本のエコミュージアムの事例と展開課題」(pdf:3226.6KB) 講演「日本のエコミュージアムの事例と展開課題」(pdf:3226.6KB)
 パネルディスカッション「多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開」(pdf:7642.5KB) パネルディスカッション「多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開」(pdf:7642.5KB)
| 日時 |
2006年1月14日(土) 13:00〜19:00 (18:00〜 交流会) |
| 会場 |
講演会:東京学芸大学 北講義棟(N棟) 4階410教室
交流会:大学構内 環境教育実践施設 多目的教室
[アクセスマップ] |
| 参加者 |
62名(一般 52名、学生 10名) |
| プログラム |
■13:00〜
講演「海外のエコミュージアムの事例から考える」
講師: 大原 一興 (おおはら かずおき)
(横浜国立大学大学院 工学研究院 システムの創生部門 教授)
■14:30〜
講演「日本のエコミュージアムの事例と展開課題」
講師: 井原 満明 (いはら みつあき)
(株式会社 地域計画研究所 代表取締役)
■16:00〜
パネルディスカッション
「多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開」
コーディネーター: 原子 栄一郎
(東京学芸大学 環境教育実践施設 助教授)
パネリスト: 大原 一興 ・ 井原 満明
■18:00〜19:00
ネットワーク交流会
会場:学芸大 環境教育実践施設 多目的教室
|
| 参加者の感想 |
・エコミュージアムとは何かを理解することができた。海外ではこのシステムはとても進んでいると理解したが、西欧と日本のバックグラウンド、国民性の違いだと思った。
・「地域資源」を基本に置くエコミュージアムの理解の仕方は良かった。
・持続・発展させるための自主・自立の重要さ、主体の問題が実に重要という事がよく認識できた。
・地域社会と連携する環境をテーマとした「場づくり」を学芸大の中につくって貰いたい。地域の中に住む働く人々が立場をこえて話し合える「場づくり」を小金井で創設し、実践・学習と同時に地域の人々の活力を活用して貰いたい。
|
|