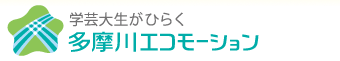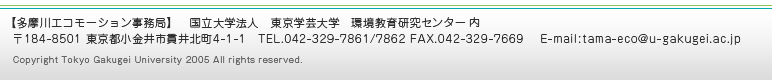|
エコミュージアム日本村
「植物と人々の博物館」づくりを目指して
|
「エコミュージアム日本村〜植物と人々の博物館づくりを目指して〜」をテーマに、本学教員及び地域の方々による多様な活動実践の報告及び今後の連携に向けた活発な話し合いの場が持たれました。
調査研究報告では、雑穀や野生動物に関する貴重な研究報告がなされました。特別講義では、来日中のインド研究者によりアッサム地方の生態系及びその住民による伝統的な保全の取組が紹介されました。
事例報告1「エコミュージアム日本村構想」では、本学の木俣美樹男教授より、小菅村を拠点に日本の山村に伝承されてきた伝統的知識体系を学習し、環境保全・創造する活動を通じて、持続可能な地域社会を形成する事業の構想が紹介されました。また、この事業を通じて秩父多摩甲斐国立公園内での山村振興モデルを提案してゆくことが示されました。
事例報告2「東京の森林林業と農山村」では、木こりという職業の視点から、東京の森林の歴史と現状や、森林を活用した取組について、また、次世代へ技を伝承してゆくことの重要性について語られました。
事例報告3「小金井市における江戸野菜の復活」では、郊外のベッドタウンとして人口が増加してきた小金井市の現状を変えるきっかけとして、現在取り組まれている江戸野菜の復活の試みが紹介されました。
事例報告4「小菅村における農山村エコセラピー」では、「癒し」をキーワードとして、森林や温泉など、山梨県小菅村の自然資源を活かした取り組みについて紹介されました。
最後に参加者は4つのグループに分かれ、「エコミュージアム日本村」づくりをテーマに、今後の上流域の連携と都市農村交流の可能性、及びその方策について話し合い、その結果を模造紙にまとめました。その後は、村内で開催されていた「大地の恵祭」に参加し、郷土料理に舌鼓を打ちつつ、住民との交流を行いました。
【予告ページ】
講演記録
 講演「エコミュージアム日本村構想」(pdf:1.45MB) 講演「エコミュージアム日本村構想」(pdf:1.45MB)
 報告1「東京の森林林業と農山村」(pdf:1.28MB) 報告1「東京の森林林業と農山村」(pdf:1.28MB)
 報告2「小金井市における江戸野菜の復活」(pdf:1.25MB) 報告2「小金井市における江戸野菜の復活」(pdf:1.25MB)
 報告3「小菅村における農山村エコセラピー」(pdf1.47MB) 報告3「小菅村における農山村エコセラピー」(pdf1.47MB)
| 日時 |
2006年10月21日(土) 13:00〜17:00
22日(日) 9:00〜15:00 (1泊2日) |
| 会場 |
山梨県北都留郡小菅村 〔アクセスマップ〕
小菅村中央公民館、植物と人々の博物館ほか |
| 参加者 |
46名(一般 29名、学生 15名、大学職員 2名) |
| プログラム |
10月21日(土)
■13:00〜16:00
調査研究報告「多摩川上流・鶴川流域の生物文化多様性保全」
1)「雑穀類の遺伝侵食と生物文化多様性の現地保全」
講師:木俣 美樹男 (東京学芸大学) ・ 石川 裕子 (京都大学)
2)「野生動物と伝統食文化の関わり」
講師:井村 礼恵 (東京学芸大学) ・井上 典昭 (大月短大附属高校)
3)雑穀の地域社会史
講師:増田 昭子 (立教大学)
■16:00〜17:00
特別講義
1)「アッサム農山村の生物文化多様性」
講師:S.パンダ(カルカッタ大学)
2)香とキリスト教信仰〜芳香性植物のかたち
講師:大澤 由美 (ケント大学)
10月22日(日)
■9:00〜11:00
事例報告
1)エコミュージアム日本村構想
講師:木俣 美樹男 (東京学芸大学)
2)東京の森林林業と農山村
講師:小机 篤 (東京都林業家)
3)小金井市における江戸野菜の復活
講師:土井 利彦 (NPO法人ミュゼドアグリ)
4)小菅村における農山村エコセラピー
講師:中田 無双 (エコセラピー研究会)
■11:00〜13:30
分科会および昼食
■13:30〜15:00
全体会
|
| 参加者の感想 |
・ 鉄砲ぶちの話が、小菅村の方と自然との関わりを知るきっかけとなり面白かったし勉強になりました。
・ 植物がなければ生物、私たち人間は生きられない。この認識なくして今後の人類は成立しない。このプロジェクトの重要性を少なくとも日本人には理解してほしい。
・ 地元・学問・学生・一般が一堂に会して肩を並べて話し合えることがすばらしい。特に土と汗にまみれる生業のすばらしさがあり、地元の人といっしょに創り上げていく所の意義が大きい。
・ 小菅の人と長時間討論できたのは有意義だった。たくさんの小菅の人が参加してくれたことに感謝します。
|
|