�P.�͂��߂�
�����ʂƂ��������ʂ́A���Ƃ��Ă��镨�����\�����Ă���v�f���q(elementary entities)�̐��ɔ�Ⴗ��(���̗v�f���q�́A�K�����w����p���ē��肵�Ă���)�B���̔��萔�́A�A�{�K�h���萔�mA(6.022�~1023mol�|1)�̋t���ł���B���̃A�{�K�h���萔�m�`�������ɂ�苁�߂�B
�A�{�K�h���萔�����߂���@�͂��������邪�A����́A�����߂��Ă���A�{�K�h���萔�����߂��Ƃ��Ɠ������@�ł���A���x���i�q�萔���狁�߂���@�ōs���B
���x���́A����(�l)��̐�(�u)�ŏ�������܂�B
�ρ��l�^�u
�����ŁA�P�������ɂ��čl����ƁA�P����������̑̐ς��u���Ƃ���ƁA
�ρ��l�^�u���@(�l�͕����l��p����)
1����������̑̐ς́A���q1����߂�̐�(��)�ƃA�{�K�h���萔(�m�`)�Ƃ̐ςł���킹��̂ŁA
�ρ��l�^�ҥ�m�`
���������āA�A�{�K�h���萔�m�`�͈ȉ��̂悤�ɕ\����B
NA���lm�^�ϥ��
���q1����߂�̐σ҂́A�i�q�萔�����狁�܂�B
����āA���x�ρA�i�q�萔�������߂�A�{�K�h���萔�����߂邱�Ƃ��ł���B
���x�̋��ߕ��͂��������邪(�e�����ׂĂ݂Ă�������)�����ͤ�A���L���f�X�@�ōs���B
�i�q�萔�����痧�����̏ꍇ��҂͂�3�^��(���͒P�ʊi�q�Ɋ܂܂�闱�q��)�ŕ\����B
�� SI��{�P�ʂ̒�`�F0.012kg�̒Y�f�|12�Ɋ܂܂��Y�f���q�Ɠ����̒P�ʗ��q���܂ތn�̕����̗ʂ�1�����Ƃ���B
�������܂łɈȉ��̎������w�K���Ă����ĉ������B
�E Bragg�̎��E�i�q�萔�EMiller�w���E�\�����q�E�w���Â�(�A�g�L���X�������w �Q��)
�E ��d�r�̎g����
2�D�������@
�T.���x�����߂�
�@ �P�������Q�T���ɒ�������B
�A ��d�r�ɏ����������A�����ƕʁX�ɍP�����ɐZ���B
�B �P�T����Ɏ��o���A���������Ă����d�r�ɂ������������ӂ����A���ʂ���B(��W1[g])
�C ��d�r�̒��̐����̂āA�����ɖ߂��B
�D �A���~�j�E���̏d���𑪒肷��B(��W2[g])
�E �D�̃A���~�j�E�����C�̔�d�r�ɓ���A�A�A�B�̑�����s���B
�@�@�@�@(��W3[g])
�F �����̌��ʂ����ƂɁA���x�����߂�B
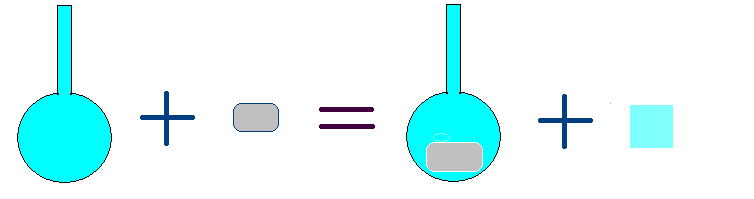
�@�@�@�@�@
�@�@�v1/g �@�@�@�@ �v2/�� �@�@�@�@�v3/�� �@�@�@�@ �@ �H
����ăA���~�j�E���̖��x��Al�́A25���ł̐��̖��x�ςv��p���Ĉȉ��̂悤�ɕ\����B
���x��Al���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��W���@�@�@�@�@�@�@�@�@g/cm3
�ȏ�̑����3��ȏ�J��Ԃ��A���ϒl�����߁A�A���~�j�E���̖��x�Ƃ���B
�� �M����Ԃɂ���
99���M�����(����l�̊m����)
�@����l���ǂꂾ���M������ɒl������̂��������B
�\���}���l(�Ӄ�){��(�\���|����)2/��(���|1)}1/2�@�E�E�E�@
���F�L�Ӑ����@�ӁF���R�x(���]1)�@�E�E�E�@�ʎ��Q��
���ϒl�\����������/���@����1�C2�C�E�E�E
�` �a �b �c
�P 1��� 2��� 3���
�Q �v1/g
�R �v�Q/g
�S �v�R/g
�T
�U ���x��
�� ���ϒl�\���̋��ߕ�+
�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���
�@�@�@�@�@�@��AVERAGE(�a6�F�c6)
�@�@ �c"E2����E4�̒l�̕��ϒl�����߂�"�Ƃ�������
�����̕����a ��(�\���|����)2 �̋��ߕ�
�@�@�@�@�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���
�@�@�@�@�@�@��DEVSQ(�a6�F�c6)�@���`
�c"E2����E4�̒l�̕��̕����a�����߂�"�Ƃ�������
�� �@���̔g�����̋��ߕ�
�@�@�@�@�@�Z���Ɉȉ��̂悤�ɓ��͂���
�@�@�@�@�@�@��SQRT(A�^(��(���|�P)))�@�@
�@�@�@�c"(�@)�Ƀ��[�g��������"�Ƃ�������
���x�̕��ϒl�@�@�@�@�@�� cm�]3
�X�X���M����ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@