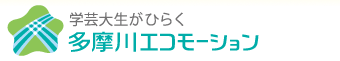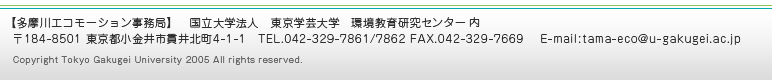|
多摩川エコミュージアム交流フォーラム
〜自然・文化、そして人をつなぎ、持続可能なコミュニティー〜 |
「多摩川エコミュージアム交流フォーラム〜自然・文化、そして人をつなぎ、持続可能なコミュニティー〜」をテーマに、5名の講師による講演が行われました。
基調講演「エコミュージアムによる持続可能な地域社会づくり」では、エコミュージアムを展開して行く際に要となる「記憶の継承」と「対話の場づくり」について、博物館とまちづくりをつなぐ「地域学」の方法論や地域で積み重ねられてきた経験などを基に提言されました。
その後、4名の講師による地域のエコミュージアムの活動報告がありました。
報告1「多摩川源流のむらづくり」では、多摩源流の山梨県小菅村におけるむらづくりについて、村の現状と課題、またそれを乗り越えてゆくための様々な取り組みについて報告されました。
報告2「多摩NT (ニュータウン) ・オアシスの新たな公園管理スタイル」では、八王子市の長池公園におけるNPOが主体となる公園管理の特徴やボランティアの活動について報告されました。
報告3「みどりのカラーマップと田んぼの時間」では、小金井市環境市民会議が、今後の市の環境施策に反映してゆくことを目標に作成した小金井市の緑地マップの紹介と、市民でも特に主婦・母親という視点から、田んぼでの子ども達との米作りの取組みについて紹介されました。
報告4「環境学習と流域ネットワーク」では、川崎市の「等々力水辺の楽校」の例から、地域の団体、行政、企業の連携についてのあり方が提言されました。
プログラムの最後には「おしゃべりワークショップ」が行われ、報告者と参加者のより緊密な交流の機会を持つことができました。
【予告ページ】
講演記録
 基調講演「エコミュージアムによる持続可能な地域社会づくり」 (pdf:1.29MB) 基調講演「エコミュージアムによる持続可能な地域社会づくり」 (pdf:1.29MB)
 報告1「多摩川源流のむらづくり」(pdf:1.28MB) 報告1「多摩川源流のむらづくり」(pdf:1.28MB)
 報告2「多摩ニュータウン・オアシスの新たな公園管理スタイル」(pdf:1.30MB) 報告2「多摩ニュータウン・オアシスの新たな公園管理スタイル」(pdf:1.30MB)
 報告3「みどりのカラーマップと田んぼの時間」(pdf:1.32MB) 報告3「みどりのカラーマップと田んぼの時間」(pdf:1.32MB)
 報告4「環境学習と流域ネットワーク」(pdf:1.31MB) 報告4「環境学習と流域ネットワーク」(pdf:1.31MB)
 多摩川エコミュージアム交流フォーラムワークショップの内容報告(pdf:1.28MB) 多摩川エコミュージアム交流フォーラムワークショップの内容報告(pdf:1.28MB)
| 日時 |
2006年6月28日(水) 13:00〜17:40 (18:00〜交流会) |
| 会場 |
東京学芸大学 環境教育実践施設 1F 多目的教室
[アクセスマップ] |
| 参加者 |
38名 (一般 24名、学生 12名、教職員 2名) |
| プログラム |
第1部
■13:00〜
挨拶/プロジェクト紹介
(“多摩川バイオリージョンにおけるエコミュージアムの展開”について)
■13:20〜
基調講演:「エコミュージアムによる持続可能な地域社会づくり」
講師:嵯峨 創平 (NPO法人「環境文化のための対話研究所」(IDEC) 代表)
■14:00〜
地域のエコミュージアム活動報告(各30分)
1 「多摩川源流のむらづくり」
講師:青柳 諭 (山梨県小菅村 源流振興課長)
2 「多摩NT(ニュータウン)・オアシスの新たな公園管理スタイル」
講師:内野 秀重 (八王子市 長池公園自然観 副館長)
3 「みどりのカラーマップと田んぼの時間」
講師:平井 正風・早崎 眞佐子 (小金井市環境市民会議)
4 「環境学習と流域ネットワーク」
講師: 鈴木 眞智子 (NPO法人 多摩川エコミュージアム 事務局長)
■16:00〜
おしゃべりワークショップ
*4つの報告事例ごとにグループに分かれ、報告者と参加者の間で質疑応答・ディスカッション
■17:00〜
ワークショップの内容報告&全体のまとめ
■17:40 フォーラム終了
第2部
■18:00〜20:00
ネットワーキング交流会
|
| 参加者の感想 |
・とてもおもしろかった。地域のつながりの大切さを感じた。
・実生活を伴った報告は危機感があり楽しめました。
・実際に主体的に活動している話を聞くことができてよかった。
・プレゼンテーションも良かったが、ワークショップで色々自由に話せたことは、とても良い企画だった。大学で流域について等を習ったので興味深かった。
|
|