
令和4年4月より、第17代校長をしております小森 伸一(こもりしんいち)と申します。大学では健康スポーツ科学講座に所属し、野外環境教育/野外教育、持続可能な社会にむけた教育、ホリスティック教育、体験を基盤とする学びと成長の重要性などについて研究しています。どうぞよろしくお願いいたします。
本校は1911年の開校以来、日本の初等教育研究を牽引してきた伝統ある附属小学校です。「①教育実習校」「②教育研究の実験・実証」「③『生きる力』『非認知能力』を育む大自然の中での宿泊生活体験」という3つの特色を持ちます。
1つ目の特色として、本校は「教育実習校」であることです。東京学芸大学は教員養成を主たる目的とした日本の基幹大学であることから、とくに大学構内に所在する本校は、未来の先生を育成する教育実習の場ならびにその研究を推進するという大切な役割を持ちます。例年9~10月と2月に、大学3・4年生が各学級に数名ずつ配属され、総勢170名もが実習を行います。普段の先生とは違う若いお姉さん・お兄さん先生たちとのふれ合いを通して、子供たちが人との関わりにおける気づきや学びを広げ深めていく良い機会にもなっています。
2つ目の特色にある「教育研究の実験・実証」では、本校は教科教育研究を大切にして授業研究に取り組んでいます。授業場面で一人一人の子供がもつ認識や考えといった個を大切にしつつ、他者との出会い・対話・協働を通した学びを推進しています。また、日頃からの教育研究の成果を披露する場として、2月に開催される研究会があります。日本全国から初等教育に携わる多くの方々に、本校の研究成果を参観していただいています。
3つ目の特色である「『生きる力』『非認知能力』を育む大自然の中での宿泊生活体験」は、第3〜6学年において行われる豊かな自然環境の中での長期の宿泊体験活動となります。山間で行われる野外活動が中心となる一宇荘生活(林間学校/長野県茅野市)、大海原での遠泳活動をする至楽荘生活(臨海学校/千葉県鵜原)について、3年生から始まり卒業するまでにトータル21泊27日の活動を行います。この2つの荘生活での宿泊体験活動は、戦前から今日まで継承されてきた約80年という長い歴史があり、本校における伝統的活動となります。
この山と海の大自然を体感しながら、主体的かつ仲間との協働生活をする多様な体験を通して、“自然・仲間・自己”への感性や理解を促進し、知・徳・体・情の全人的な力、すなわち「生きる力」を醸成します。また、本校において実践されるような自然の中での豊かな体験活動は、生涯にわたって充実した人生を形成するうえで必要とされる「非認知能力」を育むためにも重要なことが実証されています。
本校は、上掲3つの特色を伝統的に受け継ぎつつ取り組んで参りました。一方で、社会背景や情勢を鑑みつつ、つねに新しいことにも挑戦しています。その1つとして、積極的にICT(情報通信技術)を活用した授業・学校運営・研究に取り組んでいます。生成AIも含め、ICTを使った効果的な授業方法や、授業のみならず事務業務における効率化にも積極的に着手しています。職員会議はコロナ禍以降も全てMicrosoft Teamsで実施し、ペーパーレス化や在宅勤務等を推進しています。
加えて、近年における学校教育かつ社会の大きな課題となっている「いじめ防止対策」については、本校では、児童に丁寧に寄り添いながら、スピード感をもってチームとしての組織的な対応を心がけるころを基本姿勢として取り組んでいます。より具体的には、今般ではどの学校にも「いじめ防止対策委員会」がありますが、本校ではその強みでもあるICTを生かしたTeamsのチャット機能を活用し、常に最新の情報を委員および当該学年で共有しつつ、附属学校運営部とも連携しながら迅速に対処しています。
問題が発覚した際には、その当日または遅くとも翌日の朝には当委員会(当該学年教員を含む)を開催し、同日の業間休みや昼休みには関係児童に対する複数人での聞き取りを実施します。聞き取り後は、関係保護者への速やかな連絡を通してコミュニケーションと情報共有を図ります。そして、それらの結果を当委員と密に共有しながら関係児童への指導もふくめて事案改善にあたるといった、いじめに対する素早い初動に留意し、早期対応及び解決に向けて従事しています(要所において、附属学校運営部に適宜報告かつ助言を受けながら進めています)。また、いじめ事案について当該児童が担任教員や保護者のみならず、他の教職員にも相談しやすい雰囲気や環境づくりについても重視し、その実践に努めることで「早期発見→対応→改善・解決」を目指しています。
このように、上述した「いじめ防止対策」も含めて、ICTの活用を積極的に取り入れていくという時代に応じた試みに挑戦しつつ、伝統で培ってきた本質的なことも大切にするという本校のあり方は、まさに「不易流行」を体現しているものといえるでしょう。不易流行とは、いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しい変化をも取り入れていく姿勢のことです。また、そのような新しさを求めて変容をしていくこと自体が世の常とも説かれ、より良い様態へとなりゆく成長・進化に向けて欠かせないことであることが示唆されます。
本校は、つねにこの「不易流行」の精神を携えた教育実践の中で、子供たちの潜在可能性を引き出して伸ばしていくよう努めていきます。そして、子供たちが各々の個性を発現させつつ自己創造・自己実現して、未来に向けて羽ばたき輝いていく応援をしていきたいと考えています。
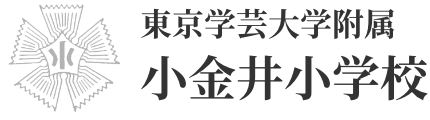
 東京学芸⼤学
東京学芸⼤学 アクセス・お問合せ
アクセス・お問合せ