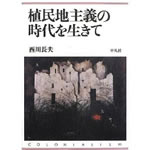�s�g���h�̋ɕn�A����̎��R�A�����ĎO�����̒n�ł̊��z�t
�P�j Tondo�i���s�j�� Happyland�iUlingan)�ABaseco,Dumpsite(Payatas)in Manila
and Quezon City(former capital,1948�`1976) ,Philippines
�t�B���s���̃}�j���ł̍��ۃt�H�[�����Ŕ��\�����邱�ƂɂȂ�A�ȑO���獑�ېl�����ƂŎ����o������p���Ĉ����Ă����A�W�A�ő�̃X�����X�i�n�����j�Ƃ�����u�g���h�v��Payatas ��Dumpsite�i�S�~�̍ŏI�̂ď�A�����n�j�ɍs���Ă��̎��Ԃ�ڂŊm�F���ė��܂����B�Ȋ��͗\�z�ȏ�ɂЂǂ��A�����Ĕ����o���Ȃ��J��Ԃ����n���̍\���ɕ��肳���o���܂����B
���n�K��̎ʐ^�Ȃǂ͈ȉ��̐V���̘A�ڋL���Ŋm�F���ł��܂��B�ʐ^�����ł��u�ɕn�v�Ƃ͉�������������������Ǝv���܂��B�����āA��X�̗אl�ł�����ݓ��E�݊t�B���s���l���Ȃ�����Ȃɑ����A���𗣂�ĕ�炵�Ă���̂��B����Tondo�n��̐������d�C���A�w�Z���a�@���܂Ƃ��ɂȂ����E�ŁA������ʂقǓ����Ă�200�~���������̉҂��ň�Ƃ̐��v��d���ނ�Ɉ�̉����o���邾�낤���A����̋@����A�Z�p�������g�ɂ�������p�ӂł��Ă��Ȃ��g���h�̃E�����K���̔ނ���ǂ̂悤�ɂ�����l�Ԃ炵�����ł̐������\�ɂȂ�̂��B�^���ɍl���Ă݂��̑f�ނɂȂ�K���ł��B
�wSeoul Moonhwa Today�x2012�N7��5���`7��11��
�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14766
�Ahttp://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14782
�Bhttp://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14823
�Chttp://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14841
�w���E�ؐl�V���x�i�݊O�؍��l�����V���j2012�N7��4���`7��6��
�@http://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2844
�Ahttp://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2847
�Bhttp://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2852
�@�����}�j���̒n�ōŒ�̕�炵�����Ă���אl�����Ă݂ʂӂ�����錠�͎҂���������ǂ�قǂ��邾�낤�B�Ȃ��A�T��������Ό��͂𖡂���Ă�������̖��Ɓi���ƌ��̗͂��j�����L���Ă����̂����ƂƂ����邩�ǂ����͊e���̔��f�ɔC����j�́A����x�̒~�ρE�҂̋ɂ܂�̈ꕔ���Љ�Ҍ�������A�����Ȃ��l�X�Ƃ̔z���ɂ͂܂������������Ȃ����낤���B
�N�������ʁB���̍ۂ͉��������Ă����Ȃ����ȕ��ɂ����ݕt���A�X�����͂��×~�ƕ��s�ɐZ��A�ɕn�Ɖ삦�ɋꂵ�ސl�X���Ȃ�������ɂ���l�X�̐��E�A�t�B���s���B���Ő��܂�A�ꎞ�̖����������Ă��炤�u�l���v���[���ɉc�݁A���������̐��Ŏg�����Ƃ��Ă��܂�����ߖ�ł��镪�͎Љ�ɊҌ����A�����Ȃ��l�E������l�Ɏ�������L�ׁA���������ӎ��������ł������I�ɍs����Љ�ɂȂ�Ȃ�A���̂悤�ȃX�����X�͑��݂��Ȃ��Ȃ邾�낤�B���ɂȂ�����ނ�ɕ����Ɗ��������A���ʂƖ\�͂ƕ��s���͎҂��Ȃ��A�V�b�̎��R�������݂�Ȃ�����ł��鎞�オ����̂��낤���B


�i�̂Ă�ꂽ�S�~���E���ĒY������Đ��v�𗧂Ă�g���h�̃E�����K�����̊��B2012�N6��24�����݁j
�����瓭���Ă��n���Ƃ����Q�̒��ŁA�܂��Ƃ��Ȍo�ϓI�z�������҂��邱�Ƃ͏o���Ȃ�����B�@���Ƃ������_�I�x�������Ȃ������Ȃ�ނ�͐�]�I�ŔߎS�Ȗ����ɂǂ�قNjꂵ�ނ��낤�ƍl����ƁA���̍��̑f�p�ŏ����Ȑl�X�̂��ƂȂ��������߂Ċ����܂����B�ċz���܂܂Ȃ�Ȃ������g���h�̊X��P�\���s�̃_���v�T�C�g������A��c��ł������ō����̃z�e���̉ߏ���d�͂��������邩�̂悤�ȗ�[�ɂ���Đg�̂����ꂽ���A���̖����������}�j���̌������Ǝv���A��邹�Ȃ��C�����ł����ς��B
�l�������A��H�s�ׂ����Ȃ����~�̎q�ǂ������̏Ί�ƁA���̐g�̂̎���Ƃ���Ɏc����Ă����S�~�̔j�Ђ̏��ɁA�����ɉ����ł��邩���l�������Ԃɂ��Ȃ�܂����B�����ɖ߂��Ă͋��m�̈�҂����ɉ��Ƃ����悤�Ɛ������������̂́A��]�I�Ȃ��̎q�ǂ��������~�����߂ɂ͂��̊��𑁋}�ɉ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Əł�������Ă��܂��B
 �@
�@ 
�i���s����p�����ʼn��ꂽ�C���ʼnj���ŗ����q�ǂ������B�E�͔p�ނ�S�~������ɂȂ���̂�����q�ǂ������j
��{�I�����̈��S�ƕۏႪ�ł���v���Z�X��@���Ɋm�ۂ��ׂ����B
�������܂��͂��̊댯�ȃS�~�̔p�ނ��U�����鑺�𗇑��ŕ����q�ǂ��ɂ͌C�Ɛ��ƐH�����K�v�B�u�撣����̏�����o���邱�Ƃ��ł���Ƃ�����]�v������������p�I�x���Ƒ��l�ȉ������K�v�B��������A�����I�Ɏ�������L�ׂ邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂����B�����āA���U��l�Ԃ炵���������邽�߂ɂ��A�e��Z�p�̃X�L����̓��ł��鋳��I�C���t���i�J���L���������܂ށj�̊J���ƒB�����̋����������ۏ�Ƃ��̊Ԃ̌o�ϓI�x���𐭕{�K�͂ōs�����ƁB�u�n�v�n�A�x�v�x�v�̍\���Ƀ��X�����A���̗��v�ݏo����Ƃ�̐ŋ���i�ǐS�I�Љ�Ҍ����o����Ȃ��悢���j�̈�Ƃ��Ă̋���E�Z�p�K���{�݂̊������ւ̓����A�ٗp�n�o�̂��߂̎{�ݐݒu�i���̂��߂̋Z�p���炪�K�v�j�A��{�I�J�������������H��Ȃǂ̗U�v�ɂ��Љ�o�ς̐��x���s���I�ɋO���ɏ��A�����ɓ����ނ�̐������̌�������҂ł���Ǝv���܂��B
�@
���ɐ����鍑�ۉ��Љ�i�ޒ��A��X�͂����Ɓu�����b��v�̂���u�����l�v�ɂ���āu������v�Ӗ������Ӌ`���邱�Ƃɂ��邽�߂ɂ��A�q�ǂ������̖��邢�����̂��߂ɂ��A�ό��Ə�����̗��s�ł͂Ȃ��A�g���h�̂悤�ȏꏊ�Ő����������Ƃ���l�X�Ɏ�������L�ׂ���]�T�����̂͑�ω��l�̂��鐶�����Ɍq����ł��傤�B�����������ƂŐ��܂��S�̏[�����́A���̎g�������킩��Ȃ��n�����S�̋����������͂邩�ɖL���Ȑ������ɂȂ�Ɗm�M���܂��B
���͋��t�Ƃ��Ă̎����ɂł��邱�Ƃ����������A�^���ɖ͍��������Ă��܂��B���ꂼ��̗��ꂩ��ł��邱�Ƃ����H���邱�ƁB�����āA�����ł������̎q�ǂ������̏Ί������Ȃ�A��X�̎Љ�͖��邢�����Ɍ������Ǝv���܂��B�����ɂł��邱�ƁA�܂��͌��n�����ė����ӔC�Ƃ��Ă̕ƁA����Ɍg���l�ԂƂ��Ă̍���̖����ɂ��čl���āA�ǂ��`�Ńg���h�̎q��ɍĉ�ł���悤�ȋ@�����肽���ƍl���邱�̍��ł��B�i7��6���j
�Q�j�T���Ƃ����X�̒��̑f�G�ȃL�����p�X�������̖{�w�ƁA�k��̌��������ɂ��閼�����ǂ��y�������z�̂��v�Ȃ��؍��ɏЉ�܂����B�ΖL���Ȗ{�w�ō����������Ȃ�A�H�ו��͊w�H��_���b�p�������邯�ǁA���̂��v�Ȃ̂��ǂ��f�G�B���܂ł�����l���������ł�������Ⴂ�܂��悤�ɁB�i���X��2013�N���Ȃ��Ĕp�ƂƂȂ�܂����B�ƂĂ��c�O!!!�j
�wSeoul Moonhwa Today�x�@2012�N6��18���t
http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14436
�w���E�ؐl�V���x2012�N6��11���t
http://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2804
�R�j�����̒n�E����iMy favorite place,Nagano)
�@1986�N�̉Ăɖ����̒n�E����̈���ƈ��ܖ�ɖ������Ĉȗ��A�@�������Ă͂悭����ɏo�������肵�Ă��܂��B�[�~�ł����s�ł����N�̂悤�ɍs���Ă���̂ŁA�����[�~������̓[�~���s�ɍs�����Ɛ�ɂ�����قǁB
�@���s����͊��R����A�����ł͍����ŏ��{�������܂��B��R�O�O�L���قǑ���ƁA�����͕ʐ��E�B��n�����芷���B���{�̒��ł������Ƃ��������Ǝv���ꏊ�ł��B���ɏ㍂�n�͑�D���B
�@
�@����A���m���\�E�����猩�����̂Ŕޏ��ƐV�Έ���厩�R�̏㍂�n��P�����A�����āA����ێR�n�����ɍs���Ă��܂����B������R�̕䍂�A��A��������i�����͍ō��B�ł��A�㍂�n����̓��͍H�����B��ƍ�����ʂ��Ė`�������Ă��܂����j�ŋ��m�͒Q���B�P�������V�Ǝ��R�̔������B���������l�ԂƂ��Đ��܂�Ă悩�����Ǝv����u��(�������A�A���n��H�c�̓c���k�C�����牫��܂őf���炵���Ƃ���͑��X����܂����A���̎����̒���͊i�ʂɔ������ł��B)�B
�@�P�����̂��₫���l�Ԗ��������čō��B����͕��G�����ǁA��͂�푈�͐�A�@���Ȃ�ł����Ă������Ă����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ċm�F�ł����S�߂Ŕ߂����ꏊ�B�ׂ̂����̓��̉Ԃ͌����ŁA���a�Ɋ��ӂł����B�{�����e�B�A�̕��a�K�C�h����̕��X�ɂ����ӂł��B���ЊF��������͈���A����C�̒���ɑ����^��ł݂Ă��������B���{�̑f�G�Ȗ��͂��Ĕ����ł���͂��ł��B���̋I�s���͈ȉ��ɁB�ʐ^�����ł������ɂȂ�܂��B
�@�wSeoul Moonwha Today�x�iHealing�̒n�E����Ŋ؍��̐Ղ�������B�T��ڂ͌������̎ʐ^�܂Łj
�@�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14234
�A�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14239
�B http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14261
�C http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14262
�Dhttp://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=14278�@
�w���E�ؐl�V���x�i���g���l���A�㍂�n�A�A�P�����A����܂ŃR���p�N�g�Ɂj
�@http://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2775
�Ahttp://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2778
�Bhttp://www.oktimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=2782
�S�j�w�O���u�x�̒n�E�����̒����Łe�����̐����f���v��!!
�@2�����{���璆���E�����̒n�ŏ����E��������̐����l�ƒm�b�����߂čl���A�w�O���u�x�̎j�Ղ⑽���̕��w�ҁE�v�z�Ƃ�ɏo�����A�l�X�Ȑh��v���̒n�ŋM�d�Ȏ������m�F���ė��܂����B�I�R�̔��I�i�Ӊ��ё䂩��́j�R�����Ӂi���m�l�̕ʑ��n�Ƃ��ĊJ�����ꂽ�j��G���e�z�i�����������������R�B�������A�T�o�C�o���̖`���j���܂߂āA�����E��������ԕǂ̒n�Ȃǂ̍]���E�Γ�E�Ζk�n�����o�āA�����܂ł̎��ɒ������j�̒n�����āA�d�v�l���Ɋւ���ꎟ�����Ȃǂ��m�F�ł����̂͊���������ł����B


(�h��v���̒n�E�����̕��������ߘO�Ō����낷) �i�Γ����R�̖ё̐��Ƃ��j
�ё̐��Ƃł͎v��ʏo�������B������_������Ɠ��e�Ƃ��ĊF����ɂ����܂��傤�B�Ȃ��A���̋I�s�̏ڍׂ́wSeoul Moonhwa Today�x�w���E�ؐl�V���x�i�ȉ��̃T�C�g�Q�Ɓj��8��V���[�Y�ŘA�ڂ���܂����B
�ꏏ�ɓ��s���A�����g�����z�����������������̕��X�ɉ��߂Ċ��ӂ��܂��B�ӎ�!!�i1204�j
�@�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13644
�A�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13645
�B�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13659
�C�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13660
�D�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13678
�E�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13679
�F�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13700
�G�@http://www.sctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=13701
�������̍D������ɉ��߂��A���Ȓ��S�I�ɕ������Ă���u�c�S�[�i�s���j�C�X�g�v�̖������뜜����
����͉ʂ����Ăǂ��Ɍ������Ă���̂��H
�ŋ߁A�l�b�g�ʐM�̔��B�ƂƂ��ɗL���ȏ��������Ȃ������ʁA�D������ɕҏW����A���ꂪ�^�����̂悤�Ɉꕔ���������グ�Ă���u�c�S�E�C�X�g�v����������B�����āA�ǎ��E���{��g�ɂ��闧��ł������̎��̂��m�F�������A�������̂悤�Ɏ~�߂Ă��܂��B���ꂪ��������ƁE�E�E���āA�ǂ��Ȃ邩�H
������Ɠ������l����l�����邱�Ƃ𗝉����Ȃ��A���A���e�B�̂Ȃ��ɂ͂т����肷��B�ŏ����甽�Θ_�ō\������^�����~�߂�]�n���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�D��I���z���Ȃ������Ƃ͐l�Ԃ̒m�b��|�����ƂŃR���g���[���ł���͂����B�������A�{�\����ɂ͐l���I�ǐS�ƒm���Ǝ����m�F�ւ̗E�C���K�v�ƂȂ��Ă���B���E������ɂ���邱�Ƃ̕K�v���B���ꂱ���O���[�o���Љ�ւ̔F���B��X���l����ׂ��Ƃ���͖ڐ�ł͂Ȃ��A�������肵����Ղ̕��a�Љ���\�z���A�㐢�Ɏc�����Ƃł���B���̕����͉��������炷���낤���B���ӔC�łނ�݂Ɏ�������咣���肵�Ă���u�c�S�E�C�X�g�v�ɂ��肷������B�i201405�A�v�X�̎G���j
���؍��؉Y�i���b�|�j��������K�˂čl����ؓ��F�D�ւ̓�
2010�N�āA�c����ߎq���������؍��̒n�Ǝq�ǂ������������邽�߂Ɍ��n�ɕ����܂����B�����āA�ޏ��̌��g�I���ɂ��čĊm�F���ė��܂����B�q���[�}�j�Y���ƐӔC�̔ޏ��̎��H�I���U�����A���ɐ�����Љ�ւ̓�����ׂł͂Ȃ����Ƌ����v��������ł��B

�i2010.07�A�؉Y�������œA�����̐�������M�ҁj
�����ꂽ�l�����炱�����̈����ɕ����^���邱�Ƃ��o�����̂ł��傤�B
�������z�����q��ĂɌ��g�������̐��U���A���͋��d�ł����ƍL���m�点�čs�����Ǝv���܂��B
���t�Ɍb�܂��
�@���×{���ł��������鐼�쒷�v�搶����o������̑傫�Ȓ������������Ă����B
�w�A���n��`�̎�����āx�i���}�ЁA2013�N5�����s�j�B619�ł̏d�݂͂܂��ɐ搶�̘J�͂̎����ł���A������Ƃ����d���ł��㉹��f���Ă��܂������̕M�҂̑Ӗ������ӂ��邩�̂悤�ȁA79�̐搶�����H�I�Ɍ����ĉ��������e�Â��Ȃ鋳�爤�f�ł�����B
����搶�ɏ��߂Ă�������͉̂@������ŁA���ۊW�_�ɂ�����u�����̉z�����v�̗��_�Ɍ˘f�������ɂ��̉�������������������A�������⋤���Љ��O���ɓ��ꂽ�t�����X�̍������Ƙ_�ƐA���n��`�ᔻ�Ɋւ�����Ƃł������B����ȗ��A�M�҂ɂƂ��Đ搶�̉e���͑傫�������Ă���B������������A���̕s���ȃO���o�[������̏��z�����𑱂��Ă����������邱�Ƃ�Ɋ肤�̂ł���B
�l���Ă݂�ƁA���͌����҂Ƃ��Ă̌��������̂���x���ĉ������������̎t�Ɍb�܂ꂽ���ł������B�n�����_��Ȋw�I�Ȃ��̂̍l�����ƕ��a�w�ւ̓����������ĉ�������ֈ�Y�搶(���Ȃ݂ɁA���֕��a�w��ASAP�̌������̃T�C�g����m�F�ł���B������X�͈��搶�͐^�̓V�ˊw�҂��ƕ]�����Ă��܂����A��q�����ɂƂ��Ă͗h�炬�̂Ȃ��M�O�Ő�����p�������ĉ�����A痂����A�@�ׂȉ��t�ł�����܂��B�j�ɏo�������̂͑傫�ȍK���ł���B
����ɁA�@������ɍ��܂��������ɁA�����҂̓��𑱂�����悤�Ɍ��㉺���������쏟�Y�E���q�搶���v�Ȃ̂�����Y��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ɐ�����M�O�Ō����҂ւ̓����т��悤�ɗ�܂��ĉ�����������搶���v�Ȃ��͂��߁A�r�����q�搶�A���E�I�ڐ����畽�a�w�̎��H�ƍ\���I�\�͂������ĉ�������Johan Galtung�搶�Ȃǂɂ���Đ��E�����鎋���������Ԃ�ƕς�����B
���m�_���ɔY��ł����ɁA���͖S����������搶����t�����X���w�^���ɂ��Ă̎�������i�搶����̓t�����X��̌���̎莆���A�Ɗw�ŕ�����i�ɒ��������������̂��j�A�����搶�̂��Љ�œn�ӈꖯ�搶�̂��w���������Ƃ͑傫�������B����ɁA���n���̂̎��̃N�����e�_�ɂ`�D�O�����V�ƃo���r���X�ɂ��ċ����ĉ�������M.H�搶�⌤���҂ւ̓������������ĉ�������G.M�搶�A�����č��̎����x���ĉ�����T.S�v�Ȃɂ��[�����ӂ���݂̂ł���B
����ɁA���؋ߑ㕶�w�Ɋւ��Ă����ł͂Ȃ��A�l�I�ɑ�ɂ��Ă��������Ȃǂ������ĉ�����A�M�҂̔��_���������ĉ��������́E���c�؏G�Y�搶��A�u�r�W�l�X�Ő�ΐ����ł��邼�`�v�ƌ��C�t����悤�ɁA���{�̎Љ�J���^����ߑ�o�ώ���������ĉ��������́E���c�����q�搶�A�ݓ������̂��ߕK�v�������M�d�ȕ����ƌ�����莆�ŗ�܂��ĉ��������́E�c���]����搶��́E�A���c�搶�A�w�O�痢�x�S���Ȃǂʼn��������́E���i���搶�i�����q�搶�̂��z���ɑ��ӂł��j�A���}������[�����ƕ��a�v�z�Ō��㉺�������́E���W�P�i�ٌ�m�A�w�펪���l�x�����ʼn��������������́E�ߍ]�J���n�V��搶�ƋˎR����搶�ȂǁA�����̕��X���������Ă����B
�������A�����Ɍ����҂Ƃ��Ă̒��J�Ȏd���⌻���`�������ĉ�����ߑ㌾�_�j�̓A�W���搶��呺�v�v�搶�i���l�E�������̕��T���A���ؕ��w�W�ɑ���Ȍ��т��c�����j�A���{�ߑ�j�W�ł�����������{�n���l�搶�A�{�l�����a���ł���Ȃ���o�̂悤�ɐS�z���ĉ�����A��i�����𑱂��鎍�l�E���C�m�C���A88�ł������ō�i�����������镶�d�̗��j�ł�����������Δ͐搶�Ȃǂ����߁A����Ӗ��Ő��U�������ɂ��������̂悤�ȁu�����X�^�[�v�̂悤�Ȑ�y�⓯���i���ɎR���̃o�J�Z�g���I�̎h���͑傫���j�E��y�ȂǂȂǂȂǂȂǁA�����ɂ͑S���Љ�ł��Ȃ������̌����҂����ɏo����Ă����͍̂K�����������A���Ԃɒǂ����ςȂ��̎��������X��Ȃ��Ȃ��Ďd�����Ȃ��B
���ɂȂ��Ă͎����Ɍ�������������ނق��Ȃ��̂����A�����������o��̒��Ŕ|���Ă��������҂Ƃ��Ă̎p���́u���J���n���Ȏd���v�Ɓu���U�����Ő�����������v���Ƃւ̊�]�݂̂ł���B24���Ԃ͌����Ă���A����Ă����˂Ȃ�Ȃ��d���͎R�ςł���B�������A�n�������A�����Ȍ�����ʂ��Ď����Ɗւ��l�X�A���Ɏ�u����Ɏd���̓��e�J�ɓ`���Ă�����悤�Ɋ撣�邱�ƁB���ꂪ�����̖������Ɖ��߂čl���Ă݂�B�����u���I�ᔻ���_�͎����̂́A�c�݂����Ĕr���I�Ȃ����ƑP�I�咣�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA������ۂ��ƁB�ȒP�ł͂Ȃ����A���ӂɐU���Ȃ��\�����B���̎���ɂ����ɂ���Ӗ���A�����̂��߂Ɏ��������ׂ����ƁA�ł��邱�Ƃւ̒Nj��B
���Ԃ̊m�ۂ͂����e�Ղł͂Ȃ����A�}���\���̂��߂ɖ������m�ۂ��A���L���m���̋z���ŗǎ��̋����S�����邽�߂ɂ��A�L���Ȏ��Ԃ̎g�����ɐs�͂��Ȃ���B
�i130605.�@B.Russell��j�[�`�F�̖{�ƁA�͂�������搶�̖{�߂Ȃ��甽�Ȓ��̖}�ˁj
�������������������������
�k�ɕʁl�E�E�E���̊Ԃ̋L���̎��ԁE�E�E
�����̉@�����ォ��w��I�ɂ��w���������n�ӈꖯ�搶��2013�N12��21���ɉi���ƂȂ�܂����B�n�Ӑ搶�ɂ���ł����̂͌́E��������搶����̏Љ�ɂ����̂ł����B�Ȍ�A�t�����X�̃N�����e���ە����^�����������Ă������ɍł��ǂ������҂̂���l�Ƃ��āA���m�_���̎��M�₻�̐R���ψ��A���̌���l�X�Ȍ�������̂ł����A�c�O�Ȃ���搶�ɓ�x�Ɖ���Ƃ��o���܂���B�����ꂵ�݂܂��B
�@�֓��̓n�ӈꖯ�搶�A���̐��쒷�v�搶�A�����w�ɂ�����傫�ȕ��X���S���Ȃ��A�l�I�ɂ�1995�N�́u���E���E�N�����e���ۃV���|�W�E���v�ȗ��A�����ƌ����҂ւ̓����x���ĉ�����������l�������A����������2013�N�̓~���ƂĂ��c���Ɏv���ĂȂ�܂���B���h����n�Ӑ搶�A�����Đ���搶�A�ǂ������炩�ɂ����艺�����܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
��2013�N�������ƁA���t�̈�l�ł������������쒷�v�搶���i���ƂȂ�܂����B�������̂��ʂ�B�L�����������蔽�Ȃ̎��ԂɂȂ�Ǝv���܂��B�e�͐����Ă���Ԃɐe�F�s�����ׂ����Ƌ����v�����̍��B����搶����͈��ƂȂ����w�A���n��`�̎�����āx�i���}�Ёj�Ƃ��t�����܂������A���Ɠ��������ɖS���Ȃ��܂����B�����ɂޖ����E�E�E����ł��O�����ɐ����Ă����˂B�i2014�N�V�w���Ɂj
���L�J�y���蕶�����Œ��������i���搶������A���Ȃ��Ȃ�ɂȂ�܂����B���A�ꍇ���l�̌����q�搶�Ƃ͈ꏏ�ɍݓ��֘A�̋����������ł��������߁A��ςȏ̉��Ō����Ɍg����ĉ����������ƂɊ��ӂ���݂̂ł��B���i���搶�Ƃ͂Q�N�O�̑�g�َ�Ẫp�[�e�B�[�ŏo������̂��Ō�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�̐l�̂����������F�肢�����܂��B�w���Ȃǂ��d�Ȃ��Ă��܂��A�{���̂��ʖ�ɂ����f���ł����A���搶�ɂ͐\����܂���B�i2012.04.18�j
���ٌ�m�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A���w�≹�y�ɂ����L���m�����������ł��������W�P�i�搶���疈�N�uONO�@ZENJI�@CALENDAR�v���͂����ƂŁA���`�A�܂���N���n�܂�̂��ƋC�Â������ł������A2010�N�Ă���̓C�M���X�Ō�����O���Ԃ��߂����Ă������߁A�J�����_�[��x���q���B�N�����ɏ��낤�Ǝv���ăJ�����_�[���߂����Ăт�����B�Q�O�P�O�N12��15����79�ʼni���Ȃ������̂ł��B
�搶�Ƃ�1996�N�A���炪���Ɍg��������s�����ّ�w�ł̕����N�����e���ۃV���|�̍ۂɃ��}�����[�����ƃA������o���r���X�ɂ��Ă��b�����̂��_�@�ɁA�@��鎞�ɘA���������Ă���܂����B�܂��A���ٌ�m��̉�̌o�����������ŁA���x���@�I�m���������Ƃ�����܂��B
���̖��邢���W�搶�̏Ί��A�f�G�ȍ�i��q���ł��Ȃ��Ȃ����͎̂c�O�łȂ�܂���B�x���Ȃ��Đ\����Ȃ��ł����A�搶�̂����������F��\���グ�܂��B���W�搶�A����܂ł��肪�Ƃ��������܂����B
���ꏏ�ɋ������������������N�j���A���c�搶�i�����A��J��w�����j��2010�N2��4���A�i������܂����B���U���ؔ����̗��j�����ƍݓ��R���A���̎Љ�I�ʒu�Â��A�l�����Ɍ��g������r�Ȑ������ł����B�ޗNj����w�ł̕S�ϕ����V���|�W�E���ɂɗ���ꂽ���Ɍ��������̏Ί��Y��邱�Ƃ͂ł��܂���B�N���̈˗����e�����̂���e�ƂȂ��Ă��܂��Ƃ́B�R���A���������A�������������̎��ɐS��育�������F�����ł��B�i2010.02.05�j
�������������������������