今年、「10代がえらぶ海外文学大賞」という試みが始まっています。本校も応援学校図書館として参加しており、今後投票にも結び付けられたらと考えています。これまでも、子どもたちには世界への広い視野を持ってほしい、そのためにも海外文学の扉を開いてほしいと願い、意識的に海外の作品を紹介するようにしてきました。それでもやはり文学作品そのものへのハードルは高くて、みんなが読むようになるわけではありませんが、高学年でもクラスに数人は、海外YA作品を読み続ける子もいるので、うれしくて紹介を続けています。今回は、この賞を意識して、昨年出た新しい作品を中心に、6年生に行ったブックトークに、少し内容を加えて紹介します。
今日は、生きものの好きな人たちに読んでほしい海外の作品を紹介しますね。野生の生きものと友達になったこと、ありますか? みんなだと、学校で捕まえたヤモリをかわいがっていたりすることはありましたね。ヤモリもかわいいのですが、はじめに紹介するのはもっと大きな動物、マナティーが出てくるおはなしです。
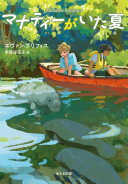
『マナティーがいた夏』エヴァン グリフィス∥作 ほるぷ出版
2024 9784-593-10430-7
野生のフロリダマナティーと出会った男の子の物語ですが、マナティーといってもあまりピンとこない人も多いかもしれませんね。ではまずこの写真絵本を見てください。
『マナティーはやさしいともだち』

福田 幸広∥写真 文 ポプラ社
2002 4-591-07155-3
思わず「かわいい!」と声があがるような写真の数々が載っているこの絵本を見せると、一気に子どもたちのマナティーへの親近感が増すのがわかります。最後にはボートで傷つけられたマナティーの写真が出ていて、これを見せて、物語の紹介へ戻ります。
この主人公の男の子も、ボートによって傷つけられて大けがをしたマナティーを見つけて、その子を助け、保護施設に預けたり、マナティーを傷つけるボートが減るように運動をしたりします。物語の冒頭部分がすごく素敵なので、序章部分を読み聞かせます。おじいちゃんが昔マナティーに出会った夢のような時間の思い出を話してくれるシーンで、主人公がおじいちゃんの認知症に悩んでいることもわかるのです。読み聞かせで実際の文章を聞くことで、子どもたちは「読みたい、読めそう」と気持ちのハードルが下がるようで、紹介だけした本よりずっとよく、子どもたちに借りられるようになります。
『ソリアを森へ マレーグマを救ったチャーンの物語』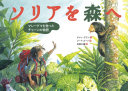
チャン・グエン 作 鈴木出版 2024 9784790254409
前の作品にも、野生のマナティーを保護するプロの人たちが出てきましたが、この作品は、実在のマレーグマの研究者であるチャンさんが、保護した赤ちゃんマレーグマを育て、森で一緒に生活しながら野生に返す様子を描いたノンフィクションです。日本の漫画のような形式で描かれたグラフィックノベルになっていて、マレーグマの表情が本当に生き生きしていてかわいくて、魅力的です。長い文章が苦手な人にも読みやすいので、開いて眺めてみてほしい本です。

『わたしの名前はオクトーバー』
カチャ・ベーレン 評論社 2024 9784566024809
研究者のチャンさんも森の中で相当ワイルドな生活をしていましたが、この物語の主人公も、なかなかに野性的です。ロンドン郊外の森の中で、父親と二人、電気も使わない自給自足的な暮らしをしているのです。けれどもある時そんな暮らしから引き離される事態が起こります。父親が足に大けがを負い、入院することになったのです。オクトーバーは、森の暮らしに耐えられず町に出ていった母親に預けられ、森で拾って世話をしていたメンフクロウの赤ちゃんとも会えなくなってしまいます。最初はかたくなに町の暮らしを拒否していたオクトーバーですが、だんだん心を開いて学校でも友達ができ、成長していく姿が詩的に描かれています。
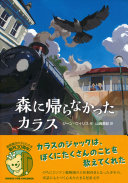
『森に帰らなかったカラス』
ジーン・ウィリス 徳間書店 2024 9784198658946
最後は、野生に帰らなかったカラスと少年のお話です。この物語は、のちに動物園の飼育係になった男性の少年時代の実話をもとにしています。森でケガをしたニシコクマルガラスのひなを拾ったミック少年は、家に連れて帰り、ジャックと名付けて世話をします。家は駅の前にあるパブで、ジャックは家族にも駅員にもパブの常連さんにもかわいがられて育っていきます。時には列車に乗ってしまい、別の街の駅まで捜索に行った事件なども、実際にあったことだそうで、当時の新聞記事も巻末に紹介されています。物語はこうしたほっこりエピソードだけでなく、父親の過去の秘密なども交えながら、ぐいぐい読める作品です。
今日は、いろいろな野生生物が出てくる物語を紹介しました。あまりなじみのない生き物ですが、私は物語を読んだことで、マナティーもマレーグマもニシコクマルガラスも、もっと知りたくなり、ネット検索して動画を見たりして大好きになりました。またマナティーのいるフロリダの泉や、ベトナムの熱帯の森、ロンドン郊外の森などにも行ってきたような気持になりました。知らない世界を知ることができる、これが海外文学を読む醍醐味のひとつだと思います。みなさんも、ぜひ本を通して広い世界への扉を開いてほしいなと思っています。
(東京学芸大学附属竹早小学校 司書宮﨑伊豆美)


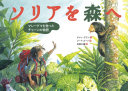
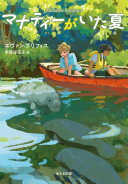 『マナティーがいた夏』エヴァン グリフィス∥作 ほるぷ出版
『マナティーがいた夏』エヴァン グリフィス∥作 ほるぷ出版 『わたしの名前はオクトーバー』
『わたしの名前はオクトーバー』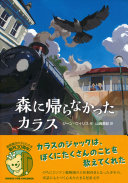 『森に帰らなかったカラス』
『森に帰らなかったカラス』