図書館と出版がテーマの短いブックトーク
2025-02-10 15:14 | by 村上 |
中学校では、なかなかブックトークをする機会がありません。が、2月がブックトークの担当と知り、ちょうど中学3年生が”「知る」ことで「見える」もの”と題して、5時間図書館での授業を行っていたこともあり、「図書館と出版」をテーマに短いブックトークをさせてもらうことにしました。
みなさん、「図書館ってどういうところ?」って聞かれたら何と答えますか?
図書館とは、簡単に言えば、資料を収集し、整理し、保存して、必要な時に利用できるようにしておく施設…です。ただ資料があるだけでは図書館とは言わず、やはり何らかのルールで分類整理されていることが必須です。
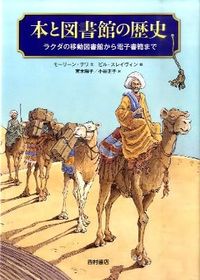 いつ頃から図書館というものがあるかというと、まだ粘土板とかパピルスとかの時代からあるんですね。『本と図書館の歴史』(モーリーン・サワ文 ビル・スレイヴィン絵 宮木陽子/小谷正子訳 西村書店 2010)によれば、古代の図書館で有名なのは、アレキサンドリア図書館です。アレクサンダー大王といえば、紀元前336年頃、巨大な帝国を築いた人です。アレクサンダー大王の少年時代の家庭教師はかの有名な哲学者アリストテレスです。アリストテレスから算数から音楽まで、あらゆることを学んだアレクサンダーは優れた戦士で指導者となりましたが、33歳の若さで亡くなってしまいます。
いつ頃から図書館というものがあるかというと、まだ粘土板とかパピルスとかの時代からあるんですね。『本と図書館の歴史』(モーリーン・サワ文 ビル・スレイヴィン絵 宮木陽子/小谷正子訳 西村書店 2010)によれば、古代の図書館で有名なのは、アレキサンドリア図書館です。アレクサンダー大王といえば、紀元前336年頃、巨大な帝国を築いた人です。アレクサンダー大王の少年時代の家庭教師はかの有名な哲学者アリストテレスです。アリストテレスから算数から音楽まで、あらゆることを学んだアレクサンダーは優れた戦士で指導者となりましたが、33歳の若さで亡くなってしまいます。
生涯知的探求心を持ち続けた大王に敬意を表してつくられたのが、アレクサンドリア図書館です。エジプトの支配者たちは、書物を集めるために力を尽くし、その蔵書はついには40万冊にもなります。残念ながら、アレクサンドリア図書館はやがて消滅してしまいます。ローマ帝国との戦いでカエサルが火を放ったという説もあるのですが、定かではないそうです。むしろカエサルは図書館の建築にとても意欲的でした。
古代ローマといえば、『テルマエ・ロマエ』というマンガや映画もありますが、公衆浴場が有名ですよね。そこに実は図書館や読書室、講演やコンサートもできる場所も併設されていて、まさにローマ人の憩いの場所だったそうです。こんな文化度が高いローマ帝国が滅亡していなかったら、中世時代もあれほど暗黒化しなかったかもしれないと思いませんか?
その中世時代に大きな光となったのが、グーテンベルクの発明した活版印刷機です。それまで聖書をはじめ書物はみなラテン語で書かれていて、修道院や大聖堂の附属の図書館で厳重に所蔵されていました。しかし活版印刷機の普及により、聖書がドイツ語でしかも安価な価格で世に出回り、民衆も読めるようになります。結果的に活版印刷術はルターの宗教改革を支えていくことにもなります。
印刷機で新しい本が次々とつくられ、大学に附属して作られた図書館が充実していきます。一方で、私設の図書館も増えていきます。裕福な権力者が、書物をステイタスシンボルとして、たくさん所蔵するようになるのです。
18世紀、多くの人々が新大陸アメリカをめざしました。政治家で発明家としても有名なベンジャミン・フランクリンは、会員制の図書館を思いつき、それは、たちまち全米に広がっていきます。知識が特権階級だけのものではなく、文字が読めれば、多くの情報に接することができるようになり、一人ひとりが自分の意見を持ち、考えることができるようになっていきます。そしてついに、「庶民の御殿」と呼ばれたボストン公共図書館が、1854年に誕生します。素晴らしい施設と豊かな蔵書をボストン市民は無料で使えるようになるのです。
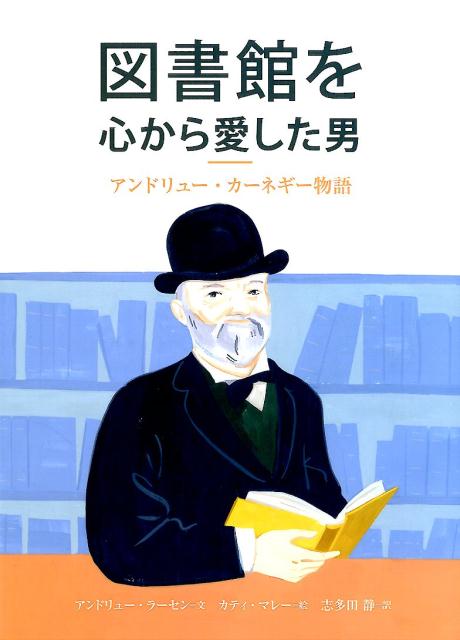 時を同じくして、図書館で多くのことを学んだ貧しい移民の少年が、莫大な財を築きました。彼の図書館愛がどれだけ強かったかがわかるのが、『図書館を心から愛した男:アンドリュー・カーネギー物語』(アンドリュー・ラーセン文 カティ・マレー絵 志多田静訳 六曜社)です。スコットランドの小さな田舎町で生まれたカーネギーは、1848年、12歳の時に家族と共にアメリカのピッツバーグにやってきます。働き者で勉強熱心なカーネギーですが、学校に行く時間はなく、本は読めてもピッツバーグにはボストン公共図書館のように無料で貸してくれる図書館はまだなかったのです。そんな彼を救ってくれたのが、毎週土曜日に個人図書館を開放してくれたアンダーソン大佐です。たくさんの本をむさぼるように読んだカーネギーは、自分が何をすべきかを常に考え行動し、やがては自分で事業を起こし鉄鋼王として大成功を収めます。そしてその莫大な財産を、図書館の建築をはじめ様々な社会活動や慈善活動に使ったのです。最終的にカーネギーは財産のほぼ80%にあたる30億ドル近い金額を寄付して、世界中に2811の公共図書館をつくりました。
時を同じくして、図書館で多くのことを学んだ貧しい移民の少年が、莫大な財を築きました。彼の図書館愛がどれだけ強かったかがわかるのが、『図書館を心から愛した男:アンドリュー・カーネギー物語』(アンドリュー・ラーセン文 カティ・マレー絵 志多田静訳 六曜社)です。スコットランドの小さな田舎町で生まれたカーネギーは、1848年、12歳の時に家族と共にアメリカのピッツバーグにやってきます。働き者で勉強熱心なカーネギーですが、学校に行く時間はなく、本は読めてもピッツバーグにはボストン公共図書館のように無料で貸してくれる図書館はまだなかったのです。そんな彼を救ってくれたのが、毎週土曜日に個人図書館を開放してくれたアンダーソン大佐です。たくさんの本をむさぼるように読んだカーネギーは、自分が何をすべきかを常に考え行動し、やがては自分で事業を起こし鉄鋼王として大成功を収めます。そしてその莫大な財産を、図書館の建築をはじめ様々な社会活動や慈善活動に使ったのです。最終的にカーネギーは財産のほぼ80%にあたる30億ドル近い金額を寄付して、世界中に2811の公共図書館をつくりました。
 ところで、今は、こどものための本もたくさんありますが、もともとは本は大人のものでした。子どものための本を初めて出版した人について書かれた絵本が、『子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語』(ミッシェル・マーケル文 ナンシー・カーペンター絵 金原瑞人訳 西村書店)です。1713年生まれのジョン・ニューベリーは、大きくなると印刷屋で働くようになります。やがて自分の会社をつくりロンドンに進出しますが、こどもたちは聖書や説教臭い物語を読まされていることに気づきます。「子どもの本は楽しくなくちゃいけない!」ニューベリーが亡くなって155年経った1922年に、ニューベリー賞が設立しました。その年、アメリカ児童文学に最も貢献した作品に与えられる賞です。
ところで、今は、こどものための本もたくさんありますが、もともとは本は大人のものでした。子どものための本を初めて出版した人について書かれた絵本が、『子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語』(ミッシェル・マーケル文 ナンシー・カーペンター絵 金原瑞人訳 西村書店)です。1713年生まれのジョン・ニューベリーは、大きくなると印刷屋で働くようになります。やがて自分の会社をつくりロンドンに進出しますが、こどもたちは聖書や説教臭い物語を読まされていることに気づきます。「子どもの本は楽しくなくちゃいけない!」ニューベリーが亡くなって155年経った1922年に、ニューベリー賞が設立しました。その年、アメリカ児童文学に最も貢献した作品に与えられる賞です。
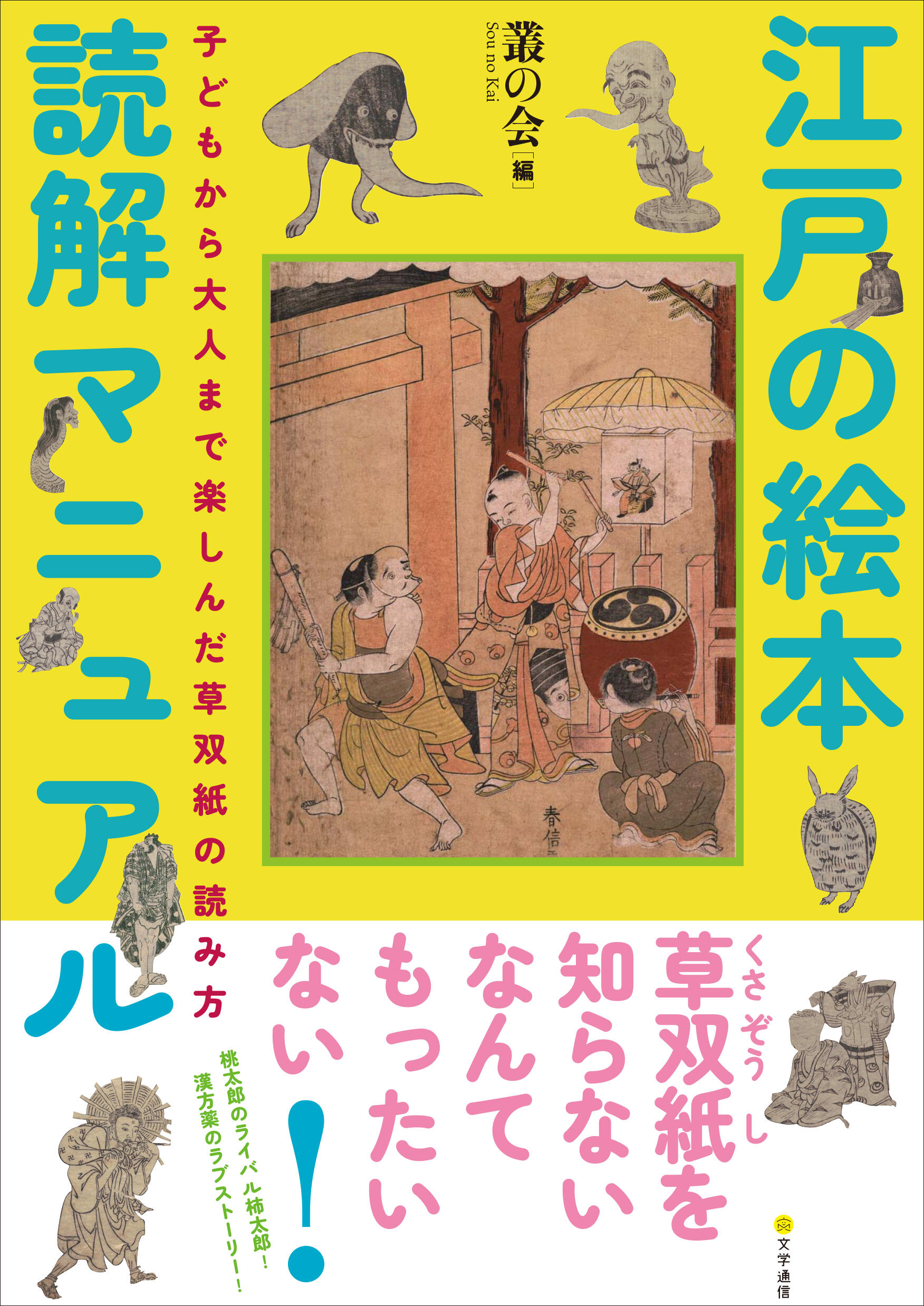 西洋の活版印刷機は、天正少年使節団が日本にも持ち込んでいるし、豊臣秀吉も朝鮮から持ち帰っていますが、当時のキリシタン禁止令もあったし、文字数が多いということもあり、明治の初期まで普及していません。でも日本には、古くから木版刷りの技術があって、早くから庶民も草双紙と呼ばれる絵と文の総合的な表現による大衆読物がありました。おそらく、こどもも大人も楽しめる物だったのだろうと思います。『江戸の絵本読解マニュアル:子どもから大人まで楽しんだ草双紙の読みかた』(叢の会編 文学通信 2023)を見ると、絵と文字が一体化していて、まるで今のマンガですよね。実は「草双紙とマンガをつなぐもの」という見出しで、ここ(P.271)には、『鬼滅の刃』や『呪術回線』が取り上げられています。
西洋の活版印刷機は、天正少年使節団が日本にも持ち込んでいるし、豊臣秀吉も朝鮮から持ち帰っていますが、当時のキリシタン禁止令もあったし、文字数が多いということもあり、明治の初期まで普及していません。でも日本には、古くから木版刷りの技術があって、早くから庶民も草双紙と呼ばれる絵と文の総合的な表現による大衆読物がありました。おそらく、こどもも大人も楽しめる物だったのだろうと思います。『江戸の絵本読解マニュアル:子どもから大人まで楽しんだ草双紙の読みかた』(叢の会編 文学通信 2023)を見ると、絵と文字が一体化していて、まるで今のマンガですよね。実は「草双紙とマンガをつなぐもの」という見出しで、ここ(P.271)には、『鬼滅の刃』や『呪術回線』が取り上げられています。
2025年1月から大河ドラマ「べらぼう」が始まりましたが、主人公の蔦屋重三郎は、江戸のメディア王とも言われていますが、江戸中期に活躍した版元です。江戸の出版事情や、江戸の庶民が何を読み、何を楽しんでいたのか、吉原という特殊な場所の様々な問題も描きながら、1年という長丁場で放送されていくので、私も楽しみに見ています。『蔦屋』(谷津矢車著 文春文庫 2024)、『蔦屋銃三郎 江戸を編集した男』(田中優子著 文春新書 2024)も入れたので、興味のある人は良かったら読んでみてください。
ということで、図書館から最後はべらぼうの話になってしまいましたが、最初に紹介した本の副題に、ラクダの移動図書館から電子書籍までとあるように、最後は電子書籍や電子図書館の話に触れています。本が紙ではなく電子媒体で読めるようになったことで、大きく変わっていく時代だと思っています。それをこれから体感していくのは、皆さんですよね。ただ、媒体が何に変わっても、本というものはなくならないし、大切にされていいものだし、それらが読めるリアルな場所である「図書館」もなくなってほしくないなと思っています。
(東京学芸大学附属世田谷中学校 学校司書 村上恭子)