襷をつなぐ、思いをつなぐ
2024-01-12 22:08 | by 渡辺(主担) |
今年の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)は創設100周年の記念大会でした。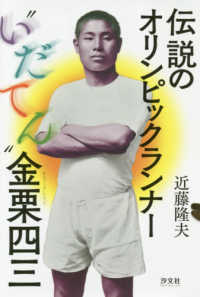 通常開催よりも3校多い23校が出場し、往路と復路の2日間をかけて各校10人が襷をつないで走りました。今やお正月の風物詩ともいえる大会ですが、まったく関心がない人から見れば、2日間ずっと学生が走っているだけとしか見えないかもしれません。ではどうして100回もこの大会が続いているのでしょうか。その歴史を紐解くことができるのが、こちらの本です。
通常開催よりも3校多い23校が出場し、往路と復路の2日間をかけて各校10人が襷をつないで走りました。今やお正月の風物詩ともいえる大会ですが、まったく関心がない人から見れば、2日間ずっと学生が走っているだけとしか見えないかもしれません。ではどうして100回もこの大会が続いているのでしょうか。その歴史を紐解くことができるのが、こちらの本です。
『伝説のオリンピックランナー“金栗四三』近藤隆夫(汐文社 2018年)
この箱根駅伝という大会を100年以上前に思いついたのは、日本人として初めてオリンピックに出場した金栗四三です。しかし初めからマラソンランナーを目指していたというわけではありません。四三は“体を強くしたい”と徒歩(陸上競技)部で走りはじめたことをきっかけに、“もっと速く走りたい”と強く思うようになります。やがて走る才能を開花させた四三は、ついにオリンピックへの出場を果たすのです。
帰国後の四三は、日本のマラソンを強化するために、大学対抗の駅伝レースを思いつきました。その競技が今日まで続いている箱根駅伝へとつながっていきました。
 この箱根駅伝をテーマにした小説でもっとも有名なのは映画化もされた三浦しをん『風は強く吹いている』(新潮社 2009年)ではないでしょうか。メンバーギリギリ、心もバラバラなチームがいかにして10区間の襷をつないで走るのか、読みながらも沿道で応援しているような気持ちにさせられます。
この箱根駅伝をテーマにした小説でもっとも有名なのは映画化もされた三浦しをん『風は強く吹いている』(新潮社 2009年)ではないでしょうか。メンバーギリギリ、心もバラバラなチームがいかにして10区間の襷をつないで走るのか、読みながらも沿道で応援しているような気持ちにさせられます。
近年本校の生徒に人気な箱根駅伝小説は、額賀澪『タスキメシ 箱根』(小学館 2019年)。
箱根を目指していた早馬は、度重なる怪我で4年間一度も箱根を走ることはできませんでした。悔恨の念を残しつつ、大学院で栄養学を学びながら、管理栄養士として駅伝部の学生に関わることになります。多くの挫折を経験したからこそ、学生たちの苦悩や重圧からくる焦りを察知する早馬。チームは紆余曲折しながらも、はたして襷をつないで走ることができるのか、臨場感満載な展開が待っています。
ちなみに12月には額賀さんの新刊『タスキ彼方』(小学館)が出版されました。実は箱根駅伝は100回大会を迎えましたが、それは100年目ということではありません。戦争中で中止された期間があるからです。現代と戦争前後の時代とが交錯しながら語られるこの作品を通じて、大会を絶やしたくないという戦時下の学生たちの思いを知り、ぜひ100回大会に至った軌跡をたどってほしいです。
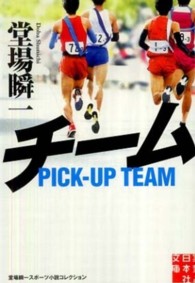 ところで箱根駅伝でユニークなのは、予選会で敗れた学校から実力上位者を集めてチームを編成した「関東学生連合チーム」が参加することです。当日走る10人は、学校が違う寄せ集めメンバー。一緒に練習を重ねてきたわけでもなく、誇りをかけて襷を繋ぐ意識も薄いメンバーが、いかに意思を統一し、本戦で走りぬくか。この連合チームの選手たちの心理描写が秀逸なのが、堂場瞬一『チーム』(実業之日本社 2010年)。競技についても細部までとてもリアルに描かれています。
ところで箱根駅伝でユニークなのは、予選会で敗れた学校から実力上位者を集めてチームを編成した「関東学生連合チーム」が参加することです。当日走る10人は、学校が違う寄せ集めメンバー。一緒に練習を重ねてきたわけでもなく、誇りをかけて襷を繋ぐ意識も薄いメンバーが、いかに意思を統一し、本戦で走りぬくか。この連合チームの選手たちの心理描写が秀逸なのが、堂場瞬一『チーム』(実業之日本社 2010年)。競技についても細部までとてもリアルに描かれています。
最後にご紹介するのはかつて箱根駅伝を走り、東京オリンピックで日本人最高の5位入賞を果たした大迫傑『走って、悩んで、見つけたこと。I did it!』(文藝春秋 2019年)。東京オリンピック後に引退しましたが、来年パリオリンピック出場をめざし現役復帰をはたしました。最終選考が残っているため、まだ出場は確定されていませんが、家族で東京ディズニーランドを訪れても、一人だけディズニーランドの外周を走っているという、根っからのランナー気質。
今やこの大迫選手に限らず、箱根駅伝を経験した選手たちが、マラソン界で力を発揮しています。まさに日本のマラソンの強化を、という金栗四三の願いが、100年の年月をへて花開いているのかもしれませんね。
(東京学芸大学附属国際中等教育学校:司書 渡邊 有理子)