しばし(?)さよならパンダ
2026-01-29 12:17 | by 渡辺 |
 先日上野動物園の双子のパンダが中国に返還され、ついに日本からパンダがいなくなりました。別れを惜しみ、テレビではパンダを輸送するトラックにも手を振る人たちのようすが流れ、パンダ愛を感じずにはいられません。
先日上野動物園の双子のパンダが中国に返還され、ついに日本からパンダがいなくなりました。別れを惜しみ、テレビではパンダを輸送するトラックにも手を振る人たちのようすが流れ、パンダ愛を感じずにはいられません。
そこでメディアセタンターでも、「しばし(?)さよなら、パンダ」コーナーを設けました。今回のブックトークはここに展示をした本から紹介をします!
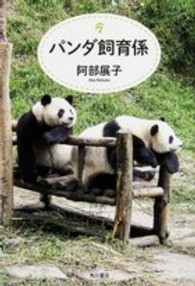
最初に紹介するのは『パンダ飼育係』阿部展子 角川書店2013年 (ISBN:978-4041104705)
作者の阿部さんは、小学校の修学旅行で初めて上野動物園のパンダと対面し、その虜に。以来中学生になっても、高校生になってもパンダ好きは変わりませんでした。いよいよ高校3年の進路選択のとき、お母さんが「そんなにパンダが好きなら、パンダを仕事にすればいいじゃない?」と。この一言にご本人は“パッと視界が開けた感じがした”そうです。でも好きを仕事にするのはけして簡単なことではありませんよね。
今、阿部さんは中国の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で唯一の外国人飼育員として働いています。その紆余曲折をぜひこの本で。
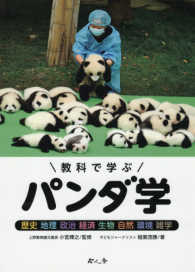
ところで多くの人を虜にするパンダって、そもそもどういう動物なのでしょう?そんなパンダを歴史、地理、生物、政治、経済、環境、雑学・・・などさまざまな視点からひもとく一冊がこちら。
『教科で学ぶパンダ学』小宮輝之 今人舎 2017年 (ISBN:978-4905530701)
まずは赤ちゃんパンダたちが寝転ぶ表紙に目が留まりませんか?なんとなくパンダって新しい動物のように感じていましたが、パンダの先祖は人類よりも300万年以上も前に地球に現れたそうです。また、見た目はふわふわしていますが、実際にさわると剛毛でゴワゴワで脂っぽいとか。パンダのあれこれを知りたい人はぜひ!
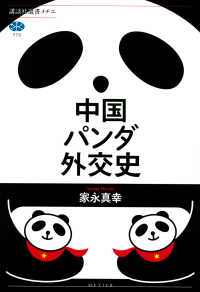
さて、パンダは戦後中国との国交回復10周年を記念して、日本に贈られました。しかし日本よりも先にロシアやアメリカに贈られています。パンダは「友好」の名の下に、たびたび外交に利用され、独特な政治的役割を果たしてきました。このため「パンダ外交」という言葉もうまれています。では中国と日本との外交にどのようにパンダが利用されてきたのでしょうか。パンダについて政治的視点から読み解きたい人はこちらを。『中国パンダ外交史』家永真幸 講談社 2022年 (ISBN:978-4065297278)
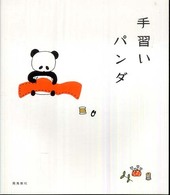 それにしても、日本からパンダが1頭もいなくなってしまった現実は寂しい限りです。もちろん動画や本でも眺められますが、パンダが再び日本に来るまでの間、”パンダと毎日一緒にいたい!”という人は、ぜひこの本を参考にパンダグッズを作ってみませんか? 『手習いパンダ』後藤美奈子ほか 飛鳥新社 2009年 (ISBN:978-4870319127)
それにしても、日本からパンダが1頭もいなくなってしまった現実は寂しい限りです。もちろん動画や本でも眺められますが、パンダが再び日本に来るまでの間、”パンダと毎日一緒にいたい!”という人は、ぜひこの本を参考にパンダグッズを作ってみませんか? 『手習いパンダ』後藤美奈子ほか 飛鳥新社 2009年 (ISBN:978-4870319127)
この本ではパンダのカード、輪ゴムホルダー、財布、バッグなど、比較的簡単に作れるパンダグッズをまとめて紹介しています。私もまずはパンダのメッセージホルダーにチャレンジしてみますので、カウンターで見られる日を楽しみにまっていてくださいね!
(東京学芸大学附属国際中等教育学校 司書 渡邊 有理子)