はじまりの1冊に出会う旅 夏休みの課題を自力でレファレンス!
2025-07-10 10:31 | by 村上 |
レファレンスの記事、何を書こう…と思いつつ、本日、図書館で行っていた授業を見ていて気が付きました。これって”自力でレファレンスしよう”という話ではないかと。
3学期にある中1のスピーチ大会は、自分の好きなことについて語ります。そこで夏休みの課題のひとつが、「はじまりの1冊に出会う旅」。つまり自分の好きを広げる、あるいは深めるための新書を1冊読むことです。そこで机の上には岩波ジュニア新書・ちくまプリマー新書・講談社ブルーバックス・岩波ジュニアスタートブックス・ちくまQブックスの5冊を置きました。先生が、「新書って何だと思う?」と聞くと、ほぼ100%「新しい本!」という答えが返ってきます。そこでテーブルの本をしばし手に取ってもらい、実は新書はサイズからきている話をするのですが、若干大きい2冊が新書が読めるようになるためのさらなる入門書であることを伝えます。
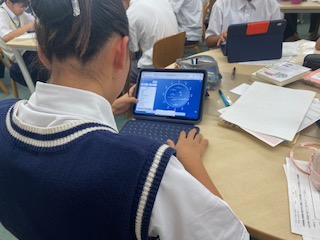 今回、先生が紹介したかったのは、「新書マップ4D」。まずは先生が画面を見せると、どのクラスも、「おーっ」と声が上がります。テーマ別にも出版社別にも並び替えができること、最近加わった「わたしの本棚」機能も説明します。さらにはテーマリウムの使い方を説明。テーマリウムは生徒の端末からもサクサク動くのですが、新書マップ4Dは重たいので学校で同時にアクセスするのには不向きかもしれません。
今回、先生が紹介したかったのは、「新書マップ4D」。まずは先生が画面を見せると、どのクラスも、「おーっ」と声が上がります。テーマ別にも出版社別にも並び替えができること、最近加わった「わたしの本棚」機能も説明します。さらにはテーマリウムの使い方を説明。テーマリウムは生徒の端末からもサクサク動くのですが、新書マップ4Dは重たいので学校で同時にアクセスするのには不向きかもしれません。
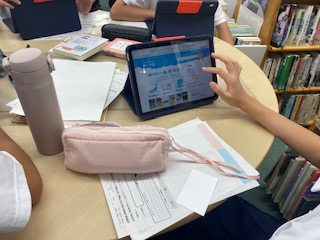 読みたい新書を見つけたら、世中OPACで所蔵を調べてみる。もし所蔵されていなかったら、公共図書館の蔵書が調べられるカーリルを紹介。自分の住んでいる地域の公共図書館の蔵書を調べて予約もできることを伝えると、「へぇ~」と感心する声が聞こえてきます。カーリルは、公共図書館自前のOPACよりもビジュアル的に優れているし、所蔵情報だけではないのも、魅力です。
読みたい新書を見つけたら、世中OPACで所蔵を調べてみる。もし所蔵されていなかったら、公共図書館の蔵書が調べられるカーリルを紹介。自分の住んでいる地域の公共図書館の蔵書を調べて予約もできることを伝えると、「へぇ~」と感心する声が聞こえてきます。カーリルは、公共図書館自前のOPACよりもビジュアル的に優れているし、所蔵情報だけではないのも、魅力です。
さらには、今年から導入した「ジャパンナレッジスクール」では、岩波新書・岩波ジュニア新書・ちくまプリマーブックス・講談社ブルーバックスそれぞれ100冊、計400冊もの新書が読めます。ジャパンなレジには、セマンティック検索という便利な機能もあるので、本を探すときに、使ってみるのもいいかもしれません。