翻訳の世界へようこそ
2023-07-05 16:09 | by 村上 |
本校では、様々なテーマで探究学習が行われていますが、その中のひとつに、「翻訳の世界」があります。自分が好きな本,歌,詩、ドラマ等を自分なりに解釈し,自分の言葉で翻訳します。翻訳活動を通して、言語・文化・他作品との比較をし、「日本」を見つめ直していくことがねらいです。そんな「翻訳」に挑戦する中学生に向けて、この夏休みに役立ちそうな本を紹介しました。
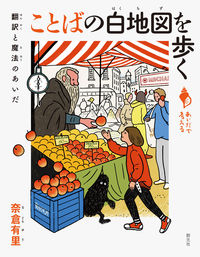 最初に紹介するのは出版されたばかりの新刊『ことばの白地図を歩く:翻訳と魔法のあいだ』(奈倉有里 創元社 2023)です。著者は、ロシア文学研究者でもあり、翻訳も手掛けています。ロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業した初めての日本人で、2021年に出版した『夕暮れに夜明けのうたを』(イーストプレス)で紫式部文学賞を受賞しました。(こちらもおすすめです。)
最初に紹介するのは出版されたばかりの新刊『ことばの白地図を歩く:翻訳と魔法のあいだ』(奈倉有里 創元社 2023)です。著者は、ロシア文学研究者でもあり、翻訳も手掛けています。ロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業した初めての日本人で、2021年に出版した『夕暮れに夜明けのうたを』(イーストプレス)で紫式部文学賞を受賞しました。(こちらもおすすめです。) なぜ、奈倉さんがロシア語を選んだのか?まず子ども時代を母方の故郷新潟で祖父母と過ごすことが多く、雪国にあこがれていたこと、中学生で出会ったトルストイの作品が大好きだったこと。そのトルストイを、新潟でコメ作りをしていた祖父も好きだったこと、英語とは違うロシア語のアクセントに、しっくり感を感じたこと、これらの事柄が奈倉さんにとって、「ロシア語」という運命の言語に結び付いたのですね。
「翻訳の世界」を選んだみなさんにとっての運命の言語は、もっかのところ英語です。奈倉さんが勧める勉強法のひとつに、「ことばの子ども時代」を楽しむとあります。語学学習が子どもに向いているのは、ものごとに対する興味が尽きず、何でも自分でやってみたがり、新しいものをどんどん吸収するから。だから大人でも遊びの要素たっぷりに外国語を学んでみると、楽しいし効果的なのでしょう。
「翻訳」を通して二つの国の文化について考えることも、皆さんの課題です。この本のなかで奈倉さんは、「文化」とは、本来は互いに理解し合う営みであるはずなのに、昨今は違いを強調しすぎて優劣をつけたがる…と憂いています。奈倉さんにとっては、「本」「詩」「小説」こそが文化。その文化をもってモスクワに行ったからこそ、同級生から異質な存在とみなされず、仲間になれたこと実感したといいます。
さて、奈倉さんの大好きな「本」こそが、最終章に出てくる魔法なのです。本好きならわかってもらえるでしょうが、本の中に入り込み、体験し、自分の記憶にしていくこと。言葉を獲得し、翻訳をするには、何より好きな世界の「本」を読むに限るってことですね。
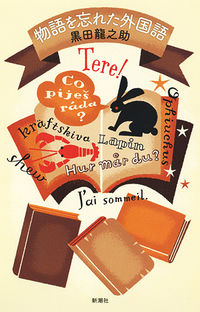 奈倉さんのこの本を読んで思い出したのが、黒田龍太郎さんの『物語を忘れた外国語』(新潮社 2018)です。言語学的なアプローチをする人は、なぜか文学を読まず、文学が好きな人は言語学を学ばない。たまにいる両方好きな人は歴史を知ろうとしない。言語・文学・歴史を切り離すことなく、学び続けてきた著者が、その醍醐味を語ってくれるのが、この本なのです。黒田氏は、ロシア語学科を卒業していますが、あらゆる言語に興味があり、その関心は一つの言語に閉じていません。そのため、この本がとりあげている言語も多岐にわたり、様々な言語から日本語に翻訳された外国の物語、その逆に他言語に翻訳された日本の物語、加えて映画もとりあげています。普通、言語学の先生が研究の対象とするのは、音や単語、せいぜい文といった小さなレベルで、物語をまるごと一つ研究するというのはアリエナイらしい。だから言語学から物語はどんどん遠くなっていくのですね。
奈倉さんのこの本を読んで思い出したのが、黒田龍太郎さんの『物語を忘れた外国語』(新潮社 2018)です。言語学的なアプローチをする人は、なぜか文学を読まず、文学が好きな人は言語学を学ばない。たまにいる両方好きな人は歴史を知ろうとしない。言語・文学・歴史を切り離すことなく、学び続けてきた著者が、その醍醐味を語ってくれるのが、この本なのです。黒田氏は、ロシア語学科を卒業していますが、あらゆる言語に興味があり、その関心は一つの言語に閉じていません。そのため、この本がとりあげている言語も多岐にわたり、様々な言語から日本語に翻訳された外国の物語、その逆に他言語に翻訳された日本の物語、加えて映画もとりあげています。普通、言語学の先生が研究の対象とするのは、音や単語、せいぜい文といった小さなレベルで、物語をまるごと一つ研究するというのはアリエナイらしい。だから言語学から物語はどんどん遠くなっていくのですね。 けれども、外国語を学ぶのに、文学を読まないは、なんとももったいない話。黒田さん曰く、外国語学習は長編小説に限る。心がけるはすべてを分かろうとしないことである。辞書をひくなんてもっての外、ときにはわかんないなぁと愚痴りながら、とりあえず先に進む。それが読書である。あまりにわからなかったら映像で見てみる(文学作品は映画化されているものも多いですからね)。私の外国語はどこまでも物語と一緒であるという黒田さんの、生のお話を聞いてみたくなります。きっと楽しいんでしょうね!
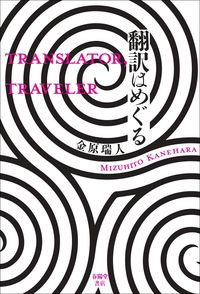 先の2冊は偶然ロシア語を専門とするお二人でしたが、学校図書館の蔵書は、なんといっても英米文学の占める割合が、他の外国文学に比べても圧倒的に多いのが現状です。その英語圏の作品約600冊を翻訳してきたのが金原瑞人さんです。30年に及ぶ翻訳人生のなかで感じたことを1冊の本にまとめたものが、『翻訳はめぐる』(春陽堂書店 2022)です。ご本人は、出版するにあたり、誰か面白がってくれるのだろうか?と懐疑的だったようですが、本に関わる仕事をしている司書や、翻訳モノが好きな読者、なにより「言語」に関心のある人たちには十分面白い一冊です。
先の2冊は偶然ロシア語を専門とするお二人でしたが、学校図書館の蔵書は、なんといっても英米文学の占める割合が、他の外国文学に比べても圧倒的に多いのが現状です。その英語圏の作品約600冊を翻訳してきたのが金原瑞人さんです。30年に及ぶ翻訳人生のなかで感じたことを1冊の本にまとめたものが、『翻訳はめぐる』(春陽堂書店 2022)です。ご本人は、出版するにあたり、誰か面白がってくれるのだろうか?と懐疑的だったようですが、本に関わる仕事をしている司書や、翻訳モノが好きな読者、なにより「言語」に関心のある人たちには十分面白い一冊です。 その国の文化を知るために言語を学び、互いに理解を深める目的を持っていた外国語学習が、英語に限っては、コミュニケーションツールとして大きな力を持つようになり、それと並行して通訳・翻訳マシーンもどんどん性能アップ。どんな英語ツールをどれだけ使いこなせるかが問われる時代がすぐにやってくるに違いないと。そうはいっても、英語をモノにして、ツールを挟まず直接話をしたいという願望は、英語が好きなら、きっといつの時代もありますよね。
長く翻訳と格闘(?)してきた金原さんは、日本語を特別視していません。日本語が格別優れているとも、ことさら大切だとも美しいとも思っていないのです。それをいうなら、全ての言語は大切で美しい。こと言語に関してはどうしたって”博愛主義者”になるとあります。たぶん、どちらの言語にもフェアな態度で接してきたからでしょうね。
後半は、翻訳にあたっての、縦書きと横書きの問題だったり、これまで集めてきた幕末から明治にかけての辞書や英会話本に纏わる話など、金原さんしか書けないあれこれが詰まった一冊です。
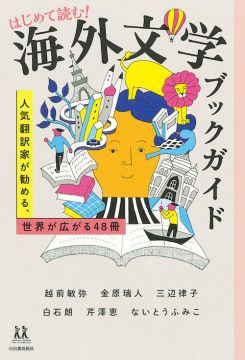 最後に紹介するのは、金原さんも筆者のひとりである、『はじめて読む!海外文学ブックガイド』(越前敏弥他 河出書房新社 2022)です。もとになっているのは、NHKラジオ「中学生の基礎英語 レベル2」のテキストに、6人の英語圏小説の翻訳者が執筆していたものです。英語を学び続けている(主に)中学生に向けて、ただ英語を勉強するだけでなく、英語圏で生活する人たちの生活や考え方を深くしってほしいと、お薦めの小説を紹介してきたのです。「物語」を読むことで地に足がついたしっかりした語学力をつけてほしいと、あとがきにあります。語学を学ぶとは、文法や発音を知り、語彙を増やすことだけを意味するのではなく、その言語を使って暮らす人々の営みを知ることで、初めて生きた言葉として、感じることができるのでしょう。嬉しいことに、「物語」は、それらを楽しみながら得ることができのです。
最後に紹介するのは、金原さんも筆者のひとりである、『はじめて読む!海外文学ブックガイド』(越前敏弥他 河出書房新社 2022)です。もとになっているのは、NHKラジオ「中学生の基礎英語 レベル2」のテキストに、6人の英語圏小説の翻訳者が執筆していたものです。英語を学び続けている(主に)中学生に向けて、ただ英語を勉強するだけでなく、英語圏で生活する人たちの生活や考え方を深くしってほしいと、お薦めの小説を紹介してきたのです。「物語」を読むことで地に足がついたしっかりした語学力をつけてほしいと、あとがきにあります。語学を学ぶとは、文法や発音を知り、語彙を増やすことだけを意味するのではなく、その言語を使って暮らす人々の営みを知ることで、初めて生きた言葉として、感じることができるのでしょう。嬉しいことに、「物語」は、それらを楽しみながら得ることができのです。 連載当時は英語圏の翻訳者だけでしたが、1冊にまとめるにあたり、その他の言語で翻訳している方にも声をかけ、計18人の翻訳者の方が48冊の本の魅力を語ってくれています。この本に紹介されている本の多くが、本校の図書館で読むことができます。ないものは、公共図書館で手に入るはずです。この夏、ぜひ自分の心に響く海外文学を見つけて、どっぷりその国の文化に浸り、そして自分との共通点も見つけてほしいと思います。何より、「本」を読む文化を愛する人たちは、世界中にたくさんいます。だからこそ、「本」は生まれ、「図書館」はその本を次の世代の人々に手渡す場として、変わらず皆さんのすぐそばにあるのです。
(東京学芸大学附属世田谷中学校 村上恭子)