様々な視点から「戦争」を読む
2026-01-30 12:34 | by 野呂 |
社会科の先生から「6年生の授業で第二次世界大戦についてのレポート課題を出したいと思っている。しかし、ただ「戦争はよくない」「原爆はこわい」で終わらないように、戦時中の人々の生活の様子や兵器、制度、報道など「様々な視点」から戦争について学べる本を紹介してほしい。その資料を活用しながら事実に基づいた深い考察をさせたい。」という依頼を頂きました。
「平和学習」に関する本は、たくさんありますが、今回は頂いたレファレンスに応える中で紹介した本を数冊、データベースでも紹介します。
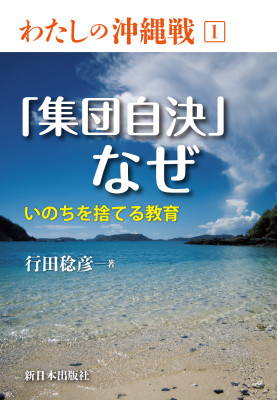
『わたしの沖縄戦1⃣ 「集団自決」なぜ いのちを捨てる教育』
行田稔彦 新日本出版社 2013年 ISBN 978440605729
この本は、沖縄戦のことを網羅的に理解することができます。
戦火の中で、「生と死の分かれ道」に翻弄され、国のために死ぬことは尊いことだと教わっていた。そんな子供時代を過ごした証言者のリアルな体験を読み進めれば、「平和と命」の尊さを感じることができるでしょう。
沖縄住民に「集団自決」を強制した軍隊が、自らは、自決せず、投降し、生き延びているという事実なども書かれており、到底納得のいくものではない真実がここに残されています。
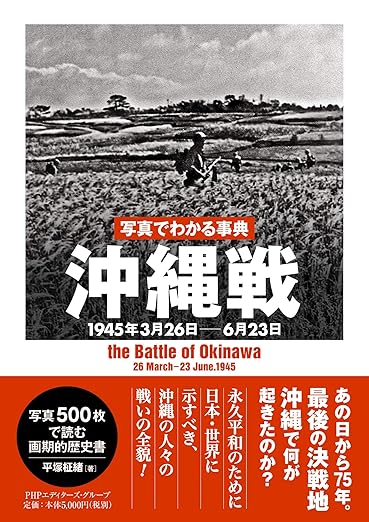
『写真でわかる事典 沖縄戦 1945年3月26日ー6月23日』
平塚柾緒 株式会社PHPエディターズ・グループ 2020年 ISBN 978-4909417480
沖縄戦について、こちらは写真から読み取ってほしいと思って紹介しました。
米軍の第一陣が、1945年(昭和20年)4月1日に沖縄本島に上陸してから約2カ月後の6月23日には、日本軍司令官の牛島満中将と参謀長の長勇中将が指揮権を放棄して自決しますが、全ての戦いが終わる9月7日まで、沖縄本島は死闘の地と化しています。
沖縄攻略のために送り込まれた米第10軍の総兵力は7個師団約18万3,000名、これに対する日本軍守備隊は、将兵約9万6,000名でした。
―これに沖縄の現地召集兵約2万5,000名の他、女子学生をはじめ、健康な男女の大半が軍属や衛生要員、看護師などの名目で徴用され、沖縄のすべての住民を巻き込んだ戦いとなります。
約500枚の写真を見ながら、沖縄戦の悲惨さ、真実を感じ取ることができる1冊です。
次に「子どもたちの生活と戦争」の視点から1冊紹介します。
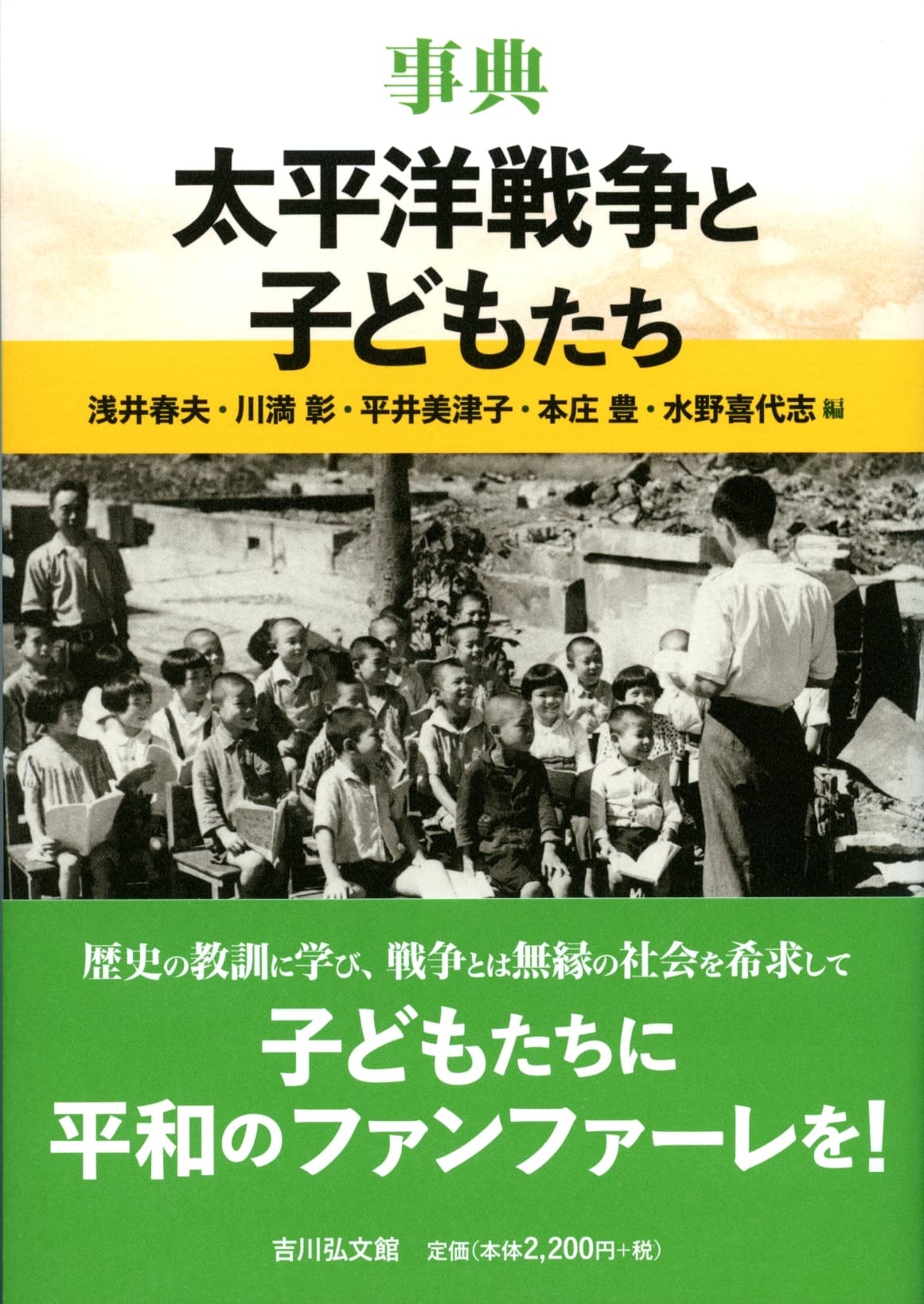
『事典 太平洋戦争と子どもたち』
浅井 春夫, 川満 彰, 平井 美津子,本庄 豊,水野 喜代志 吉川弘文館 2022年 ISBN 978-4642084147
戦争は子どもたちに何をもたらすのか。暮らしや教育、戦後も含めて太平洋戦争を振り返っているこの本は、軍国少年・少女、教育勅語と御真影、学童疎開、沖縄戦、引揚、孤児生活など、47の問いに図版を交えて答えています。
その問いの1つに、「マスメディアは太平洋戦争にどのようにかかわりましたか」というものがありました。
日本は、日中戦争以来、みずからの選択によって国際的孤立を深めていたにも関わらず、そういった経緯を新聞などに載せることはなかったことや、兵糧攻めと弾圧で「政府の広報」を強要していたことなどが書かれています。現代においても、偏向報道、マスメディアとの接し方、「情報」がいかに重要であるかは注目すべきテーマです。「報道」の在り方に注意し、過去と現在の繋がりについても子どもたちが考えるきっかけになってもらえればと思います。
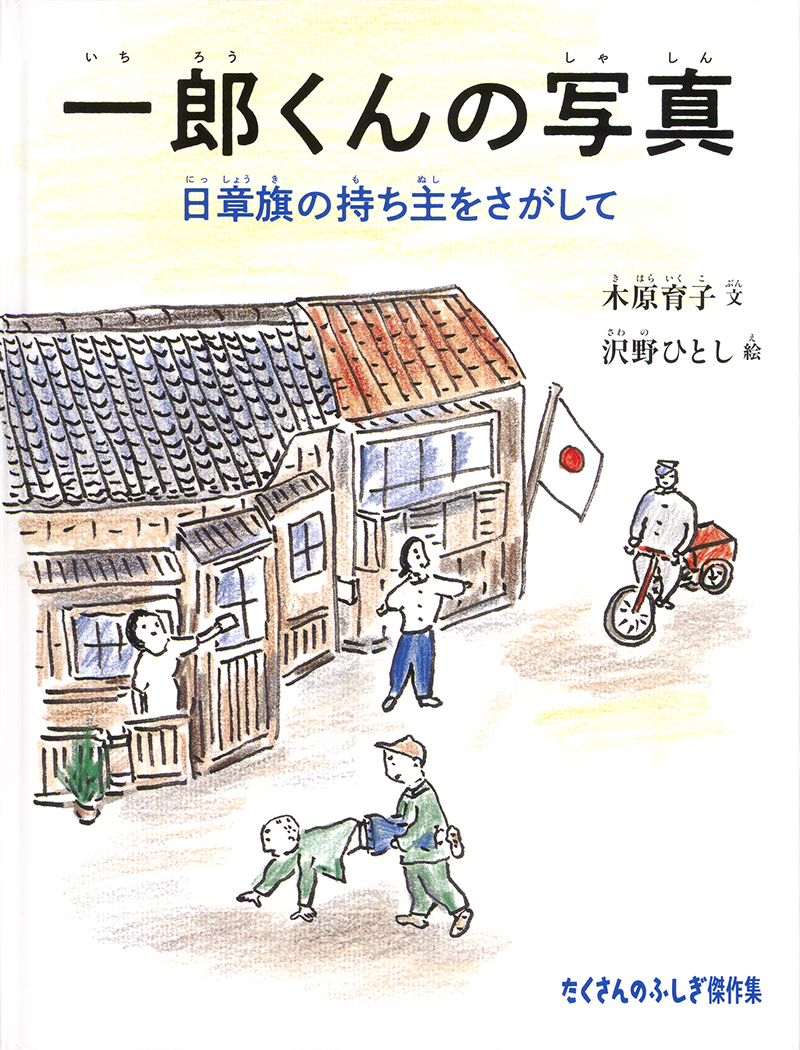
『たくさんのふしぎ傑作集 一郎くんの写真 日章旗の持ち主をさがして』
木原育子(文) 沢野ひとし(絵) 福音館書店 2025年 ISBN 978-4-8340-8863-2
2014年、アメリカで「一郎君へ」と書かれた日章旗が見つかります。日章旗とは、兵隊に行く人がお守り代わりに持っていた、周囲の人たちが日の丸の旗に名前を寄せ書きしたものです。戦場に残された旗をアメリカ兵が持ち帰り、元の持ち主がわからないまま出てくることも多いのです。
その日章旗に書かれた59人の名前を手がかりに、「一郎くん」がどんな人だったのかを探る新聞記者の視点から描かれている1冊です。
新聞記者が調査を進める中で見えてくるのは、「一郎くん」が周りの人から愛されていたということ。そんな一郎君が「お国のため」と出征していかなければいけなかった姿から子供たちには平和の尊さやありがたさを改めて感じてほしいと思います。
「戦争」の怖さ、恐ろしさ。二度と繰り返してはいけない。歴史を学ぶ中で、頭ではそう理解していても、「深く考える」という機会はあまりなかったと、このレファレンスを通して痛感しました。
これからも「本」を通して、戦争の時代を生きておられた方々の経験・体験を子どもたちに伝えていきたいと思います。
(東京学芸大学附属世田谷小学校 司書 野呂 昭子)