3・11 震災の記録と復興支援について
2011-07-15 05:36 | by 村上 |
0.文部科学省から「平成22年度 学校図書館の現状に関する調査について」が公表されました。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/1306743.htm
1.子どもたちの発信 『つなみ 被災地のこども80人の作文集』『宮城気仙沼発!ファイト新聞』
2.新聞社の記録は被災地地元新聞も集めてみました。
3.三陸の水産業を考える授業…東京学芸大学附属小金井小学校
4.図書委員会の活動
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/1306743.htm
1.子どもたちの発信 『つなみ 被災地のこども80人の作文集』『宮城気仙沼発!ファイト新聞』
2.新聞社の記録は被災地地元新聞も集めてみました。
3.三陸の水産業を考える授業…東京学芸大学附属小金井小学校
4.図書委員会の活動
1)顔の見える支援を継続的に…茨城県立水戸第二高等学校
2)文化祭でエネルギーについて考えました…兵庫県立西宮今津高等学校
5.2011年3月の校長・学長の卒業式の言葉
5.2011年3月の校長・学長の卒業式の言葉
1.子どもたちからの発信
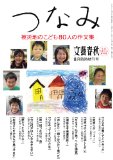
『つなみ 被災地のこども80人の作文集 文芸春秋8月号臨時増刊号』…2ヶ月後に書かれた小学生から高校生までの作文。吉村昭『三陸海岸大津波』に中でも、当時の子どもたちの作文を集めた「子供の眼」という章があり、貴重な記録になっている。今回、岩手・宮城の避難所を回り子供たちに声をかけていったジャーナリストがいて、平成の「子供の眼」がを世に出されたことに拍手を送りたいと思う。

『宮城気仙沼発!ファイト新聞』 ファイト新聞社/著(河出書房新社 2011.7)…伝記が復活した3月18日から、避難所の人たちを元気づけようと小中学生4人で始めた壁新聞1月半の記録。ルールはひとつ「暗い話は書かない」。色マジックをつかい、イラストがちりばめられた交換ノートのような新聞だが、いや、だから、エネルギッシュな、子どもたちからの記録になっている。拙い言葉にこめられた、または幼子をかばい、大人をも支える高校生の、真に迫る記録である。
なお、一部がニューヨークの報道博物館入りしたという、大人の手書き新聞も本になっている。
『6枚の壁新聞 石巻日日新聞・東日本大震災後7日間の記録』(角川SSC新書)
石巻から男鹿半島にかけて被災した人々の「いのちの言葉」をつづるノンフィクション。
『ふたたび、ここから 東日本大震災・石巻の人たちの50日間』 井上正樹著(ポプラ社)
2.被災地地元新聞の記録―全国紙では報道しない地元の記録を確かめよう―
岩手日報 『特別報道写真集 平成の三陸大津波 東日本大震災 岩手の記録』
http://www.iwate-np.co.jp/
河北新報社 『河北新報特別縮刷版 3.11東日本大震災1ヵ月の記録』
『報道写真集 巨大津波が襲った3・11大震災 発生から10日間 東北の記録』
http://www.kahoku.co.jp/
石巻日日新聞 http://www.hibishinbun.com/
福島民報 『縮刷版 東日本大震災特別編=激動の50日を追って―』
http://www.minpo.jp/
福島民友新聞社 http://www.minyu-net.com/index.html
新聞 『東日本大震災茨城全記録―特別報道写真集』
http://www.ibaraki-np.co.jp/books/genre.php
『心をつなぐニュース』池上彰+文藝春秋=編(文藝春秋社)東日本の地元の新聞社の記事から心温まる話をテーマ別に、1話を見開きでその新聞記事の切り抜きと共に紹介する。
岩手日報 『特別報道写真集 平成の三陸大津波 東日本大震災 岩手の記録』
http://www.iwate-np.co.jp/
河北新報社 『河北新報特別縮刷版 3.11東日本大震災1ヵ月の記録』
『報道写真集 巨大津波が襲った3・11大震災 発生から10日間 東北の記録』
http://www.kahoku.co.jp/
石巻日日新聞 http://www.hibishinbun.com/
福島民報 『縮刷版 東日本大震災特別編=激動の50日を追って―』
http://www.minpo.jp/
福島民友新聞社 http://www.minyu-net.com/index.html
新聞 『東日本大震災茨城全記録―特別報道写真集』
http://www.ibaraki-np.co.jp/books/genre.php
『心をつなぐニュース』池上彰+文藝春秋=編(文藝春秋社)東日本の地元の新聞社の記事から心温まる話をテーマ別に、1話を見開きでその新聞記事の切り抜きと共に紹介する。
〈DVD〉
DVD東日本大震災 岩手 http://p.tl/46nY
DVD東日本大震災 宮城 http://p.tl/oren
東日本大震災 宮城・石巻沿岸部の記録 DVD http://p.tl/sVt9
〈全国紙 記録〉
『朝日新聞縮刷版 東日本大震災 特別紙面集成2011.3.11~4.12』
『報道写真全記録2011.3.11-4.11 東日本大震災』(朝日新聞社)
『読売新聞特別縮刷版 東日本大震災 1か月の記録』
『東日本大震災―読売新聞報道写真集』
『東日本大震災―地震・津波・原発被災の記録 特別報道写真集』(共同通信社)
他
DVD東日本大震災 岩手 http://p.tl/46nY
DVD東日本大震災 宮城 http://p.tl/oren
東日本大震災 宮城・石巻沿岸部の記録 DVD http://p.tl/sVt9
〈全国紙 記録〉
『朝日新聞縮刷版 東日本大震災 特別紙面集成2011.3.11~4.12』
『報道写真全記録2011.3.11-4.11 東日本大震災』(朝日新聞社)
『読売新聞特別縮刷版 東日本大震災 1か月の記録』
『東日本大震災―読売新聞報道写真集』
『東日本大震災―地震・津波・原発被災の記録 特別報道写真集』(共同通信社)
他
(写真集))
『写真集 THE DAYS AFTER東日本大震災の記憶』石川梵 飛鳥新社 http://p.tl/gS6D
『東日本大震災 2011・3・11「あの日」のこと』高橋邦典 写真 ポプラ社 http://p.tl/FfnU
『TSUNAMI3・11: 東日本大震災記録写真集』豊田直巳 編 第三書館http://p.tl/ev7u
3.三陸の水産業を考える授業…東京学芸大学附属小金井小学校
朝日新聞(東京版・多摩版 6/30付)に、5年4組で行われた三陸漁業の授業が紹介された。子どもたちは、仙台出身の小倉教諭が、地元の漁協や築地の市場などに取材に電話を入れて集めた資料や、学校の近所の魚屋さんの店先で撮った写真やインタビューなど独自に入手した情報を通して学び、三陸の漁業の復興について話し合いをした。(→データベースに事例をアップ予定)
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201107050219.html
その日、畠山重篤さんと懇意の『漁師は山に木を植えました』(講談社)を書いたスギヤマカナヨさんが、新聞記事を読んで、大変うれしかったと学校まで小倉教諭に会いにきてくださっり、新刊のご本などを頂戴した。
朝日新聞(東京版・多摩版 6/30付)に、5年4組で行われた三陸漁業の授業が紹介された。子どもたちは、仙台出身の小倉教諭が、地元の漁協や築地の市場などに取材に電話を入れて集めた資料や、学校の近所の魚屋さんの店先で撮った写真やインタビューなど独自に入手した情報を通して学び、三陸の漁業の復興について話し合いをした。(→データベースに事例をアップ予定)
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201107050219.html
その日、畠山重篤さんと懇意の『漁師は山に木を植えました』(講談社)を書いたスギヤマカナヨさんが、新聞記事を読んで、大変うれしかったと学校まで小倉教諭に会いにきてくださっり、新刊のご本などを頂戴した。
さて、地元の産業・経済の復興を支援するというこの授業の話し合いの方向を、もう一度私たちも考えてみたいと思う。
たとえば、そろそろ本を送る活動は、ストップしてはどうだろう。地元の書店の営業を圧迫してはいないだろうか。送られた本の段ボールが、広いホールに山と積まれ、そこからの送り先への支分けや、本にブッカ―という透明ファイルをはり、分類してラベルをはり、本棚に並べる…送った後の作業は誰がいつやるのだろう…。もらってうれしい本とそうでない本もあるだろう。本を送るのではなく、図書カードを送れば、地元の収入になると、支援の方法を変えたところもある。
「〈できること〉と〈すべきこと〉はちがう。ほんとにすべきことを考えよう。」とは、saveMLAKという博物館・図書館・文書館・公民館の被災情報と支援情報を発信しているWebサイト(http://savemlak.jp/)のプロジェクトリーダー岡本真さんの言葉です。
たとえば、そろそろ本を送る活動は、ストップしてはどうだろう。地元の書店の営業を圧迫してはいないだろうか。送られた本の段ボールが、広いホールに山と積まれ、そこからの送り先への支分けや、本にブッカ―という透明ファイルをはり、分類してラベルをはり、本棚に並べる…送った後の作業は誰がいつやるのだろう…。もらってうれしい本とそうでない本もあるだろう。本を送るのではなく、図書カードを送れば、地元の収入になると、支援の方法を変えたところもある。
「〈できること〉と〈すべきこと〉はちがう。ほんとにすべきことを考えよう。」とは、saveMLAKという博物館・図書館・文書館・公民館の被災情報と支援情報を発信しているWebサイト(http://savemlak.jp/)のプロジェクトリーダー岡本真さんの言葉です。
4.図書委員会の活動から
1)顔の見える支援を継続的に…茨城県立水戸第二高等学校
茨城県立第二高等学校は体育館や校舎の一部が被害を受けての新学期スタートになった。にもかかわらず、図書委員会では昨年交流のあった福島県立磐城高等学校 図書委員会に連絡して、支援を申し出たところ、サテライト形式で学ぶことになった双葉高等学校の生徒が通っていることを知って、新品・あるいは新品に近い英語と国語の辞書を役30冊ほど送った。磐城高等学校図書委員会に手紙を、双葉高等学校には各学年宛のメッセージを添えたところ、磐城高等学校の図書委員会から代表して、自らも被災校であるにもかかわらず、このような行動がとれることに敬意を表しますと返事かきたという。1度きり、短期の支援ではなく、長期に継続のできる活動を考えたいと、次の企画を図書委員会では模索中である。
今回の被災地は広範囲におよび、はじめはどこから何をしていいか途方に暮れる。しかし、やはりもともとの付き合いがあったところ、何らかの縁があったところ、1対1の顔の見えるところからの支援活動から始めるのがいいのではないだろうかと、生徒たちと話し合った結果であった。(司書 勝山万里子談)
2)文化祭でエネルギーについて考えました…兵庫県立西宮今津高等学校
6月の文化祭に行われた関西地区の図書委員会の活動を紹介する。
6月の文化祭に行われた関西地区の図書委員会の活動を紹介する。

図書委員会「私たちのエネルギーと電気」文化祭展示風景
毎年、特集を組んで展示しているが、今年、図書委員長から原発にしたいという声が上がった。今取り上げることで、私たちが使っている電気の現状と新しいエネルギーを知り、これからのエネルギー問題を考える契機となり、重要な課題である。特集の担当チームで原発について取り組んだ。原発など何を取り上げるか話し合い、役割分担をして、それぞれ調べた。内容は以下の8項目で、原発・新エネルギー関係の図書を展示した。
①原子力の歴史、②原子力発電、③原子力発電のしくみ、④日本の原発の分布図、⑤身近な電気;関西電力、⑥原子力発電所事故、⑦放射性物質、⑧新エネルギーなど
展示リストDB震災事例鈴木啓子.doc
①原子力の歴史、②原子力発電、③原子力発電のしくみ、④日本の原発の分布図、⑤身近な電気;関西電力、⑥原子力発電所事故、⑦放射性物質、⑧新エネルギーなど
展示リストDB震災事例鈴木啓子.doc
5.2011年3月の校長・学長の卒業式の贈る言葉
『時に 海を見よ―これからの日本を生きる君に贈る』渡辺憲司 双葉社
2011年3月。首都圏を含む東日本の多くの学校の卒業式が中止、あるいは延期、縮小となった。中止となった立教新座高等学校の校長先生が、卒業生へのはなむけの言葉を学校ホームページに掲げて、twitterなどで話題になった。誰もが不安であった3月末。その学校の卒業生のみならず、多くの人が励まされたメッセージだった。これからの日本を生きる若者へ向けての言葉として新たに出版された。印税は全額寄付とのこと。
『これからを生きる君たちへ―校長先生からの心揺さぶるメッセージ (SHINCHO MOOK)』(新潮社)
『それでもいまは、真っ白な帆を上げよう -3.11東日本大震災後に発信された、学長からの感動メッセージ』 旺文社 編 (旺文社)
『時に 海を見よ―これからの日本を生きる君に贈る』渡辺憲司 双葉社
2011年3月。首都圏を含む東日本の多くの学校の卒業式が中止、あるいは延期、縮小となった。中止となった立教新座高等学校の校長先生が、卒業生へのはなむけの言葉を学校ホームページに掲げて、twitterなどで話題になった。誰もが不安であった3月末。その学校の卒業生のみならず、多くの人が励まされたメッセージだった。これからの日本を生きる若者へ向けての言葉として新たに出版された。印税は全額寄付とのこと。
『これからを生きる君たちへ―校長先生からの心揺さぶるメッセージ (SHINCHO MOOK)』(新潮社)
『それでもいまは、真っ白な帆を上げよう -3.11東日本大震災後に発信された、学長からの感動メッセージ』 旺文社 編 (旺文社)
4ヶ月たった今、もう一度、あのときかみしめた言葉と出会いなおしてみたいと思う。
(東京学芸大学附属小金井小学校 司書 中山美由紀)