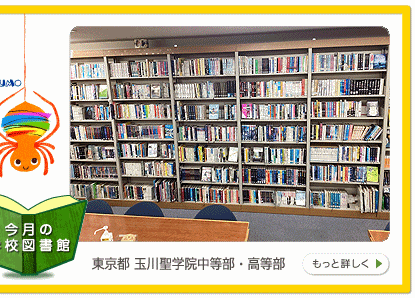お知らせ
みんなで学ぼう!学校司書講座2025は、7月30日(水)、31日(木)の両日開催します。
7月30日 オンライン講座「生成AIと著作権」 講師 原口直氏(著作権アドバイザー)
7月31日 対面講座 「これからの学校図書館」 講師 吉田右子氏(筑波大学教授)
学校司書講座2025は、I Dig Eduを窓口に募集をします。講座名をクリックすると申し込み画面に飛びます。初めての方はアカウントの作成をお願いします。両講座とも参加費は無料です。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
新着案内
「今月の学校図書館」は玉川聖学院中等部・高等部です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0018 校種 特別支援 教科・領域等 その他 単元 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料案内 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) マルチ・メディア・デイジー図書とは、どのようなものですか? 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教員研修・司書研修・初任者研修をおこなった。
日本障害者リハビリテーション協会HPには以下のように書いてある。 (参照:2009.12.09)
「DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されています。
ここ数年来、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためにカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム(本部スイス)により開発と維持が行なわれている情報システムを表しています。
中略
DAISYが視覚障害者のほかに学習障害、知的障害、精神障害の方にとっても有効であることが国際的に広く認められてきています。例えばアメリカやスウェーデンの録音図書館などではディスレクシアへの録音図書のサービスが行われています。
マルチメディア化したDAISY図書は、音声にテキストおよび画像を同時に表示しますので
ユーザーは音声を聞きながらハイライトされたテキストを読み、同じ画面上で絵をみることもできます。」
コンピュータを操作できるようになったら、読めるので対象は高学年以上になるだろう。
年齢の低い子どもには、タッチパネル式で対応することもできる。
以下、代表的なものを紹介する。
提示資料 マルチ・メディア・デイジー図書 
『おはよう・おやすみ 』
布絵本作者:渡辺 順子
DAISY版・文:野村 美佐子
資料種別:マルチメディアDAISY
朗読: おかあさん編 ありた ゆうこ
こども編 いしかわ めぐみ
製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会
製作年:2009年8月
附属特別支援学校では布絵本の研修も行った。
このデイジー図書は、布絵本をどのように読み聞かせていくかが、
画像と朗読によって理解しやすい。
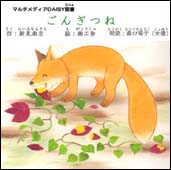
ごんぎつね 価格
著者名:新美南吉
資料種別:マルチメディアDAISY
絵:画工舎
朗読:森口瑤子
製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会
製作年:2004年
小学校4年生国語の共通教材になっている作品のデイジー化。
学習のために、50数種のデイジー教科書も出来ている。
それらを必要とする子ども〈代理申請可能)が申請すれば、
送料とCD代だけで送ってもらうことが出来る。
詳細は、日本障害者リハビリテーション協会に問い合わせされたい。 
著者名:ロッタ・ソールセン(文),ビョーン・アーベリン(写真),
中村冬美(訳),相良麻里子(朗読)
出版者:(財)日本障害者リハビリテーション協会
出版年:2006年6月
『赤いハイヒール』は、知的障害のある若い女性の恋のお話で、シンプルに理解しや
すい文章で構成されている。
また「障害」のある人たちとその親の思いや、自立への強い願いが「赤いハイヒー
ル」によって象徴的に描かれている。
原作は、スウェーデンで、1994年に「読みやすい図書基金」より出版された「読みや
すい図書」である。
「わかりやすい・読みやすい」ということを念頭におき、イラストや写真の構成、レ
イアウト、文字の大きさ、ストーリー構成、語彙などに様々な工夫がなされている。
日本での翻訳出版にあたっては、わかりやすくするために様々な工夫がほどこされて
いる原作を意識して、漢字にルビをつけ、わかりやすい言葉を選び、マルチメディア
DAISYのCD-ROMを付けた。
((財)日本障害者リハビリテーション協会より)
参考資料(含HP) http://www.jsrpd.jp/ 参考資料リンク http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/ ブックリスト
キーワード1 特別支援 キーワード2 ディスレクシア キーワード3 マルチ・メディア・デイジー図書 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 授業者コメント デイジー図書の対象者は、知的レベルは比較的高い子どもがつかえるだろう。特別支援学校というよりも、特別支援学級などの方がニーズが高いのではないだろうか。
(附属特別支援学校 教員談) 司書・司書教諭コメント 初任研では、帰国子女を持つ国際中等教育学校の先生から、日本語で学習していくことに不安を持つ子どもたちの学習に、デイジー図書が役に立つ可能性もあるとの示唆をもらった。
LDなど特別なニーズを必要とする子どもは普通学級にもいる可能性があり、学校図書館員にとっても、必須の図書資料として認識していく必要があると思われる。
養護教諭が、特別なニーズを必要とする子どもを把握しているので、担任、教科教諭、特別支援教育コーディネーターとも連携・協力できるとよい。
参照 http://www.nhk.or.jp/heart-net/fnet/arch/tue/50524.html 情報提供校 学校図書館運営専門委員会 事例作成日 2009.11.26 事例作成者氏名
記入者:中山
カウンタ
3192075 : 2010年9月14日より
みんなで学ぼう!学校司書講座2025は、7月30日(水)、31日(木)の両日開催します。
7月30日 オンライン講座「生成AIと著作権」 講師 原口直氏(著作権アドバイザー)
7月31日 対面講座 「これからの学校図書館」 講師 吉田右子氏(筑波大学教授)
学校司書講座2025は、I Dig Eduを窓口に募集をします。講座名をクリックすると申し込み画面に飛びます。初めての方はアカウントの作成をお願いします。両講座とも参加費は無料です。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
「今月の学校図書館」は玉川聖学院中等部・高等部です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0018 校種 特別支援 教科・領域等 その他 単元 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料案内 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) マルチ・メディア・デイジー図書とは、どのようなものですか? 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教員研修・司書研修・初任者研修をおこなった。
日本障害者リハビリテーション協会HPには以下のように書いてある。 (参照:2009.12.09)
「DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されています。
ここ数年来、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためにカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム(本部スイス)により開発と維持が行なわれている情報システムを表しています。
中略
DAISYが視覚障害者のほかに学習障害、知的障害、精神障害の方にとっても有効であることが国際的に広く認められてきています。例えばアメリカやスウェーデンの録音図書館などではディスレクシアへの録音図書のサービスが行われています。
マルチメディア化したDAISY図書は、音声にテキストおよび画像を同時に表示しますので
ユーザーは音声を聞きながらハイライトされたテキストを読み、同じ画面上で絵をみることもできます。」
コンピュータを操作できるようになったら、読めるので対象は高学年以上になるだろう。
年齢の低い子どもには、タッチパネル式で対応することもできる。
以下、代表的なものを紹介する。
提示資料 マルチ・メディア・デイジー図書 
『おはよう・おやすみ 』
布絵本作者:渡辺 順子
DAISY版・文:野村 美佐子
資料種別:マルチメディアDAISY
朗読: おかあさん編 ありた ゆうこ
こども編 いしかわ めぐみ
製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会
製作年:2009年8月
附属特別支援学校では布絵本の研修も行った。
このデイジー図書は、布絵本をどのように読み聞かせていくかが、
画像と朗読によって理解しやすい。
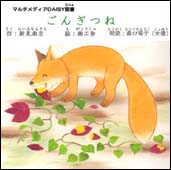
ごんぎつね 価格
著者名:新美南吉
資料種別:マルチメディアDAISY
絵:画工舎
朗読:森口瑤子
製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会
製作年:2004年
小学校4年生国語の共通教材になっている作品のデイジー化。
学習のために、50数種のデイジー教科書も出来ている。
それらを必要とする子ども〈代理申請可能)が申請すれば、
送料とCD代だけで送ってもらうことが出来る。
詳細は、日本障害者リハビリテーション協会に問い合わせされたい。 
著者名:ロッタ・ソールセン(文),ビョーン・アーベリン(写真),
中村冬美(訳),相良麻里子(朗読)
出版者:(財)日本障害者リハビリテーション協会
出版年:2006年6月
『赤いハイヒール』は、知的障害のある若い女性の恋のお話で、シンプルに理解しや
すい文章で構成されている。
また「障害」のある人たちとその親の思いや、自立への強い願いが「赤いハイヒー
ル」によって象徴的に描かれている。
原作は、スウェーデンで、1994年に「読みやすい図書基金」より出版された「読みや
すい図書」である。
「わかりやすい・読みやすい」ということを念頭におき、イラストや写真の構成、レ
イアウト、文字の大きさ、ストーリー構成、語彙などに様々な工夫がなされている。
日本での翻訳出版にあたっては、わかりやすくするために様々な工夫がほどこされて
いる原作を意識して、漢字にルビをつけ、わかりやすい言葉を選び、マルチメディア
DAISYのCD-ROMを付けた。
((財)日本障害者リハビリテーション協会より)
参考資料(含HP) http://www.jsrpd.jp/ 参考資料リンク http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/ ブックリスト
キーワード1 特別支援 キーワード2 ディスレクシア キーワード3 マルチ・メディア・デイジー図書 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 授業者コメント デイジー図書の対象者は、知的レベルは比較的高い子どもがつかえるだろう。特別支援学校というよりも、特別支援学級などの方がニーズが高いのではないだろうか。
(附属特別支援学校 教員談) 司書・司書教諭コメント 初任研では、帰国子女を持つ国際中等教育学校の先生から、日本語で学習していくことに不安を持つ子どもたちの学習に、デイジー図書が役に立つ可能性もあるとの示唆をもらった。
LDなど特別なニーズを必要とする子どもは普通学級にもいる可能性があり、学校図書館員にとっても、必須の図書資料として認識していく必要があると思われる。
養護教諭が、特別なニーズを必要とする子どもを把握しているので、担任、教科教諭、特別支援教育コーディネーターとも連携・協力できるとよい。
参照 http://www.nhk.or.jp/heart-net/fnet/arch/tue/50524.html 情報提供校 学校図書館運営専門委員会 事例作成日 2009.11.26 事例作成者氏名
記入者:中山
カウンタ
3192075 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0018 |
|---|---|
| 校種 | 特別支援 |
| 教科・領域等 | その他 |
| 単元 | |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料案内 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | マルチ・メディア・デイジー図書とは、どのようなものですか? |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 教員研修・司書研修・初任者研修をおこなった。 日本障害者リハビリテーション協会HPには以下のように書いてある。 (参照:2009.12.09) 「DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、日本では「アクセシブルな情報システム」と訳されています。 ここ数年来、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のためにカセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として、50カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアム(本部スイス)により開発と維持が行なわれている情報システムを表しています。 中略 DAISYが視覚障害者のほかに学習障害、知的障害、精神障害の方にとっても有効であることが国際的に広く認められてきています。例えばアメリカやスウェーデンの録音図書館などではディスレクシアへの録音図書のサービスが行われています。 マルチメディア化したDAISY図書は、音声にテキストおよび画像を同時に表示しますので ユーザーは音声を聞きながらハイライトされたテキストを読み、同じ画面上で絵をみることもできます。」 コンピュータを操作できるようになったら、読めるので対象は高学年以上になるだろう。 年齢の低い子どもには、タッチパネル式で対応することもできる。 以下、代表的なものを紹介する。 |
| 提示資料 | マルチ・メディア・デイジー図書 |
 | 『おはよう・おやすみ 』 布絵本作者:渡辺 順子 DAISY版・文:野村 美佐子 資料種別:マルチメディアDAISY 朗読: おかあさん編 ありた ゆうこ こども編 いしかわ めぐみ 製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会 製作年:2009年8月 附属特別支援学校では布絵本の研修も行った。 このデイジー図書は、布絵本をどのように読み聞かせていくかが、 画像と朗読によって理解しやすい。 |
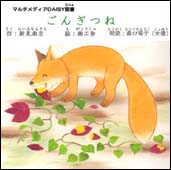 | ごんぎつね 価格 著者名:新美南吉 資料種別:マルチメディアDAISY 絵:画工舎 朗読:森口瑤子 製作:(財)日本障害者リハビリテーション協会 製作年:2004年 小学校4年生国語の共通教材になっている作品のデイジー化。 学習のために、50数種のデイジー教科書も出来ている。 それらを必要とする子ども〈代理申請可能)が申請すれば、 送料とCD代だけで送ってもらうことが出来る。 詳細は、日本障害者リハビリテーション協会に問い合わせされたい。 |
 | 著者名:ロッタ・ソールセン(文),ビョーン・アーベリン(写真), 中村冬美(訳),相良麻里子(朗読) 出版者:(財)日本障害者リハビリテーション協会 出版年:2006年6月 『赤いハイヒール』は、知的障害のある若い女性の恋のお話で、シンプルに理解しや すい文章で構成されている。 また「障害」のある人たちとその親の思いや、自立への強い願いが「赤いハイヒー ル」によって象徴的に描かれている。 原作は、スウェーデンで、1994年に「読みやすい図書基金」より出版された「読みや すい図書」である。 「わかりやすい・読みやすい」ということを念頭におき、イラストや写真の構成、レ イアウト、文字の大きさ、ストーリー構成、語彙などに様々な工夫がなされている。 日本での翻訳出版にあたっては、わかりやすくするために様々な工夫がほどこされて いる原作を意識して、漢字にルビをつけ、わかりやすい言葉を選び、マルチメディア DAISYのCD-ROMを付けた。 ((財)日本障害者リハビリテーション協会より) |
| 参考資料(含HP) | http://www.jsrpd.jp/ |
| 参考資料リンク | http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/ |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 特別支援 |
| キーワード2 | ディスレクシア |
| キーワード3 | マルチ・メディア・デイジー図書 |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | |
| 授業者コメント | デイジー図書の対象者は、知的レベルは比較的高い子どもがつかえるだろう。特別支援学校というよりも、特別支援学級などの方がニーズが高いのではないだろうか。 (附属特別支援学校 教員談) |
| 司書・司書教諭コメント | 初任研では、帰国子女を持つ国際中等教育学校の先生から、日本語で学習していくことに不安を持つ子どもたちの学習に、デイジー図書が役に立つ可能性もあるとの示唆をもらった。 LDなど特別なニーズを必要とする子どもは普通学級にもいる可能性があり、学校図書館員にとっても、必須の図書資料として認識していく必要があると思われる。 養護教諭が、特別なニーズを必要とする子どもを把握しているので、担任、教科教諭、特別支援教育コーディネーターとも連携・協力できるとよい。 参照 http://www.nhk.or.jp/heart-net/fnet/arch/tue/50524.html |
| 情報提供校 | 学校図書館運営専門委員会 |
| 事例作成日 | 2009.11.26 |
| 事例作成者氏名 |
記入者:中山