お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0229 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 くらしの中に伝わる願い (2)むかしのくらし、今のくらし 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 昔のくらしの学習をしているが、洗濯板の出ている資料がほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 班ごとに昔の暮らし体験をして調べるので、少しの記述や写真でも資料は多くほしい。
提示資料 
『新版 昔のくらしの道具事典』 小林克 神野善治 監修 岩崎書店 2014年 洗濯板と盥(たらい)が大きく写真で紹介されている。「洗濯板の使い方」「きざみ目」の上下の効用(これは今回の新版に付け加わったところ)と洗濯機の進化がコンパクトに紹介されている。 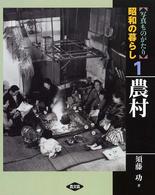
『写真ものがたり 昭和の暮らし1 農村』須藤功著 農山漁村文化協会 2004年 「洗濯板でこすって洗う」という項で、盥と洗濯板をつかって洗濯する婦人の写真がある。また、同じシリーズの 『写真ものがたり 昭和の暮らし9 技と知恵』(須藤功著 農山漁村文化協会 2007年)では、 「洗い流す」という項で、洗濯板やバケツでの洗濯、小川でのすすぎを紹介する。 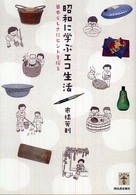
『昭和に学ぶエコ生活 日本らしさにヒントを探る』(市橋芳則 河出書房新社 2008年) 著者は愛知県の北名古屋市歴史民族資料館「昭和日常博物館」学芸員である。「洗濯の心得」という項で、洗濯料や洗濯術を紹介するが、洗濯板の使い方のほか、日本、日本の今風、イギリス、中国、韓国の洗濯板についてコラムで紹介しているのがめずらしい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 昔のくらし(洗濯)ブックリスト 小4社会 2015年.xlsx
キーワード1 昔の暮らし キーワード2 洗濯板 キーワード3 体験 授業計画・指導案等 昔の暮らし 小4社会 2012.pdf 児童・生徒の作品 授業者 牧岡俊夫 授業者コメント この小単元の学習のねらいは、むかしの道具を調べて道具の使い方が分かり、その道具を使えるようになることではありません。昔の道具を調べることで、その道具を使っていた時代の人々の暮らしについて理解することが大切です。また、むかしの道具の使い方や人々の暮らしについて調べると、子どもたちは、現在の暮らしと比べて、往々にして「むかしは不便だった。」とか「むかしの人々は大変な生活をしていた。」などといった考えをもつこともあります。確かに、現在の物質文明の中での生活に比べたら、むかしの生活は、不便で大変かもしれません。しかし、学習を通して便利か不便かを考えるのではなく、「いつの時代の人々も、工夫や努力を重ね、自分たちの生活を向上させてきた」ことに気付かせることも大切です。
そのためには、むかしの道具を使っていた人々の心情やむかしの道具に込められた工夫、その道具を使う以前の生活などについて、調べたり考えたりする学習活動を行いたいと計画しました。そこで、具体的にむかしの道具について、児童が自分たちで調べられたり、指導者が使い方やその道具を使っていた時代の人々の暮らしについて調べたり出来る「図書資料」を学校図書館で探しました。そこで見つけたこれらの図書を参考に、調べ活動・体験的な活動・努力や工夫について考える活動などを組み込み、単元の学習を構成しました。
実際の学習活動では、昔の道具を調べ、その道具を使っていた人の心情を考えたり、洗濯板での洗濯を体験的に行い、洗濯板で洗濯をしていた人の気持ちを実感したりできました。昔の道具に込められた目に見える工夫や技だけでなく、目に見えない人々の気持ちや当時の暮らしについても学ぶことができました。
司書・司書教諭コメント 洗濯板のでてくる資料として、「生活」「家庭生活」「衣服」「くらし」などのキーワードから、本を探した。関連キーワードとして「家電」「洗濯機」も加えた。事典としてポプラ社や岩崎書店の参考図書は基本を押さえる事ができる。洗濯板が写っている写真があっても「きざみ目」の解説までしてあるものは、そう多くはないが、イメージをつかむことはできたのではないかと思う。小学4年生には難しいと思われる「らんぷの本」のシリーズもあるが、写真で理解もできるし、コラムは理解しやすいのでいれることにした。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 事例作成 2015年6月23日 / 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校 牧岡俊夫教諭 中山美由紀司書
記入者:中山(主担)
カウンタ
3146120 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0229 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 くらしの中に伝わる願い (2)むかしのくらし、今のくらし 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 昔のくらしの学習をしているが、洗濯板の出ている資料がほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 班ごとに昔の暮らし体験をして調べるので、少しの記述や写真でも資料は多くほしい。
提示資料 
『新版 昔のくらしの道具事典』 小林克 神野善治 監修 岩崎書店 2014年 洗濯板と盥(たらい)が大きく写真で紹介されている。「洗濯板の使い方」「きざみ目」の上下の効用(これは今回の新版に付け加わったところ)と洗濯機の進化がコンパクトに紹介されている。 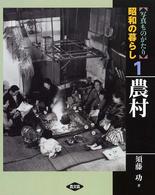
『写真ものがたり 昭和の暮らし1 農村』須藤功著 農山漁村文化協会 2004年 「洗濯板でこすって洗う」という項で、盥と洗濯板をつかって洗濯する婦人の写真がある。また、同じシリーズの 『写真ものがたり 昭和の暮らし9 技と知恵』(須藤功著 農山漁村文化協会 2007年)では、 「洗い流す」という項で、洗濯板やバケツでの洗濯、小川でのすすぎを紹介する。 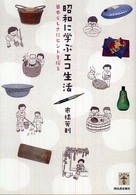
『昭和に学ぶエコ生活 日本らしさにヒントを探る』(市橋芳則 河出書房新社 2008年) 著者は愛知県の北名古屋市歴史民族資料館「昭和日常博物館」学芸員である。「洗濯の心得」という項で、洗濯料や洗濯術を紹介するが、洗濯板の使い方のほか、日本、日本の今風、イギリス、中国、韓国の洗濯板についてコラムで紹介しているのがめずらしい。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 昔のくらし(洗濯)ブックリスト 小4社会 2015年.xlsx
キーワード1 昔の暮らし キーワード2 洗濯板 キーワード3 体験 授業計画・指導案等 昔の暮らし 小4社会 2012.pdf 児童・生徒の作品 授業者 牧岡俊夫 授業者コメント この小単元の学習のねらいは、むかしの道具を調べて道具の使い方が分かり、その道具を使えるようになることではありません。昔の道具を調べることで、その道具を使っていた時代の人々の暮らしについて理解することが大切です。また、むかしの道具の使い方や人々の暮らしについて調べると、子どもたちは、現在の暮らしと比べて、往々にして「むかしは不便だった。」とか「むかしの人々は大変な生活をしていた。」などといった考えをもつこともあります。確かに、現在の物質文明の中での生活に比べたら、むかしの生活は、不便で大変かもしれません。しかし、学習を通して便利か不便かを考えるのではなく、「いつの時代の人々も、工夫や努力を重ね、自分たちの生活を向上させてきた」ことに気付かせることも大切です。
そのためには、むかしの道具を使っていた人々の心情やむかしの道具に込められた工夫、その道具を使う以前の生活などについて、調べたり考えたりする学習活動を行いたいと計画しました。そこで、具体的にむかしの道具について、児童が自分たちで調べられたり、指導者が使い方やその道具を使っていた時代の人々の暮らしについて調べたり出来る「図書資料」を学校図書館で探しました。そこで見つけたこれらの図書を参考に、調べ活動・体験的な活動・努力や工夫について考える活動などを組み込み、単元の学習を構成しました。
実際の学習活動では、昔の道具を調べ、その道具を使っていた人の心情を考えたり、洗濯板での洗濯を体験的に行い、洗濯板で洗濯をしていた人の気持ちを実感したりできました。昔の道具に込められた目に見える工夫や技だけでなく、目に見えない人々の気持ちや当時の暮らしについても学ぶことができました。
司書・司書教諭コメント 洗濯板のでてくる資料として、「生活」「家庭生活」「衣服」「くらし」などのキーワードから、本を探した。関連キーワードとして「家電」「洗濯機」も加えた。事典としてポプラ社や岩崎書店の参考図書は基本を押さえる事ができる。洗濯板が写っている写真があっても「きざみ目」の解説までしてあるものは、そう多くはないが、イメージをつかむことはできたのではないかと思う。小学4年生には難しいと思われる「らんぷの本」のシリーズもあるが、写真で理解もできるし、コラムは理解しやすいのでいれることにした。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 事例作成 2015年6月23日 / 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校 牧岡俊夫教諭 中山美由紀司書
記入者:中山(主担)
カウンタ
3146120 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0229 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | くらしの中に伝わる願い (2)むかしのくらし、今のくらし |
| 対象学年 | 中学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 昔のくらしの学習をしているが、洗濯板の出ている資料がほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 班ごとに昔の暮らし体験をして調べるので、少しの記述や写真でも資料は多くほしい。 |
| 提示資料 | |
 | 『新版 昔のくらしの道具事典』 小林克 神野善治 監修 岩崎書店 2014年 洗濯板と盥(たらい)が大きく写真で紹介されている。「洗濯板の使い方」「きざみ目」の上下の効用(これは今回の新版に付け加わったところ)と洗濯機の進化がコンパクトに紹介されている。 |
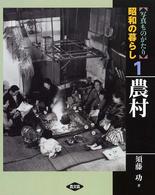 | 『写真ものがたり 昭和の暮らし1 農村』須藤功著 農山漁村文化協会 2004年 「洗濯板でこすって洗う」という項で、盥と洗濯板をつかって洗濯する婦人の写真がある。また、同じシリーズの 『写真ものがたり 昭和の暮らし9 技と知恵』(須藤功著 農山漁村文化協会 2007年)では、 「洗い流す」という項で、洗濯板やバケツでの洗濯、小川でのすすぎを紹介する。 |
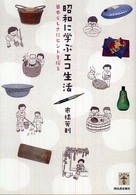 | 『昭和に学ぶエコ生活 日本らしさにヒントを探る』(市橋芳則 河出書房新社 2008年) 著者は愛知県の北名古屋市歴史民族資料館「昭和日常博物館」学芸員である。「洗濯の心得」という項で、洗濯料や洗濯術を紹介するが、洗濯板の使い方のほか、日本、日本の今風、イギリス、中国、韓国の洗濯板についてコラムで紹介しているのがめずらしい。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 昔のくらし(洗濯)ブックリスト 小4社会 2015年.xlsx |
| キーワード1 | 昔の暮らし |
| キーワード2 | 洗濯板 |
| キーワード3 | 体験 |
| 授業計画・指導案等 | 昔の暮らし 小4社会 2012.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 牧岡俊夫 |
| 授業者コメント | この小単元の学習のねらいは、むかしの道具を調べて道具の使い方が分かり、その道具を使えるようになることではありません。昔の道具を調べることで、その道具を使っていた時代の人々の暮らしについて理解することが大切です。また、むかしの道具の使い方や人々の暮らしについて調べると、子どもたちは、現在の暮らしと比べて、往々にして「むかしは不便だった。」とか「むかしの人々は大変な生活をしていた。」などといった考えをもつこともあります。確かに、現在の物質文明の中での生活に比べたら、むかしの生活は、不便で大変かもしれません。しかし、学習を通して便利か不便かを考えるのではなく、「いつの時代の人々も、工夫や努力を重ね、自分たちの生活を向上させてきた」ことに気付かせることも大切です。 そのためには、むかしの道具を使っていた人々の心情やむかしの道具に込められた工夫、その道具を使う以前の生活などについて、調べたり考えたりする学習活動を行いたいと計画しました。そこで、具体的にむかしの道具について、児童が自分たちで調べられたり、指導者が使い方やその道具を使っていた時代の人々の暮らしについて調べたり出来る「図書資料」を学校図書館で探しました。そこで見つけたこれらの図書を参考に、調べ活動・体験的な活動・努力や工夫について考える活動などを組み込み、単元の学習を構成しました。 実際の学習活動では、昔の道具を調べ、その道具を使っていた人の心情を考えたり、洗濯板での洗濯を体験的に行い、洗濯板で洗濯をしていた人の気持ちを実感したりできました。昔の道具に込められた目に見える工夫や技だけでなく、目に見えない人々の気持ちや当時の暮らしについても学ぶことができました。 |
| 司書・司書教諭コメント | 洗濯板のでてくる資料として、「生活」「家庭生活」「衣服」「くらし」などのキーワードから、本を探した。関連キーワードとして「家電」「洗濯機」も加えた。事典としてポプラ社や岩崎書店の参考図書は基本を押さえる事ができる。洗濯板が写っている写真があっても「きざみ目」の解説までしてあるものは、そう多くはないが、イメージをつかむことはできたのではないかと思う。小学4年生には難しいと思われる「らんぷの本」のシリーズもあるが、写真で理解もできるし、コラムは理解しやすいのでいれることにした。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2015年6月23日 / |
| 事例作成者氏名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 牧岡俊夫教諭 中山美由紀司書 |
記入者:中山(主担)

























