お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0227 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 詩 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 詩の学習の後に、詩集をまるごと読ませたい 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教科書では一人の作家の詩は一篇ごとに出てくるが、詩集としてまとまって読むとまた印象が違う。色々な作家の詩集を読み、詩人の持つ世界を味わう活動をさせたいとのこと。
司書が『読書へのアニマシオン 75の作戦』(M・M・サルト著 柏書房)の作戦68「詩を持ってきました」を参考に、各自が一つ詩集を選び、その中から選んだ一篇をグループ内で読みあい、投票することを提案した。
授業では選んだ一篇に各自付箋を貼ってグループで読みあい、「額に入れておきたい詩」一篇を選んで一人一枚シールを貼るようにと指示があった。
提示資料 色々な作家のアンソロジーではなく、作家個人の詩集か、作家ごとのアンソロジーを約100冊準備した。以下の三冊はグループ内で一番票の集まった詩集から。 
『現代詩文庫14 吉岡実詩集』 思潮社 1968年
古いものですが、教科書などで名前が出てくる詩人のものなどもあり、手に取っている生徒も多かったです。 
『すこやかに おだやかに しなやかに』 谷川俊太郎 佼成出版社 2006年
谷川俊太郎さんにはなじみがあるせいか、選んだ生徒も多かったです。 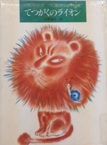
『工藤直子少年詩集 てつがくのライオン』 理論社 1982年
子ども向けの詩のシリーズ「詩の散歩道」の一冊です。詩を読みなれない生徒にも読みやすかったようです。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 詩 キーワード2 詩集 キーワード3 授業計画・指導案等 私の選んだ一篇.pdf 児童・生徒の作品 授業者 秋吉英理子 授業者コメント 多くの生徒は詩に対して抵抗がなく、すぐに選んでいました。歌の歌詞等で馴染んでいるということもあるのかもしれません。詩集の読み方がわからない生徒も、他の生徒が読んでいる姿を見ながら、たくさんの詩集に触れることで、一つでも気になる詩を見つけ、詩のリズムや言葉の取り合わせなどを楽しむ体験ができたのではないでしょうか。
机二つに、表紙を見せるように詩集を広げてもらった光景は迫力がありました。表紙を見て、本の装丁などからも選んでいたようです。
授業時間が一時間だったので長い詩は選ばれにくかったようですが、生徒は良い詩に付箋を貼っていたと思います。付箋にシールを貼って投票するという形でみんなにシェアする形にしたことで、楽しんでゲーム感覚で選ぶことができました。
一グループ6人程度だったので、時間があればもう少し多く10人程度のグループで選ばせてもよかったかもしれません。
選んだ詩の展示もしてもらえ、生徒も嬉しかったと思います。 司書・司書教諭コメント 授業の後に、班ごとに生徒の選んだ詩を図書館に展示しました。普段は手に取られにくい詩集ですが、展示したことで授業に参加した生徒はもちろん、多くの生徒が読んでいました。
生徒が選んだ詩も現代詩文庫、少年詩集、現代の詩人の詩集などバラエティに富んでいました。 情報提供校 東京都立狛江高等学校 事例作成日 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2014年3月 事例作成者氏名 千田つばさ
記入者:千田
カウンタ
3106405 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0227 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 詩 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 詩の学習の後に、詩集をまるごと読ませたい 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教科書では一人の作家の詩は一篇ごとに出てくるが、詩集としてまとまって読むとまた印象が違う。色々な作家の詩集を読み、詩人の持つ世界を味わう活動をさせたいとのこと。
司書が『読書へのアニマシオン 75の作戦』(M・M・サルト著 柏書房)の作戦68「詩を持ってきました」を参考に、各自が一つ詩集を選び、その中から選んだ一篇をグループ内で読みあい、投票することを提案した。
授業では選んだ一篇に各自付箋を貼ってグループで読みあい、「額に入れておきたい詩」一篇を選んで一人一枚シールを貼るようにと指示があった。
提示資料 色々な作家のアンソロジーではなく、作家個人の詩集か、作家ごとのアンソロジーを約100冊準備した。以下の三冊はグループ内で一番票の集まった詩集から。 
『現代詩文庫14 吉岡実詩集』 思潮社 1968年
古いものですが、教科書などで名前が出てくる詩人のものなどもあり、手に取っている生徒も多かったです。 
『すこやかに おだやかに しなやかに』 谷川俊太郎 佼成出版社 2006年
谷川俊太郎さんにはなじみがあるせいか、選んだ生徒も多かったです。 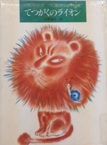
『工藤直子少年詩集 てつがくのライオン』 理論社 1982年
子ども向けの詩のシリーズ「詩の散歩道」の一冊です。詩を読みなれない生徒にも読みやすかったようです。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 詩 キーワード2 詩集 キーワード3 授業計画・指導案等 私の選んだ一篇.pdf 児童・生徒の作品 授業者 秋吉英理子 授業者コメント 多くの生徒は詩に対して抵抗がなく、すぐに選んでいました。歌の歌詞等で馴染んでいるということもあるのかもしれません。詩集の読み方がわからない生徒も、他の生徒が読んでいる姿を見ながら、たくさんの詩集に触れることで、一つでも気になる詩を見つけ、詩のリズムや言葉の取り合わせなどを楽しむ体験ができたのではないでしょうか。
机二つに、表紙を見せるように詩集を広げてもらった光景は迫力がありました。表紙を見て、本の装丁などからも選んでいたようです。
授業時間が一時間だったので長い詩は選ばれにくかったようですが、生徒は良い詩に付箋を貼っていたと思います。付箋にシールを貼って投票するという形でみんなにシェアする形にしたことで、楽しんでゲーム感覚で選ぶことができました。
一グループ6人程度だったので、時間があればもう少し多く10人程度のグループで選ばせてもよかったかもしれません。
選んだ詩の展示もしてもらえ、生徒も嬉しかったと思います。 司書・司書教諭コメント 授業の後に、班ごとに生徒の選んだ詩を図書館に展示しました。普段は手に取られにくい詩集ですが、展示したことで授業に参加した生徒はもちろん、多くの生徒が読んでいました。
生徒が選んだ詩も現代詩文庫、少年詩集、現代の詩人の詩集などバラエティに富んでいました。 情報提供校 東京都立狛江高等学校 事例作成日 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2014年3月 事例作成者氏名 千田つばさ
記入者:千田
カウンタ
3106405 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0227 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 詩 |
| 対象学年 | 高1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 詩の学習の後に、詩集をまるごと読ませたい |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 教科書では一人の作家の詩は一篇ごとに出てくるが、詩集としてまとまって読むとまた印象が違う。色々な作家の詩集を読み、詩人の持つ世界を味わう活動をさせたいとのこと。 司書が『読書へのアニマシオン 75の作戦』(M・M・サルト著 柏書房)の作戦68「詩を持ってきました」を参考に、各自が一つ詩集を選び、その中から選んだ一篇をグループ内で読みあい、投票することを提案した。 授業では選んだ一篇に各自付箋を貼ってグループで読みあい、「額に入れておきたい詩」一篇を選んで一人一枚シールを貼るようにと指示があった。 |
| 提示資料 | 色々な作家のアンソロジーではなく、作家個人の詩集か、作家ごとのアンソロジーを約100冊準備した。以下の三冊はグループ内で一番票の集まった詩集から。 |
 | 『現代詩文庫14 吉岡実詩集』 思潮社 1968年 古いものですが、教科書などで名前が出てくる詩人のものなどもあり、手に取っている生徒も多かったです。 |
 | 『すこやかに おだやかに しなやかに』 谷川俊太郎 佼成出版社 2006年 谷川俊太郎さんにはなじみがあるせいか、選んだ生徒も多かったです。 |
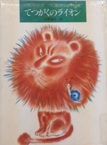 | 『工藤直子少年詩集 てつがくのライオン』 理論社 1982年 子ども向けの詩のシリーズ「詩の散歩道」の一冊です。詩を読みなれない生徒にも読みやすかったようです。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 詩 |
| キーワード2 | 詩集 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 私の選んだ一篇.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 秋吉英理子 |
| 授業者コメント | 多くの生徒は詩に対して抵抗がなく、すぐに選んでいました。歌の歌詞等で馴染んでいるということもあるのかもしれません。詩集の読み方がわからない生徒も、他の生徒が読んでいる姿を見ながら、たくさんの詩集に触れることで、一つでも気になる詩を見つけ、詩のリズムや言葉の取り合わせなどを楽しむ体験ができたのではないでしょうか。 机二つに、表紙を見せるように詩集を広げてもらった光景は迫力がありました。表紙を見て、本の装丁などからも選んでいたようです。 授業時間が一時間だったので長い詩は選ばれにくかったようですが、生徒は良い詩に付箋を貼っていたと思います。付箋にシールを貼って投票するという形でみんなにシェアする形にしたことで、楽しんでゲーム感覚で選ぶことができました。 一グループ6人程度だったので、時間があればもう少し多く10人程度のグループで選ばせてもよかったかもしれません。 選んだ詩の展示もしてもらえ、生徒も嬉しかったと思います。 |
| 司書・司書教諭コメント | 授業の後に、班ごとに生徒の選んだ詩を図書館に展示しました。普段は手に取られにくい詩集ですが、展示したことで授業に参加した生徒はもちろん、多くの生徒が読んでいました。 生徒が選んだ詩も現代詩文庫、少年詩集、現代の詩人の詩集などバラエティに富んでいました。 |
| 情報提供校 | 東京都立狛江高等学校 |
| 事例作成日 | 事例作成日 2015年3月 授業実践日 2014年3月 |
| 事例作成者氏名 | 千田つばさ |
記入者:千田

























