お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0292 校種 特別支援 教科・領域等 国語 単元 みんなで「いっぽんのせん」を書こう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ・授業支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) いっぽんのせんを描くピクトグラム絵本を紹介したいが、その後に続く活動をしたい。(学校司書からの提案) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 文字がようやく書けるようになった段階の子どもたちである。ただ、読み聞かせるだけでなく、活動につながるなんらかの工夫が必要だろう。
提示資料 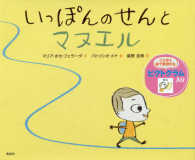
『いっぽんのせんとマヌエル』マリア・ホセ・フェラーダ/文 偕成社 2017年9月初版 「せん」が大好きな自閉症の男の子マヌエル君。みずいろの一本の線から、世界がどんどん広がっていきます。 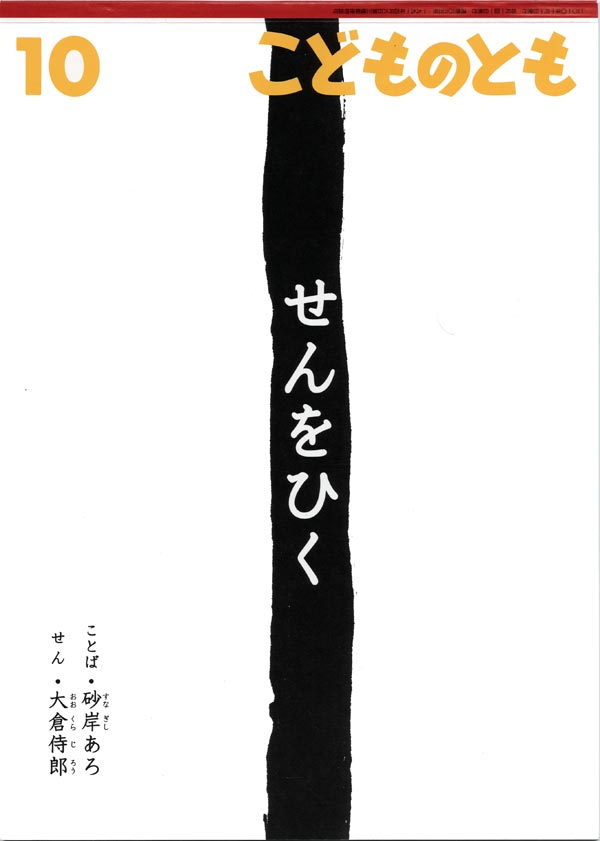
『こどものとも 2010年10月号 せんをひく』ことば・砂岸あろ せん・大倉侍郎 福音館書店 びゅーんとせんをひくからはじまり、筆でかいた くねくねした線、ぐにゅぐにゅした線 かっくんかっくんした線 など、擬態語を交えて描かれている。 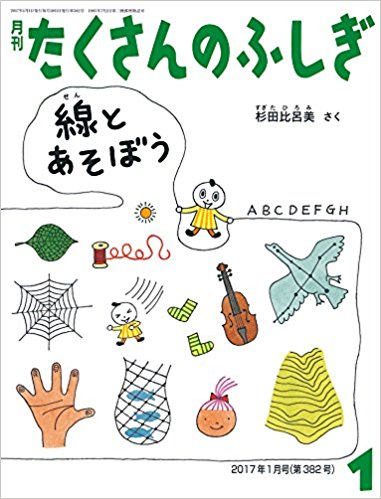
『たくさんのふしぎ 線とあそぼう』 福音館書店 私たちのまわりのあらゆるところにある線。例えば、くものす、葉っぱの葉脈、電車の路線図など。子どもも大人も、新発見がある。また、早速、身近なもので、線を探したくなるような構成である。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 名前 キーワード2 ピクトグラム絵本 キーワード3 協力 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 遠藤 祐子 授業者コメント 1人では出来なくても、みんなと一緒ならできるだろうと考え、7人全員で「いっぽんのせん」にチャレンジすることにした。友だちと一緒に取り組むことで、楽しみながら自分の思いを表現したり、発想を広げたりすることができたのではないだろうか。絵を描くことを苦手とし、何事も集中して取り組むことが、なかなか出来ない児童も、友だちが一生懸命描いている姿を見て、最後まで参加することができた。友だちの「せん(思い)」を受け取って、次の友だちへつなげていく・・・そして「いっぽんのせんと7人の仲間たち」という素敵な作品が出来上がった。こんな素晴らしい、取り組みの機会を与えてくれた『マヌエル君』に心より感謝したい。これからも、児童の表現力や発想力、想像力を広げていけるような読み聞かせの授業を考えていこうと思う。 司書・司書教諭コメント 読み聞かせをすると、ページをめくる度に「すごーい」「かわいい」等の声が上がり、絵本の主人公のマヌエルくんに親近感を感じた様子であった。もっとも反応を示したページは「せんにとりがとまる」だった。読み聞かせの後、先生の説明でマヌエルくんの水色の線をみんなで指でたどる経験をした。それが生き生きとした絵と線につながっていったと思う。「せんにとりがとまる」のページのように、水色の線と描きたいものの組み合わせを楽しめていたのだと思う。学芸大学司書教諭講習の講師として、お世話になった中山先生から示唆をいただき、また、中山先生から紹介のあった2冊を紹介した。『せんをひく』は、縦開きのページに、筆で描かれたダイナミックな線とその線にあわせた擬態語を楽しみ、ページをめくるたびに盛り上がった。『線とあそぼう』は、生活の中に、あふれている線をさがすことへのきっかけ作りとなった。 情報提供校 市川市立国分小学校 事例作成日 事例作成 2017年9月29日 /授業実践2017年9月27日 事例作成者氏名 市川市立国分小学校学校司書 多勢千夏
記入者:村上
カウンタ
3146148 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 石川県白山市立北星中学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0292 校種 特別支援 教科・領域等 国語 単元 みんなで「いっぽんのせん」を書こう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ・授業支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) いっぽんのせんを描くピクトグラム絵本を紹介したいが、その後に続く活動をしたい。(学校司書からの提案) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 文字がようやく書けるようになった段階の子どもたちである。ただ、読み聞かせるだけでなく、活動につながるなんらかの工夫が必要だろう。
提示資料 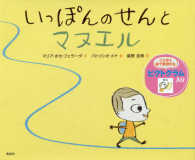
『いっぽんのせんとマヌエル』マリア・ホセ・フェラーダ/文 偕成社 2017年9月初版 「せん」が大好きな自閉症の男の子マヌエル君。みずいろの一本の線から、世界がどんどん広がっていきます。 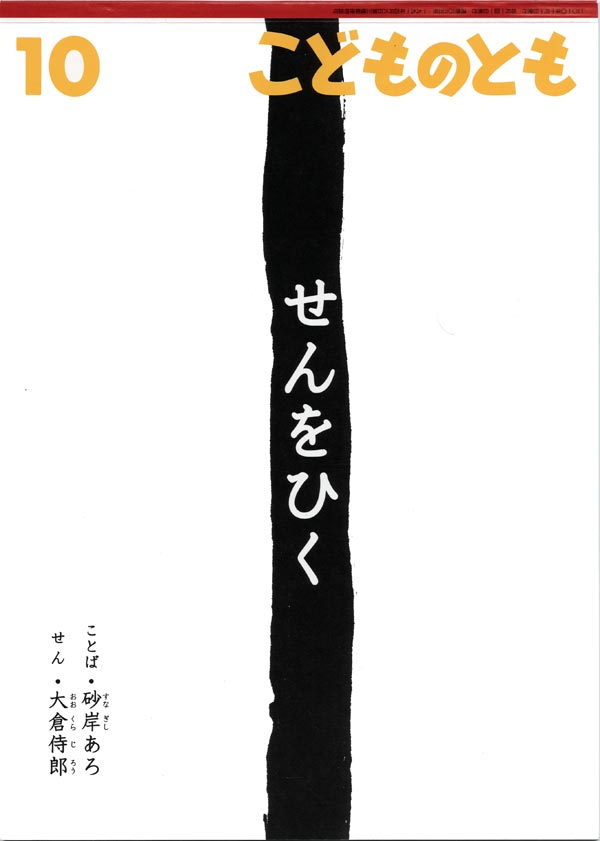
『こどものとも 2010年10月号 せんをひく』ことば・砂岸あろ せん・大倉侍郎 福音館書店 びゅーんとせんをひくからはじまり、筆でかいた くねくねした線、ぐにゅぐにゅした線 かっくんかっくんした線 など、擬態語を交えて描かれている。 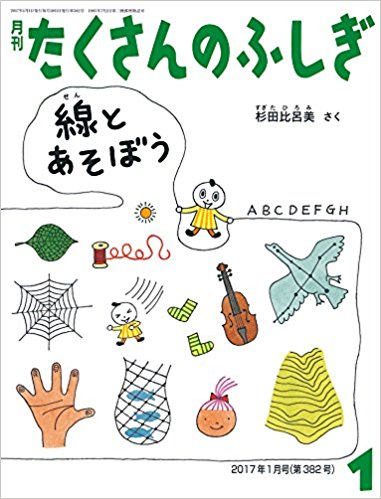
『たくさんのふしぎ 線とあそぼう』 福音館書店 私たちのまわりのあらゆるところにある線。例えば、くものす、葉っぱの葉脈、電車の路線図など。子どもも大人も、新発見がある。また、早速、身近なもので、線を探したくなるような構成である。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 名前 キーワード2 ピクトグラム絵本 キーワード3 協力 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 遠藤 祐子 授業者コメント 1人では出来なくても、みんなと一緒ならできるだろうと考え、7人全員で「いっぽんのせん」にチャレンジすることにした。友だちと一緒に取り組むことで、楽しみながら自分の思いを表現したり、発想を広げたりすることができたのではないだろうか。絵を描くことを苦手とし、何事も集中して取り組むことが、なかなか出来ない児童も、友だちが一生懸命描いている姿を見て、最後まで参加することができた。友だちの「せん(思い)」を受け取って、次の友だちへつなげていく・・・そして「いっぽんのせんと7人の仲間たち」という素敵な作品が出来上がった。こんな素晴らしい、取り組みの機会を与えてくれた『マヌエル君』に心より感謝したい。これからも、児童の表現力や発想力、想像力を広げていけるような読み聞かせの授業を考えていこうと思う。 司書・司書教諭コメント 読み聞かせをすると、ページをめくる度に「すごーい」「かわいい」等の声が上がり、絵本の主人公のマヌエルくんに親近感を感じた様子であった。もっとも反応を示したページは「せんにとりがとまる」だった。読み聞かせの後、先生の説明でマヌエルくんの水色の線をみんなで指でたどる経験をした。それが生き生きとした絵と線につながっていったと思う。「せんにとりがとまる」のページのように、水色の線と描きたいものの組み合わせを楽しめていたのだと思う。学芸大学司書教諭講習の講師として、お世話になった中山先生から示唆をいただき、また、中山先生から紹介のあった2冊を紹介した。『せんをひく』は、縦開きのページに、筆で描かれたダイナミックな線とその線にあわせた擬態語を楽しみ、ページをめくるたびに盛り上がった。『線とあそぼう』は、生活の中に、あふれている線をさがすことへのきっかけ作りとなった。 情報提供校 市川市立国分小学校 事例作成日 事例作成 2017年9月29日 /授業実践2017年9月27日 事例作成者氏名 市川市立国分小学校学校司書 多勢千夏
記入者:村上
カウンタ
3146148 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0292 |
|---|---|
| 校種 | 特別支援 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | みんなで「いっぽんのせん」を書こう |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 読み聞かせ・授業支援 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | いっぽんのせんを描くピクトグラム絵本を紹介したいが、その後に続く活動をしたい。(学校司書からの提案) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 文字がようやく書けるようになった段階の子どもたちである。ただ、読み聞かせるだけでなく、活動につながるなんらかの工夫が必要だろう。 |
| 提示資料 | |
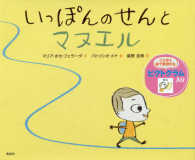 | 『いっぽんのせんとマヌエル』マリア・ホセ・フェラーダ/文 偕成社 2017年9月初版 「せん」が大好きな自閉症の男の子マヌエル君。みずいろの一本の線から、世界がどんどん広がっていきます。 |
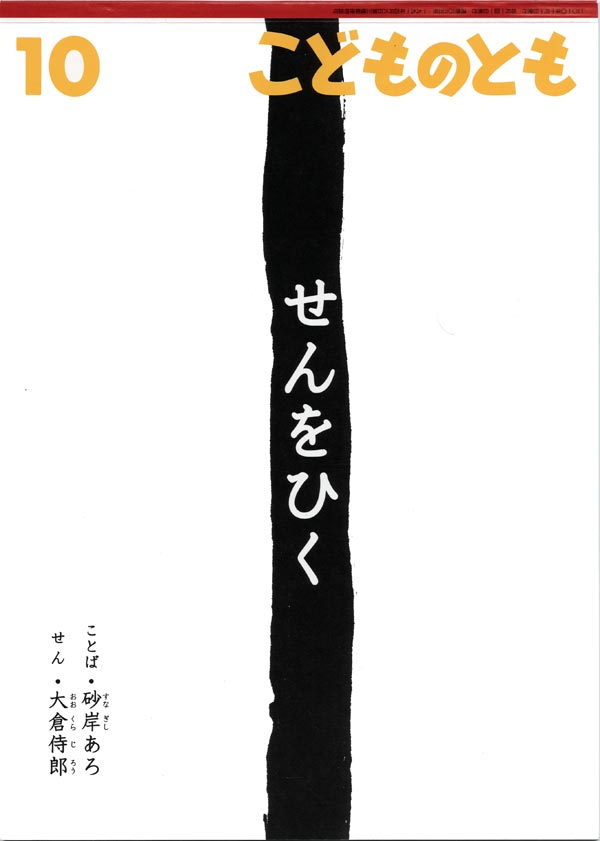 | 『こどものとも 2010年10月号 せんをひく』ことば・砂岸あろ せん・大倉侍郎 福音館書店 びゅーんとせんをひくからはじまり、筆でかいた くねくねした線、ぐにゅぐにゅした線 かっくんかっくんした線 など、擬態語を交えて描かれている。 |
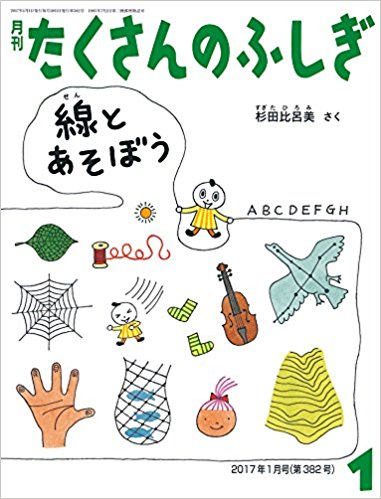 | 『たくさんのふしぎ 線とあそぼう』 福音館書店 私たちのまわりのあらゆるところにある線。例えば、くものす、葉っぱの葉脈、電車の路線図など。子どもも大人も、新発見がある。また、早速、身近なもので、線を探したくなるような構成である。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 名前 |
| キーワード2 | ピクトグラム絵本 |
| キーワード3 | 協力 |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 遠藤 祐子 |
| 授業者コメント | 1人では出来なくても、みんなと一緒ならできるだろうと考え、7人全員で「いっぽんのせん」にチャレンジすることにした。友だちと一緒に取り組むことで、楽しみながら自分の思いを表現したり、発想を広げたりすることができたのではないだろうか。絵を描くことを苦手とし、何事も集中して取り組むことが、なかなか出来ない児童も、友だちが一生懸命描いている姿を見て、最後まで参加することができた。友だちの「せん(思い)」を受け取って、次の友だちへつなげていく・・・そして「いっぽんのせんと7人の仲間たち」という素敵な作品が出来上がった。こんな素晴らしい、取り組みの機会を与えてくれた『マヌエル君』に心より感謝したい。これからも、児童の表現力や発想力、想像力を広げていけるような読み聞かせの授業を考えていこうと思う。 |
| 司書・司書教諭コメント | 読み聞かせをすると、ページをめくる度に「すごーい」「かわいい」等の声が上がり、絵本の主人公のマヌエルくんに親近感を感じた様子であった。もっとも反応を示したページは「せんにとりがとまる」だった。読み聞かせの後、先生の説明でマヌエルくんの水色の線をみんなで指でたどる経験をした。それが生き生きとした絵と線につながっていったと思う。「せんにとりがとまる」のページのように、水色の線と描きたいものの組み合わせを楽しめていたのだと思う。学芸大学司書教諭講習の講師として、お世話になった中山先生から示唆をいただき、また、中山先生から紹介のあった2冊を紹介した。『せんをひく』は、縦開きのページに、筆で描かれたダイナミックな線とその線にあわせた擬態語を楽しみ、ページをめくるたびに盛り上がった。『線とあそぼう』は、生活の中に、あふれている線をさがすことへのきっかけ作りとなった。 |
| 情報提供校 | 市川市立国分小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2017年9月29日 /授業実践2017年9月27日 |
| 事例作成者氏名 | 市川市立国分小学校学校司書 多勢千夏 |
記入者:村上

























