お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0334 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 むかしばなしがいっぱい(光村図書) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 クイズ作り(ワークシート提供) 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) ブックトーク時に司書が見せたクイズを、子どもたちが作りたがっているので、図書の時間にさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ワークシートを書いてから作るようにしたいことを伝える。
提示資料 ブックトークでは、教科書(光村)に紹介されているものの中で、子どもたちがあまり知らなかったものを先生に聞いておいて、紹介しました。そのうちの3冊です。
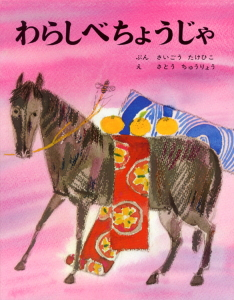
『わらしべ長者』むかしばなし絵本17 文/西郷 竹彦 絵/佐藤 忠良 1967 ポプラ社
「わらってなあに?」と問いかける。
稲穂の実物を見せて説明し、いくつかの絵本の挿絵を見せながら、昔の人が暮らしの中で、わらでいろいろな物を作っていたことを話す。
(「昔の暮らしの道具事典」わらじ・わらぞうり・みの・むしろなどを見せる。)

『ぶんぶんちゃがま』日本名作おはなし絵本 文/富安陽子 絵/植垣歩子 小学館 2010
茶釜とは鉄でできたお茶をわかすもの…と写真を見せる。 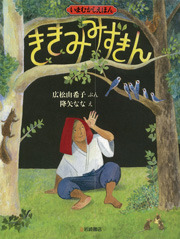
『ききみみずきん』広松由希子 文 降矢なな 絵 岩崎書店 2012
ずきんとは、布でできた寒いときにかぶるもの…と説明。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 むかしばなし キーワード2 クイズ キーワード3 授業計画・指導案等 Book1.xlsむかしばなしクイズ.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=891#_1330 授業者 秦雪美 授業者コメント クイズにするために、言葉を選ぶ力が身についたように思う。本を読んだ後、クイズを作ることで、本を読む目的が明確になった。
クイズを出すことで、友だちが楽しんでくれ、さらに次のクイズを作るために本を読もうとする意欲が見られた。
家庭でどんどんクイズを作ってきたり、お楽しみ会でむかしばなしクイズを出したり、充分楽しんだ。放課後、友だちと作って出し合ったと日記に書いてくれる児童もいて、遊びながら学習できていると感じた。
本を読んだら感想を書くという記録重視の指導より、何倍も楽しんで学習できていた。
司書・司書教諭コメント 昔話のブックトークを依頼された際に、簡単なクイズをして見せたら、子どもたちも作りたがっていると言われたので、ワークシートを作成した。
①登場人物の意味を確認(挿絵ではダメ、お話にでてくる人や物)
②それをいくつか書き出す
③その中から4つ選ぶ
④順番を考える(すぐには当てられないが、最後にはちゃんと当てられるように)
⑤決まったら、用紙に清書する
適切な登場人物を選ぶことができているか、順番をよく考えているか(矢印などを使って、何度も考え直してよい)などを、先生が指導してくださっていた。
子どもたちが行きつ戻りつして、何度も読み返しながら作成していく様子が見られた。出来上がったものを、後日、図書館まで見せに来てくれた児童もいた。 情報提供校 新居浜市立中萩小学校 事例作成日 事例作成 31年 3月 5日 /授業実践 30年 12月1日 事例作成者氏名 学校司書 寺田章代
記入者:村上
カウンタ
3108931 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0334 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 むかしばなしがいっぱい(光村図書) 対象学年 低学年 活用・支援の種類 クイズ作り(ワークシート提供) 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) ブックトーク時に司書が見せたクイズを、子どもたちが作りたがっているので、図書の時間にさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ワークシートを書いてから作るようにしたいことを伝える。
提示資料 ブックトークでは、教科書(光村)に紹介されているものの中で、子どもたちがあまり知らなかったものを先生に聞いておいて、紹介しました。そのうちの3冊です。
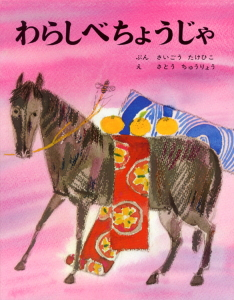
『わらしべ長者』むかしばなし絵本17 文/西郷 竹彦 絵/佐藤 忠良 1967 ポプラ社
「わらってなあに?」と問いかける。
稲穂の実物を見せて説明し、いくつかの絵本の挿絵を見せながら、昔の人が暮らしの中で、わらでいろいろな物を作っていたことを話す。
(「昔の暮らしの道具事典」わらじ・わらぞうり・みの・むしろなどを見せる。)

『ぶんぶんちゃがま』日本名作おはなし絵本 文/富安陽子 絵/植垣歩子 小学館 2010
茶釜とは鉄でできたお茶をわかすもの…と写真を見せる。 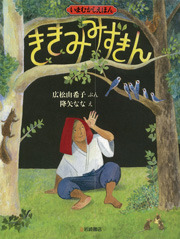
『ききみみずきん』広松由希子 文 降矢なな 絵 岩崎書店 2012
ずきんとは、布でできた寒いときにかぶるもの…と説明。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 むかしばなし キーワード2 クイズ キーワード3 授業計画・指導案等 Book1.xlsむかしばなしクイズ.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=891#_1330 授業者 秦雪美 授業者コメント クイズにするために、言葉を選ぶ力が身についたように思う。本を読んだ後、クイズを作ることで、本を読む目的が明確になった。
クイズを出すことで、友だちが楽しんでくれ、さらに次のクイズを作るために本を読もうとする意欲が見られた。
家庭でどんどんクイズを作ってきたり、お楽しみ会でむかしばなしクイズを出したり、充分楽しんだ。放課後、友だちと作って出し合ったと日記に書いてくれる児童もいて、遊びながら学習できていると感じた。
本を読んだら感想を書くという記録重視の指導より、何倍も楽しんで学習できていた。
司書・司書教諭コメント 昔話のブックトークを依頼された際に、簡単なクイズをして見せたら、子どもたちも作りたがっていると言われたので、ワークシートを作成した。
①登場人物の意味を確認(挿絵ではダメ、お話にでてくる人や物)
②それをいくつか書き出す
③その中から4つ選ぶ
④順番を考える(すぐには当てられないが、最後にはちゃんと当てられるように)
⑤決まったら、用紙に清書する
適切な登場人物を選ぶことができているか、順番をよく考えているか(矢印などを使って、何度も考え直してよい)などを、先生が指導してくださっていた。
子どもたちが行きつ戻りつして、何度も読み返しながら作成していく様子が見られた。出来上がったものを、後日、図書館まで見せに来てくれた児童もいた。 情報提供校 新居浜市立中萩小学校 事例作成日 事例作成 31年 3月 5日 /授業実践 30年 12月1日 事例作成者氏名 学校司書 寺田章代
記入者:村上
カウンタ
3108931 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0334 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | むかしばなしがいっぱい(光村図書) |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | クイズ作り(ワークシート提供) |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | ブックトーク時に司書が見せたクイズを、子どもたちが作りたがっているので、図書の時間にさせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ワークシートを書いてから作るようにしたいことを伝える。 |
| 提示資料 | ブックトークでは、教科書(光村)に紹介されているものの中で、子どもたちがあまり知らなかったものを先生に聞いておいて、紹介しました。そのうちの3冊です。 |
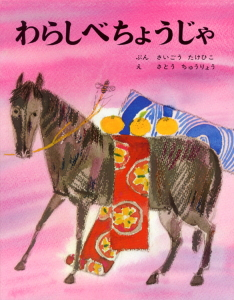 | 『わらしべ長者』むかしばなし絵本17 文/西郷 竹彦 絵/佐藤 忠良 1967 ポプラ社 「わらってなあに?」と問いかける。 稲穂の実物を見せて説明し、いくつかの絵本の挿絵を見せながら、昔の人が暮らしの中で、わらでいろいろな物を作っていたことを話す。 (「昔の暮らしの道具事典」わらじ・わらぞうり・みの・むしろなどを見せる。) |
 | 『ぶんぶんちゃがま』日本名作おはなし絵本 文/富安陽子 絵/植垣歩子 小学館 2010 茶釜とは鉄でできたお茶をわかすもの…と写真を見せる。 |
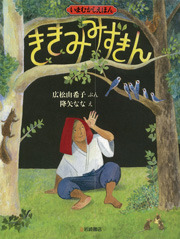 | 『ききみみずきん』広松由希子 文 降矢なな 絵 岩崎書店 2012 ずきんとは、布でできた寒いときにかぶるもの…と説明。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | むかしばなし |
| キーワード2 | クイズ |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | Book1.xlsむかしばなしクイズ.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=891#_1330 |
| 授業者 | 秦雪美 |
| 授業者コメント | クイズにするために、言葉を選ぶ力が身についたように思う。本を読んだ後、クイズを作ることで、本を読む目的が明確になった。 クイズを出すことで、友だちが楽しんでくれ、さらに次のクイズを作るために本を読もうとする意欲が見られた。 家庭でどんどんクイズを作ってきたり、お楽しみ会でむかしばなしクイズを出したり、充分楽しんだ。放課後、友だちと作って出し合ったと日記に書いてくれる児童もいて、遊びながら学習できていると感じた。 本を読んだら感想を書くという記録重視の指導より、何倍も楽しんで学習できていた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 昔話のブックトークを依頼された際に、簡単なクイズをして見せたら、子どもたちも作りたがっていると言われたので、ワークシートを作成した。 ①登場人物の意味を確認(挿絵ではダメ、お話にでてくる人や物) ②それをいくつか書き出す ③その中から4つ選ぶ ④順番を考える(すぐには当てられないが、最後にはちゃんと当てられるように) ⑤決まったら、用紙に清書する 適切な登場人物を選ぶことができているか、順番をよく考えているか(矢印などを使って、何度も考え直してよい)などを、先生が指導してくださっていた。 子どもたちが行きつ戻りつして、何度も読み返しながら作成していく様子が見られた。出来上がったものを、後日、図書館まで見せに来てくれた児童もいた。 |
| 情報提供校 | 新居浜市立中萩小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 31年 3月 5日 /授業実践 30年 12月1日 |
| 事例作成者氏名 | 学校司書 寺田章代 |
記入者:村上

























