お知らせ
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
新着案内
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0377 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 見ぬ世の人の世界を知ろう ~儀兵衛と五兵衛~ 対象学年 中1 活用・支援の種類 レファレンス・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 生徒が自分の研究に必要な情報を図書館で見つける体験をさせたい。生徒が個々に調べに行くので、レファレンスをしてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 「稲むらの火」とそのモデルとなった濱口梧陸の手記を読み比べて、その違いをみつけ、違いがなぜ生まれたかの論拠を図書館の棚にならぶ資料の中から見つける体験をさせたい。学校図書館に生徒が個々に調べに行くので、レファレンスを。
提示資料 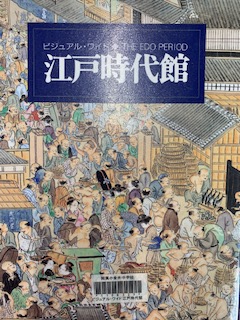
『ビジュアルワイド 江戸時代館』ポプラ社、2011年
安政の大地震についての記述が多く掲載されている。 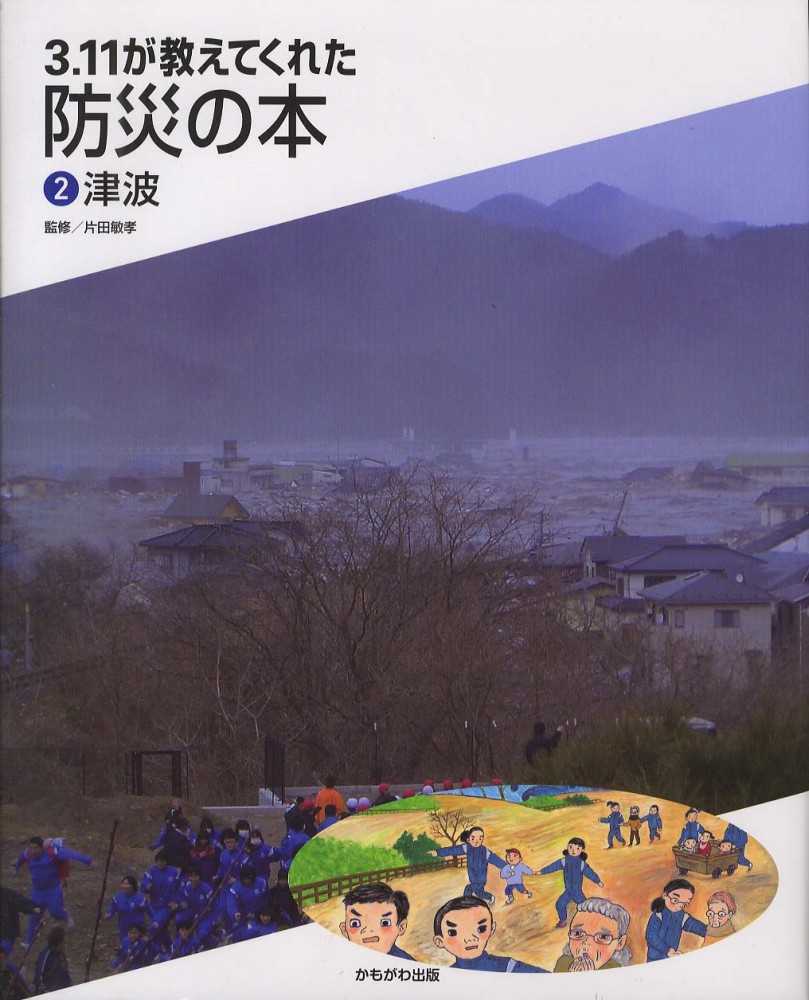
『3.11がおしえてくれた防災の本 ②津波』片田敏孝、かもがわ出版 2012年
地震と津波のメカニズムについての説明がわかりやすく説明されている。 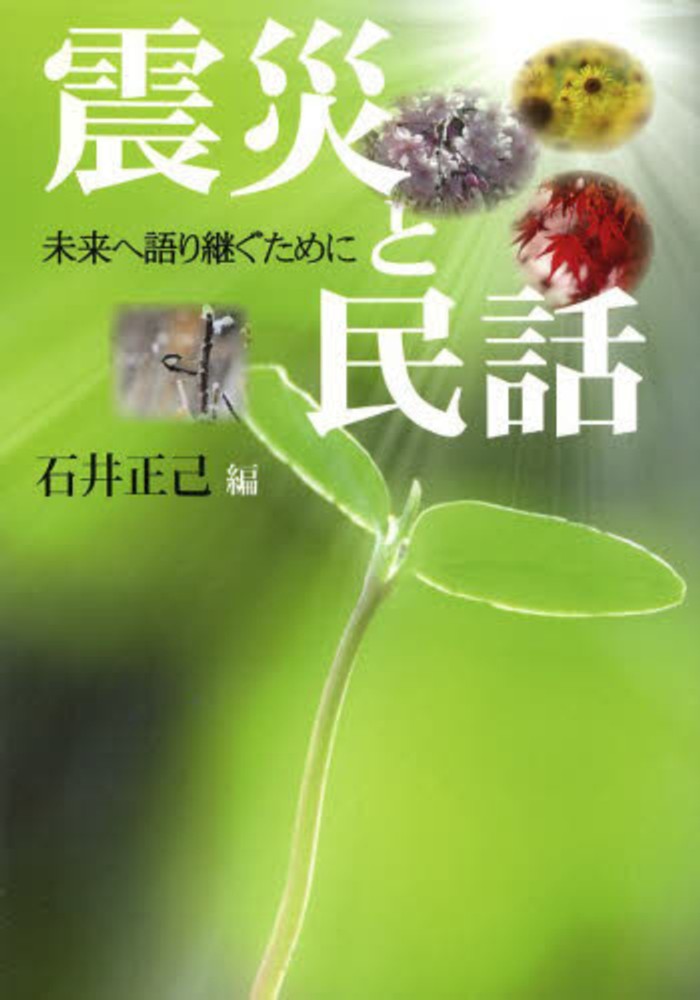
『震災と民話:未来へ語り継ぐために』石井正己編、三弥井書店、2013年
震災と民話についての論文集。「稲むらの火」についての記述あり。 参考資料(含HP) https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/ 参考資料リンク https://www.yamasa.com/enjoy/history/inamura/ ブックリスト 「儀兵衛と五兵衛」レファレンスブックリストxlsx.xlsx
キーワード1 稲むらの火 キーワード2 安政の大地震 キーワード3 濱口梧陵 授業計画・指導案等 授業の流れシート (儀兵衛と五兵衛).pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 愛甲修子先生 授業者コメント 自分の知りたいことを「検索」に打ち込んで、エンターキーを押せば、必要な情報が出てくるのが「調べる」ことだと、生徒は無意識に思っていた。しかし、現実はそうではないのだ、ということを生徒は実感した。「書籍を探すのは難しいが、正しい情報を得るには、書籍を探した方が良い」ということを学ぶことができた。また、司書の先生が図書館の案内人であることもわかった。
一方で、「昔の指導要領が見たい」「子供に本を薦めるときの基準を知りたい」など、学校図書館に実物がないような質問を司書にした生徒もいた。その時、「文部科学省のHPを見ると良いよ」「全国学校図書館協議会図書選定基準というものがあるんだよ」というように、インターネットで、何を探せば良いかというヒントももらった。こういったアドバイスは教師がするよりも、知の案内人として、図書館司書にしてもらった方が、良いと考える。それは図書館司書を含む学校図書館が、一つの百科事典であるという認識を生徒が持ってくれれば、国語に限らず、生徒が「何か知りたい」と思ったときの拠り所になると考えたからである。今回の授業で、その一歩が踏み出せたと考える。 司書・司書教諭コメント コロナ禍の中で、集まっての学習が行われにくい中、班の中から代表を決め、図書館へ調べに生徒を派遣という利用法に助けられた。生徒からの問いは、どの分類の棚に関連の本があるかを知らせるとその後はすぐに本が見つかる場合と、どういったことを調べたいのかを、会話のなかで互いに明確にしていく作業が必要な場合があり、生徒の問いの内容を的確に把握するために司書側のレファレンス能力の研鑽の必要性を痛感した。また、知りたいことがあるなら学校図書館へと認識してもらうためにも、参考図書の充実は大切であり、百科事典などの基本図書は、予算との関連もあるが、最新のものの充実をはかっていく必要があるとあらためて感じた。 授業での生徒のまとめの発表の様子を見学し、最終的に生徒が使った資料やWEB情報についても教えてもらった。館内に希望の書籍がない場合でも、他館よりの取り寄せを行ったり、インターネット情報を紹介する際にも、情報の水先案内人として学校司書はWEB情報への検索スキルも必要であると改めて思った。(例えば文科省HPの中に国立教育政策研究所の指導要領データベースが紹介されていた。)今回の経験は今後にフィードバックしていきたい。 情報提供校 学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2021年1月4日 事例作成者氏名 附属小金井中学校 教諭 愛甲修子 司書 杉本ゆかり
記入者:杉本(主担)
カウンタ
3108927 : 2010年9月14日より
令和7年度がスタートしました。今年度より学校著作権ナビゲーターとして活躍中の原口直先生に、著作権アドバイザーになっていただきました。7月末には、「生成AIと著作権」をテーマに研修を企画中です。
また、当サイトは、「10代がえらぶ海外文学大賞」を一緒に盛り上げるために、活動していきます。ぜひ、全国の学校司書・司書教諭の皆様、ご協力よろしくお願いします。
I Dig Eduに動画コンテンツ「学校図書館を活用した教科連携事例 東京学芸大学附属国際中等教育学校の実践から」を掲載しました。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「今月の学校図書館」は 東京学芸大学附属高等学校です。
「読書・情報リテラシー」は 学習発表会 2年生生活科で「NDCのうた」です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0377 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 見ぬ世の人の世界を知ろう ~儀兵衛と五兵衛~ 対象学年 中1 活用・支援の種類 レファレンス・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 生徒が自分の研究に必要な情報を図書館で見つける体験をさせたい。生徒が個々に調べに行くので、レファレンスをしてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 「稲むらの火」とそのモデルとなった濱口梧陸の手記を読み比べて、その違いをみつけ、違いがなぜ生まれたかの論拠を図書館の棚にならぶ資料の中から見つける体験をさせたい。学校図書館に生徒が個々に調べに行くので、レファレンスを。
提示資料 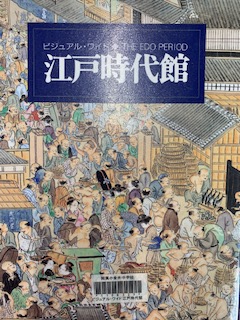
『ビジュアルワイド 江戸時代館』ポプラ社、2011年
安政の大地震についての記述が多く掲載されている。 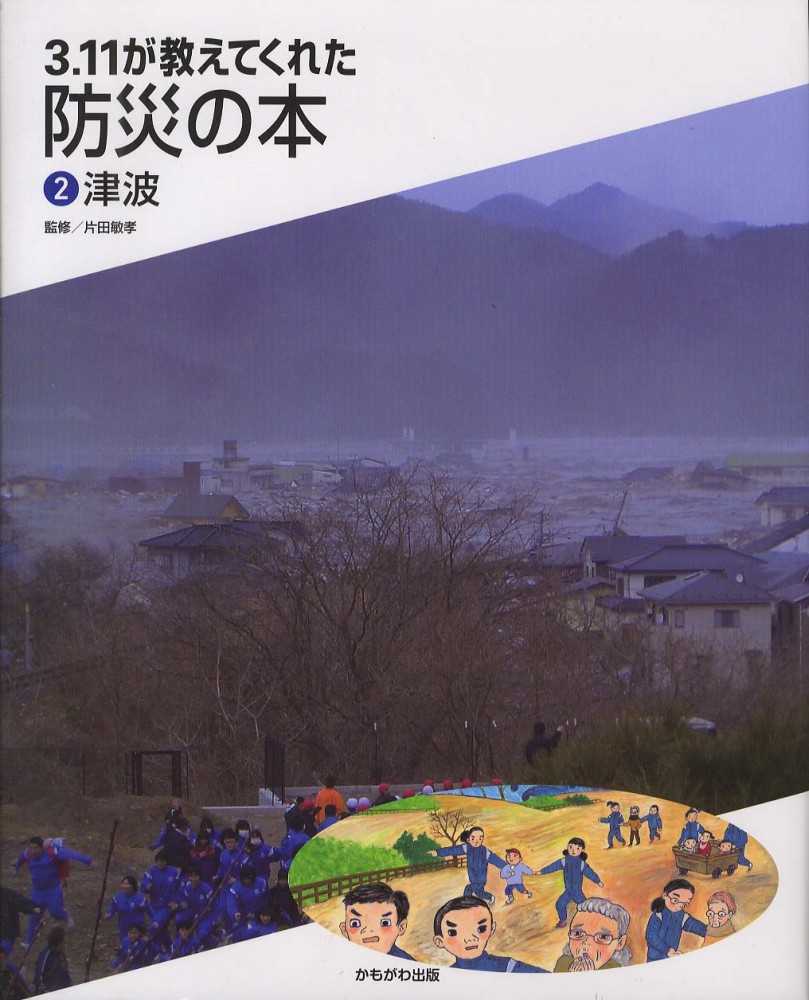
『3.11がおしえてくれた防災の本 ②津波』片田敏孝、かもがわ出版 2012年
地震と津波のメカニズムについての説明がわかりやすく説明されている。 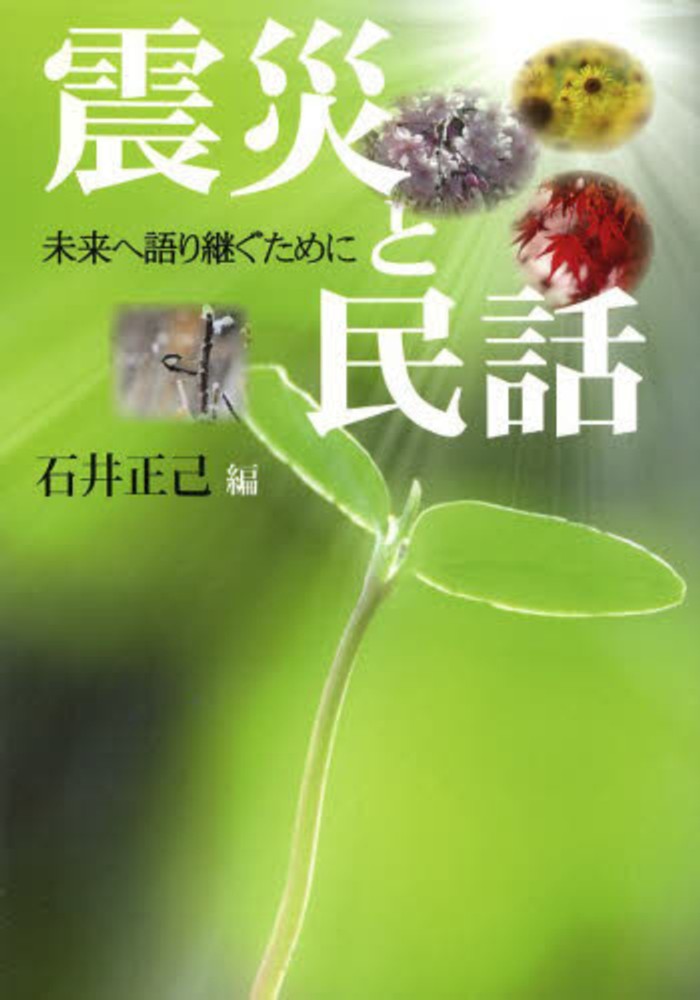
『震災と民話:未来へ語り継ぐために』石井正己編、三弥井書店、2013年
震災と民話についての論文集。「稲むらの火」についての記述あり。 参考資料(含HP) https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/ 参考資料リンク https://www.yamasa.com/enjoy/history/inamura/ ブックリスト 「儀兵衛と五兵衛」レファレンスブックリストxlsx.xlsx
キーワード1 稲むらの火 キーワード2 安政の大地震 キーワード3 濱口梧陵 授業計画・指導案等 授業の流れシート (儀兵衛と五兵衛).pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 愛甲修子先生 授業者コメント 自分の知りたいことを「検索」に打ち込んで、エンターキーを押せば、必要な情報が出てくるのが「調べる」ことだと、生徒は無意識に思っていた。しかし、現実はそうではないのだ、ということを生徒は実感した。「書籍を探すのは難しいが、正しい情報を得るには、書籍を探した方が良い」ということを学ぶことができた。また、司書の先生が図書館の案内人であることもわかった。
一方で、「昔の指導要領が見たい」「子供に本を薦めるときの基準を知りたい」など、学校図書館に実物がないような質問を司書にした生徒もいた。その時、「文部科学省のHPを見ると良いよ」「全国学校図書館協議会図書選定基準というものがあるんだよ」というように、インターネットで、何を探せば良いかというヒントももらった。こういったアドバイスは教師がするよりも、知の案内人として、図書館司書にしてもらった方が、良いと考える。それは図書館司書を含む学校図書館が、一つの百科事典であるという認識を生徒が持ってくれれば、国語に限らず、生徒が「何か知りたい」と思ったときの拠り所になると考えたからである。今回の授業で、その一歩が踏み出せたと考える。 司書・司書教諭コメント コロナ禍の中で、集まっての学習が行われにくい中、班の中から代表を決め、図書館へ調べに生徒を派遣という利用法に助けられた。生徒からの問いは、どの分類の棚に関連の本があるかを知らせるとその後はすぐに本が見つかる場合と、どういったことを調べたいのかを、会話のなかで互いに明確にしていく作業が必要な場合があり、生徒の問いの内容を的確に把握するために司書側のレファレンス能力の研鑽の必要性を痛感した。また、知りたいことがあるなら学校図書館へと認識してもらうためにも、参考図書の充実は大切であり、百科事典などの基本図書は、予算との関連もあるが、最新のものの充実をはかっていく必要があるとあらためて感じた。 授業での生徒のまとめの発表の様子を見学し、最終的に生徒が使った資料やWEB情報についても教えてもらった。館内に希望の書籍がない場合でも、他館よりの取り寄せを行ったり、インターネット情報を紹介する際にも、情報の水先案内人として学校司書はWEB情報への検索スキルも必要であると改めて思った。(例えば文科省HPの中に国立教育政策研究所の指導要領データベースが紹介されていた。)今回の経験は今後にフィードバックしていきたい。 情報提供校 学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2021年1月4日 事例作成者氏名 附属小金井中学校 教諭 愛甲修子 司書 杉本ゆかり
記入者:杉本(主担)
カウンタ
3108927 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0377 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 見ぬ世の人の世界を知ろう ~儀兵衛と五兵衛~ |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | レファレンス・資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 生徒が自分の研究に必要な情報を図書館で見つける体験をさせたい。生徒が個々に調べに行くので、レファレンスをしてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 「稲むらの火」とそのモデルとなった濱口梧陸の手記を読み比べて、その違いをみつけ、違いがなぜ生まれたかの論拠を図書館の棚にならぶ資料の中から見つける体験をさせたい。学校図書館に生徒が個々に調べに行くので、レファレンスを。 |
| 提示資料 | |
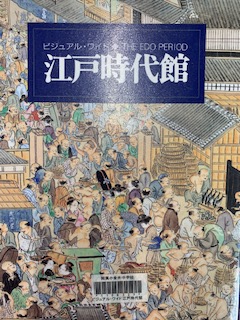 | 『ビジュアルワイド 江戸時代館』ポプラ社、2011年 安政の大地震についての記述が多く掲載されている。 |
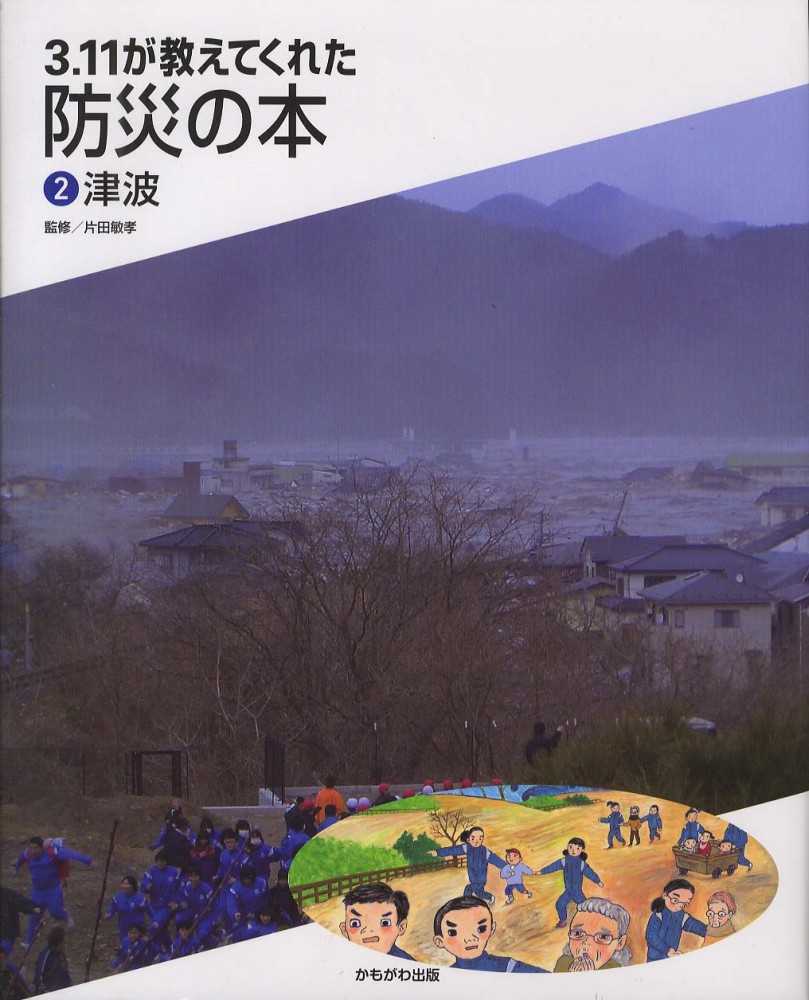 | 『3.11がおしえてくれた防災の本 ②津波』片田敏孝、かもがわ出版 2012年 地震と津波のメカニズムについての説明がわかりやすく説明されている。 |
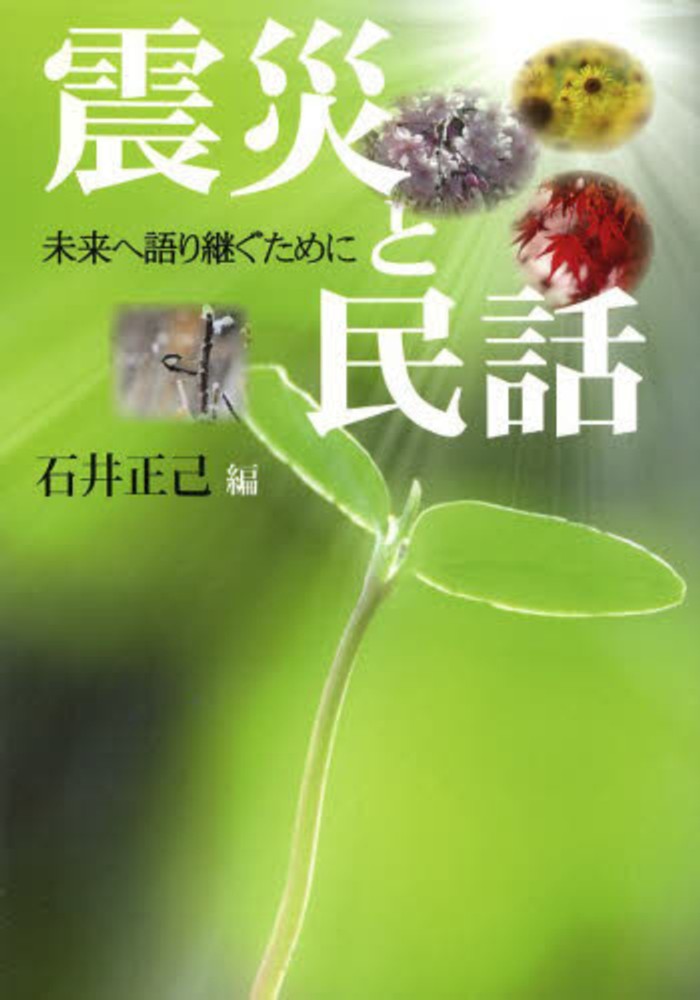 | 『震災と民話:未来へ語り継ぐために』石井正己編、三弥井書店、2013年 震災と民話についての論文集。「稲むらの火」についての記述あり。 |
| 参考資料(含HP) | https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/ |
| 参考資料リンク | https://www.yamasa.com/enjoy/history/inamura/ |
| ブックリスト | 「儀兵衛と五兵衛」レファレンスブックリストxlsx.xlsx |
| キーワード1 | 稲むらの火 |
| キーワード2 | 安政の大地震 |
| キーワード3 | 濱口梧陵 |
| 授業計画・指導案等 | 授業の流れシート (儀兵衛と五兵衛).pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 愛甲修子先生 |
| 授業者コメント | 自分の知りたいことを「検索」に打ち込んで、エンターキーを押せば、必要な情報が出てくるのが「調べる」ことだと、生徒は無意識に思っていた。しかし、現実はそうではないのだ、ということを生徒は実感した。「書籍を探すのは難しいが、正しい情報を得るには、書籍を探した方が良い」ということを学ぶことができた。また、司書の先生が図書館の案内人であることもわかった。 一方で、「昔の指導要領が見たい」「子供に本を薦めるときの基準を知りたい」など、学校図書館に実物がないような質問を司書にした生徒もいた。その時、「文部科学省のHPを見ると良いよ」「全国学校図書館協議会図書選定基準というものがあるんだよ」というように、インターネットで、何を探せば良いかというヒントももらった。こういったアドバイスは教師がするよりも、知の案内人として、図書館司書にしてもらった方が、良いと考える。それは図書館司書を含む学校図書館が、一つの百科事典であるという認識を生徒が持ってくれれば、国語に限らず、生徒が「何か知りたい」と思ったときの拠り所になると考えたからである。今回の授業で、その一歩が踏み出せたと考える。 |
| 司書・司書教諭コメント | コロナ禍の中で、集まっての学習が行われにくい中、班の中から代表を決め、図書館へ調べに生徒を派遣という利用法に助けられた。生徒からの問いは、どの分類の棚に関連の本があるかを知らせるとその後はすぐに本が見つかる場合と、どういったことを調べたいのかを、会話のなかで互いに明確にしていく作業が必要な場合があり、生徒の問いの内容を的確に把握するために司書側のレファレンス能力の研鑽の必要性を痛感した。また、知りたいことがあるなら学校図書館へと認識してもらうためにも、参考図書の充実は大切であり、百科事典などの基本図書は、予算との関連もあるが、最新のものの充実をはかっていく必要があるとあらためて感じた。 授業での生徒のまとめの発表の様子を見学し、最終的に生徒が使った資料やWEB情報についても教えてもらった。館内に希望の書籍がない場合でも、他館よりの取り寄せを行ったり、インターネット情報を紹介する際にも、情報の水先案内人として学校司書はWEB情報への検索スキルも必要であると改めて思った。(例えば文科省HPの中に国立教育政策研究所の指導要領データベースが紹介されていた。)今回の経験は今後にフィードバックしていきたい。 |
| 情報提供校 | 学芸大学附属小金井中学校 |
| 事例作成日 | 2021年1月4日 |
| 事例作成者氏名 | 附属小金井中学校 教諭 愛甲修子 司書 杉本ゆかり |
記入者:杉本(主担)

























