お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0117 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 武士の世の中へ(メディアリテラシ―) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 一の谷の戦いで源義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために複数の資料を提供したい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために、源平の合戦、とりわけ一の谷や鵯越の逆落としに関して書かれている複数の資料を、比較しながら分析的に読むことで「可能だったかどうか」について検証を行うためのもの。著者の立場の違い、表現の違い(マンガ、歴史書、人物紹介、戦法など)で書かれ方、解釈のされ方が違うことに気づかせ、児童の批判的思考力やメディアリテラシーを育みたい。
提示資料 源平合戦に関わる資料と新聞記事(「逆おとししなかった?源義経」朝日新聞 2012年7月2日) 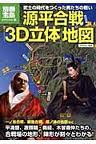
『源平合戦「3D立体」地図』 (別冊宝島) (別冊宝島 1843 ノンフィクション) 2012
源平の合戦で戦われた場所、双方の戦力、地形などが細かく書かれている。特に地形に関しては立体的に示されているため、一の谷・鵯越について調べる上で有効な資料の一つ。

『決定版 図説・源平合戦人物伝』 歴史群像編集部 2011
源平の合戦に関わった主要人物186人の肖像画や遺品、エピソードなどを紹介している。調べ学習を進めていく中で登場する人物がどのような人間であったかについて知ることで、戦いへどのような影響を及ぼす人物だったかを検証できる。 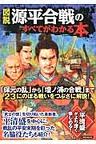
図説源平合戦のすべてがわかる本 (洋泉社MOOK)2011
源平の全合戦が網羅されており、一の谷に至るまでのそれぞれのルートや状況が詳しく書かれているため、戦いの背景を詳しく調べることができる。 参考資料(含HP) http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201207030235.html 参考資料リンク http://www.slideshare.net/kazunorisatou/142012-15255141 ブックリスト 源平の合戦(一の谷 鵯越)ブックリスト(小6社会・情報教育).xls
キーワード1 メディアリテラシー キーワード2 情報教育 キーワード3 武士 授業計画・指導案等 鵯越の逆落としは可能だったか 小6指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 佐藤和紀 授業者コメント 平安時代から鎌倉時代にかけて、武士の世の中へ変わっていく中で源平の合戦が繰り広げられていきますが、これらを学習していく中で児童が疑問に感じたり、不思議に思ったことについて問題作りをした中の一つがこの授業となりました。
問題を解決する学習過程で、批判的思考やメディアリテラシーを育みたいという思いから、複数の資料を集めて、一つのテーマに着いて複数の資料を読み、比較して分析し、自分なりの見解(意思決定)を示し、その考えを元に議論を行いました。
自分で資料を調べる、という主体性は資料を読み込んでいく中で児童自身に生まれ、最初に与えた資料をより深く読もうとしたり、インターネットで関連情報を調べたりしていました。
資料自体はとても難しいものもあり、支援が必要なものもありますが、支援すれば紹介した資料に関しても十分に読解することは可能でした。
調べ学習はすぐインターネットで検索しがちですが、児童自身が問題に対して十分な知識と見解がなければインターネットで検索しても、ほしい情報は見つかりませんし、ただ答えを見つけようとするような検索に陥ってしまいます。情報はあくまでも問題解決のための手段である、ということを理解させるためには、まずは様々な資料を読み込むことが大切だと改めて感じました。
(第14回図書館総合展プレ企画「デジタルネットワーク社会における学校教育と図書館」紹介事例 http://2012.libraryfair.jp/node/824
発表されたパワーポイントは「参考資料リンク」からアクセスすることができます。) 司書・司書教諭コメント 学校図書館には資料も少なく、公共図書館の学校支援の体制も整っていない中で、教材を先生ご自身の資料で補っているとのことでした。学級の環境としては、個人提供の資料、公共図書館から借りた資料、辞書・事典等の参考図書を整えておられるのがミニ図書館のようで素晴らしいと思います。しかし、本来なら資料相談ができ、資料を整えてくれる学校図書館や公共図書館の支援が望まれるところです。
もしも、図書の時間があれば『ひよどりごえ』(源平絵巻物語第5巻 偕成社)を読み聞かせして、『平家物語』等の文学、義経の伝記、絵巻や屏風の表現などもしっかり読みこんで比較してもらえるとおもしろそうな題材でした。時間があれば、歴史の基本としては『武士の研究』(ポプラ社 2001年)ほか、歴史をきちんと取り上げている通史のこの時代のものも一緒に奨めてみたかもしれませんが、そもそも、あまり記述の少ないところなので、苦労することになりそうですが…。佐藤先生は短い時間でフォーカスできる資料をつかわれたのだと思います。「ブックリスト」に授業で取り上げられたものと、それ以外の文献もあげてみましたので、ご参照ください。
(東京学芸大学附属小金井小学校 中山美由紀) 情報提供校 東京都北区立豊川小学校 事例作成日 2012年11月10日 (実践日2012年6月下旬から7月上旬 事例作成者氏名 佐藤和紀教諭
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0117 校種 小学校 教科・領域等 社会 単元 武士の世の中へ(メディアリテラシ―) 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 一の谷の戦いで源義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために複数の資料を提供したい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために、源平の合戦、とりわけ一の谷や鵯越の逆落としに関して書かれている複数の資料を、比較しながら分析的に読むことで「可能だったかどうか」について検証を行うためのもの。著者の立場の違い、表現の違い(マンガ、歴史書、人物紹介、戦法など)で書かれ方、解釈のされ方が違うことに気づかせ、児童の批判的思考力やメディアリテラシーを育みたい。
提示資料 源平合戦に関わる資料と新聞記事(「逆おとししなかった?源義経」朝日新聞 2012年7月2日) 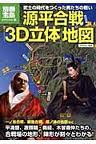
『源平合戦「3D立体」地図』 (別冊宝島) (別冊宝島 1843 ノンフィクション) 2012
源平の合戦で戦われた場所、双方の戦力、地形などが細かく書かれている。特に地形に関しては立体的に示されているため、一の谷・鵯越について調べる上で有効な資料の一つ。

『決定版 図説・源平合戦人物伝』 歴史群像編集部 2011
源平の合戦に関わった主要人物186人の肖像画や遺品、エピソードなどを紹介している。調べ学習を進めていく中で登場する人物がどのような人間であったかについて知ることで、戦いへどのような影響を及ぼす人物だったかを検証できる。 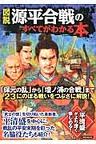
図説源平合戦のすべてがわかる本 (洋泉社MOOK)2011
源平の全合戦が網羅されており、一の谷に至るまでのそれぞれのルートや状況が詳しく書かれているため、戦いの背景を詳しく調べることができる。 参考資料(含HP) http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201207030235.html 参考資料リンク http://www.slideshare.net/kazunorisatou/142012-15255141 ブックリスト 源平の合戦(一の谷 鵯越)ブックリスト(小6社会・情報教育).xls
キーワード1 メディアリテラシー キーワード2 情報教育 キーワード3 武士 授業計画・指導案等 鵯越の逆落としは可能だったか 小6指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 佐藤和紀 授業者コメント 平安時代から鎌倉時代にかけて、武士の世の中へ変わっていく中で源平の合戦が繰り広げられていきますが、これらを学習していく中で児童が疑問に感じたり、不思議に思ったことについて問題作りをした中の一つがこの授業となりました。
問題を解決する学習過程で、批判的思考やメディアリテラシーを育みたいという思いから、複数の資料を集めて、一つのテーマに着いて複数の資料を読み、比較して分析し、自分なりの見解(意思決定)を示し、その考えを元に議論を行いました。
自分で資料を調べる、という主体性は資料を読み込んでいく中で児童自身に生まれ、最初に与えた資料をより深く読もうとしたり、インターネットで関連情報を調べたりしていました。
資料自体はとても難しいものもあり、支援が必要なものもありますが、支援すれば紹介した資料に関しても十分に読解することは可能でした。
調べ学習はすぐインターネットで検索しがちですが、児童自身が問題に対して十分な知識と見解がなければインターネットで検索しても、ほしい情報は見つかりませんし、ただ答えを見つけようとするような検索に陥ってしまいます。情報はあくまでも問題解決のための手段である、ということを理解させるためには、まずは様々な資料を読み込むことが大切だと改めて感じました。
(第14回図書館総合展プレ企画「デジタルネットワーク社会における学校教育と図書館」紹介事例 http://2012.libraryfair.jp/node/824
発表されたパワーポイントは「参考資料リンク」からアクセスすることができます。) 司書・司書教諭コメント 学校図書館には資料も少なく、公共図書館の学校支援の体制も整っていない中で、教材を先生ご自身の資料で補っているとのことでした。学級の環境としては、個人提供の資料、公共図書館から借りた資料、辞書・事典等の参考図書を整えておられるのがミニ図書館のようで素晴らしいと思います。しかし、本来なら資料相談ができ、資料を整えてくれる学校図書館や公共図書館の支援が望まれるところです。
もしも、図書の時間があれば『ひよどりごえ』(源平絵巻物語第5巻 偕成社)を読み聞かせして、『平家物語』等の文学、義経の伝記、絵巻や屏風の表現などもしっかり読みこんで比較してもらえるとおもしろそうな題材でした。時間があれば、歴史の基本としては『武士の研究』(ポプラ社 2001年)ほか、歴史をきちんと取り上げている通史のこの時代のものも一緒に奨めてみたかもしれませんが、そもそも、あまり記述の少ないところなので、苦労することになりそうですが…。佐藤先生は短い時間でフォーカスできる資料をつかわれたのだと思います。「ブックリスト」に授業で取り上げられたものと、それ以外の文献もあげてみましたので、ご参照ください。
(東京学芸大学附属小金井小学校 中山美由紀) 情報提供校 東京都北区立豊川小学校 事例作成日 2012年11月10日 (実践日2012年6月下旬から7月上旬 事例作成者氏名 佐藤和紀教諭
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0117 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 武士の世の中へ(メディアリテラシ―) |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 一の谷の戦いで源義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために複数の資料を提供したい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 義経が行ったとされる「鵯越の逆落とし」は可能だったかについて問題解決学習を行うために、源平の合戦、とりわけ一の谷や鵯越の逆落としに関して書かれている複数の資料を、比較しながら分析的に読むことで「可能だったかどうか」について検証を行うためのもの。著者の立場の違い、表現の違い(マンガ、歴史書、人物紹介、戦法など)で書かれ方、解釈のされ方が違うことに気づかせ、児童の批判的思考力やメディアリテラシーを育みたい。 |
| 提示資料 | 源平合戦に関わる資料と新聞記事(「逆おとししなかった?源義経」朝日新聞 2012年7月2日) |
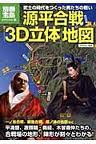 | 『源平合戦「3D立体」地図』 (別冊宝島) (別冊宝島 1843 ノンフィクション) 2012 源平の合戦で戦われた場所、双方の戦力、地形などが細かく書かれている。特に地形に関しては立体的に示されているため、一の谷・鵯越について調べる上で有効な資料の一つ。 |
 | 『決定版 図説・源平合戦人物伝』 歴史群像編集部 2011 源平の合戦に関わった主要人物186人の肖像画や遺品、エピソードなどを紹介している。調べ学習を進めていく中で登場する人物がどのような人間であったかについて知ることで、戦いへどのような影響を及ぼす人物だったかを検証できる。 |
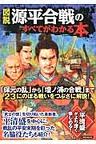 | 図説源平合戦のすべてがわかる本 (洋泉社MOOK)2011 源平の全合戦が網羅されており、一の谷に至るまでのそれぞれのルートや状況が詳しく書かれているため、戦いの背景を詳しく調べることができる。 |
| 参考資料(含HP) | http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201207030235.html |
| 参考資料リンク | http://www.slideshare.net/kazunorisatou/142012-15255141 |
| ブックリスト | 源平の合戦(一の谷 鵯越)ブックリスト(小6社会・情報教育).xls |
| キーワード1 | メディアリテラシー |
| キーワード2 | 情報教育 |
| キーワード3 | 武士 |
| 授業計画・指導案等 | 鵯越の逆落としは可能だったか 小6指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 佐藤和紀 |
| 授業者コメント | 平安時代から鎌倉時代にかけて、武士の世の中へ変わっていく中で源平の合戦が繰り広げられていきますが、これらを学習していく中で児童が疑問に感じたり、不思議に思ったことについて問題作りをした中の一つがこの授業となりました。 問題を解決する学習過程で、批判的思考やメディアリテラシーを育みたいという思いから、複数の資料を集めて、一つのテーマに着いて複数の資料を読み、比較して分析し、自分なりの見解(意思決定)を示し、その考えを元に議論を行いました。 自分で資料を調べる、という主体性は資料を読み込んでいく中で児童自身に生まれ、最初に与えた資料をより深く読もうとしたり、インターネットで関連情報を調べたりしていました。 資料自体はとても難しいものもあり、支援が必要なものもありますが、支援すれば紹介した資料に関しても十分に読解することは可能でした。 調べ学習はすぐインターネットで検索しがちですが、児童自身が問題に対して十分な知識と見解がなければインターネットで検索しても、ほしい情報は見つかりませんし、ただ答えを見つけようとするような検索に陥ってしまいます。情報はあくまでも問題解決のための手段である、ということを理解させるためには、まずは様々な資料を読み込むことが大切だと改めて感じました。 (第14回図書館総合展プレ企画「デジタルネットワーク社会における学校教育と図書館」紹介事例 http://2012.libraryfair.jp/node/824 発表されたパワーポイントは「参考資料リンク」からアクセスすることができます。) |
| 司書・司書教諭コメント | 学校図書館には資料も少なく、公共図書館の学校支援の体制も整っていない中で、教材を先生ご自身の資料で補っているとのことでした。学級の環境としては、個人提供の資料、公共図書館から借りた資料、辞書・事典等の参考図書を整えておられるのがミニ図書館のようで素晴らしいと思います。しかし、本来なら資料相談ができ、資料を整えてくれる学校図書館や公共図書館の支援が望まれるところです。 もしも、図書の時間があれば『ひよどりごえ』(源平絵巻物語第5巻 偕成社)を読み聞かせして、『平家物語』等の文学、義経の伝記、絵巻や屏風の表現などもしっかり読みこんで比較してもらえるとおもしろそうな題材でした。時間があれば、歴史の基本としては『武士の研究』(ポプラ社 2001年)ほか、歴史をきちんと取り上げている通史のこの時代のものも一緒に奨めてみたかもしれませんが、そもそも、あまり記述の少ないところなので、苦労することになりそうですが…。佐藤先生は短い時間でフォーカスできる資料をつかわれたのだと思います。「ブックリスト」に授業で取り上げられたものと、それ以外の文献もあげてみましたので、ご参照ください。 (東京学芸大学附属小金井小学校 中山美由紀) |
| 情報提供校 | 東京都北区立豊川小学校 |
| 事例作成日 | 2012年11月10日 (実践日2012年6月下旬から7月上旬 |
| 事例作成者氏名 | 佐藤和紀教諭 |
記入者:中山(主担)

























