お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0119 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 わかりやすく伝えよう(プレゼンテーション) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 東京都内に残る江戸の痕跡を探すために、東京都内の歴史に関わる書籍や、「江戸名所」などの書籍を用意・展示してほしい。また、生徒の疑問によって、書籍を紹介してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒は、東京都内に残る江戸の痕跡を探すためのフィールドワークを計画・実施する。そのための事前調査をインターネットだけでなく、書籍を用いてさせたい。
また、フィールドワーク後、自分たちが見つけた江戸を学年の友達にプレゼンテーションするために、「なぜそこが江戸なのか」という裏付けを、資料でもさせたい。現在の東京に関する資料と、江戸に関する資料、特に地図や図版など視覚に訴えるもの、また江戸時代に出版されたものが紹介されている資料を用意してほしい。
提示資料 
『江戸切絵図で歩く 広重の大江戸名所百景散歩』. 堀晃明著. 人文社. 1996
歌川広重が幕末に描いた『名所江戸百景』。その風景がどの角度から描かれたものなのか、『江戸切絵図』と現代地図を見開きに配して検証している。『名所江戸百景』のそれぞれの絵にも丁寧な解説がつけられている。 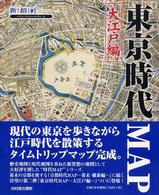
『東京時代MAP 大江戸編』.松岡満箸.光村推古書院.2005
江戸時代の地図と、現代の東京の地図の2つの地図を照らし合わせることが可能。江戸時代の地図の上に、現代の東京の地図が印刷された半透明のトレーシング・ペーパーを重ね、江戸と現在の東京の位置関係を知ることができる。
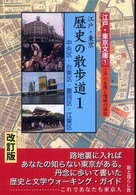
『江戸東京 歴史の散歩道』.街の暮らし社編.街と暮らし社.2001~2003
東京23区内に残る歴史の名残を詳細地図と詳しい解説でつづっている。寺・神社・記念碑・城址・資料館など、江戸から東京にかけて様々な施設が掲載されており、実際に手にして現地に行くとより理解が深まる 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 江戸東京古地図関係本(中学生以上).xls
キーワード1 江戸 キーワード2 フィールドワーク キーワード3 プレゼンテーション 授業計画・指導案等 日本文化探訪.pdf 児童・生徒の作品 授業者 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科) 授業者コメント 現代、生徒たちは調べると言えばインターネット、発表すると言えばパワーポイントといった具合である。しかし、現実とネット上の世界とは別物であり、またネット上の情報がすべて正しいとは限らない。その場に行ってこそ分かること、元になった資料を見てこそ分かることがあると気づかせたい。そのために、図書館の協力は欠かせない。キーワードを入力しなくても、江戸の世界が広がっている書籍、またその書籍が並んでいる図書館のスペースで、生徒は多くの発見をする。図書館を利用しての授業中はもちろんだが、放課後などを使っての自主学習の時間でも、学校司書の助言で、生徒はさまざまな資料に気づくことができた。
実際のプレゼンテーションでも、図書館から借りた本を提示し、「図書館にありますから、興味のある人は開いてみてください」と発表する生徒がいた。
司書・司書教諭コメント 公共図書館の団体貸し出しも受け、学校の蔵書とあわせ約150冊の資料を提供。東京の古地図が掲載された資料が多数あるなか、どの資料がより生徒に活用しやすいものか、社会科の教員の目でみてもらい、特にすすめる資料を3点上記に紹介している。
古地図に慣れるまでは、生徒も少々手間取っていたが、見慣れてくると自分たちが訪れる場所の掲載されている本を探しだし、フィールドワークや発表に活用しているようすがうかがえた。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2012年12月5日 事例作成者氏名 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科)・渡辺有理子(司書)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863483 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0119 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 わかりやすく伝えよう(プレゼンテーション) 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 東京都内に残る江戸の痕跡を探すために、東京都内の歴史に関わる書籍や、「江戸名所」などの書籍を用意・展示してほしい。また、生徒の疑問によって、書籍を紹介してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 生徒は、東京都内に残る江戸の痕跡を探すためのフィールドワークを計画・実施する。そのための事前調査をインターネットだけでなく、書籍を用いてさせたい。
また、フィールドワーク後、自分たちが見つけた江戸を学年の友達にプレゼンテーションするために、「なぜそこが江戸なのか」という裏付けを、資料でもさせたい。現在の東京に関する資料と、江戸に関する資料、特に地図や図版など視覚に訴えるもの、また江戸時代に出版されたものが紹介されている資料を用意してほしい。
提示資料 
『江戸切絵図で歩く 広重の大江戸名所百景散歩』. 堀晃明著. 人文社. 1996
歌川広重が幕末に描いた『名所江戸百景』。その風景がどの角度から描かれたものなのか、『江戸切絵図』と現代地図を見開きに配して検証している。『名所江戸百景』のそれぞれの絵にも丁寧な解説がつけられている。 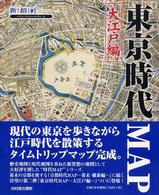
『東京時代MAP 大江戸編』.松岡満箸.光村推古書院.2005
江戸時代の地図と、現代の東京の地図の2つの地図を照らし合わせることが可能。江戸時代の地図の上に、現代の東京の地図が印刷された半透明のトレーシング・ペーパーを重ね、江戸と現在の東京の位置関係を知ることができる。
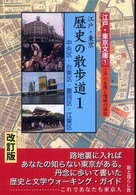
『江戸東京 歴史の散歩道』.街の暮らし社編.街と暮らし社.2001~2003
東京23区内に残る歴史の名残を詳細地図と詳しい解説でつづっている。寺・神社・記念碑・城址・資料館など、江戸から東京にかけて様々な施設が掲載されており、実際に手にして現地に行くとより理解が深まる 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 江戸東京古地図関係本(中学生以上).xls
キーワード1 江戸 キーワード2 フィールドワーク キーワード3 プレゼンテーション 授業計画・指導案等 日本文化探訪.pdf 児童・生徒の作品 授業者 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科) 授業者コメント 現代、生徒たちは調べると言えばインターネット、発表すると言えばパワーポイントといった具合である。しかし、現実とネット上の世界とは別物であり、またネット上の情報がすべて正しいとは限らない。その場に行ってこそ分かること、元になった資料を見てこそ分かることがあると気づかせたい。そのために、図書館の協力は欠かせない。キーワードを入力しなくても、江戸の世界が広がっている書籍、またその書籍が並んでいる図書館のスペースで、生徒は多くの発見をする。図書館を利用しての授業中はもちろんだが、放課後などを使っての自主学習の時間でも、学校司書の助言で、生徒はさまざまな資料に気づくことができた。
実際のプレゼンテーションでも、図書館から借りた本を提示し、「図書館にありますから、興味のある人は開いてみてください」と発表する生徒がいた。
司書・司書教諭コメント 公共図書館の団体貸し出しも受け、学校の蔵書とあわせ約150冊の資料を提供。東京の古地図が掲載された資料が多数あるなか、どの資料がより生徒に活用しやすいものか、社会科の教員の目でみてもらい、特にすすめる資料を3点上記に紹介している。
古地図に慣れるまでは、生徒も少々手間取っていたが、見慣れてくると自分たちが訪れる場所の掲載されている本を探しだし、フィールドワークや発表に活用しているようすがうかがえた。 情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2012年12月5日 事例作成者氏名 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科)・渡辺有理子(司書)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863483 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0119 |
|---|---|
| 校種 | 中高一貫校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | わかりやすく伝えよう(プレゼンテーション) |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・学習支援 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 東京都内に残る江戸の痕跡を探すために、東京都内の歴史に関わる書籍や、「江戸名所」などの書籍を用意・展示してほしい。また、生徒の疑問によって、書籍を紹介してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 生徒は、東京都内に残る江戸の痕跡を探すためのフィールドワークを計画・実施する。そのための事前調査をインターネットだけでなく、書籍を用いてさせたい。 また、フィールドワーク後、自分たちが見つけた江戸を学年の友達にプレゼンテーションするために、「なぜそこが江戸なのか」という裏付けを、資料でもさせたい。現在の東京に関する資料と、江戸に関する資料、特に地図や図版など視覚に訴えるもの、また江戸時代に出版されたものが紹介されている資料を用意してほしい。 |
| 提示資料 | |
 | 『江戸切絵図で歩く 広重の大江戸名所百景散歩』. 堀晃明著. 人文社. 1996 歌川広重が幕末に描いた『名所江戸百景』。その風景がどの角度から描かれたものなのか、『江戸切絵図』と現代地図を見開きに配して検証している。『名所江戸百景』のそれぞれの絵にも丁寧な解説がつけられている。 |
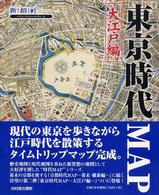 | 『東京時代MAP 大江戸編』.松岡満箸.光村推古書院.2005 江戸時代の地図と、現代の東京の地図の2つの地図を照らし合わせることが可能。江戸時代の地図の上に、現代の東京の地図が印刷された半透明のトレーシング・ペーパーを重ね、江戸と現在の東京の位置関係を知ることができる。 |
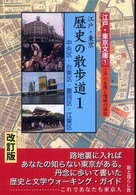 | 『江戸東京 歴史の散歩道』.街の暮らし社編.街と暮らし社.2001~2003 東京23区内に残る歴史の名残を詳細地図と詳しい解説でつづっている。寺・神社・記念碑・城址・資料館など、江戸から東京にかけて様々な施設が掲載されており、実際に手にして現地に行くとより理解が深まる |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 江戸東京古地図関係本(中学生以上).xls |
| キーワード1 | 江戸 |
| キーワード2 | フィールドワーク |
| キーワード3 | プレゼンテーション |
| 授業計画・指導案等 | 日本文化探訪.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科) |
| 授業者コメント | 現代、生徒たちは調べると言えばインターネット、発表すると言えばパワーポイントといった具合である。しかし、現実とネット上の世界とは別物であり、またネット上の情報がすべて正しいとは限らない。その場に行ってこそ分かること、元になった資料を見てこそ分かることがあると気づかせたい。そのために、図書館の協力は欠かせない。キーワードを入力しなくても、江戸の世界が広がっている書籍、またその書籍が並んでいる図書館のスペースで、生徒は多くの発見をする。図書館を利用しての授業中はもちろんだが、放課後などを使っての自主学習の時間でも、学校司書の助言で、生徒はさまざまな資料に気づくことができた。 実際のプレゼンテーションでも、図書館から借りた本を提示し、「図書館にありますから、興味のある人は開いてみてください」と発表する生徒がいた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 公共図書館の団体貸し出しも受け、学校の蔵書とあわせ約150冊の資料を提供。東京の古地図が掲載された資料が多数あるなか、どの資料がより生徒に活用しやすいものか、社会科の教員の目でみてもらい、特にすすめる資料を3点上記に紹介している。 古地図に慣れるまでは、生徒も少々手間取っていたが、見慣れてくると自分たちが訪れる場所の掲載されている本を探しだし、フィールドワークや発表に活用しているようすがうかがえた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
| 事例作成日 | 2012年12月5日 |
| 事例作成者氏名 | 愛甲修子(国語科)・藤木正史(社会科)・渡辺有理子(司書) |
記入者:渡辺(主担)

























