お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0130 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 栄養 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供、レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 栄養や食事に関するグループ別の調べ学習を行うので、各グループのテーマに沿った図書を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 調べる課題は以下の通り。
①風邪をひいたときに食べるといい食材 ②砂糖のとりすぎは体にどう影響するか ③魚を食べると頭は良くなるの? ④スポーツをする人のための栄養学 ⑤腹もちのよい食事 ⑥身体を温める食事 ⑦日本人の栄養事情 ⑧血液がさらさらとは?
提示資料 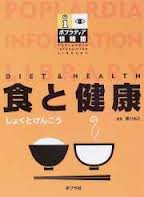
『食と健康』(ポプラディア情報館) 豊川弘之/監修 ポプラ社 2006年
どのグループのテーマでも、参考になった本。 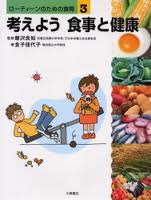
『ローティーンのための食育1~3』 藤沢良知 小峰書店 2005年
2巻健康な体と栄養 3巻考えよう食事と健康 が役立った。 
『「食育」の大研究』 PHP研究所 2008年
今回のテーマに合っていたので、数を用意したかった1冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 栄養 (中1 家庭 2011).xls
キーワード1 食事 キーワード2 栄養 キーワード3 食育 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 鎌野育代 授業者コメント 食事記録からのテーマ設定であったため、ある程度は予想されるテーマであった。一斉学習より一人ひとりの生徒が得る知識は少ないが、自分のテーマについては、非常に詳しくなっている生徒が見られた。栄養についての学習は継続が必要であることからもまた違った分野でも今回の学習をつなげたい。なお、簡単な授業計画は以下の通り。
☆ 指導計画
・食事記録から自分の食事の検討をしよう(1)
・テーマを決定する(1)
・文献調査・発表内容の計画(2)
・発表会(1)グループごとの発表。(一人発表3分、質疑2分) 司書・司書教諭コメント 事前にテーマを知らせてもらい、テーマに関連する資料を準備した。調べ学習を家庭科室で行うので、本と一緒に授業に参加させていただいた。テーマを探している生徒に資料を提示し、アドバイスすることができた。自分の調べたいテーマがどの本に載っているのかを探すのがまず一苦労といった様子だが、本を手に入れた後の調べは早い。『食と健康』のように、テーマ全般をカバーした本をまずは事典のように使い、その後テーマ個別の図書を見つける…というように、調べを進める子の姿が見られた。病人食を調べている子たちには、一般書の方が役に立っていた様子だった。また、糖尿病と食事の関係について調べを進めていた生徒の中には、一般書でも飽き足らず、記述を追って専門書まで手に取っていた子もいた。
児童書は市立図書館から、一般書、専門書は県立図書館から団体貸出を利用し取り寄せておいたものだった。
児童向けの資料だけでなく、テーマに沿った資料を手渡すことができれば、調べの成果も変わって来るのだと実感した。 情報提供校 千葉大学教育学部附属中学校 事例作成日 2012年1月(入力は1013年1月) 実践日2012年1月18日 事例作成者氏名 千葉大学教育学部附属中学校司書 子安伸枝
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863409 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0130 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 栄養 対象学年 中1 活用・支援の種類 資料提供、レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 栄養や食事に関するグループ別の調べ学習を行うので、各グループのテーマに沿った図書を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 調べる課題は以下の通り。
①風邪をひいたときに食べるといい食材 ②砂糖のとりすぎは体にどう影響するか ③魚を食べると頭は良くなるの? ④スポーツをする人のための栄養学 ⑤腹もちのよい食事 ⑥身体を温める食事 ⑦日本人の栄養事情 ⑧血液がさらさらとは?
提示資料 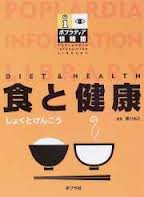
『食と健康』(ポプラディア情報館) 豊川弘之/監修 ポプラ社 2006年
どのグループのテーマでも、参考になった本。 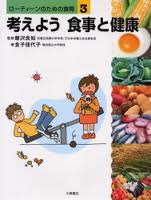
『ローティーンのための食育1~3』 藤沢良知 小峰書店 2005年
2巻健康な体と栄養 3巻考えよう食事と健康 が役立った。 
『「食育」の大研究』 PHP研究所 2008年
今回のテーマに合っていたので、数を用意したかった1冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 栄養 (中1 家庭 2011).xls
キーワード1 食事 キーワード2 栄養 キーワード3 食育 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 授業者 鎌野育代 授業者コメント 食事記録からのテーマ設定であったため、ある程度は予想されるテーマであった。一斉学習より一人ひとりの生徒が得る知識は少ないが、自分のテーマについては、非常に詳しくなっている生徒が見られた。栄養についての学習は継続が必要であることからもまた違った分野でも今回の学習をつなげたい。なお、簡単な授業計画は以下の通り。
☆ 指導計画
・食事記録から自分の食事の検討をしよう(1)
・テーマを決定する(1)
・文献調査・発表内容の計画(2)
・発表会(1)グループごとの発表。(一人発表3分、質疑2分) 司書・司書教諭コメント 事前にテーマを知らせてもらい、テーマに関連する資料を準備した。調べ学習を家庭科室で行うので、本と一緒に授業に参加させていただいた。テーマを探している生徒に資料を提示し、アドバイスすることができた。自分の調べたいテーマがどの本に載っているのかを探すのがまず一苦労といった様子だが、本を手に入れた後の調べは早い。『食と健康』のように、テーマ全般をカバーした本をまずは事典のように使い、その後テーマ個別の図書を見つける…というように、調べを進める子の姿が見られた。病人食を調べている子たちには、一般書の方が役に立っていた様子だった。また、糖尿病と食事の関係について調べを進めていた生徒の中には、一般書でも飽き足らず、記述を追って専門書まで手に取っていた子もいた。
児童書は市立図書館から、一般書、専門書は県立図書館から団体貸出を利用し取り寄せておいたものだった。
児童向けの資料だけでなく、テーマに沿った資料を手渡すことができれば、調べの成果も変わって来るのだと実感した。 情報提供校 千葉大学教育学部附属中学校 事例作成日 2012年1月(入力は1013年1月) 実践日2012年1月18日 事例作成者氏名 千葉大学教育学部附属中学校司書 子安伸枝
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863409 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0130 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 家庭 |
| 単元 | 栄養 |
| 対象学年 | 中1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供、レファレンス |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 栄養や食事に関するグループ別の調べ学習を行うので、各グループのテーマに沿った図書を用意してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 調べる課題は以下の通り。 ①風邪をひいたときに食べるといい食材 ②砂糖のとりすぎは体にどう影響するか ③魚を食べると頭は良くなるの? ④スポーツをする人のための栄養学 ⑤腹もちのよい食事 ⑥身体を温める食事 ⑦日本人の栄養事情 ⑧血液がさらさらとは? |
| 提示資料 | |
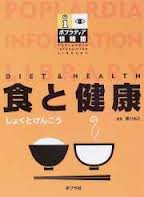 | 『食と健康』(ポプラディア情報館) 豊川弘之/監修 ポプラ社 2006年 どのグループのテーマでも、参考になった本。 |
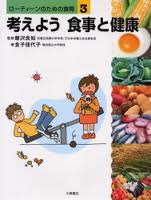 | 『ローティーンのための食育1~3』 藤沢良知 小峰書店 2005年 2巻健康な体と栄養 3巻考えよう食事と健康 が役立った。 |
 | 『「食育」の大研究』 PHP研究所 2008年 今回のテーマに合っていたので、数を用意したかった1冊。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 栄養 (中1 家庭 2011).xls |
| キーワード1 | 食事 |
| キーワード2 | 栄養 |
| キーワード3 | 食育 |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 鎌野育代 |
| 授業者コメント | 食事記録からのテーマ設定であったため、ある程度は予想されるテーマであった。一斉学習より一人ひとりの生徒が得る知識は少ないが、自分のテーマについては、非常に詳しくなっている生徒が見られた。栄養についての学習は継続が必要であることからもまた違った分野でも今回の学習をつなげたい。なお、簡単な授業計画は以下の通り。 ☆ 指導計画 ・食事記録から自分の食事の検討をしよう(1) ・テーマを決定する(1) ・文献調査・発表内容の計画(2) ・発表会(1)グループごとの発表。(一人発表3分、質疑2分) |
| 司書・司書教諭コメント | 事前にテーマを知らせてもらい、テーマに関連する資料を準備した。調べ学習を家庭科室で行うので、本と一緒に授業に参加させていただいた。テーマを探している生徒に資料を提示し、アドバイスすることができた。自分の調べたいテーマがどの本に載っているのかを探すのがまず一苦労といった様子だが、本を手に入れた後の調べは早い。『食と健康』のように、テーマ全般をカバーした本をまずは事典のように使い、その後テーマ個別の図書を見つける…というように、調べを進める子の姿が見られた。病人食を調べている子たちには、一般書の方が役に立っていた様子だった。また、糖尿病と食事の関係について調べを進めていた生徒の中には、一般書でも飽き足らず、記述を追って専門書まで手に取っていた子もいた。 児童書は市立図書館から、一般書、専門書は県立図書館から団体貸出を利用し取り寄せておいたものだった。 児童向けの資料だけでなく、テーマに沿った資料を手渡すことができれば、調べの成果も変わって来るのだと実感した。 |
| 情報提供校 | 千葉大学教育学部附属中学校 |
| 事例作成日 | 2012年1月(入力は1013年1月) 実践日2012年1月18日 |
| 事例作成者氏名 | 千葉大学教育学部附属中学校司書 子安伸枝 |
記入者:中山(主担)

























