お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0134 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 「読書発表会」をしよう 対象学年 中学年 活用・支援の種類 ブックトークの説明・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 4年国語「読書発表会」はブックトークである。ブックトークのやり方を司書から説明させてもらい授業に関わった。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ・友達に本を紹介する。
・ブックトークと通常行っている本の紹介との違いを明確にする。
・いろいろなジャンルの本に触れさせる。
・子ども達のブックトークは、何冊で行うのか?発表は個人か?グループか?
提示資料 見本として2種類(巳年なので「ヘビは好きですか」と雪が降った後だったので「空を飛べたら」)のブックトークテーマで用意し、5クラスにそれぞれ1種類行った。その中で紹介した本。普段あまり動かない岩波少年文庫が借りられた。 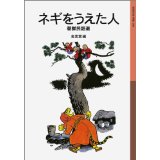
ネギをうえた人-朝鮮民話選(岩波少年文庫)
金素雲編 岩波書店 (2001年)
へびの出てくる話『大蛇とヒキガエル』を途中まで読んだ。 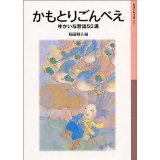
かもとりごんべえ-ゆかいな昔話50選(岩波少年文庫)
稲田和子編 岩波書店(2000年)
同じくへびの出てくる話『たのきゅう』を途中まで読んだ。 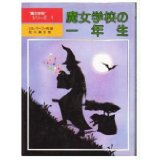
魔女学校の一年生(児童図書館文学の部屋-魔女学校シリーズ)
ジル・マーフィ著 評論社(1987年)
本文に出てくる魔女学校の校歌を使ってクイズ。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 ブックトーク キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 配布資料・ワークシート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 田邉雅子他4名(4学年の先生方) 授業者コメント ・子ども達は、ブックトークの説明を聞き、自分もやってみたいという気持ちになり原稿作りや発表の練習をしていた。
・本を選ぶ時はいつもと違ったジャンルをと説明があったので、普段手にしない本を見つけてくる子どももいた。そのことから、いろいろな分類の本に目が向いていたように思う。
・1冊の本のあらすじを書くことは、子ども達にとって難しかったようである。どこをどのようにまとめたらよいのか苦戦していた。
・友達の前での発表は緊張したようだったが、ブックトークを体験したことにより、最後までやり終えた達成感や満足感を体験できよかったようだ。
・友達の発表も自分と比べながら聞くことができ楽しかったと話していた。 司書・司書教諭コメント 昨年度から教科書が変わりブックトークが入った。昨年度の活動の様子を見て、教科書の説明を読んだだけで行うのは難しそうだと思った(昨年は紹介する本の相談にだけ関わった)。
そこで今年度は、ブックトークの説明をさせていただくことにした。
司書の見本ブックトークでは、普段目立たない本を紹介した。それらが借りられ、予約までついたので嬉しかった。
子ども達の発表を少しだけ見せていただいたり、原稿を読ませていただいたりした。クラスによって、グループ発表と個人発表という違いがあったが、ほとんどの子ども達が組み立てに苦心したようだ。そのような中で、司書が真似したくなるくらい上手な発表もあった。司書にとっても勉強になった。
なお、ブックトークの説明方法については、袖ケ浦市立昭和中学校司書和田幸子氏の実践を参考にさせていただいた。
情報提供校 千葉県船橋市立塚田小学校 事例作成日 2013/02/12 事例作成者氏名 中村貴子
記入者:中村
カウンタ
3863392 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0134 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 「読書発表会」をしよう 対象学年 中学年 活用・支援の種類 ブックトークの説明・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 4年国語「読書発表会」はブックトークである。ブックトークのやり方を司書から説明させてもらい授業に関わった。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ・友達に本を紹介する。
・ブックトークと通常行っている本の紹介との違いを明確にする。
・いろいろなジャンルの本に触れさせる。
・子ども達のブックトークは、何冊で行うのか?発表は個人か?グループか?
提示資料 見本として2種類(巳年なので「ヘビは好きですか」と雪が降った後だったので「空を飛べたら」)のブックトークテーマで用意し、5クラスにそれぞれ1種類行った。その中で紹介した本。普段あまり動かない岩波少年文庫が借りられた。 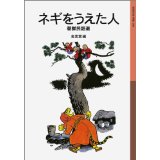
ネギをうえた人-朝鮮民話選(岩波少年文庫)
金素雲編 岩波書店 (2001年)
へびの出てくる話『大蛇とヒキガエル』を途中まで読んだ。 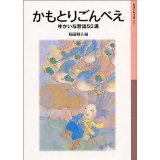
かもとりごんべえ-ゆかいな昔話50選(岩波少年文庫)
稲田和子編 岩波書店(2000年)
同じくへびの出てくる話『たのきゅう』を途中まで読んだ。 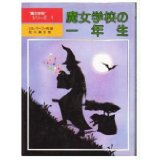
魔女学校の一年生(児童図書館文学の部屋-魔女学校シリーズ)
ジル・マーフィ著 評論社(1987年)
本文に出てくる魔女学校の校歌を使ってクイズ。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 ブックトーク キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 配布資料・ワークシート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 田邉雅子他4名(4学年の先生方) 授業者コメント ・子ども達は、ブックトークの説明を聞き、自分もやってみたいという気持ちになり原稿作りや発表の練習をしていた。
・本を選ぶ時はいつもと違ったジャンルをと説明があったので、普段手にしない本を見つけてくる子どももいた。そのことから、いろいろな分類の本に目が向いていたように思う。
・1冊の本のあらすじを書くことは、子ども達にとって難しかったようである。どこをどのようにまとめたらよいのか苦戦していた。
・友達の前での発表は緊張したようだったが、ブックトークを体験したことにより、最後までやり終えた達成感や満足感を体験できよかったようだ。
・友達の発表も自分と比べながら聞くことができ楽しかったと話していた。 司書・司書教諭コメント 昨年度から教科書が変わりブックトークが入った。昨年度の活動の様子を見て、教科書の説明を読んだだけで行うのは難しそうだと思った(昨年は紹介する本の相談にだけ関わった)。
そこで今年度は、ブックトークの説明をさせていただくことにした。
司書の見本ブックトークでは、普段目立たない本を紹介した。それらが借りられ、予約までついたので嬉しかった。
子ども達の発表を少しだけ見せていただいたり、原稿を読ませていただいたりした。クラスによって、グループ発表と個人発表という違いがあったが、ほとんどの子ども達が組み立てに苦心したようだ。そのような中で、司書が真似したくなるくらい上手な発表もあった。司書にとっても勉強になった。
なお、ブックトークの説明方法については、袖ケ浦市立昭和中学校司書和田幸子氏の実践を参考にさせていただいた。
情報提供校 千葉県船橋市立塚田小学校 事例作成日 2013/02/12 事例作成者氏名 中村貴子
記入者:中村
カウンタ
3863392 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0134 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 「読書発表会」をしよう |
| 対象学年 | 中学年 |
| 活用・支援の種類 | ブックトークの説明・資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 4年国語「読書発表会」はブックトークである。ブックトークのやり方を司書から説明させてもらい授業に関わった。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ・友達に本を紹介する。 ・ブックトークと通常行っている本の紹介との違いを明確にする。 ・いろいろなジャンルの本に触れさせる。 ・子ども達のブックトークは、何冊で行うのか?発表は個人か?グループか? |
| 提示資料 | 見本として2種類(巳年なので「ヘビは好きですか」と雪が降った後だったので「空を飛べたら」)のブックトークテーマで用意し、5クラスにそれぞれ1種類行った。その中で紹介した本。普段あまり動かない岩波少年文庫が借りられた。 |
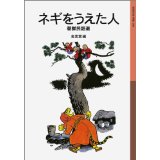 | ネギをうえた人-朝鮮民話選(岩波少年文庫) 金素雲編 岩波書店 (2001年) へびの出てくる話『大蛇とヒキガエル』を途中まで読んだ。 |
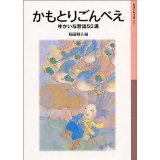 | かもとりごんべえ-ゆかいな昔話50選(岩波少年文庫) 稲田和子編 岩波書店(2000年) 同じくへびの出てくる話『たのきゅう』を途中まで読んだ。 |
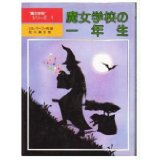 | 魔女学校の一年生(児童図書館文学の部屋-魔女学校シリーズ) ジル・マーフィ著 評論社(1987年) 本文に出てくる魔女学校の校歌を使ってクイズ。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | ブックトーク |
| キーワード2 | |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 配布資料・ワークシート.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 田邉雅子他4名(4学年の先生方) |
| 授業者コメント | ・子ども達は、ブックトークの説明を聞き、自分もやってみたいという気持ちになり原稿作りや発表の練習をしていた。 ・本を選ぶ時はいつもと違ったジャンルをと説明があったので、普段手にしない本を見つけてくる子どももいた。そのことから、いろいろな分類の本に目が向いていたように思う。 ・1冊の本のあらすじを書くことは、子ども達にとって難しかったようである。どこをどのようにまとめたらよいのか苦戦していた。 ・友達の前での発表は緊張したようだったが、ブックトークを体験したことにより、最後までやり終えた達成感や満足感を体験できよかったようだ。 ・友達の発表も自分と比べながら聞くことができ楽しかったと話していた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 昨年度から教科書が変わりブックトークが入った。昨年度の活動の様子を見て、教科書の説明を読んだだけで行うのは難しそうだと思った(昨年は紹介する本の相談にだけ関わった)。 そこで今年度は、ブックトークの説明をさせていただくことにした。 司書の見本ブックトークでは、普段目立たない本を紹介した。それらが借りられ、予約までついたので嬉しかった。 子ども達の発表を少しだけ見せていただいたり、原稿を読ませていただいたりした。クラスによって、グループ発表と個人発表という違いがあったが、ほとんどの子ども達が組み立てに苦心したようだ。そのような中で、司書が真似したくなるくらい上手な発表もあった。司書にとっても勉強になった。 なお、ブックトークの説明方法については、袖ケ浦市立昭和中学校司書和田幸子氏の実践を参考にさせていただいた。 |
| 情報提供校 | 千葉県船橋市立塚田小学校 |
| 事例作成日 | 2013/02/12 |
| 事例作成者氏名 | 中村貴子 |
記入者:中村

























