お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0141 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 1年1組絵本の森へようこそ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 一人ひとりが学校図書館で選んだ自分の絵本に向き合い、絵本を紹介する。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 図書館という空間には、いろいろな種類の本があり、絵本は絵本の棚にまとまっている。1年1組の子どもたちはその絵本のまとまっている空間を「絵本の森」と呼んでいた。彼らがこの「森」で読んだ本から、それぞれが気に入った「自分の絵本」を紹介し合い、マップにまとめる活動をするということだった。協働にあたり、司書として選書に戸惑う児童への助言を行うとともに、児童の語りを丁寧に聞くことに努める。
提示資料 子どもの選んだ本と事後に影響のあった本の一部 
『14ひきのとんぼいけ』 いわむらかずお著 童心社 2002年 実在する いわむらかずお美術館の北の森に掘られた田んぼのための池を3年間観察してできた絵本。くんちゃん、とっくんたちを乗せたボートが池を進むと「みず ゆらゆら、くさ ゆらゆら、とんぼ ゆらゆら。」自分の名前が登場するそのくだりに魅かれたY君は、この本がお気に入りになった。 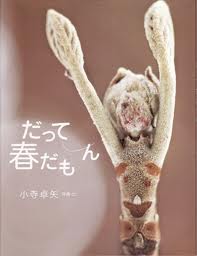
『だって 春だもん』 小寺卓也著 アリス館 2009年 森にやってきた春をよろこぶ自然の様子を写真で伝える絵本。3月に司書が読み聞かせしたところ、「ゆーら ゆーら ぷりん おたまじゃくしが およぎだす」というくだりがあって、「Y君のすきな〈ゆら〉だ!」とクラス内のみなが一斉に反応し、Y君の顔をみた。 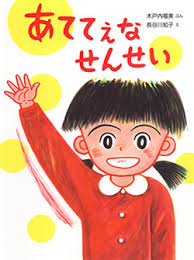
『あててぇな せんせい』 木戸内福美文 長谷川真知子絵 あかね書房 2012年 「本もよく読むよしみちゃんですが…、国語の授業中はなかなか発言することができません。」これを読んだNちゃんは、「自分と同じだ。」と言って、この本が好きになった。授業中にNちゃんが手をあげると、クラス中が「Nちゃんをあててぇな、先生!」と教師に注意を促し、Nちゃんの発言意欲をみんなで盛り立てる場面が見られるようになった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 絵本の森(小1国語)201303 改訂版.xls
キーワード1 絵本 キーワード2 読書生活 キーワード3 紹介 授業計画・指導案等 授業セミナー指導案最終(吉永).pdf 児童・生徒の作品 授業者 吉永 安里教諭 (2013年度より 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 教員) 授業者コメント 自分の好きな本とその本への思いを友だちに受け止めてもらうことで、本を介して新たな人間関係が生まれたり、新たな関係性が生まれる様子が見られ、大変有意義な活動であったと感じた。読書は個別性の高い、プライベートな行為ではあるが、学級の人間関係と本を巧みにつないでいくことで、読書生活が豊かになることを確信した。 (2013年2月KOGANEI授業セミナー公開授業) 司書・司書教諭コメント 授業者からの依頼は、選書に迷った児童には、紹介し合うのにふさわしい内容をもった本かどうかのアドバイスしてほしいということだった。なにが「ふさわしい」かの内容について授業者と話し合い、知識の本・解説の本ではなく、ストーリー性のあるものに限定することとした。1年1組全員で紹介し合い、次にお相手の2年1組に紹介し、最後は副校長と司書が全員の紹介を聞いた。子どもたちは、それぞれのお薦めのポイント<キラキラ>を伝えた。互いに話したり聞いたりすることを通して、子どもたちは相互に影響し合い、読みが深まったことを感じた。子どもたちのこの1年間の読書生活の総仕上げとしての「語り」を聞いてもらう人たちの一員として、「本のプロ」である司書を子どもたち自身が選んでくれたことを何よりうれしく思う。そういう子どもたちに育てた授業者に深く感謝したい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2013年3月 (実践は 2013年1月から2月) 事例作成者氏名 入力 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863476 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0141 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 1年1組絵本の森へようこそ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 一人ひとりが学校図書館で選んだ自分の絵本に向き合い、絵本を紹介する。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 図書館という空間には、いろいろな種類の本があり、絵本は絵本の棚にまとまっている。1年1組の子どもたちはその絵本のまとまっている空間を「絵本の森」と呼んでいた。彼らがこの「森」で読んだ本から、それぞれが気に入った「自分の絵本」を紹介し合い、マップにまとめる活動をするということだった。協働にあたり、司書として選書に戸惑う児童への助言を行うとともに、児童の語りを丁寧に聞くことに努める。
提示資料 子どもの選んだ本と事後に影響のあった本の一部 
『14ひきのとんぼいけ』 いわむらかずお著 童心社 2002年 実在する いわむらかずお美術館の北の森に掘られた田んぼのための池を3年間観察してできた絵本。くんちゃん、とっくんたちを乗せたボートが池を進むと「みず ゆらゆら、くさ ゆらゆら、とんぼ ゆらゆら。」自分の名前が登場するそのくだりに魅かれたY君は、この本がお気に入りになった。 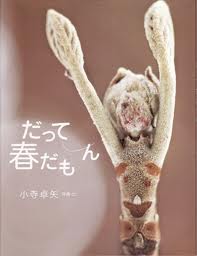
『だって 春だもん』 小寺卓也著 アリス館 2009年 森にやってきた春をよろこぶ自然の様子を写真で伝える絵本。3月に司書が読み聞かせしたところ、「ゆーら ゆーら ぷりん おたまじゃくしが およぎだす」というくだりがあって、「Y君のすきな〈ゆら〉だ!」とクラス内のみなが一斉に反応し、Y君の顔をみた。 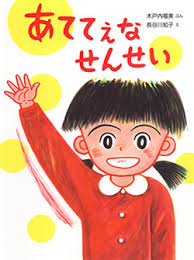
『あててぇな せんせい』 木戸内福美文 長谷川真知子絵 あかね書房 2012年 「本もよく読むよしみちゃんですが…、国語の授業中はなかなか発言することができません。」これを読んだNちゃんは、「自分と同じだ。」と言って、この本が好きになった。授業中にNちゃんが手をあげると、クラス中が「Nちゃんをあててぇな、先生!」と教師に注意を促し、Nちゃんの発言意欲をみんなで盛り立てる場面が見られるようになった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 絵本の森(小1国語)201303 改訂版.xls
キーワード1 絵本 キーワード2 読書生活 キーワード3 紹介 授業計画・指導案等 授業セミナー指導案最終(吉永).pdf 児童・生徒の作品 授業者 吉永 安里教諭 (2013年度より 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 教員) 授業者コメント 自分の好きな本とその本への思いを友だちに受け止めてもらうことで、本を介して新たな人間関係が生まれたり、新たな関係性が生まれる様子が見られ、大変有意義な活動であったと感じた。読書は個別性の高い、プライベートな行為ではあるが、学級の人間関係と本を巧みにつないでいくことで、読書生活が豊かになることを確信した。 (2013年2月KOGANEI授業セミナー公開授業) 司書・司書教諭コメント 授業者からの依頼は、選書に迷った児童には、紹介し合うのにふさわしい内容をもった本かどうかのアドバイスしてほしいということだった。なにが「ふさわしい」かの内容について授業者と話し合い、知識の本・解説の本ではなく、ストーリー性のあるものに限定することとした。1年1組全員で紹介し合い、次にお相手の2年1組に紹介し、最後は副校長と司書が全員の紹介を聞いた。子どもたちは、それぞれのお薦めのポイント<キラキラ>を伝えた。互いに話したり聞いたりすることを通して、子どもたちは相互に影響し合い、読みが深まったことを感じた。子どもたちのこの1年間の読書生活の総仕上げとしての「語り」を聞いてもらう人たちの一員として、「本のプロ」である司書を子どもたち自身が選んでくれたことを何よりうれしく思う。そういう子どもたちに育てた授業者に深く感謝したい。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2013年3月 (実践は 2013年1月から2月) 事例作成者氏名 入力 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863476 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0141 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 1年1組絵本の森へようこそ |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 一人ひとりが学校図書館で選んだ自分の絵本に向き合い、絵本を紹介する。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 図書館という空間には、いろいろな種類の本があり、絵本は絵本の棚にまとまっている。1年1組の子どもたちはその絵本のまとまっている空間を「絵本の森」と呼んでいた。彼らがこの「森」で読んだ本から、それぞれが気に入った「自分の絵本」を紹介し合い、マップにまとめる活動をするということだった。協働にあたり、司書として選書に戸惑う児童への助言を行うとともに、児童の語りを丁寧に聞くことに努める。 |
| 提示資料 | 子どもの選んだ本と事後に影響のあった本の一部 |
 | 『14ひきのとんぼいけ』 いわむらかずお著 童心社 2002年 実在する いわむらかずお美術館の北の森に掘られた田んぼのための池を3年間観察してできた絵本。くんちゃん、とっくんたちを乗せたボートが池を進むと「みず ゆらゆら、くさ ゆらゆら、とんぼ ゆらゆら。」自分の名前が登場するそのくだりに魅かれたY君は、この本がお気に入りになった。 |
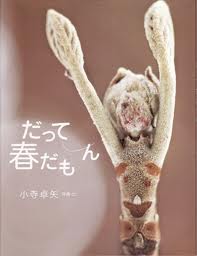 | 『だって 春だもん』 小寺卓也著 アリス館 2009年 森にやってきた春をよろこぶ自然の様子を写真で伝える絵本。3月に司書が読み聞かせしたところ、「ゆーら ゆーら ぷりん おたまじゃくしが およぎだす」というくだりがあって、「Y君のすきな〈ゆら〉だ!」とクラス内のみなが一斉に反応し、Y君の顔をみた。 |
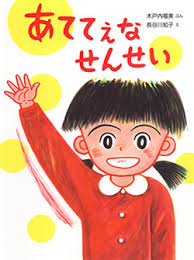 | 『あててぇな せんせい』 木戸内福美文 長谷川真知子絵 あかね書房 2012年 「本もよく読むよしみちゃんですが…、国語の授業中はなかなか発言することができません。」これを読んだNちゃんは、「自分と同じだ。」と言って、この本が好きになった。授業中にNちゃんが手をあげると、クラス中が「Nちゃんをあててぇな、先生!」と教師に注意を促し、Nちゃんの発言意欲をみんなで盛り立てる場面が見られるようになった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 絵本の森(小1国語)201303 改訂版.xls |
| キーワード1 | 絵本 |
| キーワード2 | 読書生活 |
| キーワード3 | 紹介 |
| 授業計画・指導案等 | 授業セミナー指導案最終(吉永).pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 吉永 安里教諭 (2013年度より 國學院大學人間開発学部子ども支援学科 教員) |
| 授業者コメント | 自分の好きな本とその本への思いを友だちに受け止めてもらうことで、本を介して新たな人間関係が生まれたり、新たな関係性が生まれる様子が見られ、大変有意義な活動であったと感じた。読書は個別性の高い、プライベートな行為ではあるが、学級の人間関係と本を巧みにつないでいくことで、読書生活が豊かになることを確信した。 (2013年2月KOGANEI授業セミナー公開授業) |
| 司書・司書教諭コメント | 授業者からの依頼は、選書に迷った児童には、紹介し合うのにふさわしい内容をもった本かどうかのアドバイスしてほしいということだった。なにが「ふさわしい」かの内容について授業者と話し合い、知識の本・解説の本ではなく、ストーリー性のあるものに限定することとした。1年1組全員で紹介し合い、次にお相手の2年1組に紹介し、最後は副校長と司書が全員の紹介を聞いた。子どもたちは、それぞれのお薦めのポイント<キラキラ>を伝えた。互いに話したり聞いたりすることを通して、子どもたちは相互に影響し合い、読みが深まったことを感じた。子どもたちのこの1年間の読書生活の総仕上げとしての「語り」を聞いてもらう人たちの一員として、「本のプロ」である司書を子どもたち自身が選んでくれたことを何よりうれしく思う。そういう子どもたちに育てた授業者に深く感謝したい。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2013年3月 (実践は 2013年1月から2月) |
| 事例作成者氏名 | 入力 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀 |
記入者:中山(主担)

























