お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0152 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 民謡を楽しもう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもたちが民謡を知り学ぶことを資料から深めさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 1.子どもたちがインターネットを使った調べ学習をしていく際に、誤情報で理解をしていくことのないよう、民謡についての研究書など、教師の教材研究資料の提供依頼。
2.図書資料で子どもたちが民謡について調べることのできる資料の提供依頼。"
提示資料 『日本のおどり①②③』『日本民謡集』『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』
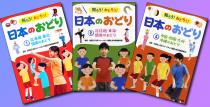
『日本のおどり①②③』社団法人日本フォークダンス連盟(日本民謡委員会) すずき出版 2013年初版
日本各地の伝統的な踊りを歴史、特色とともに、図解。とくに有名なものは旋律の楽譜も添付されている。①北海道・東北・関東 ②北信越・東海・関西 ③中国・四国・九州・沖縄 全3冊に分冊"
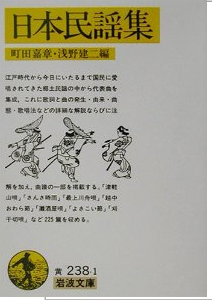
"『日本民謡集』町田嘉章,浅野健二 岩波書店 1960年初版 (1986年第25版を使用)
江戸時代から今日に至るまで国民に愛唱されてきた郷土民謡から225編をあつめ、歌詞、曲解説、歌詞の解説、とくに重要作品は採譜資料を添付されている。"

『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』東洋音楽学会編 音楽之友社 1967年初版(1982年第3版を使用)
民謡および民俗芸能(神楽・祭囃子)の歴史や系譜を子細に研究した専門書。とくに追分節、ハイヤ節、おけさ節について詳しい。"
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 民謡 キーワード2 (民謡の)歴史 キーワード3 授業計画・指導案等 2013年5.docx 児童・生徒の作品 授業者 齊藤 豊 授業者コメント 授業者の自分も民謡のことを知らなかったので、今回の取り組みを通して子どもとともに興味を広げながら活動を展開することができた。
今回は運動会で毎年取り組んでいる「ソーラン節」への取り組みに関連づけて活動を描いている。また、5年生はインターネットを使っての調べ学習、6年生はさらに調べたことをまとめ、一人一人がパワーポイントを使って表現する活動も行った。インターネットによる調べ学習の良さは、画像や音も並行して資料にしていくことができるところだった。文字情報で「民謡」を調べたうえに、実際の音楽を鑑賞したり、動画で視聴することで、理解が深まることをあらためて感じることができた。しかし、この活動を支えるにあたって、教師が事前に「民謡」についての教材研究を深める必要性が、より高まることも実感することができた。インターネット上の情報の中には、時折誤情報もあるため、子どもの集めた情報を一斉授業でシェアしながら修正するための教材研究のために、司書と協働する必要があった。
また、調べ学習をしたあとに、実際の演奏に触れる機会として、民謡の唄い手、津軽三味線奏者、太鼓と唄囃子の唄い手を招聘した。プログラムの中では、「ソーラン節」を民謡の唄い方を習うワークショップも行い、子どもたちに取って大変貴重な経験を提供することができた。
事後には、アウトリーチ活動当日の演奏の様子、子どもたちのパワーポイント作品、参考資料にした民謡の動画のURLを、掲示のみならず校内LANで公開し、子どもたちが任意でアクセスし視聴することができるようにし、今後の調べ学習の参考になるように整備した。
本実践は、校内外にわたる多くの方の協力があって実現することができた。授業をデザインするにあたっては、協力者の方々に授業のコンセプトを共有していただけるよう、メールや資料の提示を通して密な連絡を心がけた。しかし、授業者の見通しの甘さから、たびたび日程や活動内容の変更をせざるを得なくなるなどの迷惑をかけてしまった。次回の取り組みには本実践の経験を生かし、授業者が明確な見通しを描き、関係各所への連絡を確実に行えるようにしなくてはならないと反省をしている。 司書・司書教諭コメント 4月新学期から民謡を5年、6年で行うということを聞いて、資料を探していた。そんな時、すずき出版の『日本のおどり①②③』を見つけ、齊藤先生と検討した。子どもたちがわかりやすく書かれているのでこの3冊を購入して使うことにした。
他の2冊は、教員が民謡のことをよく知る上で大変有効な資料であった。ただ、絶版になっていたり、なかなか手に入らないものだったりで、世田谷区の図書館から借りた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 2013年6月14日作成 2013年5~6月実践 事例作成者氏名 吉岡裕子
記入者:吉岡(主担)
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0152 校種 小学校 教科・領域等 音楽 単元 民謡を楽しもう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもたちが民謡を知り学ぶことを資料から深めさせたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 1.子どもたちがインターネットを使った調べ学習をしていく際に、誤情報で理解をしていくことのないよう、民謡についての研究書など、教師の教材研究資料の提供依頼。
2.図書資料で子どもたちが民謡について調べることのできる資料の提供依頼。"
提示資料 『日本のおどり①②③』『日本民謡集』『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』
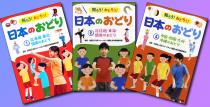
『日本のおどり①②③』社団法人日本フォークダンス連盟(日本民謡委員会) すずき出版 2013年初版
日本各地の伝統的な踊りを歴史、特色とともに、図解。とくに有名なものは旋律の楽譜も添付されている。①北海道・東北・関東 ②北信越・東海・関西 ③中国・四国・九州・沖縄 全3冊に分冊"
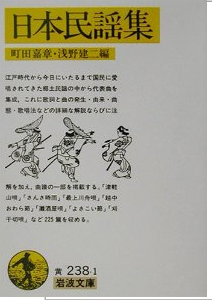
"『日本民謡集』町田嘉章,浅野健二 岩波書店 1960年初版 (1986年第25版を使用)
江戸時代から今日に至るまで国民に愛唱されてきた郷土民謡から225編をあつめ、歌詞、曲解説、歌詞の解説、とくに重要作品は採譜資料を添付されている。"

『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』東洋音楽学会編 音楽之友社 1967年初版(1982年第3版を使用)
民謡および民俗芸能(神楽・祭囃子)の歴史や系譜を子細に研究した専門書。とくに追分節、ハイヤ節、おけさ節について詳しい。"
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 民謡 キーワード2 (民謡の)歴史 キーワード3 授業計画・指導案等 2013年5.docx 児童・生徒の作品 授業者 齊藤 豊 授業者コメント 授業者の自分も民謡のことを知らなかったので、今回の取り組みを通して子どもとともに興味を広げながら活動を展開することができた。
今回は運動会で毎年取り組んでいる「ソーラン節」への取り組みに関連づけて活動を描いている。また、5年生はインターネットを使っての調べ学習、6年生はさらに調べたことをまとめ、一人一人がパワーポイントを使って表現する活動も行った。インターネットによる調べ学習の良さは、画像や音も並行して資料にしていくことができるところだった。文字情報で「民謡」を調べたうえに、実際の音楽を鑑賞したり、動画で視聴することで、理解が深まることをあらためて感じることができた。しかし、この活動を支えるにあたって、教師が事前に「民謡」についての教材研究を深める必要性が、より高まることも実感することができた。インターネット上の情報の中には、時折誤情報もあるため、子どもの集めた情報を一斉授業でシェアしながら修正するための教材研究のために、司書と協働する必要があった。
また、調べ学習をしたあとに、実際の演奏に触れる機会として、民謡の唄い手、津軽三味線奏者、太鼓と唄囃子の唄い手を招聘した。プログラムの中では、「ソーラン節」を民謡の唄い方を習うワークショップも行い、子どもたちに取って大変貴重な経験を提供することができた。
事後には、アウトリーチ活動当日の演奏の様子、子どもたちのパワーポイント作品、参考資料にした民謡の動画のURLを、掲示のみならず校内LANで公開し、子どもたちが任意でアクセスし視聴することができるようにし、今後の調べ学習の参考になるように整備した。
本実践は、校内外にわたる多くの方の協力があって実現することができた。授業をデザインするにあたっては、協力者の方々に授業のコンセプトを共有していただけるよう、メールや資料の提示を通して密な連絡を心がけた。しかし、授業者の見通しの甘さから、たびたび日程や活動内容の変更をせざるを得なくなるなどの迷惑をかけてしまった。次回の取り組みには本実践の経験を生かし、授業者が明確な見通しを描き、関係各所への連絡を確実に行えるようにしなくてはならないと反省をしている。 司書・司書教諭コメント 4月新学期から民謡を5年、6年で行うということを聞いて、資料を探していた。そんな時、すずき出版の『日本のおどり①②③』を見つけ、齊藤先生と検討した。子どもたちがわかりやすく書かれているのでこの3冊を購入して使うことにした。
他の2冊は、教員が民謡のことをよく知る上で大変有効な資料であった。ただ、絶版になっていたり、なかなか手に入らないものだったりで、世田谷区の図書館から借りた。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 2013年6月14日作成 2013年5~6月実践 事例作成者氏名 吉岡裕子
記入者:吉岡(主担)
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0152 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 音楽 |
| 単元 | 民謡を楽しもう |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 子どもたちが民謡を知り学ぶことを資料から深めさせたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 1.子どもたちがインターネットを使った調べ学習をしていく際に、誤情報で理解をしていくことのないよう、民謡についての研究書など、教師の教材研究資料の提供依頼。 2.図書資料で子どもたちが民謡について調べることのできる資料の提供依頼。" |
| 提示資料 | 『日本のおどり①②③』『日本民謡集』『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』 |
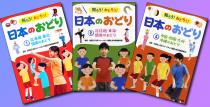 | 『日本のおどり①②③』社団法人日本フォークダンス連盟(日本民謡委員会) すずき出版 2013年初版 日本各地の伝統的な踊りを歴史、特色とともに、図解。とくに有名なものは旋律の楽譜も添付されている。①北海道・東北・関東 ②北信越・東海・関西 ③中国・四国・九州・沖縄 全3冊に分冊" |
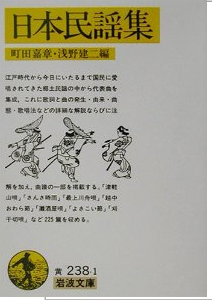 | "『日本民謡集』町田嘉章,浅野健二 岩波書店 1960年初版 (1986年第25版を使用) 江戸時代から今日に至るまで国民に愛唱されてきた郷土民謡から225編をあつめ、歌詞、曲解説、歌詞の解説、とくに重要作品は採譜資料を添付されている。" |
 | 『日本の民謡と民俗芸能〔東洋音楽学会選書1〕』東洋音楽学会編 音楽之友社 1967年初版(1982年第3版を使用) 民謡および民俗芸能(神楽・祭囃子)の歴史や系譜を子細に研究した専門書。とくに追分節、ハイヤ節、おけさ節について詳しい。" |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 民謡 |
| キーワード2 | (民謡の)歴史 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 2013年5.docx |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 齊藤 豊 |
| 授業者コメント | 授業者の自分も民謡のことを知らなかったので、今回の取り組みを通して子どもとともに興味を広げながら活動を展開することができた。 今回は運動会で毎年取り組んでいる「ソーラン節」への取り組みに関連づけて活動を描いている。また、5年生はインターネットを使っての調べ学習、6年生はさらに調べたことをまとめ、一人一人がパワーポイントを使って表現する活動も行った。インターネットによる調べ学習の良さは、画像や音も並行して資料にしていくことができるところだった。文字情報で「民謡」を調べたうえに、実際の音楽を鑑賞したり、動画で視聴することで、理解が深まることをあらためて感じることができた。しかし、この活動を支えるにあたって、教師が事前に「民謡」についての教材研究を深める必要性が、より高まることも実感することができた。インターネット上の情報の中には、時折誤情報もあるため、子どもの集めた情報を一斉授業でシェアしながら修正するための教材研究のために、司書と協働する必要があった。 また、調べ学習をしたあとに、実際の演奏に触れる機会として、民謡の唄い手、津軽三味線奏者、太鼓と唄囃子の唄い手を招聘した。プログラムの中では、「ソーラン節」を民謡の唄い方を習うワークショップも行い、子どもたちに取って大変貴重な経験を提供することができた。 事後には、アウトリーチ活動当日の演奏の様子、子どもたちのパワーポイント作品、参考資料にした民謡の動画のURLを、掲示のみならず校内LANで公開し、子どもたちが任意でアクセスし視聴することができるようにし、今後の調べ学習の参考になるように整備した。 本実践は、校内外にわたる多くの方の協力があって実現することができた。授業をデザインするにあたっては、協力者の方々に授業のコンセプトを共有していただけるよう、メールや資料の提示を通して密な連絡を心がけた。しかし、授業者の見通しの甘さから、たびたび日程や活動内容の変更をせざるを得なくなるなどの迷惑をかけてしまった。次回の取り組みには本実践の経験を生かし、授業者が明確な見通しを描き、関係各所への連絡を確実に行えるようにしなくてはならないと反省をしている。 |
| 司書・司書教諭コメント | 4月新学期から民謡を5年、6年で行うということを聞いて、資料を探していた。そんな時、すずき出版の『日本のおどり①②③』を見つけ、齊藤先生と検討した。子どもたちがわかりやすく書かれているのでこの3冊を購入して使うことにした。 他の2冊は、教員が民謡のことをよく知る上で大変有効な資料であった。ただ、絶版になっていたり、なかなか手に入らないものだったりで、世田谷区の図書館から借りた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 |
| 事例作成日 | 2013年6月14日作成 2013年5~6月実践 |
| 事例作成者氏名 | 吉岡裕子 |
記入者:吉岡(主担)

























