お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0157 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 インタビューについて考えよう 対象学年 中2 活用・支援の種類 生徒のインタビューに答える 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) インタビューの授業にインタビュイーとして参加してほしい 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 各クラス6グループあり、班ごとに二つの柱となる質問を考えている。生徒の質問には、子どものためを意識した答えではなく、あくまでも自然に思ったままに答えてほしい。
提示資料 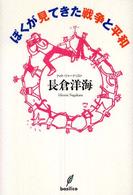
『ぼくが見てきた戦争と平和』長倉洋海著.バジリコ.2007年
*インタビューの授業で、おすすめしたノンフィクションの1冊。戦争ジャーナリストとして戦地をめぐり、衝撃的な写真をとることに視点をおいていた著者が、あるとき戦地の日常にこそ、人びとに訴えるものがあることに気づきます。言葉ができることだけが国際人なのではなく、日本とは違う過酷な状況にある人びとの生活や思いをはせる想像力がとても大切であることに気づかせてくれる一冊。 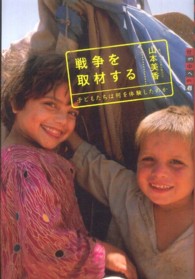
『戦争を取材する-子どもたちは何を体験したのか世の中への扉-』山本美香.講談社.2011年
*インタビューの授業で、おすすめのノンフィクションの1冊として紹介。シリアで亡くなったジャーナリスト、山本美香さんの目を通じて、世界で過酷な状況にある子どもたちの生活がわかる。これからを生きる若い世代へのメッセージでもある一冊。 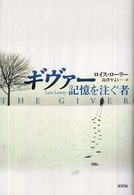
『ザ・ギバー:記憶を伝える者』ロイス・ローリー.新評論.2010年
*インタビューの授業で、今中学生におすすめの本をという問いの答えで紹介した1冊。近未来を描いた作品だが、すべての人に平等に機会が与えられ、そのために犯罪もおきない社会。しかし自ら選択することのできない社会は、真の幸福な社会なのか、ということをつきつける。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 インタビュー キーワード2 交流 キーワード3 取材 授業計画・指導案等 インタビューを経験しよう(.pdf 児童・生徒の作品 授業者 国語科 荻野聡 授業者コメント 今回インタビューの学習を実施するにあたって、まず一番悩んだのが、「インタビュー対象を誰にするか」という問題でした。学校の教員にしようか、あるいは学校外の方に依頼しようか、と迷ったのですが、最終的に学校司書さんにお願いすることにしました。
理由は、学校司書という立場が、インタビューの取材対象として最適だったということです。学校司書さんは「生徒の身近な存在である」、「生徒にとって学校の教員ほど堅苦しくなく、ある程度リラックスできる」、「学習が終わった後も学校内で会うことができ、その後の読書指導につなげられる可能性もある」・・・と挙げればキリがないほどに、さまざまな学習効果が期待されました。
実際にインタビューを学習した後の生徒の感想として、「インタビューで大切なことは、インタビュアーとインタビュイーとが心を通わせて、お互いにその場を楽しめるようにすることだと思いました。」「はじめは、自分がいかに取材をするかということしか考えていなかったけど、そうではなかったんだとわかりました。インタビューは取材相手と自分たちとで積み重ねて作り上げるものだと思うようになりました」というものがありました。用意した質問を投げかけるだけではなく、その場の交流によって取材活動を進めていくというインタビューの価値について気づいた生徒も多いようでした。 司書・司書教諭コメント インタビューイーとして生徒の授業に参加をさせてもらったが、事前の打ち合わせで「自然に」ということだったため、特に意識した答えを準備することなくのぞませてもらった。生徒によっては緊張している生徒、どのように話をふくらませたらいいのかとまどう生徒、話の途中で時間が終了してしまった生徒、などさまざまだった。しかし、授業後に記入されたインタビューの授業を通じた感想のプリントには、相槌をうちながら話を聞くことの大切さ、インタビュー中の表情など、実際にインタビューを経験したからこそわかるポイントをそれぞれの生徒が体感したことが伝わってきた。この経験が、来年以降のフィールドワークでインタビューをする際に活きてくるのではないかと思う。
また、この授業後にはカウンターへ来る中2の生徒が増え、レファレンスや夏休みの課題となっている本の相談など、以前よりも関わりが前進し距離が縮まったことを感じている。
情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2013年7月19日 事例作成者氏名 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863448 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0157 校種 中高一貫校 教科・領域等 国語 単元 インタビューについて考えよう 対象学年 中2 活用・支援の種類 生徒のインタビューに答える 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) インタビューの授業にインタビュイーとして参加してほしい 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 各クラス6グループあり、班ごとに二つの柱となる質問を考えている。生徒の質問には、子どものためを意識した答えではなく、あくまでも自然に思ったままに答えてほしい。
提示資料 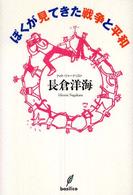
『ぼくが見てきた戦争と平和』長倉洋海著.バジリコ.2007年
*インタビューの授業で、おすすめしたノンフィクションの1冊。戦争ジャーナリストとして戦地をめぐり、衝撃的な写真をとることに視点をおいていた著者が、あるとき戦地の日常にこそ、人びとに訴えるものがあることに気づきます。言葉ができることだけが国際人なのではなく、日本とは違う過酷な状況にある人びとの生活や思いをはせる想像力がとても大切であることに気づかせてくれる一冊。 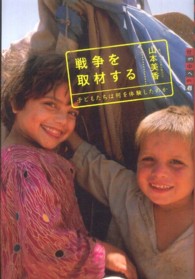
『戦争を取材する-子どもたちは何を体験したのか世の中への扉-』山本美香.講談社.2011年
*インタビューの授業で、おすすめのノンフィクションの1冊として紹介。シリアで亡くなったジャーナリスト、山本美香さんの目を通じて、世界で過酷な状況にある子どもたちの生活がわかる。これからを生きる若い世代へのメッセージでもある一冊。 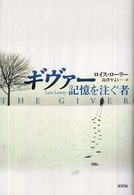
『ザ・ギバー:記憶を伝える者』ロイス・ローリー.新評論.2010年
*インタビューの授業で、今中学生におすすめの本をという問いの答えで紹介した1冊。近未来を描いた作品だが、すべての人に平等に機会が与えられ、そのために犯罪もおきない社会。しかし自ら選択することのできない社会は、真の幸福な社会なのか、ということをつきつける。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 インタビュー キーワード2 交流 キーワード3 取材 授業計画・指導案等 インタビューを経験しよう(.pdf 児童・生徒の作品 授業者 国語科 荻野聡 授業者コメント 今回インタビューの学習を実施するにあたって、まず一番悩んだのが、「インタビュー対象を誰にするか」という問題でした。学校の教員にしようか、あるいは学校外の方に依頼しようか、と迷ったのですが、最終的に学校司書さんにお願いすることにしました。
理由は、学校司書という立場が、インタビューの取材対象として最適だったということです。学校司書さんは「生徒の身近な存在である」、「生徒にとって学校の教員ほど堅苦しくなく、ある程度リラックスできる」、「学習が終わった後も学校内で会うことができ、その後の読書指導につなげられる可能性もある」・・・と挙げればキリがないほどに、さまざまな学習効果が期待されました。
実際にインタビューを学習した後の生徒の感想として、「インタビューで大切なことは、インタビュアーとインタビュイーとが心を通わせて、お互いにその場を楽しめるようにすることだと思いました。」「はじめは、自分がいかに取材をするかということしか考えていなかったけど、そうではなかったんだとわかりました。インタビューは取材相手と自分たちとで積み重ねて作り上げるものだと思うようになりました」というものがありました。用意した質問を投げかけるだけではなく、その場の交流によって取材活動を進めていくというインタビューの価値について気づいた生徒も多いようでした。 司書・司書教諭コメント インタビューイーとして生徒の授業に参加をさせてもらったが、事前の打ち合わせで「自然に」ということだったため、特に意識した答えを準備することなくのぞませてもらった。生徒によっては緊張している生徒、どのように話をふくらませたらいいのかとまどう生徒、話の途中で時間が終了してしまった生徒、などさまざまだった。しかし、授業後に記入されたインタビューの授業を通じた感想のプリントには、相槌をうちながら話を聞くことの大切さ、インタビュー中の表情など、実際にインタビューを経験したからこそわかるポイントをそれぞれの生徒が体感したことが伝わってきた。この経験が、来年以降のフィールドワークでインタビューをする際に活きてくるのではないかと思う。
また、この授業後にはカウンターへ来る中2の生徒が増え、レファレンスや夏休みの課題となっている本の相談など、以前よりも関わりが前進し距離が縮まったことを感じている。
情報提供校 東京学芸大学附属国際中等教育学校 事例作成日 2013年7月19日 事例作成者氏名 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校)
記入者:渡辺(主担)
カウンタ
3863448 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0157 |
|---|---|
| 校種 | 中高一貫校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | インタビューについて考えよう |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 生徒のインタビューに答える |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | インタビューの授業にインタビュイーとして参加してほしい |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 各クラス6グループあり、班ごとに二つの柱となる質問を考えている。生徒の質問には、子どものためを意識した答えではなく、あくまでも自然に思ったままに答えてほしい。 |
| 提示資料 | |
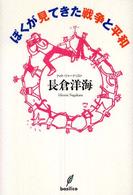 | 『ぼくが見てきた戦争と平和』長倉洋海著.バジリコ.2007年 *インタビューの授業で、おすすめしたノンフィクションの1冊。戦争ジャーナリストとして戦地をめぐり、衝撃的な写真をとることに視点をおいていた著者が、あるとき戦地の日常にこそ、人びとに訴えるものがあることに気づきます。言葉ができることだけが国際人なのではなく、日本とは違う過酷な状況にある人びとの生活や思いをはせる想像力がとても大切であることに気づかせてくれる一冊。 |
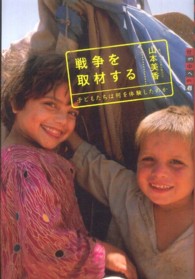 | 『戦争を取材する-子どもたちは何を体験したのか世の中への扉-』山本美香.講談社.2011年 *インタビューの授業で、おすすめのノンフィクションの1冊として紹介。シリアで亡くなったジャーナリスト、山本美香さんの目を通じて、世界で過酷な状況にある子どもたちの生活がわかる。これからを生きる若い世代へのメッセージでもある一冊。 |
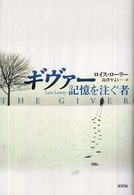 | 『ザ・ギバー:記憶を伝える者』ロイス・ローリー.新評論.2010年 *インタビューの授業で、今中学生におすすめの本をという問いの答えで紹介した1冊。近未来を描いた作品だが、すべての人に平等に機会が与えられ、そのために犯罪もおきない社会。しかし自ら選択することのできない社会は、真の幸福な社会なのか、ということをつきつける。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | インタビュー |
| キーワード2 | 交流 |
| キーワード3 | 取材 |
| 授業計画・指導案等 | インタビューを経験しよう(.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 国語科 荻野聡 |
| 授業者コメント | 今回インタビューの学習を実施するにあたって、まず一番悩んだのが、「インタビュー対象を誰にするか」という問題でした。学校の教員にしようか、あるいは学校外の方に依頼しようか、と迷ったのですが、最終的に学校司書さんにお願いすることにしました。 理由は、学校司書という立場が、インタビューの取材対象として最適だったということです。学校司書さんは「生徒の身近な存在である」、「生徒にとって学校の教員ほど堅苦しくなく、ある程度リラックスできる」、「学習が終わった後も学校内で会うことができ、その後の読書指導につなげられる可能性もある」・・・と挙げればキリがないほどに、さまざまな学習効果が期待されました。 実際にインタビューを学習した後の生徒の感想として、「インタビューで大切なことは、インタビュアーとインタビュイーとが心を通わせて、お互いにその場を楽しめるようにすることだと思いました。」「はじめは、自分がいかに取材をするかということしか考えていなかったけど、そうではなかったんだとわかりました。インタビューは取材相手と自分たちとで積み重ねて作り上げるものだと思うようになりました」というものがありました。用意した質問を投げかけるだけではなく、その場の交流によって取材活動を進めていくというインタビューの価値について気づいた生徒も多いようでした。 |
| 司書・司書教諭コメント | インタビューイーとして生徒の授業に参加をさせてもらったが、事前の打ち合わせで「自然に」ということだったため、特に意識した答えを準備することなくのぞませてもらった。生徒によっては緊張している生徒、どのように話をふくらませたらいいのかとまどう生徒、話の途中で時間が終了してしまった生徒、などさまざまだった。しかし、授業後に記入されたインタビューの授業を通じた感想のプリントには、相槌をうちながら話を聞くことの大切さ、インタビュー中の表情など、実際にインタビューを経験したからこそわかるポイントをそれぞれの生徒が体感したことが伝わってきた。この経験が、来年以降のフィールドワークでインタビューをする際に活きてくるのではないかと思う。 また、この授業後にはカウンターへ来る中2の生徒が増え、レファレンスや夏休みの課題となっている本の相談など、以前よりも関わりが前進し距離が縮まったことを感じている。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
| 事例作成日 | 2013年7月19日 |
| 事例作成者氏名 | 荻野聡(東京学芸大学附属国際中等教育学校) |
記入者:渡辺(主担)

























