お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0170 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 サケをそだてよう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 読みきかせ 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) サケの飼育に関する資料案内と読みきかせをお願いしたい。(特別支援学級) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 サケを育て、観察して調べていくという学習は、緑野小では毎年2年生が取り組んでいる。今回は特別支援 固定学級の「えのき学級」が取り組む。…命の尊さを感じ、飼育の責任、疑問や知りたいことを解決していくことをねらいとした。
提示資料 2年生用に用意した資料から、①写真が多いもの、②文字が余り多くなくて漢字にルビがあるもの、という視点で、数冊選び、学級に置くようにした。 
『キンダーブック しぜん 10 さけ』(2012年10月号)フレーベル館 (指導)市村政樹 (写真)内山りゅう
低学年でも読みやすく写真も多くてわかりやすい。1997年11月号「キンダーブック しぜん さけ」も、内山りゅう氏の写真だが、2012年10月号の方が産卵床をつくるところの写真なども加わっている。一般書店で購入できず、バックナンバーも品切れなのが残念。
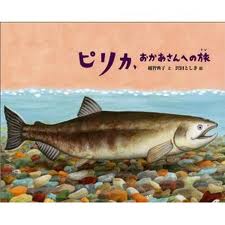
『ピリカ、おかあさんへの旅』 越智典子 文 ・沢田としき 絵 福音館書店 2006年
4才のメスサケ、ピリカが海から川へ戻り、産卵して次の世代の命を支える栄養になっていく様を描いた絵本。ピリカに寄り添うことで、資料で学んだ知識を実感することができる。読みきかせをした。
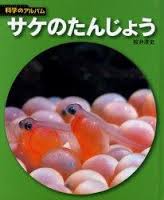
『科学のアルバム 新装版 サケのたんじょう』 桜井淳史 あかね書房 2005年
多くの写真とかなり本格的な知識が盛り込まれているが、すべての漢字にルビが振られているので、低学年や固定級の子供でも利用しやすい。写真に丁寧な解説がついているのもうれしい。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト サケをそだてよう 特支小低 2012.xlsx
キーワード1 サケ キーワード2 飼育 キーワード3 命 授業計画・指導案等 「サケ博士になろう」総合 えのき学級2013.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 彦坂 菜穂子教諭 授業者コメント 「サケを卵から育て、川に放す」という経験を通して、サケの命を絶やさないためにはどうすればよいかといった方法・なんで?と感じた疑問(ヒレや回遊の仕方など)・なんていうの?といった名称など、知りたい意欲が子供たちと本を結びました。
23年度・24年度と続けて学習することで、図書館の活用、本を使った調べ方やまとめ方など、本に関わることが増え、「本を読む」ということへの抵抗を和らげることができました。また、「わからないことは本で調べる。困った時の丸山先生(学校司書の先生)」ということが、自然につながる様子も見られます。 司書・司書教諭コメント 〔司書教諭コメント〕えのき学級ではここ数年読書活動を中心に子どもたちの力を育てるために、学校司書と協働し個々の子どもの発達段階にあわせた指導を行ってきました。地域のボランティアの語りの会に協力していただき定期的にお話会も行うなど学校図書館を入口とし生涯教育につながる力を育てたいという教師の願いでもあります。
今回、本と仲良しになっているえのき学級がサケの学習をするにあたり司書教諭として次のような提案をしました。
「サケの学習」は本校では2年生の生活科で毎年調べ学習として取り組んでいるものです。漁協から発眼卵を分けていただき飼育しながら不思議に思ったことや知りたいことをカードに書き溜めていく。同時に本物の大人のサケを岩手から取り寄せ解体して観察しこの発眼卵から大人になるまでの間にどんなことが起こっているのかを様々な視点から考え調べていく学習です。
サケは成長が早いので子どもたちの関心や興味を持続させるとても良い教材といえます。
えのき学級の子どもたちもきっと夢中になるはずです。
調べる学習の形態については、私が前任区で行った資料を見せて先生にイメージをもってもらいました。通常級でしたが、ダウン症児1名、3年生で固定の特別支援級に編入した児童が2名いる2年生での実践でした。どの子も調べられたという達成感がもてるようにするためにカードを使用せず実物大のサケの模型を作ることを通して調べ学習をするものでした。その時の子どもたちの探究していく姿が心に強く残っていて、えのき学級の子どもたちにも十分可能なのではと提案してみました。取り組む過程での写真資料が豊富にあったことも良かったと思いました。実践の資料を学校図書館が財産として収集する意味を認識させられました。
〔司書コメント〕本校では毎年2年生が「サケを育てて放流しよう!」に取り組んでいて、今回もまず2年生のために資料を提供しました。毎年のことなので、資料も結構揃っていました。
直後に初めてえのき学級もこの取り組みにチャレンジすることになり、2年生に提供した資料の中から彦坂先生に選んでいただいて、学習の期間中えのき学級に置くことにしました。観察をしながら、常に本を見るということが習慣になったようです。「資料が身近にある」ということがとても重要なのだと実感しました、
また週1回の「図書館の時間」で『ピリカ おかあさんへの旅』(越智典子作・沢田としき絵・福音館)を読み聞かせたのが学習へ気持ちを向かわせる良いきっかけになったようでした。
できあがった作品は大変すばらしく、お願いして緑野小図書館に所蔵させてもらいました。
情報提供校 東京都狛江市立緑野小学校 事例作成日 2013年12月26日 実践日2012年12月~2013年2月 事例作成者氏名 丸山英子 司書
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863486 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0170 校種 小学校 教科・領域等 総合 単元 サケをそだてよう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 読みきかせ 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) サケの飼育に関する資料案内と読みきかせをお願いしたい。(特別支援学級) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 サケを育て、観察して調べていくという学習は、緑野小では毎年2年生が取り組んでいる。今回は特別支援 固定学級の「えのき学級」が取り組む。…命の尊さを感じ、飼育の責任、疑問や知りたいことを解決していくことをねらいとした。
提示資料 2年生用に用意した資料から、①写真が多いもの、②文字が余り多くなくて漢字にルビがあるもの、という視点で、数冊選び、学級に置くようにした。 
『キンダーブック しぜん 10 さけ』(2012年10月号)フレーベル館 (指導)市村政樹 (写真)内山りゅう
低学年でも読みやすく写真も多くてわかりやすい。1997年11月号「キンダーブック しぜん さけ」も、内山りゅう氏の写真だが、2012年10月号の方が産卵床をつくるところの写真なども加わっている。一般書店で購入できず、バックナンバーも品切れなのが残念。
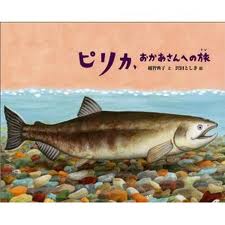
『ピリカ、おかあさんへの旅』 越智典子 文 ・沢田としき 絵 福音館書店 2006年
4才のメスサケ、ピリカが海から川へ戻り、産卵して次の世代の命を支える栄養になっていく様を描いた絵本。ピリカに寄り添うことで、資料で学んだ知識を実感することができる。読みきかせをした。
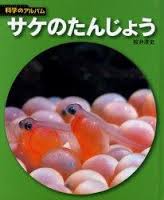
『科学のアルバム 新装版 サケのたんじょう』 桜井淳史 あかね書房 2005年
多くの写真とかなり本格的な知識が盛り込まれているが、すべての漢字にルビが振られているので、低学年や固定級の子供でも利用しやすい。写真に丁寧な解説がついているのもうれしい。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト サケをそだてよう 特支小低 2012.xlsx
キーワード1 サケ キーワード2 飼育 キーワード3 命 授業計画・指導案等 「サケ博士になろう」総合 えのき学級2013.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 彦坂 菜穂子教諭 授業者コメント 「サケを卵から育て、川に放す」という経験を通して、サケの命を絶やさないためにはどうすればよいかといった方法・なんで?と感じた疑問(ヒレや回遊の仕方など)・なんていうの?といった名称など、知りたい意欲が子供たちと本を結びました。
23年度・24年度と続けて学習することで、図書館の活用、本を使った調べ方やまとめ方など、本に関わることが増え、「本を読む」ということへの抵抗を和らげることができました。また、「わからないことは本で調べる。困った時の丸山先生(学校司書の先生)」ということが、自然につながる様子も見られます。 司書・司書教諭コメント 〔司書教諭コメント〕えのき学級ではここ数年読書活動を中心に子どもたちの力を育てるために、学校司書と協働し個々の子どもの発達段階にあわせた指導を行ってきました。地域のボランティアの語りの会に協力していただき定期的にお話会も行うなど学校図書館を入口とし生涯教育につながる力を育てたいという教師の願いでもあります。
今回、本と仲良しになっているえのき学級がサケの学習をするにあたり司書教諭として次のような提案をしました。
「サケの学習」は本校では2年生の生活科で毎年調べ学習として取り組んでいるものです。漁協から発眼卵を分けていただき飼育しながら不思議に思ったことや知りたいことをカードに書き溜めていく。同時に本物の大人のサケを岩手から取り寄せ解体して観察しこの発眼卵から大人になるまでの間にどんなことが起こっているのかを様々な視点から考え調べていく学習です。
サケは成長が早いので子どもたちの関心や興味を持続させるとても良い教材といえます。
えのき学級の子どもたちもきっと夢中になるはずです。
調べる学習の形態については、私が前任区で行った資料を見せて先生にイメージをもってもらいました。通常級でしたが、ダウン症児1名、3年生で固定の特別支援級に編入した児童が2名いる2年生での実践でした。どの子も調べられたという達成感がもてるようにするためにカードを使用せず実物大のサケの模型を作ることを通して調べ学習をするものでした。その時の子どもたちの探究していく姿が心に強く残っていて、えのき学級の子どもたちにも十分可能なのではと提案してみました。取り組む過程での写真資料が豊富にあったことも良かったと思いました。実践の資料を学校図書館が財産として収集する意味を認識させられました。
〔司書コメント〕本校では毎年2年生が「サケを育てて放流しよう!」に取り組んでいて、今回もまず2年生のために資料を提供しました。毎年のことなので、資料も結構揃っていました。
直後に初めてえのき学級もこの取り組みにチャレンジすることになり、2年生に提供した資料の中から彦坂先生に選んでいただいて、学習の期間中えのき学級に置くことにしました。観察をしながら、常に本を見るということが習慣になったようです。「資料が身近にある」ということがとても重要なのだと実感しました、
また週1回の「図書館の時間」で『ピリカ おかあさんへの旅』(越智典子作・沢田としき絵・福音館)を読み聞かせたのが学習へ気持ちを向かわせる良いきっかけになったようでした。
できあがった作品は大変すばらしく、お願いして緑野小図書館に所蔵させてもらいました。
情報提供校 東京都狛江市立緑野小学校 事例作成日 2013年12月26日 実践日2012年12月~2013年2月 事例作成者氏名 丸山英子 司書
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863486 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0170 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 総合 |
| 単元 | サケをそだてよう |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 読みきかせ |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | サケの飼育に関する資料案内と読みきかせをお願いしたい。(特別支援学級) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | サケを育て、観察して調べていくという学習は、緑野小では毎年2年生が取り組んでいる。今回は特別支援 固定学級の「えのき学級」が取り組む。…命の尊さを感じ、飼育の責任、疑問や知りたいことを解決していくことをねらいとした。 |
| 提示資料 | 2年生用に用意した資料から、①写真が多いもの、②文字が余り多くなくて漢字にルビがあるもの、という視点で、数冊選び、学級に置くようにした。 |
 | 『キンダーブック しぜん 10 さけ』(2012年10月号)フレーベル館 (指導)市村政樹 (写真)内山りゅう 低学年でも読みやすく写真も多くてわかりやすい。1997年11月号「キンダーブック しぜん さけ」も、内山りゅう氏の写真だが、2012年10月号の方が産卵床をつくるところの写真なども加わっている。一般書店で購入できず、バックナンバーも品切れなのが残念。 |
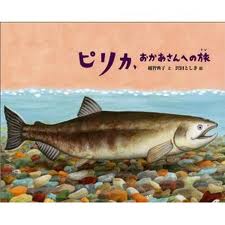 | 『ピリカ、おかあさんへの旅』 越智典子 文 ・沢田としき 絵 福音館書店 2006年 4才のメスサケ、ピリカが海から川へ戻り、産卵して次の世代の命を支える栄養になっていく様を描いた絵本。ピリカに寄り添うことで、資料で学んだ知識を実感することができる。読みきかせをした。 |
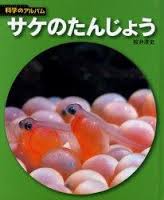 | 『科学のアルバム 新装版 サケのたんじょう』 桜井淳史 あかね書房 2005年 多くの写真とかなり本格的な知識が盛り込まれているが、すべての漢字にルビが振られているので、低学年や固定級の子供でも利用しやすい。写真に丁寧な解説がついているのもうれしい。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | サケをそだてよう 特支小低 2012.xlsx |
| キーワード1 | サケ |
| キーワード2 | 飼育 |
| キーワード3 | 命 |
| 授業計画・指導案等 | 「サケ博士になろう」総合 えのき学級2013.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 彦坂 菜穂子教諭 |
| 授業者コメント | 「サケを卵から育て、川に放す」という経験を通して、サケの命を絶やさないためにはどうすればよいかといった方法・なんで?と感じた疑問(ヒレや回遊の仕方など)・なんていうの?といった名称など、知りたい意欲が子供たちと本を結びました。 23年度・24年度と続けて学習することで、図書館の活用、本を使った調べ方やまとめ方など、本に関わることが増え、「本を読む」ということへの抵抗を和らげることができました。また、「わからないことは本で調べる。困った時の丸山先生(学校司書の先生)」ということが、自然につながる様子も見られます。 |
| 司書・司書教諭コメント | 〔司書教諭コメント〕えのき学級ではここ数年読書活動を中心に子どもたちの力を育てるために、学校司書と協働し個々の子どもの発達段階にあわせた指導を行ってきました。地域のボランティアの語りの会に協力していただき定期的にお話会も行うなど学校図書館を入口とし生涯教育につながる力を育てたいという教師の願いでもあります。 今回、本と仲良しになっているえのき学級がサケの学習をするにあたり司書教諭として次のような提案をしました。 「サケの学習」は本校では2年生の生活科で毎年調べ学習として取り組んでいるものです。漁協から発眼卵を分けていただき飼育しながら不思議に思ったことや知りたいことをカードに書き溜めていく。同時に本物の大人のサケを岩手から取り寄せ解体して観察しこの発眼卵から大人になるまでの間にどんなことが起こっているのかを様々な視点から考え調べていく学習です。 サケは成長が早いので子どもたちの関心や興味を持続させるとても良い教材といえます。 えのき学級の子どもたちもきっと夢中になるはずです。 調べる学習の形態については、私が前任区で行った資料を見せて先生にイメージをもってもらいました。通常級でしたが、ダウン症児1名、3年生で固定の特別支援級に編入した児童が2名いる2年生での実践でした。どの子も調べられたという達成感がもてるようにするためにカードを使用せず実物大のサケの模型を作ることを通して調べ学習をするものでした。その時の子どもたちの探究していく姿が心に強く残っていて、えのき学級の子どもたちにも十分可能なのではと提案してみました。取り組む過程での写真資料が豊富にあったことも良かったと思いました。実践の資料を学校図書館が財産として収集する意味を認識させられました。 〔司書コメント〕本校では毎年2年生が「サケを育てて放流しよう!」に取り組んでいて、今回もまず2年生のために資料を提供しました。毎年のことなので、資料も結構揃っていました。 直後に初めてえのき学級もこの取り組みにチャレンジすることになり、2年生に提供した資料の中から彦坂先生に選んでいただいて、学習の期間中えのき学級に置くことにしました。観察をしながら、常に本を見るということが習慣になったようです。「資料が身近にある」ということがとても重要なのだと実感しました、 また週1回の「図書館の時間」で『ピリカ おかあさんへの旅』(越智典子作・沢田としき絵・福音館)を読み聞かせたのが学習へ気持ちを向かわせる良いきっかけになったようでした。 できあがった作品は大変すばらしく、お願いして緑野小図書館に所蔵させてもらいました。 |
| 情報提供校 | 東京都狛江市立緑野小学校 |
| 事例作成日 | 2013年12月26日 実践日2012年12月~2013年2月 |
| 事例作成者氏名 | 丸山英子 司書 |
記入者:中山(主担)

























