お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0174 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 幼児との触れ合い、かかわり方の工夫 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・授業のT.T 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 中学生による絵本の読み聞かせ(幼稚園実習)の協働授業を行いたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教員からの依頼は以下の3点。①絵本を用意してほしい ②読み聞かせ実演者を紹介してほしい ③読み聞かせのポイントを示し、練習時の指導に参加してほしい
提示資料 1時間目で利用した資料と2~3時間目で生徒、園児に好評だった絵本。物語だけでなく科学絵本・しかけ絵本・言葉あそびなど色々な種類を取り混ぜることに留意した。
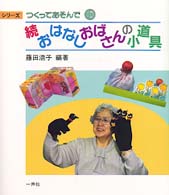
『続おはなしおばさんの小道具(シリーズつくって遊んで10)』藤田浩子/編著 一声社 1998年 この本で紹介されている「カラスの親子」の手あそびは、読み聞かせ体験授業の冒頭に披露した。手あそびに興味を持った生徒は授業後に他のページもチェックしていた。
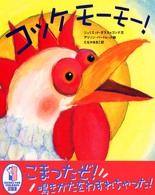
"『コッケモーモー!』ジュリエット・ダラス=コンテ/文 アリソン・バートレット/絵 たなか あきこ/訳 徳間書店 2001年 「コケコッコー」の鳴き方を思い出せないオンドリはすっかりしょげてしまうが、ある晩大活躍することになるという楽しいおはなし。 読み聞かせの絵本選びには絵の見やすさ、ストーリーのわかりやすさが大事であることを伝えるのに好適。また見返しや裏表紙のイラストを見せながら、絵本の持ち方やページのめくり方のポイントを示すことができた。

『アフリカのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』 石井ひろみ/編 日経ナショナルジオグラフィック社 2010年 ミーアキャット、カバ、キリン、ゾウ、ライオンが登場するしかけ写真絵本。同じシリーズで『せかいのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』もある。体の大きい中3男子が読むことで迫力が増し、園児にはもちろん、幼稚園教諭からも好評であった。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro/program/project3/data/PJ3_H2503.pdf ブックリスト 読み聞かせ幼稚園実習 絵本一覧・ビッグブック・参考資料(中3家庭科)2013.xls
キーワード1 幼児 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 触れ合い体験 授業計画・指導案等 中3 家庭科読み聞かせ幼稚園実習 授業計画・ワークシート .pdf 児童・生徒の作品 授業者 酒井由美 授業者コメント 小さい子どもたちとふれあう機会が少ない今の 生徒たちにとって、幼稚園での交流体験は幼児への関心を高め、理解を深めることになる。さらに、幼児を育てる家族について考える中で自分の生活を振り返り、家族と共に生活をよりよくしようとする意欲と態度を育てることにつながると考えた。
絵本の読み聞かせを計画した理由は、話すことが苦手な生徒やおとなしい生徒でも絵本があれば幼児との交流が容易にはかれ、心の交流にもなるのではないかと考えたからだ。
【1時間目 読み聞かせ実演者(ボランティア)による読み聞かせ体験】 生徒たちが幼児の気持ちになって読み聞かせを楽しむことを目的に、幼児への読み聞かせ活動を行っている実演者のコーディネートを学校司書に依頼した。体験後は「読み聞かせはただ絵本を読めばいいのではなく、色々な工夫や気遣いが必要だということを初めて知った」「小さい頃読み聞かせをしてくれたすべての人に感謝したい」という感想が多く見られた。
【2時間目 読み聞かせ練習】 1時間目と同様に、学校司書とTTで授業を行った。学校司書が事前に市内の図書館や学校から多くの絵本を準備し、昼休みや放課後も選書等生徒の様々な相談にのってくれたのでスムーズに授業をすることができた。
【3時間目 幼稚園での読み聞かせ実習 】1クラスが5班に分かれ、幼稚園教諭の指示により年少・年中・年長のいずれかを担当した。生徒1人に園児3~5名で全員一斉に始め、読み聞かせが終わったら机を移動し、少ない生徒でも最低3回は読み聞かせを行った。生徒の抱く幼児のイメージが「うるさい・わがまま」であったものが実習後では「かわいい・しっかりしている」 などプラスイメージに変化し、何より生徒たちの笑顔が印象に残った。授業のねらい以上に生徒たちの心を動かす体験になったように思われる。
司書・司書教諭コメント 本授業は平成25年度で4年目になる。毎年2学期に実施するが読み聞かせ実演者(ボランティア)の日程調整は1学期から行った。 実演者が使う絵本やビッグブック、生徒が使う絵本は市内小中学校の相互貸借や市立図書館の団体貸出のシステムを利用し、蔵書を含め合計130冊を用意した。隣接する幼稚園での実習ということで3時間目は1コマで成立した。1時間目から3時間目まで授業すべてに学校司書が関わることができ、絵本の収集や生徒への個別対応が迅速にできた。
◇事例提供 東京学芸大学 総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト「道徳性をはぐくむ 体験学習プログラムの開発」 東京学芸大学連携研究校 (平成22年度実施の授業 /実演者の体験記も掲載)
◇発表・報告 第15回図書館総合展 主催者フォーラム(平成25年10月28日) 学校図書館教育研究会2013年度大会 第13回研究会(平成25年11月24日)
情報提供校 国分寺市立第三中学校 事例作成日 事例作成 2014年1月20日 /授業実践 2013年9月13日~11月12日 事例作成者氏名 田邉ひろみ
記入者:村上
カウンタ
3863377 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0174 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 幼児との触れ合い、かかわり方の工夫 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・授業のT.T 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 中学生による絵本の読み聞かせ(幼稚園実習)の協働授業を行いたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教員からの依頼は以下の3点。①絵本を用意してほしい ②読み聞かせ実演者を紹介してほしい ③読み聞かせのポイントを示し、練習時の指導に参加してほしい
提示資料 1時間目で利用した資料と2~3時間目で生徒、園児に好評だった絵本。物語だけでなく科学絵本・しかけ絵本・言葉あそびなど色々な種類を取り混ぜることに留意した。
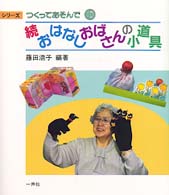
『続おはなしおばさんの小道具(シリーズつくって遊んで10)』藤田浩子/編著 一声社 1998年 この本で紹介されている「カラスの親子」の手あそびは、読み聞かせ体験授業の冒頭に披露した。手あそびに興味を持った生徒は授業後に他のページもチェックしていた。
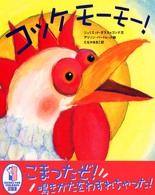
"『コッケモーモー!』ジュリエット・ダラス=コンテ/文 アリソン・バートレット/絵 たなか あきこ/訳 徳間書店 2001年 「コケコッコー」の鳴き方を思い出せないオンドリはすっかりしょげてしまうが、ある晩大活躍することになるという楽しいおはなし。 読み聞かせの絵本選びには絵の見やすさ、ストーリーのわかりやすさが大事であることを伝えるのに好適。また見返しや裏表紙のイラストを見せながら、絵本の持ち方やページのめくり方のポイントを示すことができた。

『アフリカのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』 石井ひろみ/編 日経ナショナルジオグラフィック社 2010年 ミーアキャット、カバ、キリン、ゾウ、ライオンが登場するしかけ写真絵本。同じシリーズで『せかいのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』もある。体の大きい中3男子が読むことで迫力が増し、園児にはもちろん、幼稚園教諭からも好評であった。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro/program/project3/data/PJ3_H2503.pdf ブックリスト 読み聞かせ幼稚園実習 絵本一覧・ビッグブック・参考資料(中3家庭科)2013.xls
キーワード1 幼児 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 触れ合い体験 授業計画・指導案等 中3 家庭科読み聞かせ幼稚園実習 授業計画・ワークシート .pdf 児童・生徒の作品 授業者 酒井由美 授業者コメント 小さい子どもたちとふれあう機会が少ない今の 生徒たちにとって、幼稚園での交流体験は幼児への関心を高め、理解を深めることになる。さらに、幼児を育てる家族について考える中で自分の生活を振り返り、家族と共に生活をよりよくしようとする意欲と態度を育てることにつながると考えた。
絵本の読み聞かせを計画した理由は、話すことが苦手な生徒やおとなしい生徒でも絵本があれば幼児との交流が容易にはかれ、心の交流にもなるのではないかと考えたからだ。
【1時間目 読み聞かせ実演者(ボランティア)による読み聞かせ体験】 生徒たちが幼児の気持ちになって読み聞かせを楽しむことを目的に、幼児への読み聞かせ活動を行っている実演者のコーディネートを学校司書に依頼した。体験後は「読み聞かせはただ絵本を読めばいいのではなく、色々な工夫や気遣いが必要だということを初めて知った」「小さい頃読み聞かせをしてくれたすべての人に感謝したい」という感想が多く見られた。
【2時間目 読み聞かせ練習】 1時間目と同様に、学校司書とTTで授業を行った。学校司書が事前に市内の図書館や学校から多くの絵本を準備し、昼休みや放課後も選書等生徒の様々な相談にのってくれたのでスムーズに授業をすることができた。
【3時間目 幼稚園での読み聞かせ実習 】1クラスが5班に分かれ、幼稚園教諭の指示により年少・年中・年長のいずれかを担当した。生徒1人に園児3~5名で全員一斉に始め、読み聞かせが終わったら机を移動し、少ない生徒でも最低3回は読み聞かせを行った。生徒の抱く幼児のイメージが「うるさい・わがまま」であったものが実習後では「かわいい・しっかりしている」 などプラスイメージに変化し、何より生徒たちの笑顔が印象に残った。授業のねらい以上に生徒たちの心を動かす体験になったように思われる。
司書・司書教諭コメント 本授業は平成25年度で4年目になる。毎年2学期に実施するが読み聞かせ実演者(ボランティア)の日程調整は1学期から行った。 実演者が使う絵本やビッグブック、生徒が使う絵本は市内小中学校の相互貸借や市立図書館の団体貸出のシステムを利用し、蔵書を含め合計130冊を用意した。隣接する幼稚園での実習ということで3時間目は1コマで成立した。1時間目から3時間目まで授業すべてに学校司書が関わることができ、絵本の収集や生徒への個別対応が迅速にできた。
◇事例提供 東京学芸大学 総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト「道徳性をはぐくむ 体験学習プログラムの開発」 東京学芸大学連携研究校 (平成22年度実施の授業 /実演者の体験記も掲載)
◇発表・報告 第15回図書館総合展 主催者フォーラム(平成25年10月28日) 学校図書館教育研究会2013年度大会 第13回研究会(平成25年11月24日)
情報提供校 国分寺市立第三中学校 事例作成日 事例作成 2014年1月20日 /授業実践 2013年9月13日~11月12日 事例作成者氏名 田邉ひろみ
記入者:村上
カウンタ
3863377 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0174 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 家庭 |
| 単元 | 幼児との触れ合い、かかわり方の工夫 |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・授業のT.T |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 中学生による絵本の読み聞かせ(幼稚園実習)の協働授業を行いたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 教員からの依頼は以下の3点。①絵本を用意してほしい ②読み聞かせ実演者を紹介してほしい ③読み聞かせのポイントを示し、練習時の指導に参加してほしい |
| 提示資料 | 1時間目で利用した資料と2~3時間目で生徒、園児に好評だった絵本。物語だけでなく科学絵本・しかけ絵本・言葉あそびなど色々な種類を取り混ぜることに留意した。 |
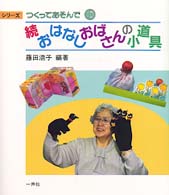 | 『続おはなしおばさんの小道具(シリーズつくって遊んで10)』藤田浩子/編著 一声社 1998年 この本で紹介されている「カラスの親子」の手あそびは、読み聞かせ体験授業の冒頭に披露した。手あそびに興味を持った生徒は授業後に他のページもチェックしていた。 |
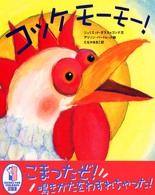 | "『コッケモーモー!』ジュリエット・ダラス=コンテ/文 アリソン・バートレット/絵 たなか あきこ/訳 徳間書店 2001年 「コケコッコー」の鳴き方を思い出せないオンドリはすっかりしょげてしまうが、ある晩大活躍することになるという楽しいおはなし。 読み聞かせの絵本選びには絵の見やすさ、ストーリーのわかりやすさが大事であることを伝えるのに好適。また見返しや裏表紙のイラストを見せながら、絵本の持ち方やページのめくり方のポイントを示すことができた。 |
 | 『アフリカのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』 石井ひろみ/編 日経ナショナルジオグラフィック社 2010年 ミーアキャット、カバ、キリン、ゾウ、ライオンが登場するしかけ写真絵本。同じシリーズで『せかいのどうぶつ とびだす!実物大☆ずかん』もある。体の大きい中3男子が読むことで迫力が増し、園児にはもちろん、幼稚園教諭からも好評であった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://www.u-gakugei.ac.jp/~kokoro/program/project3/data/PJ3_H2503.pdf |
| ブックリスト | 読み聞かせ幼稚園実習 絵本一覧・ビッグブック・参考資料(中3家庭科)2013.xls |
| キーワード1 | 幼児 |
| キーワード2 | 読み聞かせ |
| キーワード3 | 触れ合い体験 |
| 授業計画・指導案等 | 中3 家庭科読み聞かせ幼稚園実習 授業計画・ワークシート .pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 酒井由美 |
| 授業者コメント | 小さい子どもたちとふれあう機会が少ない今の 生徒たちにとって、幼稚園での交流体験は幼児への関心を高め、理解を深めることになる。さらに、幼児を育てる家族について考える中で自分の生活を振り返り、家族と共に生活をよりよくしようとする意欲と態度を育てることにつながると考えた。 絵本の読み聞かせを計画した理由は、話すことが苦手な生徒やおとなしい生徒でも絵本があれば幼児との交流が容易にはかれ、心の交流にもなるのではないかと考えたからだ。 【1時間目 読み聞かせ実演者(ボランティア)による読み聞かせ体験】 生徒たちが幼児の気持ちになって読み聞かせを楽しむことを目的に、幼児への読み聞かせ活動を行っている実演者のコーディネートを学校司書に依頼した。体験後は「読み聞かせはただ絵本を読めばいいのではなく、色々な工夫や気遣いが必要だということを初めて知った」「小さい頃読み聞かせをしてくれたすべての人に感謝したい」という感想が多く見られた。 【2時間目 読み聞かせ練習】 1時間目と同様に、学校司書とTTで授業を行った。学校司書が事前に市内の図書館や学校から多くの絵本を準備し、昼休みや放課後も選書等生徒の様々な相談にのってくれたのでスムーズに授業をすることができた。 【3時間目 幼稚園での読み聞かせ実習 】1クラスが5班に分かれ、幼稚園教諭の指示により年少・年中・年長のいずれかを担当した。生徒1人に園児3~5名で全員一斉に始め、読み聞かせが終わったら机を移動し、少ない生徒でも最低3回は読み聞かせを行った。生徒の抱く幼児のイメージが「うるさい・わがまま」であったものが実習後では「かわいい・しっかりしている」 などプラスイメージに変化し、何より生徒たちの笑顔が印象に残った。授業のねらい以上に生徒たちの心を動かす体験になったように思われる。 |
| 司書・司書教諭コメント | 本授業は平成25年度で4年目になる。毎年2学期に実施するが読み聞かせ実演者(ボランティア)の日程調整は1学期から行った。 実演者が使う絵本やビッグブック、生徒が使う絵本は市内小中学校の相互貸借や市立図書館の団体貸出のシステムを利用し、蔵書を含め合計130冊を用意した。隣接する幼稚園での実習ということで3時間目は1コマで成立した。1時間目から3時間目まで授業すべてに学校司書が関わることができ、絵本の収集や生徒への個別対応が迅速にできた。 ◇事例提供 東京学芸大学 総合的道徳教育プログラム推進プロジェクト「道徳性をはぐくむ 体験学習プログラムの開発」 東京学芸大学連携研究校 (平成22年度実施の授業 /実演者の体験記も掲載) ◇発表・報告 第15回図書館総合展 主催者フォーラム(平成25年10月28日) 学校図書館教育研究会2013年度大会 第13回研究会(平成25年11月24日) |
| 情報提供校 | 国分寺市立第三中学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2014年1月20日 /授業実践 2013年9月13日~11月12日 |
| 事例作成者氏名 | 田邉ひろみ |
記入者:村上

























