お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0176 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『夏草-「奥の細道」から』 光村図書 対象学年 中3 活用・支援の種類 パワーポイントで奥の細道を紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 奥の細道の導入部分で、江戸の旅について紹介してほしい
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについてを司書からパワーポイントを使って紹介することに。
提示資料 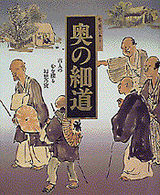
『奥の細道』 富士正晴 学習研究社 1998 芭蕉の奥の細道について 解説や写真がのっている

『モースの見た日本』 小西四郎 田辺悟【構成】 小学館 2005 セイラム・ピーボディー博物館 江戸~明治期の日用品が多くのっている。

『石に刻まれた芭蕉』弘中孝 智書房 2004年 全国各地にのこる芭蕉の句碑や文学碑などをまとめている。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 『おくのほそ道』導入中3国語.pdf
キーワード1 松尾芭蕉 キーワード2 奥の細道 キーワード3 授業計画・指導案等 指導案 おくのほそ道.pdf 児童・生徒の作品 授業者 山本 みづほ(国語科教諭) 梶川 由香理(学校司書) 授業者コメント おくのほそ道の導入として、「10分でたどる『おくの細道』」と題して、江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについて話してもらうよう依頼。実際には生徒とのやりとりを入れて15分になったが、司書の話の中で司書教諭がどんな質問を生徒に投げかけ反応を見ていくかを、本番前の4クラスの授業で調整した。当日は、市立図書館との連携事業関連で文教厚生部の市会議員も8名参加。熱心に参観され、まずはあっという間に授業が終わったとの感想を戴いた。それだけ引き込まれる授業だったのだろうと2人で納得した。生徒は、江戸時代の旅に大いに興味を持ち、芭蕉の苦労を知るとともに、これから学ぶ『おくのほそ道』に期待を寄せる様子が見られた。
司書・司書教諭コメント 話を聞いた後、質問もたくさん出ていたので、興味を持って聞いてくれたと思う。今では旅行と言えば、飛行機や電車などを使うが、当時は歩きがメインだったというところに驚きがあったようで、そのことに関する質問も多かった。松尾芭蕉についてはこれからも学習する機会や、彼の俳句に出会う機会があると思うので、その時に少しでも思い出してくれると良いなと思った。
情報提供校 佐世保市立大野中学校 事例作成日 授業実践日 平成25年11月15日~11月27日 事例作成者氏名 梶川 由香理
記入者:村上
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0176 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『夏草-「奥の細道」から』 光村図書 対象学年 中3 活用・支援の種類 パワーポイントで奥の細道を紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 奥の細道の導入部分で、江戸の旅について紹介してほしい
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについてを司書からパワーポイントを使って紹介することに。
提示資料 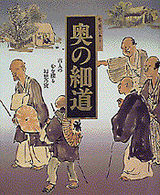
『奥の細道』 富士正晴 学習研究社 1998 芭蕉の奥の細道について 解説や写真がのっている

『モースの見た日本』 小西四郎 田辺悟【構成】 小学館 2005 セイラム・ピーボディー博物館 江戸~明治期の日用品が多くのっている。

『石に刻まれた芭蕉』弘中孝 智書房 2004年 全国各地にのこる芭蕉の句碑や文学碑などをまとめている。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 『おくのほそ道』導入中3国語.pdf
キーワード1 松尾芭蕉 キーワード2 奥の細道 キーワード3 授業計画・指導案等 指導案 おくのほそ道.pdf 児童・生徒の作品 授業者 山本 みづほ(国語科教諭) 梶川 由香理(学校司書) 授業者コメント おくのほそ道の導入として、「10分でたどる『おくの細道』」と題して、江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについて話してもらうよう依頼。実際には生徒とのやりとりを入れて15分になったが、司書の話の中で司書教諭がどんな質問を生徒に投げかけ反応を見ていくかを、本番前の4クラスの授業で調整した。当日は、市立図書館との連携事業関連で文教厚生部の市会議員も8名参加。熱心に参観され、まずはあっという間に授業が終わったとの感想を戴いた。それだけ引き込まれる授業だったのだろうと2人で納得した。生徒は、江戸時代の旅に大いに興味を持ち、芭蕉の苦労を知るとともに、これから学ぶ『おくのほそ道』に期待を寄せる様子が見られた。
司書・司書教諭コメント 話を聞いた後、質問もたくさん出ていたので、興味を持って聞いてくれたと思う。今では旅行と言えば、飛行機や電車などを使うが、当時は歩きがメインだったというところに驚きがあったようで、そのことに関する質問も多かった。松尾芭蕉についてはこれからも学習する機会や、彼の俳句に出会う機会があると思うので、その時に少しでも思い出してくれると良いなと思った。
情報提供校 佐世保市立大野中学校 事例作成日 授業実践日 平成25年11月15日~11月27日 事例作成者氏名 梶川 由香理
記入者:村上
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0176 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 『夏草-「奥の細道」から』 光村図書 |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | パワーポイントで奥の細道を紹介 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 奥の細道の導入部分で、江戸の旅について紹介してほしい |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについてを司書からパワーポイントを使って紹介することに。 |
| 提示資料 | |
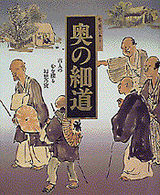 | 『奥の細道』 富士正晴 学習研究社 1998 芭蕉の奥の細道について 解説や写真がのっている |
 | 『モースの見た日本』 小西四郎 田辺悟【構成】 小学館 2005 セイラム・ピーボディー博物館 江戸~明治期の日用品が多くのっている。 |
 | 『石に刻まれた芭蕉』弘中孝 智書房 2004年 全国各地にのこる芭蕉の句碑や文学碑などをまとめている。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 『おくのほそ道』導入中3国語.pdf |
| キーワード1 | 松尾芭蕉 |
| キーワード2 | 奥の細道 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 指導案 おくのほそ道.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 山本 みづほ(国語科教諭) 梶川 由香理(学校司書) |
| 授業者コメント | おくのほそ道の導入として、「10分でたどる『おくの細道』」と題して、江戸時代の旅の様子と芭蕉のたどった道のりについて話してもらうよう依頼。実際には生徒とのやりとりを入れて15分になったが、司書の話の中で司書教諭がどんな質問を生徒に投げかけ反応を見ていくかを、本番前の4クラスの授業で調整した。当日は、市立図書館との連携事業関連で文教厚生部の市会議員も8名参加。熱心に参観され、まずはあっという間に授業が終わったとの感想を戴いた。それだけ引き込まれる授業だったのだろうと2人で納得した。生徒は、江戸時代の旅に大いに興味を持ち、芭蕉の苦労を知るとともに、これから学ぶ『おくのほそ道』に期待を寄せる様子が見られた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 話を聞いた後、質問もたくさん出ていたので、興味を持って聞いてくれたと思う。今では旅行と言えば、飛行機や電車などを使うが、当時は歩きがメインだったというところに驚きがあったようで、そのことに関する質問も多かった。松尾芭蕉についてはこれからも学習する機会や、彼の俳句に出会う機会があると思うので、その時に少しでも思い出してくれると良いなと思った。 |
| 情報提供校 | 佐世保市立大野中学校 |
| 事例作成日 | 授業実践日 平成25年11月15日~11月27日 |
| 事例作成者氏名 | 梶川 由香理 |
記入者:村上

























