お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0178 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 調べ学習の方法を学ぶさいに役立つような、1時間で完結する図書館実習はできないか。(つなげよう、3冊の本) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 3冊の本を選ぼう。各自1つのテーマに対し、3つの異なる分類からそれぞれ1冊ずつ本を選びだす。そのつながりをワークシートに記入させる。(なるべく意外性のあるつながりを奨励する。)
提示資料 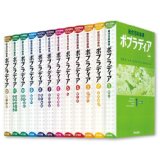
ポプラディア イメージが広がらない場合は、百科事典や辞書でその言葉を確認しようとアドバイス。

犬に関する5冊の本 司書が例として示した。
一般的には4類の動物図鑑だが、飼育という面では6類、盲導犬など福祉犬は3類、7類の画集や、9類の小説にも出てくる。

後日司書教諭と司書がワークシートを読んで意外なつながりかたの作品を3つ選び、図書館に展示した。テーマは上から「音」「ひまわり」「木」。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 分類 キーワード2 つながり キーワード3 授業計画・指導案等 3冊の本を探そう 2年D組2014.pdf 児童・生徒の作品 授業者 松原 洋子 授業者コメント 裏返したカードからテーマを選ぶ、というわくわく感から、授業は始まった。各自が選んだカードは、誰一人同じものはない。つまりこれからの自分の活動には責任が生じる。この段階で、生徒はいかに未知なる本、未知なるつながりを探すかという魅力に魅せられていた。
始めてみると、一つの問題点が見つかった。図書分類は既習事項であるにもかかわらず、忘れている生徒が複数いたのだ。こうした生徒の実態がわかったのは成果といえるかもしれないが、また将来、実践の機会があれば、はじめに図書分類番号の見方は確認すべきてある。
かくして、図書分類についてあやふやな生徒には図書分類に関する掲示物やラベルに着目させ、個別指導をしながらの1時間であった。つながりを見つけるのが難しいほど本探しに燃える生徒も多く、意外性のあるつながりを見つけるかという課題は生徒の発達段階に大変合っていると思われた。「3冊」という条件も、1時間完結の実践には適切であった。
どうしても本が見つからない生徒は、仲間の協力をあおぎながら、とても楽しく活動していた。
3冊を探し終えたらワークシートに本の情報とテーマとのつながりを簡単に書くのだが、「今まで以上に視点を広げられた。」「いつも行く文学以外の本にも目を向けられた。」「1つのテーマからいろいろなことに関連できてびっくりした。」「テーマの言葉をしっかりとらえ、特徴やいろいろな意味をとらえると、様々なつながりも見えてきた。調べ学習も、この『色々な目を持つ』ことが大切だと知った。」「テーマからイメージをふくらませると、とても面白い本が見つかることがわかった。」「普段取らないような分類の本を手に取って、新たな発見をした。」「今回の授業で、本を探せる範囲がとても広がった。これはこれからレポートを書くときにも活用したい。」といった前向きの発言が並び、生徒の視野を広げるという目的は果たせたと思う。 司書・司書教諭コメント 1時間で終わる授業として、「本の帯を作る」などの案も考えたが、なるべく普段見ないような本にも触れてほしいという思いから、この内容になった。生徒たちは図書館中の書架を歩き回ったり、掲示してある分類表を見たりと忙しく活動していた。時間内に終わらなかった生徒は昼休みに来館して、クラス全員がその日のうちにワークシートを提出することができ、感想も大変意欲的だった。
後日、9類以外の本を借りる生徒がこのクラスから出始めた。
情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2014年1月8日 事例作成者氏名 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書
記入者:井谷(主担)
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0178 校種 中学校 教科・領域等 総合 単元 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供・学習支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 調べ学習の方法を学ぶさいに役立つような、1時間で完結する図書館実習はできないか。(つなげよう、3冊の本) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 3冊の本を選ぼう。各自1つのテーマに対し、3つの異なる分類からそれぞれ1冊ずつ本を選びだす。そのつながりをワークシートに記入させる。(なるべく意外性のあるつながりを奨励する。)
提示資料 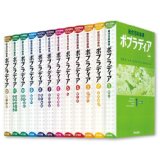
ポプラディア イメージが広がらない場合は、百科事典や辞書でその言葉を確認しようとアドバイス。

犬に関する5冊の本 司書が例として示した。
一般的には4類の動物図鑑だが、飼育という面では6類、盲導犬など福祉犬は3類、7類の画集や、9類の小説にも出てくる。

後日司書教諭と司書がワークシートを読んで意外なつながりかたの作品を3つ選び、図書館に展示した。テーマは上から「音」「ひまわり」「木」。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 分類 キーワード2 つながり キーワード3 授業計画・指導案等 3冊の本を探そう 2年D組2014.pdf 児童・生徒の作品 授業者 松原 洋子 授業者コメント 裏返したカードからテーマを選ぶ、というわくわく感から、授業は始まった。各自が選んだカードは、誰一人同じものはない。つまりこれからの自分の活動には責任が生じる。この段階で、生徒はいかに未知なる本、未知なるつながりを探すかという魅力に魅せられていた。
始めてみると、一つの問題点が見つかった。図書分類は既習事項であるにもかかわらず、忘れている生徒が複数いたのだ。こうした生徒の実態がわかったのは成果といえるかもしれないが、また将来、実践の機会があれば、はじめに図書分類番号の見方は確認すべきてある。
かくして、図書分類についてあやふやな生徒には図書分類に関する掲示物やラベルに着目させ、個別指導をしながらの1時間であった。つながりを見つけるのが難しいほど本探しに燃える生徒も多く、意外性のあるつながりを見つけるかという課題は生徒の発達段階に大変合っていると思われた。「3冊」という条件も、1時間完結の実践には適切であった。
どうしても本が見つからない生徒は、仲間の協力をあおぎながら、とても楽しく活動していた。
3冊を探し終えたらワークシートに本の情報とテーマとのつながりを簡単に書くのだが、「今まで以上に視点を広げられた。」「いつも行く文学以外の本にも目を向けられた。」「1つのテーマからいろいろなことに関連できてびっくりした。」「テーマの言葉をしっかりとらえ、特徴やいろいろな意味をとらえると、様々なつながりも見えてきた。調べ学習も、この『色々な目を持つ』ことが大切だと知った。」「テーマからイメージをふくらませると、とても面白い本が見つかることがわかった。」「普段取らないような分類の本を手に取って、新たな発見をした。」「今回の授業で、本を探せる範囲がとても広がった。これはこれからレポートを書くときにも活用したい。」といった前向きの発言が並び、生徒の視野を広げるという目的は果たせたと思う。 司書・司書教諭コメント 1時間で終わる授業として、「本の帯を作る」などの案も考えたが、なるべく普段見ないような本にも触れてほしいという思いから、この内容になった。生徒たちは図書館中の書架を歩き回ったり、掲示してある分類表を見たりと忙しく活動していた。時間内に終わらなかった生徒は昼休みに来館して、クラス全員がその日のうちにワークシートを提出することができ、感想も大変意欲的だった。
後日、9類以外の本を借りる生徒がこのクラスから出始めた。
情報提供校 東京学芸大学附属小金井中学校 事例作成日 2014年1月8日 事例作成者氏名 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書
記入者:井谷(主担)
カウンタ
3863398 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0178 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 総合 |
| 単元 | |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・学習支援 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 調べ学習の方法を学ぶさいに役立つような、1時間で完結する図書館実習はできないか。(つなげよう、3冊の本) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 3冊の本を選ぼう。各自1つのテーマに対し、3つの異なる分類からそれぞれ1冊ずつ本を選びだす。そのつながりをワークシートに記入させる。(なるべく意外性のあるつながりを奨励する。) |
| 提示資料 | |
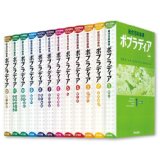 | ポプラディア イメージが広がらない場合は、百科事典や辞書でその言葉を確認しようとアドバイス。 |
 | 犬に関する5冊の本 司書が例として示した。 一般的には4類の動物図鑑だが、飼育という面では6類、盲導犬など福祉犬は3類、7類の画集や、9類の小説にも出てくる。 |
 | 後日司書教諭と司書がワークシートを読んで意外なつながりかたの作品を3つ選び、図書館に展示した。テーマは上から「音」「ひまわり」「木」。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 分類 |
| キーワード2 | つながり |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 3冊の本を探そう 2年D組2014.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 松原 洋子 |
| 授業者コメント | 裏返したカードからテーマを選ぶ、というわくわく感から、授業は始まった。各自が選んだカードは、誰一人同じものはない。つまりこれからの自分の活動には責任が生じる。この段階で、生徒はいかに未知なる本、未知なるつながりを探すかという魅力に魅せられていた。 始めてみると、一つの問題点が見つかった。図書分類は既習事項であるにもかかわらず、忘れている生徒が複数いたのだ。こうした生徒の実態がわかったのは成果といえるかもしれないが、また将来、実践の機会があれば、はじめに図書分類番号の見方は確認すべきてある。 かくして、図書分類についてあやふやな生徒には図書分類に関する掲示物やラベルに着目させ、個別指導をしながらの1時間であった。つながりを見つけるのが難しいほど本探しに燃える生徒も多く、意外性のあるつながりを見つけるかという課題は生徒の発達段階に大変合っていると思われた。「3冊」という条件も、1時間完結の実践には適切であった。 どうしても本が見つからない生徒は、仲間の協力をあおぎながら、とても楽しく活動していた。 3冊を探し終えたらワークシートに本の情報とテーマとのつながりを簡単に書くのだが、「今まで以上に視点を広げられた。」「いつも行く文学以外の本にも目を向けられた。」「1つのテーマからいろいろなことに関連できてびっくりした。」「テーマの言葉をしっかりとらえ、特徴やいろいろな意味をとらえると、様々なつながりも見えてきた。調べ学習も、この『色々な目を持つ』ことが大切だと知った。」「テーマからイメージをふくらませると、とても面白い本が見つかることがわかった。」「普段取らないような分類の本を手に取って、新たな発見をした。」「今回の授業で、本を探せる範囲がとても広がった。これはこれからレポートを書くときにも活用したい。」といった前向きの発言が並び、生徒の視野を広げるという目的は果たせたと思う。 |
| 司書・司書教諭コメント | 1時間で終わる授業として、「本の帯を作る」などの案も考えたが、なるべく普段見ないような本にも触れてほしいという思いから、この内容になった。生徒たちは図書館中の書架を歩き回ったり、掲示してある分類表を見たりと忙しく活動していた。時間内に終わらなかった生徒は昼休みに来館して、クラス全員がその日のうちにワークシートを提出することができ、感想も大変意欲的だった。 後日、9類以外の本を借りる生徒がこのクラスから出始めた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井中学校 |
| 事例作成日 | 2014年1月8日 |
| 事例作成者氏名 | 松原 洋子教諭 井谷 由紀司書 |
記入者:井谷(主担)

























