お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0186 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 シリーズで 読んでみよう! 対象学年 低学年 活用・支援の種類 選書、資料提供、ブックリスト作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 小学校1年生がシリーズで読んでいくのに適した本を教えてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 同じ主人公が活躍するもので、どの作品から読んでも楽しめるもの(順番の関係ないもの(がよいとのことだった。本はブックトラックごと、学級貸出しにした。足りないものは学校間貸出しで借りた。
提示資料 中心題材のますだくんシリーズ他、シリーズの読みものを学級貸出しにした。 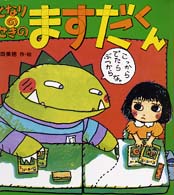
『となりのせきのまずだくん』武田美穂 ポプラ社 1991
シリーズの第1作目である。物語は、みほちゃんという小学校1年生の視点で描かれている。隣の席男子児童であるますだくんを怖がり、学校に行くことが不安でたまならない。その気持ちを見事に表現しているのが、ますだくんの姿が怪獣として描かれていることである。それを見るだけで、児童たちは、みほちゃんの気持ちに同化できる。
みほちゃんがますだくんを怖がる理由は、ますだくんのみほちゃんに対する態度にある。
・机に線を引き、ここから出たらぶつと言ってにらむ。
・消しゴムのかすがはみ出したら椅子を蹴る。
・指を使って計算すると笑う。
・苦手なにんじんを残すと大声で注意する。
・なわとびができないことをけなし、教わることを拒むと殴る。
・お気に入りの鉛筆を折る。
・消しゴムを投げつけられると驚いてにらむ。
しかし、最後の場面にほのぼのとした展開が待っている。けんかをした次の日、またぶたれることを恐れながら登校するみほちゃんを、ますだくんは「ごめんよ」といってぶつ。そこにはテープで直した鉛筆もある。次の挿絵では、ずっと怪獣として描かれていたますだくんは、人間の男の子に変わっていた。 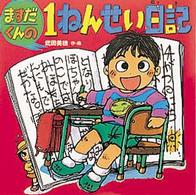
『ますだくんの1ねんせい日記』武田美穂 ポプラ社1996
シリーズの第3作目であるが、児童たちには2番目に紹介したい。この物語は、学校が大好きで元気いっぱいなますだくんが主人公であり、自分の日常生活を日記の形で紹介している。つまり、ますだくんの視点で物語が描かれているのである。この本では、みほちゃんは頼りない女の子として紹介されていて、第1作目で美保ちゃんの視点で描かれた出来事が、ますだくんから見ると全く別の話のように感じられる。
第1作目の出来事をますだくんの視点で見ていくと、頼りないみほちゃんを何とか助けてあげようとしているますだくんの姿が見えてくる。しかし、ますだくんの思いは通じず、何をしても空回りしていらいらが募るばかりである。そして、鉛筆の事件が起こるのであるが、これはますだくん自身が折ったのではなく、友達が踏んだので折れたのである。これも第1作目では分からなかった真相である。児童たちはますだくんについての意外な発見に大喜びする。この経験が、自分が同化して読む登場人物以外の行動にも興味を抱くきっかけとなれば、低学年の読みから一歩踏み出す感覚が得られるかもしれない。 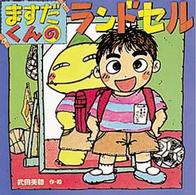
『ますだくんのランドセル』武田美穂 ポプラ社1995
シリーズの2作目であるが、児童たちには3番目に紹介する。この物語も、ますだくんの視点で描かれており、ますだくんの家での生活を中心に、小学校に入学してみほちゃんと出会うまでが描かれている。
この本を読むと、ますだくんの人物像が分かってくる。小学校生活を心から待ち望む姿や妹の面倒を一生懸命みる姿を感じ取った児童たちは、ますだくんのさらに意外な一面に驚くであろう。
そして、後半のみほちゃんとの出会いを読むと、どうしてますだくんがみほちゃんにあのような関わり方をするのかが見えてくる。みほちゃんを妹と比べたり、大好きな妹に似ていてかわいいと感じたりする場面は、ますだくんのみほちゃんへの関わり方が決まる瞬間であろう。みほちゃんの心に「ますだくん=怪獣」という印象が芽生えた瞬間も分かり、前述の2冊とつながることがとても楽しく感じられる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト シリーズで読んでみよう 小1国語 2014 改訂版.xls
キーワード1 シリーズ キーワード2 読書生活 キーワード3 ますだくん 授業計画・指導案等 シリーズでよんでみよう 小1国語 201402.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 筧理沙子教諭 授業者コメント 打ち合わせいて良かったこと…1年生の実態にあったシリーズの本(シリーズのうち、作者も登場人物も同一のもので、順番もあまり関係のないもの)を、探していたので、どんなシリースをブックリストに入れたらよいか相談できたこと。またシリーズを集めてもらえたこと。 有効だった点…シリーズを読むことによって、読書が楽しめることに児童が気がつけたこと。日常的にシリーズを楽しむ姿がたくさん見られた。家でも読んでいるようである。 学校図書館活用による児童の授業への関心・意欲…今までぱらぱらめくったり、絵を眺めたりするだけで読んだ気になっていた子が、じっくり読んで楽しんでいる姿が見られたので、意欲・関心が高まったと思う。 司書・司書教諭コメント 絵本、文学の棚を筧教諭とともに見て、二人で抜きながら、同じ主人公が出てくるもの、あまりエンタ―テーメント性の高いもの(「ぞろり」や「にんたまらんたろう」「まじょこ」「マジック・ツリーハウスなど)は外そうなどし、方針をうかがうことができた。自由読書ではなかなか手にしてもらえない本も注目され、しかもまとまって読める機会を作ってもらえたのがよかった。他のクラスや学年の子たちの読みたいという要求には、待ってもらわねばならなかったが。 図書館所蔵の14匹シリーズの人形や、各出版社のWebサイトより人物紹介、物語紹介などもプリントアウトして学級に提供した。教室を通りかかると、今これを読んでいて面白い等、話しかけてきてくれたりした。1年生最後に、じっくり読む機会となった。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2014年3月31日 授業実践 2014 年 2月8日 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863431 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0186 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 シリーズで 読んでみよう! 対象学年 低学年 活用・支援の種類 選書、資料提供、ブックリスト作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 小学校1年生がシリーズで読んでいくのに適した本を教えてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 同じ主人公が活躍するもので、どの作品から読んでも楽しめるもの(順番の関係ないもの(がよいとのことだった。本はブックトラックごと、学級貸出しにした。足りないものは学校間貸出しで借りた。
提示資料 中心題材のますだくんシリーズ他、シリーズの読みものを学級貸出しにした。 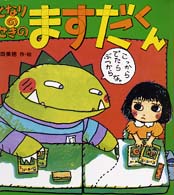
『となりのせきのまずだくん』武田美穂 ポプラ社 1991
シリーズの第1作目である。物語は、みほちゃんという小学校1年生の視点で描かれている。隣の席男子児童であるますだくんを怖がり、学校に行くことが不安でたまならない。その気持ちを見事に表現しているのが、ますだくんの姿が怪獣として描かれていることである。それを見るだけで、児童たちは、みほちゃんの気持ちに同化できる。
みほちゃんがますだくんを怖がる理由は、ますだくんのみほちゃんに対する態度にある。
・机に線を引き、ここから出たらぶつと言ってにらむ。
・消しゴムのかすがはみ出したら椅子を蹴る。
・指を使って計算すると笑う。
・苦手なにんじんを残すと大声で注意する。
・なわとびができないことをけなし、教わることを拒むと殴る。
・お気に入りの鉛筆を折る。
・消しゴムを投げつけられると驚いてにらむ。
しかし、最後の場面にほのぼのとした展開が待っている。けんかをした次の日、またぶたれることを恐れながら登校するみほちゃんを、ますだくんは「ごめんよ」といってぶつ。そこにはテープで直した鉛筆もある。次の挿絵では、ずっと怪獣として描かれていたますだくんは、人間の男の子に変わっていた。 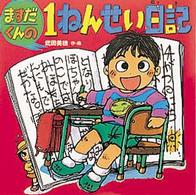
『ますだくんの1ねんせい日記』武田美穂 ポプラ社1996
シリーズの第3作目であるが、児童たちには2番目に紹介したい。この物語は、学校が大好きで元気いっぱいなますだくんが主人公であり、自分の日常生活を日記の形で紹介している。つまり、ますだくんの視点で物語が描かれているのである。この本では、みほちゃんは頼りない女の子として紹介されていて、第1作目で美保ちゃんの視点で描かれた出来事が、ますだくんから見ると全く別の話のように感じられる。
第1作目の出来事をますだくんの視点で見ていくと、頼りないみほちゃんを何とか助けてあげようとしているますだくんの姿が見えてくる。しかし、ますだくんの思いは通じず、何をしても空回りしていらいらが募るばかりである。そして、鉛筆の事件が起こるのであるが、これはますだくん自身が折ったのではなく、友達が踏んだので折れたのである。これも第1作目では分からなかった真相である。児童たちはますだくんについての意外な発見に大喜びする。この経験が、自分が同化して読む登場人物以外の行動にも興味を抱くきっかけとなれば、低学年の読みから一歩踏み出す感覚が得られるかもしれない。 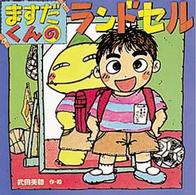
『ますだくんのランドセル』武田美穂 ポプラ社1995
シリーズの2作目であるが、児童たちには3番目に紹介する。この物語も、ますだくんの視点で描かれており、ますだくんの家での生活を中心に、小学校に入学してみほちゃんと出会うまでが描かれている。
この本を読むと、ますだくんの人物像が分かってくる。小学校生活を心から待ち望む姿や妹の面倒を一生懸命みる姿を感じ取った児童たちは、ますだくんのさらに意外な一面に驚くであろう。
そして、後半のみほちゃんとの出会いを読むと、どうしてますだくんがみほちゃんにあのような関わり方をするのかが見えてくる。みほちゃんを妹と比べたり、大好きな妹に似ていてかわいいと感じたりする場面は、ますだくんのみほちゃんへの関わり方が決まる瞬間であろう。みほちゃんの心に「ますだくん=怪獣」という印象が芽生えた瞬間も分かり、前述の2冊とつながることがとても楽しく感じられる。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト シリーズで読んでみよう 小1国語 2014 改訂版.xls
キーワード1 シリーズ キーワード2 読書生活 キーワード3 ますだくん 授業計画・指導案等 シリーズでよんでみよう 小1国語 201402.pdf 児童・生徒の作品 授業者 東京学芸大学附属小金井小学校 筧理沙子教諭 授業者コメント 打ち合わせいて良かったこと…1年生の実態にあったシリーズの本(シリーズのうち、作者も登場人物も同一のもので、順番もあまり関係のないもの)を、探していたので、どんなシリースをブックリストに入れたらよいか相談できたこと。またシリーズを集めてもらえたこと。 有効だった点…シリーズを読むことによって、読書が楽しめることに児童が気がつけたこと。日常的にシリーズを楽しむ姿がたくさん見られた。家でも読んでいるようである。 学校図書館活用による児童の授業への関心・意欲…今までぱらぱらめくったり、絵を眺めたりするだけで読んだ気になっていた子が、じっくり読んで楽しんでいる姿が見られたので、意欲・関心が高まったと思う。 司書・司書教諭コメント 絵本、文学の棚を筧教諭とともに見て、二人で抜きながら、同じ主人公が出てくるもの、あまりエンタ―テーメント性の高いもの(「ぞろり」や「にんたまらんたろう」「まじょこ」「マジック・ツリーハウスなど)は外そうなどし、方針をうかがうことができた。自由読書ではなかなか手にしてもらえない本も注目され、しかもまとまって読める機会を作ってもらえたのがよかった。他のクラスや学年の子たちの読みたいという要求には、待ってもらわねばならなかったが。 図書館所蔵の14匹シリーズの人形や、各出版社のWebサイトより人物紹介、物語紹介などもプリントアウトして学級に提供した。教室を通りかかると、今これを読んでいて面白い等、話しかけてきてくれたりした。1年生最後に、じっくり読む機会となった。 情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2014年3月31日 授業実践 2014 年 2月8日 事例作成者氏名 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863431 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0186 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | シリーズで 読んでみよう! |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 選書、資料提供、ブックリスト作成 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 小学校1年生がシリーズで読んでいくのに適した本を教えてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 同じ主人公が活躍するもので、どの作品から読んでも楽しめるもの(順番の関係ないもの(がよいとのことだった。本はブックトラックごと、学級貸出しにした。足りないものは学校間貸出しで借りた。 |
| 提示資料 | 中心題材のますだくんシリーズ他、シリーズの読みものを学級貸出しにした。 |
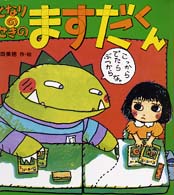 | 『となりのせきのまずだくん』武田美穂 ポプラ社 1991 シリーズの第1作目である。物語は、みほちゃんという小学校1年生の視点で描かれている。隣の席男子児童であるますだくんを怖がり、学校に行くことが不安でたまならない。その気持ちを見事に表現しているのが、ますだくんの姿が怪獣として描かれていることである。それを見るだけで、児童たちは、みほちゃんの気持ちに同化できる。 みほちゃんがますだくんを怖がる理由は、ますだくんのみほちゃんに対する態度にある。 ・机に線を引き、ここから出たらぶつと言ってにらむ。 ・消しゴムのかすがはみ出したら椅子を蹴る。 ・指を使って計算すると笑う。 ・苦手なにんじんを残すと大声で注意する。 ・なわとびができないことをけなし、教わることを拒むと殴る。 ・お気に入りの鉛筆を折る。 ・消しゴムを投げつけられると驚いてにらむ。 しかし、最後の場面にほのぼのとした展開が待っている。けんかをした次の日、またぶたれることを恐れながら登校するみほちゃんを、ますだくんは「ごめんよ」といってぶつ。そこにはテープで直した鉛筆もある。次の挿絵では、ずっと怪獣として描かれていたますだくんは、人間の男の子に変わっていた。 |
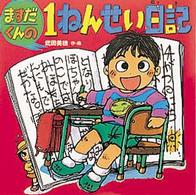 | 『ますだくんの1ねんせい日記』武田美穂 ポプラ社1996 シリーズの第3作目であるが、児童たちには2番目に紹介したい。この物語は、学校が大好きで元気いっぱいなますだくんが主人公であり、自分の日常生活を日記の形で紹介している。つまり、ますだくんの視点で物語が描かれているのである。この本では、みほちゃんは頼りない女の子として紹介されていて、第1作目で美保ちゃんの視点で描かれた出来事が、ますだくんから見ると全く別の話のように感じられる。 第1作目の出来事をますだくんの視点で見ていくと、頼りないみほちゃんを何とか助けてあげようとしているますだくんの姿が見えてくる。しかし、ますだくんの思いは通じず、何をしても空回りしていらいらが募るばかりである。そして、鉛筆の事件が起こるのであるが、これはますだくん自身が折ったのではなく、友達が踏んだので折れたのである。これも第1作目では分からなかった真相である。児童たちはますだくんについての意外な発見に大喜びする。この経験が、自分が同化して読む登場人物以外の行動にも興味を抱くきっかけとなれば、低学年の読みから一歩踏み出す感覚が得られるかもしれない。 |
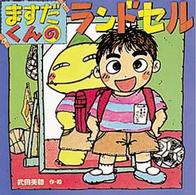 | 『ますだくんのランドセル』武田美穂 ポプラ社1995 シリーズの2作目であるが、児童たちには3番目に紹介する。この物語も、ますだくんの視点で描かれており、ますだくんの家での生活を中心に、小学校に入学してみほちゃんと出会うまでが描かれている。 この本を読むと、ますだくんの人物像が分かってくる。小学校生活を心から待ち望む姿や妹の面倒を一生懸命みる姿を感じ取った児童たちは、ますだくんのさらに意外な一面に驚くであろう。 そして、後半のみほちゃんとの出会いを読むと、どうしてますだくんがみほちゃんにあのような関わり方をするのかが見えてくる。みほちゃんを妹と比べたり、大好きな妹に似ていてかわいいと感じたりする場面は、ますだくんのみほちゃんへの関わり方が決まる瞬間であろう。みほちゃんの心に「ますだくん=怪獣」という印象が芽生えた瞬間も分かり、前述の2冊とつながることがとても楽しく感じられる。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | シリーズで読んでみよう 小1国語 2014 改訂版.xls |
| キーワード1 | シリーズ |
| キーワード2 | 読書生活 |
| キーワード3 | ますだくん |
| 授業計画・指導案等 | シリーズでよんでみよう 小1国語 201402.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 東京学芸大学附属小金井小学校 筧理沙子教諭 |
| 授業者コメント | 打ち合わせいて良かったこと…1年生の実態にあったシリーズの本(シリーズのうち、作者も登場人物も同一のもので、順番もあまり関係のないもの)を、探していたので、どんなシリースをブックリストに入れたらよいか相談できたこと。またシリーズを集めてもらえたこと。 有効だった点…シリーズを読むことによって、読書が楽しめることに児童が気がつけたこと。日常的にシリーズを楽しむ姿がたくさん見られた。家でも読んでいるようである。 学校図書館活用による児童の授業への関心・意欲…今までぱらぱらめくったり、絵を眺めたりするだけで読んだ気になっていた子が、じっくり読んで楽しんでいる姿が見られたので、意欲・関心が高まったと思う。 |
| 司書・司書教諭コメント | 絵本、文学の棚を筧教諭とともに見て、二人で抜きながら、同じ主人公が出てくるもの、あまりエンタ―テーメント性の高いもの(「ぞろり」や「にんたまらんたろう」「まじょこ」「マジック・ツリーハウスなど)は外そうなどし、方針をうかがうことができた。自由読書ではなかなか手にしてもらえない本も注目され、しかもまとまって読める機会を作ってもらえたのがよかった。他のクラスや学年の子たちの読みたいという要求には、待ってもらわねばならなかったが。 図書館所蔵の14匹シリーズの人形や、各出版社のWebサイトより人物紹介、物語紹介などもプリントアウトして学級に提供した。教室を通りかかると、今これを読んでいて面白い等、話しかけてきてくれたりした。1年生最後に、じっくり読む機会となった。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2014年3月31日 授業実践 2014 年 2月8日 |
| 事例作成者氏名 | 東京学芸大学附属小金井小学校司書 中山美由紀 |
記入者:中山(主担)

























