お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0196 校種 高校 教科・領域等 家庭 単元 調理実習 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供・ブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 栄養への興味関心・自立的な食習慣を身につけることの重要性に気づかせるための授業プランを検討しているので、資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 食事について自立的に考えるきっかけになるよう、グループで分担して4品からなる献立をたて、材料等の計算・準備も自分たちで行う。そのための計画に2時間(図書館)あて、その後調理実習を行う。ただ、実習が楽しかっただけに終わらないよう、実習後に食について考えるような時間がほしい。(司書よりブックトークを提案)
提示資料 調理実習用資料には、野菜を中心にすることがテーマであったので、やさしいレシピが書かれている本や雑誌を汁物・主菜・副菜・デザートについて用意した。(別紙)ブックトークは、教師による炭酸飲料作成の実演を組み合わせて行った。 
『食品の裏側』安部 司著 東洋経済新報社 2005 食品製造の現場での食品添加物の使用の現状に関するエピソードも衝撃的だが、食品添加物を完全に排除しようとするのではなく、知った上でつきあい方を考えるという視点を生徒に知ってほしかった。著者が講演会で実際に行っている炭酸飲料の作成実演をこの後担当教師が実演した。 
『生命と食』(岩波ブックレット No.736)福岡 伸一著 岩波書店 2008食べることを主体的に考えることの意味について、生命科学の立場から紹介している。今年全頭検査が廃止されたBSEについても、知らない生徒が多いので、ぜひ食の生産という視点でも知っておいてほしいと考えた。 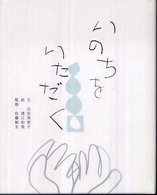
『いのちをいただく』内田 美智子文 西日本新聞 2009 食べることはいのちをいただくということをまっすぐに伝えてくれる本である。豊かな時代に育った高校生が食べることの意味について考えるきっかけを作るには、まず心を動かされることが必要なのだろうと考えた。『いのちをいただく』を読み聞かせした。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 調理実習 高1家庭科 2013 12.xls
キーワード1 食育 キーワード2 栄養 キーワード3 食習慣 授業計画・指導案等 調理実習 高1 家庭総合 201402.pdf 児童・生徒の作品 授業者 大坪千尋 授業者コメント 自分一人で料理を作った事がない生徒が多く、献立作成に非常に苦労していた。レシピを見ても調理にイメージがわかないのである。食べたい物をいくつか選び、「この中でどの料理が簡単ですか?」「どれだったら自分に作れますか?」と聞いてくる生徒が多かった。事前に簡単な調理実習を数回行い、自分の調理技術を知っておくと良いと思った。実習では危険がないか、用具や材料が足りているか、という点のみに気を配り、授業者は敢えて手出しをしないようにした。実際に作ってみるとレシピ通りに事が運ばず、1回目の実習では時間オーバーや失敗が続出した。授業時数の関係で反省の時間が十分とれなかったのが残念だったが、それぞれが2回目の実習に向けて反省を行い、驚くほどの進歩を見せた。また、自然とお互いに助け合う姿勢が見られるようになった。
ブックトークでは添加物から命の大切さまで幅広く紹介していただいた。『いのちをいただく』の読み聞かせでは皆が真剣に聞いていた。「あの後炭酸が飲めなくなった」「表示を見て選ぶようになった」「残すのに罪悪感を覚える」等の感想が聞かれた。 司書・司書教諭コメント 調理経験がほとんどない生徒が多く、献立作成が軌道にのるまで時間がかかるグループもあったが、2回の調理実習を通して、経験や自信をつけた様子がうかがえた。献立作成のための資料として、デザート作りを希望する生徒が予想外に多く、資料を途中から追加したが、間に合わないクラスもあった。使用した資料はメモをとるよう最初に伝えたが、記録していないグループもありやや混乱した。ブックトークについては、炭酸飲料水作成の実演を取り入れたことで、視覚や味覚で体感できる授業になったと思う。『いのちをいただく』の読み聞かせでは、真剣に聞き入っている様子がうかがえ、高校生にも読み聞かせは有効であるとあらためて感じた。 情報提供校 鳥取県立米子東高等学校 事例作成日 2014年3月26日 /授業実践 2013年12月18日 事例作成者氏名 司書 宇田川恵理
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0196 校種 高校 教科・領域等 家庭 単元 調理実習 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供・ブックトーク 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 栄養への興味関心・自立的な食習慣を身につけることの重要性に気づかせるための授業プランを検討しているので、資料を用意してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 食事について自立的に考えるきっかけになるよう、グループで分担して4品からなる献立をたて、材料等の計算・準備も自分たちで行う。そのための計画に2時間(図書館)あて、その後調理実習を行う。ただ、実習が楽しかっただけに終わらないよう、実習後に食について考えるような時間がほしい。(司書よりブックトークを提案)
提示資料 調理実習用資料には、野菜を中心にすることがテーマであったので、やさしいレシピが書かれている本や雑誌を汁物・主菜・副菜・デザートについて用意した。(別紙)ブックトークは、教師による炭酸飲料作成の実演を組み合わせて行った。 
『食品の裏側』安部 司著 東洋経済新報社 2005 食品製造の現場での食品添加物の使用の現状に関するエピソードも衝撃的だが、食品添加物を完全に排除しようとするのではなく、知った上でつきあい方を考えるという視点を生徒に知ってほしかった。著者が講演会で実際に行っている炭酸飲料の作成実演をこの後担当教師が実演した。 
『生命と食』(岩波ブックレット No.736)福岡 伸一著 岩波書店 2008食べることを主体的に考えることの意味について、生命科学の立場から紹介している。今年全頭検査が廃止されたBSEについても、知らない生徒が多いので、ぜひ食の生産という視点でも知っておいてほしいと考えた。 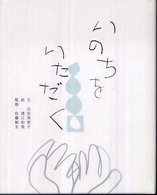
『いのちをいただく』内田 美智子文 西日本新聞 2009 食べることはいのちをいただくということをまっすぐに伝えてくれる本である。豊かな時代に育った高校生が食べることの意味について考えるきっかけを作るには、まず心を動かされることが必要なのだろうと考えた。『いのちをいただく』を読み聞かせした。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 調理実習 高1家庭科 2013 12.xls
キーワード1 食育 キーワード2 栄養 キーワード3 食習慣 授業計画・指導案等 調理実習 高1 家庭総合 201402.pdf 児童・生徒の作品 授業者 大坪千尋 授業者コメント 自分一人で料理を作った事がない生徒が多く、献立作成に非常に苦労していた。レシピを見ても調理にイメージがわかないのである。食べたい物をいくつか選び、「この中でどの料理が簡単ですか?」「どれだったら自分に作れますか?」と聞いてくる生徒が多かった。事前に簡単な調理実習を数回行い、自分の調理技術を知っておくと良いと思った。実習では危険がないか、用具や材料が足りているか、という点のみに気を配り、授業者は敢えて手出しをしないようにした。実際に作ってみるとレシピ通りに事が運ばず、1回目の実習では時間オーバーや失敗が続出した。授業時数の関係で反省の時間が十分とれなかったのが残念だったが、それぞれが2回目の実習に向けて反省を行い、驚くほどの進歩を見せた。また、自然とお互いに助け合う姿勢が見られるようになった。
ブックトークでは添加物から命の大切さまで幅広く紹介していただいた。『いのちをいただく』の読み聞かせでは皆が真剣に聞いていた。「あの後炭酸が飲めなくなった」「表示を見て選ぶようになった」「残すのに罪悪感を覚える」等の感想が聞かれた。 司書・司書教諭コメント 調理経験がほとんどない生徒が多く、献立作成が軌道にのるまで時間がかかるグループもあったが、2回の調理実習を通して、経験や自信をつけた様子がうかがえた。献立作成のための資料として、デザート作りを希望する生徒が予想外に多く、資料を途中から追加したが、間に合わないクラスもあった。使用した資料はメモをとるよう最初に伝えたが、記録していないグループもありやや混乱した。ブックトークについては、炭酸飲料水作成の実演を取り入れたことで、視覚や味覚で体感できる授業になったと思う。『いのちをいただく』の読み聞かせでは、真剣に聞き入っている様子がうかがえ、高校生にも読み聞かせは有効であるとあらためて感じた。 情報提供校 鳥取県立米子東高等学校 事例作成日 2014年3月26日 /授業実践 2013年12月18日 事例作成者氏名 司書 宇田川恵理
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863515 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0196 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 家庭 |
| 単元 | 調理実習 |
| 対象学年 | 高1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・ブックトーク |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 栄養への興味関心・自立的な食習慣を身につけることの重要性に気づかせるための授業プランを検討しているので、資料を用意してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 食事について自立的に考えるきっかけになるよう、グループで分担して4品からなる献立をたて、材料等の計算・準備も自分たちで行う。そのための計画に2時間(図書館)あて、その後調理実習を行う。ただ、実習が楽しかっただけに終わらないよう、実習後に食について考えるような時間がほしい。(司書よりブックトークを提案) |
| 提示資料 | 調理実習用資料には、野菜を中心にすることがテーマであったので、やさしいレシピが書かれている本や雑誌を汁物・主菜・副菜・デザートについて用意した。(別紙)ブックトークは、教師による炭酸飲料作成の実演を組み合わせて行った。 |
 | 『食品の裏側』安部 司著 東洋経済新報社 2005 食品製造の現場での食品添加物の使用の現状に関するエピソードも衝撃的だが、食品添加物を完全に排除しようとするのではなく、知った上でつきあい方を考えるという視点を生徒に知ってほしかった。著者が講演会で実際に行っている炭酸飲料の作成実演をこの後担当教師が実演した。 |
 | 『生命と食』(岩波ブックレット No.736)福岡 伸一著 岩波書店 2008食べることを主体的に考えることの意味について、生命科学の立場から紹介している。今年全頭検査が廃止されたBSEについても、知らない生徒が多いので、ぜひ食の生産という視点でも知っておいてほしいと考えた。 |
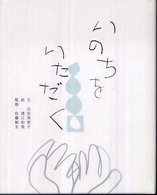 | 『いのちをいただく』内田 美智子文 西日本新聞 2009 食べることはいのちをいただくということをまっすぐに伝えてくれる本である。豊かな時代に育った高校生が食べることの意味について考えるきっかけを作るには、まず心を動かされることが必要なのだろうと考えた。『いのちをいただく』を読み聞かせした。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 調理実習 高1家庭科 2013 12.xls |
| キーワード1 | 食育 |
| キーワード2 | 栄養 |
| キーワード3 | 食習慣 |
| 授業計画・指導案等 | 調理実習 高1 家庭総合 201402.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 大坪千尋 |
| 授業者コメント | 自分一人で料理を作った事がない生徒が多く、献立作成に非常に苦労していた。レシピを見ても調理にイメージがわかないのである。食べたい物をいくつか選び、「この中でどの料理が簡単ですか?」「どれだったら自分に作れますか?」と聞いてくる生徒が多かった。事前に簡単な調理実習を数回行い、自分の調理技術を知っておくと良いと思った。実習では危険がないか、用具や材料が足りているか、という点のみに気を配り、授業者は敢えて手出しをしないようにした。実際に作ってみるとレシピ通りに事が運ばず、1回目の実習では時間オーバーや失敗が続出した。授業時数の関係で反省の時間が十分とれなかったのが残念だったが、それぞれが2回目の実習に向けて反省を行い、驚くほどの進歩を見せた。また、自然とお互いに助け合う姿勢が見られるようになった。 ブックトークでは添加物から命の大切さまで幅広く紹介していただいた。『いのちをいただく』の読み聞かせでは皆が真剣に聞いていた。「あの後炭酸が飲めなくなった」「表示を見て選ぶようになった」「残すのに罪悪感を覚える」等の感想が聞かれた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 調理経験がほとんどない生徒が多く、献立作成が軌道にのるまで時間がかかるグループもあったが、2回の調理実習を通して、経験や自信をつけた様子がうかがえた。献立作成のための資料として、デザート作りを希望する生徒が予想外に多く、資料を途中から追加したが、間に合わないクラスもあった。使用した資料はメモをとるよう最初に伝えたが、記録していないグループもありやや混乱した。ブックトークについては、炭酸飲料水作成の実演を取り入れたことで、視覚や味覚で体感できる授業になったと思う。『いのちをいただく』の読み聞かせでは、真剣に聞き入っている様子がうかがえ、高校生にも読み聞かせは有効であるとあらためて感じた。 |
| 情報提供校 | 鳥取県立米子東高等学校 |
| 事例作成日 | 2014年3月26日 /授業実践 2013年12月18日 |
| 事例作成者氏名 | 司書 宇田川恵理 |
記入者:中山(主担)

























