お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0198 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 ほうこく書を書こう「本で調べてほうこくしよう」 (光村3年下) 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・レファレンス(公共図書館と連携)、ワークシート提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 各自の疑問を「本で調べて報告書を書く」という学習のために、一人ひとりの疑問を調べる本を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ①教員へ授業展開等(1月初め、2月教材で、各自の疑問を調べる資料依頼時)→3年生向き資料を揃えるために、区立資料借用を想定し、教諭による児童のテーマ(疑問)聴き取りを1/17までにと依頼。②テーマ一覧をもらい分野別に並べ替えをした後、自校本抜き取りと不足分野の検討を行った。同時にテーマ絞り込みのために教員や必要児童に司書が再聞き取りを実施。
提示資料 子どもの疑問とあわせたブックリストをまとめました。音楽、法律、仕事などの疑問もありました。以下その一部から自然科学系のものを紹介します。 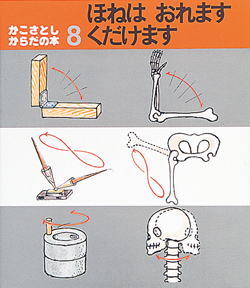
『ほねはおれますくだけます』(かこさとし がらだの本 8) かこさとし 童心社 1977年
ほねの仕組みや働きが、クラゲや昆虫などの例で示され低学年にもわかりやすい。地味で古い本なので、紹介したい。 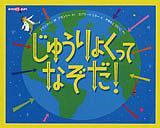
『 じゅりょくってなぞだ!』フランクリン・M・ブランリー作 エドワード・ミラー絵 やまもとけいこ訳 福音館書店 2010年
3年ではむずかしい題材だが、重力があることで普通に暮らせることには気づける。
「なぜ、じゅうりょくがあるのか だれもはっきりわからない。」と終わっている点
が科学の本らしい。調べれば答えが出てくるとは限らない。
新たな疑問を更に調べたり研究していくのが科学だと気が付いてくれると良い。 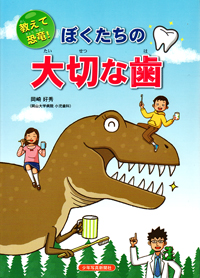
『教えて恐竜! ぼくたちの大切な歯』岡崎好秀 少年写真新聞社 2011年
導入が巧みで引きつけられる。化石や進化にも触れていて興味を持つ児童が多い。
展示したらよく貸し出された。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 本で調べて報告しよう(小3国語)2014.xls
キーワード1 レファレンス キーワード2 情報の探し方 キーワード3 報告書 授業計画・指導案等 小3国語「本で調べてほうこくしよう」学習指導案 報告書.pdf 児童・生徒の作品 授業者 田中啓子 主任教諭 安藤恵 教諭 授業者コメント 本で調べて人に伝えることを初めて学習する単元である。単元の目標は、次の3つであ る。 ① 生活の中から調べたいことを決め、必要な事柄について本を読んで調べることができ る。 ② 書こうとすることの中心を明確にし、構成を考え、まとまりに分けて書くことができ る。 ③ 自分の問いを解決するために必要な本や文章を選んで読み、文章を引用したり要約し たりすることができる。 まず3年生の実態を考えると、興味関心の幅は広く、ほとんどの児童が浅いので、まず、 調べたいことを決めることが難しい。そこで今、生活の中で疑問に思っていることや、もっと詳しく知りたいと思うことを挙げさせ、調べている途中でも変更してよいこととした。
次に、児童が調べたいテーマが載っていて、3年生の児童にも読み取れる易しい本を探すことが重要だと考えた。これを図書館指導員の方にお願いすることにした。本を探してもらうのに時間がかかることが予想されたので、授業の準備によってはかなり前から内容を 調べ関係機関や他の人の協力を得る例として、新任教員に指導することができた。 今回、調べたいことを自分の手で見つけ報告することができて、どの児童も自信がつい た。また、その後、総合の時間の調べ学習に活用できた。
一人一人のテーマにあった本を探していく中で、児童自身が図書館の利用の仕方や百科 事典などの使い方についても学ぶことができた。 学習の前に児童一人一人のテーマを把握し、図書館指導員と連携をしておくことで児童が自分で主体的に活動することができ、より深い学習の達成感を味わえることが分かった。 今後の学習においても活用していく。 司書・司書教諭コメント このクラスは読書力に幅があり、読書に入りにくい児童もいた。ところが、疑問調べの資料を初めて手にする日、大机に児童別に重ねておいた資料に向かってどの子も小走りであった。すぐにページを繰り始めた子どもたちが、皆前かがみの姿勢なのを見た時、正直驚いた。同時に図書館が「一人一人の疑問に誠意をもって対応すること」の大切さを強く感じた。当日に向けては以下のように準備した。①教員から各自テーマの一覧をもらい自館で資料探し。必要に応じ児童と教員に再聞き取りで内容を探り、公共図書館にテーマ一覧を送付。②中央図書館に赴き相談しながら資料を選択。③自館と借用資料は内容を再検討して資料選択をし直した上で、説明掲載頁に付箋を貼った。選択に当たり、各児童の読書力に配慮した。④提供時の質問等に対応しやすいように、司書と教員用に書名、掲載頁の一覧表を作成。⑤担任と相談して、目次から関連ページをさがす練習のために当日は付箋を該当頁から目次頁へ貼り直してから、児童別に重ねておき提供。これらの作業は大変だったが、以下の要素に支えられて実施できた。①教員の早めの依頼と熱意②公共のレファレンス及び資料支援③平素の児童観察。特に①は、学校図書館年間計画を元に毎月計画を作成していることが役立った。この学習の直前に社会の「昔のくらし」で百科事典利用指導を行い、事後に総合の調べ学習へと連続して図書館活用をしていただいた。新任教諭クラスでのこの実践は、指導教員が図書館活用の指導をしっかり行って下さる成果と言える。今後は教室での資料活用時にも指導員が支援ができると更に良いと思う。(福岡) 情報提供校 東京都中野区立上高田小学校 事例作成日 2014年3月31日 授業実践 2014年2月8日 事例作成者氏名 学校図書館指導員 福岡淳子
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0198 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 ほうこく書を書こう「本で調べてほうこくしよう」 (光村3年下) 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供・レファレンス(公共図書館と連携)、ワークシート提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 各自の疑問を「本で調べて報告書を書く」という学習のために、一人ひとりの疑問を調べる本を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ①教員へ授業展開等(1月初め、2月教材で、各自の疑問を調べる資料依頼時)→3年生向き資料を揃えるために、区立資料借用を想定し、教諭による児童のテーマ(疑問)聴き取りを1/17までにと依頼。②テーマ一覧をもらい分野別に並べ替えをした後、自校本抜き取りと不足分野の検討を行った。同時にテーマ絞り込みのために教員や必要児童に司書が再聞き取りを実施。
提示資料 子どもの疑問とあわせたブックリストをまとめました。音楽、法律、仕事などの疑問もありました。以下その一部から自然科学系のものを紹介します。 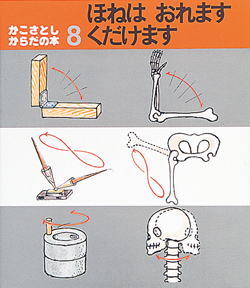
『ほねはおれますくだけます』(かこさとし がらだの本 8) かこさとし 童心社 1977年
ほねの仕組みや働きが、クラゲや昆虫などの例で示され低学年にもわかりやすい。地味で古い本なので、紹介したい。 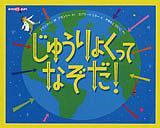
『 じゅりょくってなぞだ!』フランクリン・M・ブランリー作 エドワード・ミラー絵 やまもとけいこ訳 福音館書店 2010年
3年ではむずかしい題材だが、重力があることで普通に暮らせることには気づける。
「なぜ、じゅうりょくがあるのか だれもはっきりわからない。」と終わっている点
が科学の本らしい。調べれば答えが出てくるとは限らない。
新たな疑問を更に調べたり研究していくのが科学だと気が付いてくれると良い。 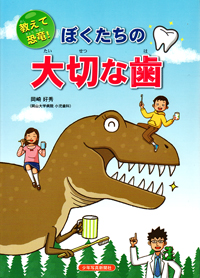
『教えて恐竜! ぼくたちの大切な歯』岡崎好秀 少年写真新聞社 2011年
導入が巧みで引きつけられる。化石や進化にも触れていて興味を持つ児童が多い。
展示したらよく貸し出された。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 本で調べて報告しよう(小3国語)2014.xls
キーワード1 レファレンス キーワード2 情報の探し方 キーワード3 報告書 授業計画・指導案等 小3国語「本で調べてほうこくしよう」学習指導案 報告書.pdf 児童・生徒の作品 授業者 田中啓子 主任教諭 安藤恵 教諭 授業者コメント 本で調べて人に伝えることを初めて学習する単元である。単元の目標は、次の3つであ る。 ① 生活の中から調べたいことを決め、必要な事柄について本を読んで調べることができ る。 ② 書こうとすることの中心を明確にし、構成を考え、まとまりに分けて書くことができ る。 ③ 自分の問いを解決するために必要な本や文章を選んで読み、文章を引用したり要約し たりすることができる。 まず3年生の実態を考えると、興味関心の幅は広く、ほとんどの児童が浅いので、まず、 調べたいことを決めることが難しい。そこで今、生活の中で疑問に思っていることや、もっと詳しく知りたいと思うことを挙げさせ、調べている途中でも変更してよいこととした。
次に、児童が調べたいテーマが載っていて、3年生の児童にも読み取れる易しい本を探すことが重要だと考えた。これを図書館指導員の方にお願いすることにした。本を探してもらうのに時間がかかることが予想されたので、授業の準備によってはかなり前から内容を 調べ関係機関や他の人の協力を得る例として、新任教員に指導することができた。 今回、調べたいことを自分の手で見つけ報告することができて、どの児童も自信がつい た。また、その後、総合の時間の調べ学習に活用できた。
一人一人のテーマにあった本を探していく中で、児童自身が図書館の利用の仕方や百科 事典などの使い方についても学ぶことができた。 学習の前に児童一人一人のテーマを把握し、図書館指導員と連携をしておくことで児童が自分で主体的に活動することができ、より深い学習の達成感を味わえることが分かった。 今後の学習においても活用していく。 司書・司書教諭コメント このクラスは読書力に幅があり、読書に入りにくい児童もいた。ところが、疑問調べの資料を初めて手にする日、大机に児童別に重ねておいた資料に向かってどの子も小走りであった。すぐにページを繰り始めた子どもたちが、皆前かがみの姿勢なのを見た時、正直驚いた。同時に図書館が「一人一人の疑問に誠意をもって対応すること」の大切さを強く感じた。当日に向けては以下のように準備した。①教員から各自テーマの一覧をもらい自館で資料探し。必要に応じ児童と教員に再聞き取りで内容を探り、公共図書館にテーマ一覧を送付。②中央図書館に赴き相談しながら資料を選択。③自館と借用資料は内容を再検討して資料選択をし直した上で、説明掲載頁に付箋を貼った。選択に当たり、各児童の読書力に配慮した。④提供時の質問等に対応しやすいように、司書と教員用に書名、掲載頁の一覧表を作成。⑤担任と相談して、目次から関連ページをさがす練習のために当日は付箋を該当頁から目次頁へ貼り直してから、児童別に重ねておき提供。これらの作業は大変だったが、以下の要素に支えられて実施できた。①教員の早めの依頼と熱意②公共のレファレンス及び資料支援③平素の児童観察。特に①は、学校図書館年間計画を元に毎月計画を作成していることが役立った。この学習の直前に社会の「昔のくらし」で百科事典利用指導を行い、事後に総合の調べ学習へと連続して図書館活用をしていただいた。新任教諭クラスでのこの実践は、指導教員が図書館活用の指導をしっかり行って下さる成果と言える。今後は教室での資料活用時にも指導員が支援ができると更に良いと思う。(福岡) 情報提供校 東京都中野区立上高田小学校 事例作成日 2014年3月31日 授業実践 2014年2月8日 事例作成者氏名 学校図書館指導員 福岡淳子
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0198 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | ほうこく書を書こう「本で調べてほうこくしよう」 (光村3年下) |
| 対象学年 | 中学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・レファレンス(公共図書館と連携)、ワークシート提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 各自の疑問を「本で調べて報告書を書く」という学習のために、一人ひとりの疑問を調べる本を集めてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ①教員へ授業展開等(1月初め、2月教材で、各自の疑問を調べる資料依頼時)→3年生向き資料を揃えるために、区立資料借用を想定し、教諭による児童のテーマ(疑問)聴き取りを1/17までにと依頼。②テーマ一覧をもらい分野別に並べ替えをした後、自校本抜き取りと不足分野の検討を行った。同時にテーマ絞り込みのために教員や必要児童に司書が再聞き取りを実施。 |
| 提示資料 | 子どもの疑問とあわせたブックリストをまとめました。音楽、法律、仕事などの疑問もありました。以下その一部から自然科学系のものを紹介します。 |
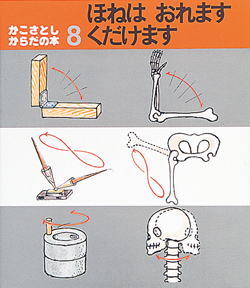 | 『ほねはおれますくだけます』(かこさとし がらだの本 8) かこさとし 童心社 1977年 ほねの仕組みや働きが、クラゲや昆虫などの例で示され低学年にもわかりやすい。地味で古い本なので、紹介したい。 |
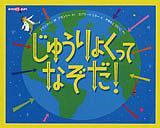 | 『 じゅりょくってなぞだ!』フランクリン・M・ブランリー作 エドワード・ミラー絵 やまもとけいこ訳 福音館書店 2010年 3年ではむずかしい題材だが、重力があることで普通に暮らせることには気づける。 「なぜ、じゅうりょくがあるのか だれもはっきりわからない。」と終わっている点 が科学の本らしい。調べれば答えが出てくるとは限らない。 新たな疑問を更に調べたり研究していくのが科学だと気が付いてくれると良い。 |
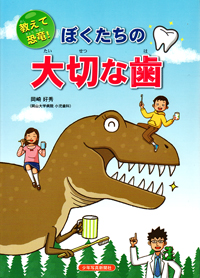 | 『教えて恐竜! ぼくたちの大切な歯』岡崎好秀 少年写真新聞社 2011年 導入が巧みで引きつけられる。化石や進化にも触れていて興味を持つ児童が多い。 展示したらよく貸し出された。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 本で調べて報告しよう(小3国語)2014.xls |
| キーワード1 | レファレンス |
| キーワード2 | 情報の探し方 |
| キーワード3 | 報告書 |
| 授業計画・指導案等 | 小3国語「本で調べてほうこくしよう」学習指導案 報告書.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 田中啓子 主任教諭 安藤恵 教諭 |
| 授業者コメント | 本で調べて人に伝えることを初めて学習する単元である。単元の目標は、次の3つであ る。 ① 生活の中から調べたいことを決め、必要な事柄について本を読んで調べることができ る。 ② 書こうとすることの中心を明確にし、構成を考え、まとまりに分けて書くことができ る。 ③ 自分の問いを解決するために必要な本や文章を選んで読み、文章を引用したり要約し たりすることができる。 まず3年生の実態を考えると、興味関心の幅は広く、ほとんどの児童が浅いので、まず、 調べたいことを決めることが難しい。そこで今、生活の中で疑問に思っていることや、もっと詳しく知りたいと思うことを挙げさせ、調べている途中でも変更してよいこととした。 次に、児童が調べたいテーマが載っていて、3年生の児童にも読み取れる易しい本を探すことが重要だと考えた。これを図書館指導員の方にお願いすることにした。本を探してもらうのに時間がかかることが予想されたので、授業の準備によってはかなり前から内容を 調べ関係機関や他の人の協力を得る例として、新任教員に指導することができた。 今回、調べたいことを自分の手で見つけ報告することができて、どの児童も自信がつい た。また、その後、総合の時間の調べ学習に活用できた。 一人一人のテーマにあった本を探していく中で、児童自身が図書館の利用の仕方や百科 事典などの使い方についても学ぶことができた。 学習の前に児童一人一人のテーマを把握し、図書館指導員と連携をしておくことで児童が自分で主体的に活動することができ、より深い学習の達成感を味わえることが分かった。 今後の学習においても活用していく。 |
| 司書・司書教諭コメント | このクラスは読書力に幅があり、読書に入りにくい児童もいた。ところが、疑問調べの資料を初めて手にする日、大机に児童別に重ねておいた資料に向かってどの子も小走りであった。すぐにページを繰り始めた子どもたちが、皆前かがみの姿勢なのを見た時、正直驚いた。同時に図書館が「一人一人の疑問に誠意をもって対応すること」の大切さを強く感じた。当日に向けては以下のように準備した。①教員から各自テーマの一覧をもらい自館で資料探し。必要に応じ児童と教員に再聞き取りで内容を探り、公共図書館にテーマ一覧を送付。②中央図書館に赴き相談しながら資料を選択。③自館と借用資料は内容を再検討して資料選択をし直した上で、説明掲載頁に付箋を貼った。選択に当たり、各児童の読書力に配慮した。④提供時の質問等に対応しやすいように、司書と教員用に書名、掲載頁の一覧表を作成。⑤担任と相談して、目次から関連ページをさがす練習のために当日は付箋を該当頁から目次頁へ貼り直してから、児童別に重ねておき提供。これらの作業は大変だったが、以下の要素に支えられて実施できた。①教員の早めの依頼と熱意②公共のレファレンス及び資料支援③平素の児童観察。特に①は、学校図書館年間計画を元に毎月計画を作成していることが役立った。この学習の直前に社会の「昔のくらし」で百科事典利用指導を行い、事後に総合の調べ学習へと連続して図書館活用をしていただいた。新任教諭クラスでのこの実践は、指導教員が図書館活用の指導をしっかり行って下さる成果と言える。今後は教室での資料活用時にも指導員が支援ができると更に良いと思う。(福岡) |
| 情報提供校 | 東京都中野区立上高田小学校 |
| 事例作成日 | 2014年3月31日 授業実践 2014年2月8日 |
| 事例作成者氏名 | 学校図書館指導員 福岡淳子 |
記入者:中山(主担)

























