お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0217 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『平家物語』の魅力を平成に語り継ぐ35人の法師たち 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供、T.Tとして支援(音声表現指導含む) 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 平家物語の群読発表会を行うにあたって、図書館資料利用と図書館(および司書)を使ってのグループ学習をしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 学習モデルを示して、見通しをもって学習に取り組ませる。グループ学習となるので、TTとして司書にも関わってもらい、よりきめ細かい指導をする。さまざまな資料を用意し、生徒一人一人の要望に応じて提供する。群読という音声表現をゴールとすることで、読みの内容を深めさせる。
提示資料 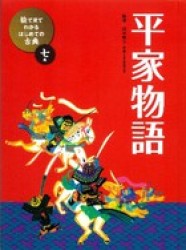
絵で見てわかるはじめての古典7『平家物語』
監修・田中貴子
学研 2012年
詳しくはないが図絵が大きくわかりやすい。 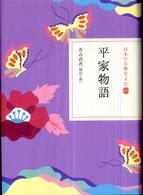
日本の古典をよむ13『平家物語』
市古貞次 校訂・訳
小学館 2007年
原文部分の活字が大きく読みやすい。 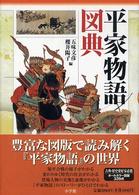
『平家物語図典』
五味文彦・櫻井陽子 編
小学館 2005年
全頁オールカラーで図版多数。平家物語を読むための背景がすべて載っている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 古典 キーワード2 平家物語 キーワード3 群読 授業計画・指導案等 平家物語学習指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 森畑浩幸 授業者コメント ・学習モデル(冒頭部分の群読CDの作成・発表会デモンストレーション)の提示について、司書の協力なしには成し得なかった。具体的に学習モデルを提示したことにより、見通しをもって学習に取り組む姿が見られた。また、単元のゴールにCD録音と発表会を設定することにより、生徒たちの意欲を喚起し持続させることができた。
・群読練習については、各グループごとにボイスレコーダーを用意することで、主体的な学習に生徒を誘うことができた。また、司書の協力があればこそ、きめ細かなアドバイスなどをすることができた。
・様々な図書資料を用意することで、生徒一人一人、自分にとって理解しやすい本を選び、担当章段の内容理解を広げたり深めたりする姿が見られた。このことが、群読に生かされたと思われる。
・本単元では、2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の「(ア)作品の特長を生かして朗読するなどして,古典の世界を楽しむこと。」と「(イ)古典に表れたものの見方や考え方に触れ,登場人物や作者の思いなどを想像すること。」及び,2年「C読むこと」の「オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て,自分の考えをまとめること。」に関する知識や技能も身に付けさせることにした。全9時間で組織したが、指導事項を2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の二つに限定し、言語活動である群読に絞った単元の構想も可能であろう。 司書・司書教諭コメント TTとして授業にかかわれると、生徒の顔が見えてよい。人間関係ができないと 本をすすめることも難しいだけではなく、生徒の中に図書館の存在を植え付けることもできない。グループごとに部分の群読だが、それぞれ自分の担当した場所への思い入れができたと思う。それをきっかけとして、無意識のうちにも古文への親しみをもってほしい。 情報提供校 千葉県市川市立第七中学校 事例作成日 2015.1.28 事例作成者氏名 高桑弥須子(司書)
記入者:村上
カウンタ
3800296 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0217 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 『平家物語』の魅力を平成に語り継ぐ35人の法師たち 対象学年 中2 活用・支援の種類 資料提供、T.Tとして支援(音声表現指導含む) 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 平家物語の群読発表会を行うにあたって、図書館資料利用と図書館(および司書)を使ってのグループ学習をしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 学習モデルを示して、見通しをもって学習に取り組ませる。グループ学習となるので、TTとして司書にも関わってもらい、よりきめ細かい指導をする。さまざまな資料を用意し、生徒一人一人の要望に応じて提供する。群読という音声表現をゴールとすることで、読みの内容を深めさせる。
提示資料 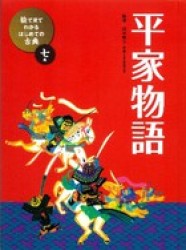
絵で見てわかるはじめての古典7『平家物語』
監修・田中貴子
学研 2012年
詳しくはないが図絵が大きくわかりやすい。 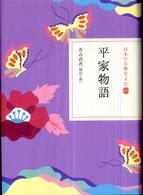
日本の古典をよむ13『平家物語』
市古貞次 校訂・訳
小学館 2007年
原文部分の活字が大きく読みやすい。 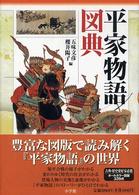
『平家物語図典』
五味文彦・櫻井陽子 編
小学館 2005年
全頁オールカラーで図版多数。平家物語を読むための背景がすべて載っている。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 古典 キーワード2 平家物語 キーワード3 群読 授業計画・指導案等 平家物語学習指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 森畑浩幸 授業者コメント ・学習モデル(冒頭部分の群読CDの作成・発表会デモンストレーション)の提示について、司書の協力なしには成し得なかった。具体的に学習モデルを提示したことにより、見通しをもって学習に取り組む姿が見られた。また、単元のゴールにCD録音と発表会を設定することにより、生徒たちの意欲を喚起し持続させることができた。
・群読練習については、各グループごとにボイスレコーダーを用意することで、主体的な学習に生徒を誘うことができた。また、司書の協力があればこそ、きめ細かなアドバイスなどをすることができた。
・様々な図書資料を用意することで、生徒一人一人、自分にとって理解しやすい本を選び、担当章段の内容理解を広げたり深めたりする姿が見られた。このことが、群読に生かされたと思われる。
・本単元では、2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の「(ア)作品の特長を生かして朗読するなどして,古典の世界を楽しむこと。」と「(イ)古典に表れたものの見方や考え方に触れ,登場人物や作者の思いなどを想像すること。」及び,2年「C読むこと」の「オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て,自分の考えをまとめること。」に関する知識や技能も身に付けさせることにした。全9時間で組織したが、指導事項を2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の二つに限定し、言語活動である群読に絞った単元の構想も可能であろう。 司書・司書教諭コメント TTとして授業にかかわれると、生徒の顔が見えてよい。人間関係ができないと 本をすすめることも難しいだけではなく、生徒の中に図書館の存在を植え付けることもできない。グループごとに部分の群読だが、それぞれ自分の担当した場所への思い入れができたと思う。それをきっかけとして、無意識のうちにも古文への親しみをもってほしい。 情報提供校 千葉県市川市立第七中学校 事例作成日 2015.1.28 事例作成者氏名 高桑弥須子(司書)
記入者:村上
カウンタ
3800296 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0217 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 『平家物語』の魅力を平成に語り継ぐ35人の法師たち |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供、T.Tとして支援(音声表現指導含む) |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 平家物語の群読発表会を行うにあたって、図書館資料利用と図書館(および司書)を使ってのグループ学習をしたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 学習モデルを示して、見通しをもって学習に取り組ませる。グループ学習となるので、TTとして司書にも関わってもらい、よりきめ細かい指導をする。さまざまな資料を用意し、生徒一人一人の要望に応じて提供する。群読という音声表現をゴールとすることで、読みの内容を深めさせる。 |
| 提示資料 | |
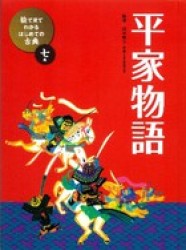 | 絵で見てわかるはじめての古典7『平家物語』 監修・田中貴子 学研 2012年 詳しくはないが図絵が大きくわかりやすい。 |
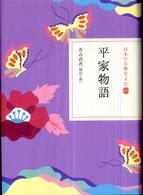 | 日本の古典をよむ13『平家物語』 市古貞次 校訂・訳 小学館 2007年 原文部分の活字が大きく読みやすい。 |
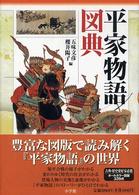 | 『平家物語図典』 五味文彦・櫻井陽子 編 小学館 2005年 全頁オールカラーで図版多数。平家物語を読むための背景がすべて載っている。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 古典 |
| キーワード2 | 平家物語 |
| キーワード3 | 群読 |
| 授業計画・指導案等 | 平家物語学習指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 森畑浩幸 |
| 授業者コメント | ・学習モデル(冒頭部分の群読CDの作成・発表会デモンストレーション)の提示について、司書の協力なしには成し得なかった。具体的に学習モデルを提示したことにより、見通しをもって学習に取り組む姿が見られた。また、単元のゴールにCD録音と発表会を設定することにより、生徒たちの意欲を喚起し持続させることができた。 ・群読練習については、各グループごとにボイスレコーダーを用意することで、主体的な学習に生徒を誘うことができた。また、司書の協力があればこそ、きめ細かなアドバイスなどをすることができた。 ・様々な図書資料を用意することで、生徒一人一人、自分にとって理解しやすい本を選び、担当章段の内容理解を広げたり深めたりする姿が見られた。このことが、群読に生かされたと思われる。 ・本単元では、2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の「(ア)作品の特長を生かして朗読するなどして,古典の世界を楽しむこと。」と「(イ)古典に表れたものの見方や考え方に触れ,登場人物や作者の思いなどを想像すること。」及び,2年「C読むこと」の「オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て,自分の考えをまとめること。」に関する知識や技能も身に付けさせることにした。全9時間で組織したが、指導事項を2年「ア 伝統的な言語文化に関する事項」の二つに限定し、言語活動である群読に絞った単元の構想も可能であろう。 |
| 司書・司書教諭コメント | TTとして授業にかかわれると、生徒の顔が見えてよい。人間関係ができないと 本をすすめることも難しいだけではなく、生徒の中に図書館の存在を植え付けることもできない。グループごとに部分の群読だが、それぞれ自分の担当した場所への思い入れができたと思う。それをきっかけとして、無意識のうちにも古文への親しみをもってほしい。 |
| 情報提供校 | 千葉県市川市立第七中学校 |
| 事例作成日 | 2015.1.28 |
| 事例作成者氏名 | 高桑弥須子(司書) |
記入者:村上

























