お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0265 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 松浦寿輝「「映像体験」の現在」 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供•展示 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教科書に記載されている松浦寿輝「「映像体験」の現在」を教育実習で取り上げる。
批評的な文章を読み取る力を養う図書館使用授業にしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教育実習が図書館授業を行う。実習の充実に向けて資料を用意してほしい。
提示資料 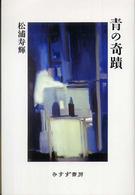
「青の奇蹟」松浦寿輝 2006 みすず書房
63編からなる批評的エッセイ。気になる文章から読み進めてもいいので、高校生にはおすすめ。
教科書教材の「「映像体験」の現在」はここから採ったもの。今回はそのほかにも「もう一つのスローモーション」を授業中に読んだ。 
「高校生のための評論文キーワード100」中山元 2005 ちくま新書
評論文に頻繁に出てくる難解な用語100個について、用語ごとにわかりやすが説明がなされている。評論文を読む際に辞書として使用できる。今回は「アウラ」の章を授業中に読み、教科書本文の理解に繋げた。 
「動物化するポストモダン」東 浩紀 2001 講談社現代新書
本校では論説文の課題図書の一つ。今回は、近代の構造についての説明で、ベンヤミンに言及されている箇所を引用、提示した。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 論説文.xlsx
キーワード1 随想 キーワード2 評論文 キーワード3 読解力 授業計画・指導案等 「「映像体験」の現在」 指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 野邉咲子(東京学芸大学 教育実習生) 授業者コメント クラス全体が真面目で意欲的、積極的な雰囲気で、教科書本文中の言葉を追うだけではものたりないだろう、つまらないだろうという考えと、文章の文脈(一つの文章と関連する思想や議論、語の使用文脈)を感じて本文の理解を深めてほしいとの考えから、教科書本文に加えていくつかの文章を読んでもらった。1,2時間目と3時間目の途中までは、本文を追い具体例を考えながら理解していくというオーソドックスな授業をし、最後まで追った段階で、「アウラ」解説の文章(『高校生のための評論文キーワード100』)を読み、4時間目に『動物化するポストモダン』から近代の構造に関する文章(ベンヤミン、「アウラ」に言及する箇所がある)、5時間目に教科書本文と同じ筆者の随想「もう一つのスローモーション」を読み、本文の問題意識は「一回性」や「反復不可能性」なのではないか、と整理した。
本文だけでは理解しにくい用語の解説や、同じ筆者の随想を読んだことが、特に生徒の理解に繋がったようだ。限られた時間数の中で、次々に別の文章を読ませたことで、「速くて追いつくのが大変」「もう少し丁寧に読解をしてほしい」という感想を持った生徒もいた。何をどれだけ副教材として提示するかを、生徒の理解に合わせて調節していくことが、今後の課題である。
司書・司書教諭コメント 本校は前期•後期合わせて、200名近くの実習生を学芸大学から毎年受け入れている。学校司書は、実習生へのオリエンテーションに始まり、資料の提供、図書館授業の見学、館内清掃まで多様な関わりを持つ。今回、指導教官から事前に資料の請求があり、本を実習までに用意する事ができた。今後も教育実習生、担当教官、生徒、学校図書館を学校司書としてつなげていきたいと考える。 情報提供校 東京学芸大学附属高等学校 事例作成日 2016/6/1 事例作成者氏名 岡田和美(東京学芸大学附属高等学校図書館司書)
記入者:岡田
カウンタ
3800285 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」は終了いたしました。当日参加してくださった皆様、配信をご覧になった皆様、こちらの参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。また、2月になりましたら、改めて視聴をご希望の皆さまには、申し込めるように整えます。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は埼玉県立松伏高等学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0265 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 松浦寿輝「「映像体験」の現在」 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供•展示 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 教科書に記載されている松浦寿輝「「映像体験」の現在」を教育実習で取り上げる。
批評的な文章を読み取る力を養う図書館使用授業にしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 教育実習が図書館授業を行う。実習の充実に向けて資料を用意してほしい。
提示資料 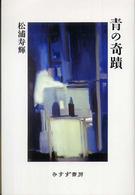
「青の奇蹟」松浦寿輝 2006 みすず書房
63編からなる批評的エッセイ。気になる文章から読み進めてもいいので、高校生にはおすすめ。
教科書教材の「「映像体験」の現在」はここから採ったもの。今回はそのほかにも「もう一つのスローモーション」を授業中に読んだ。 
「高校生のための評論文キーワード100」中山元 2005 ちくま新書
評論文に頻繁に出てくる難解な用語100個について、用語ごとにわかりやすが説明がなされている。評論文を読む際に辞書として使用できる。今回は「アウラ」の章を授業中に読み、教科書本文の理解に繋げた。 
「動物化するポストモダン」東 浩紀 2001 講談社現代新書
本校では論説文の課題図書の一つ。今回は、近代の構造についての説明で、ベンヤミンに言及されている箇所を引用、提示した。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 論説文.xlsx
キーワード1 随想 キーワード2 評論文 キーワード3 読解力 授業計画・指導案等 「「映像体験」の現在」 指導案.pdf 児童・生徒の作品 授業者 野邉咲子(東京学芸大学 教育実習生) 授業者コメント クラス全体が真面目で意欲的、積極的な雰囲気で、教科書本文中の言葉を追うだけではものたりないだろう、つまらないだろうという考えと、文章の文脈(一つの文章と関連する思想や議論、語の使用文脈)を感じて本文の理解を深めてほしいとの考えから、教科書本文に加えていくつかの文章を読んでもらった。1,2時間目と3時間目の途中までは、本文を追い具体例を考えながら理解していくというオーソドックスな授業をし、最後まで追った段階で、「アウラ」解説の文章(『高校生のための評論文キーワード100』)を読み、4時間目に『動物化するポストモダン』から近代の構造に関する文章(ベンヤミン、「アウラ」に言及する箇所がある)、5時間目に教科書本文と同じ筆者の随想「もう一つのスローモーション」を読み、本文の問題意識は「一回性」や「反復不可能性」なのではないか、と整理した。
本文だけでは理解しにくい用語の解説や、同じ筆者の随想を読んだことが、特に生徒の理解に繋がったようだ。限られた時間数の中で、次々に別の文章を読ませたことで、「速くて追いつくのが大変」「もう少し丁寧に読解をしてほしい」という感想を持った生徒もいた。何をどれだけ副教材として提示するかを、生徒の理解に合わせて調節していくことが、今後の課題である。
司書・司書教諭コメント 本校は前期•後期合わせて、200名近くの実習生を学芸大学から毎年受け入れている。学校司書は、実習生へのオリエンテーションに始まり、資料の提供、図書館授業の見学、館内清掃まで多様な関わりを持つ。今回、指導教官から事前に資料の請求があり、本を実習までに用意する事ができた。今後も教育実習生、担当教官、生徒、学校図書館を学校司書としてつなげていきたいと考える。 情報提供校 東京学芸大学附属高等学校 事例作成日 2016/6/1 事例作成者氏名 岡田和美(東京学芸大学附属高等学校図書館司書)
記入者:岡田
カウンタ
3800285 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0265 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 松浦寿輝「「映像体験」の現在」 |
| 対象学年 | 高1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供•展示 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 教科書に記載されている松浦寿輝「「映像体験」の現在」を教育実習で取り上げる。 批評的な文章を読み取る力を養う図書館使用授業にしたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 教育実習が図書館授業を行う。実習の充実に向けて資料を用意してほしい。 |
| 提示資料 | |
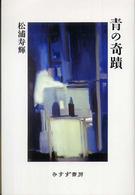 | 「青の奇蹟」松浦寿輝 2006 みすず書房 63編からなる批評的エッセイ。気になる文章から読み進めてもいいので、高校生にはおすすめ。 教科書教材の「「映像体験」の現在」はここから採ったもの。今回はそのほかにも「もう一つのスローモーション」を授業中に読んだ。 |
 | 「高校生のための評論文キーワード100」中山元 2005 ちくま新書 評論文に頻繁に出てくる難解な用語100個について、用語ごとにわかりやすが説明がなされている。評論文を読む際に辞書として使用できる。今回は「アウラ」の章を授業中に読み、教科書本文の理解に繋げた。 |
 | 「動物化するポストモダン」東 浩紀 2001 講談社現代新書 本校では論説文の課題図書の一つ。今回は、近代の構造についての説明で、ベンヤミンに言及されている箇所を引用、提示した。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 論説文.xlsx |
| キーワード1 | 随想 |
| キーワード2 | 評論文 |
| キーワード3 | 読解力 |
| 授業計画・指導案等 | 「「映像体験」の現在」 指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 野邉咲子(東京学芸大学 教育実習生) |
| 授業者コメント | クラス全体が真面目で意欲的、積極的な雰囲気で、教科書本文中の言葉を追うだけではものたりないだろう、つまらないだろうという考えと、文章の文脈(一つの文章と関連する思想や議論、語の使用文脈)を感じて本文の理解を深めてほしいとの考えから、教科書本文に加えていくつかの文章を読んでもらった。1,2時間目と3時間目の途中までは、本文を追い具体例を考えながら理解していくというオーソドックスな授業をし、最後まで追った段階で、「アウラ」解説の文章(『高校生のための評論文キーワード100』)を読み、4時間目に『動物化するポストモダン』から近代の構造に関する文章(ベンヤミン、「アウラ」に言及する箇所がある)、5時間目に教科書本文と同じ筆者の随想「もう一つのスローモーション」を読み、本文の問題意識は「一回性」や「反復不可能性」なのではないか、と整理した。 本文だけでは理解しにくい用語の解説や、同じ筆者の随想を読んだことが、特に生徒の理解に繋がったようだ。限られた時間数の中で、次々に別の文章を読ませたことで、「速くて追いつくのが大変」「もう少し丁寧に読解をしてほしい」という感想を持った生徒もいた。何をどれだけ副教材として提示するかを、生徒の理解に合わせて調節していくことが、今後の課題である。 |
| 司書・司書教諭コメント | 本校は前期•後期合わせて、200名近くの実習生を学芸大学から毎年受け入れている。学校司書は、実習生へのオリエンテーションに始まり、資料の提供、図書館授業の見学、館内清掃まで多様な関わりを持つ。今回、指導教官から事前に資料の請求があり、本を実習までに用意する事ができた。今後も教育実習生、担当教官、生徒、学校図書館を学校司書としてつなげていきたいと考える。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属高等学校 |
| 事例作成日 | 2016/6/1 |
| 事例作成者氏名 | 岡田和美(東京学芸大学附属高等学校図書館司書) |
記入者:岡田

























