お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0251 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 音読劇をしよう「お手紙」 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ、ブックトーク、アニマシオン 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) アーノルド・ローベル作品をできるだけたくさん読ませたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 アーノルド・ローベル作品が児童一人ひとりに行き渡る冊数を準備する。なかでも「がまくんとかえるくん」が登場する『ふたりは・・・』シリーズの理解を深めさせたいので複数冊読ませたい。
提示資料 アーノルド・ローベル作品の中でも構成の異なるものを選びました。 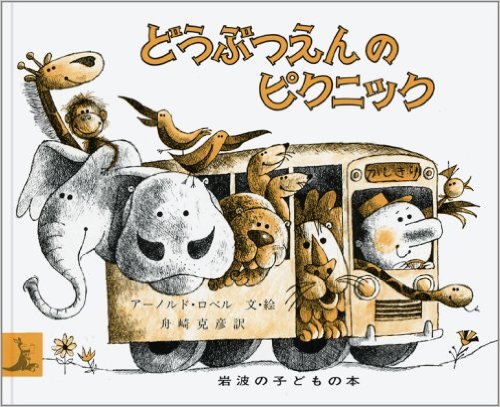
アーノルド・ローベル『どうぶつえんのピクニック』舟越克彦訳 岩波書店 1992年
運動不足で、風邪気味の動物たちにやさしいマスターさんが、
海へピクニックに連れていってくれます。
途中で遊園地に立ち寄ったところ、動物たちは大はしゃぎになりました。
マスターさんが何と言おうが、動物たちには聞こえません。
そこでマスターさんは特製のバスを作ります。
みんなが楽しく過ごせるように考えてくれたマスターさん。
その後、動物たちはマスターさんと無事に動物園へと戻るのでした。
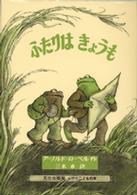
アーノルド・ローベル『ふたりはきょうも』三木卓訳 文化出版局 1980年
5話あるお話の中から「あしたするよ」をアニマシオンで紹介しました。
がまくんは、家の中を片付けな久手はいけないのに、いつまでもベッドにもぐりこんでいます。そのうえ、変えるくんが何を言っても「あしたかたづけるよ。」と、答えます。それでも、やさしく落ち着いて話しかけるかえるくんのおかげで、がまくんは、一つ一つ家の片付けを済ませることができました。
そして、がまくんは「あしたほんとうにしたいことのためにあけておけるよ。」というのでした。そして、本当にしたいことである「のんびりする」ために、おふとんをかぶってねてしまうのでした。 
アーノルド・ローベル『おはなしばんざい』三木卓訳 文化出版局 1978年
ネズミとイタチのおはなしです。
イタチに捕まえられたネズミが、今にもスープにされようとした時に、スープに入れるとおいしくなる4つのお話をします。イタチはその4つのお話を実践しようとして、散々な目に合ってしまいます。ネズミは危機一髪で逃げだすことができました。
4つの話は1話ずつ完結していて、笑いを誘います。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト アーノルド・ローベル作品 小2国語2015.xlsx
キーワード1 音読 キーワード2 劇 キーワード3 手紙 授業計画・指導案等 『音楽劇をしよう「お手紙」』指導案 小2国語2015.pdf 児童・生徒の作品 授業者 寺前孝子教諭 授業者コメント 「お手紙」の単元導入にあたり、「ふたりはともだち」の中の「はるがきた」の読み聞かせを行った。かえるくんとがまくんの関係が「お手紙」に出てくる二人と似通っていること、また、会話文が多いことから、この本を選択した。一度目は普通に、二度目は音読劇風に読み聞かせを行った。比較することによって「音読劇とは?」という話し合い活動につながった。授業では、人物の気持ちを考え、会話文の読みの練習を随時行った。物語の読み取りの後には、音読劇の練習に取り組み、一年生への音読劇発表を行った。最後に子ども達が書いた人物へのお手紙(感想)から、学習を通して、子ども達はかえるくんとがまくんが大好きになったことがうかがえる。 教室には、アーノルド=ローベルのお話を集め、並行読書を推進した。教室においておくことによって、友達同士で一緒に読んだり、薦めあったりと本に親しむことができた。休み時間などに読書することはもちろん、単元学習後も図書室でアーノルド=ローベルの本を借りる姿が見られた。 司書・司書教諭コメント アーノルド・ローベル作品『ふたりはともだち』の「お手紙」は、ふたりの思いやりの深さが伝わる作品です。児童には、お話が素直に心に響くと思います。作者が、子どもの視点で楽しいことやうれしいことを表現している点が、感情移入がしやすい部分かと思います。「お手紙」以外にも、今回紹介した『ふたりはきょうも』の「あしたするよ」や、『ふたりはいっしょ』に掲載されている「よていひょう」は、子どもたちの実生活につながりやすいので、アニマシオンやクイズ形式でブックトークするには最適な作品だと考えます。
次回は、短編一つ一つに繋がりがある点を吟味した上で、児童に紹介したいと思います。
また、本校にはブックリストの通り、アーノルド・ローベル作品の蔵書数が多く紹介しやすいので、他の機会にも、取り上げて紹介したいと思います。
情報提供校 熊本市立川上小学校 事例作成日 事例作成2016年1月19日 /授業実践2015年10月5日 事例作成者氏名 司書補助業務員 松本ゆかり
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863441 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0251 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 音読劇をしよう「お手紙」 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ、ブックトーク、アニマシオン 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) アーノルド・ローベル作品をできるだけたくさん読ませたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 アーノルド・ローベル作品が児童一人ひとりに行き渡る冊数を準備する。なかでも「がまくんとかえるくん」が登場する『ふたりは・・・』シリーズの理解を深めさせたいので複数冊読ませたい。
提示資料 アーノルド・ローベル作品の中でも構成の異なるものを選びました。 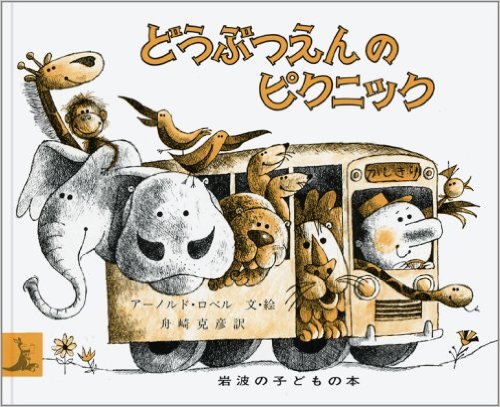
アーノルド・ローベル『どうぶつえんのピクニック』舟越克彦訳 岩波書店 1992年
運動不足で、風邪気味の動物たちにやさしいマスターさんが、
海へピクニックに連れていってくれます。
途中で遊園地に立ち寄ったところ、動物たちは大はしゃぎになりました。
マスターさんが何と言おうが、動物たちには聞こえません。
そこでマスターさんは特製のバスを作ります。
みんなが楽しく過ごせるように考えてくれたマスターさん。
その後、動物たちはマスターさんと無事に動物園へと戻るのでした。
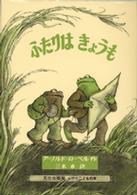
アーノルド・ローベル『ふたりはきょうも』三木卓訳 文化出版局 1980年
5話あるお話の中から「あしたするよ」をアニマシオンで紹介しました。
がまくんは、家の中を片付けな久手はいけないのに、いつまでもベッドにもぐりこんでいます。そのうえ、変えるくんが何を言っても「あしたかたづけるよ。」と、答えます。それでも、やさしく落ち着いて話しかけるかえるくんのおかげで、がまくんは、一つ一つ家の片付けを済ませることができました。
そして、がまくんは「あしたほんとうにしたいことのためにあけておけるよ。」というのでした。そして、本当にしたいことである「のんびりする」ために、おふとんをかぶってねてしまうのでした。 
アーノルド・ローベル『おはなしばんざい』三木卓訳 文化出版局 1978年
ネズミとイタチのおはなしです。
イタチに捕まえられたネズミが、今にもスープにされようとした時に、スープに入れるとおいしくなる4つのお話をします。イタチはその4つのお話を実践しようとして、散々な目に合ってしまいます。ネズミは危機一髪で逃げだすことができました。
4つの話は1話ずつ完結していて、笑いを誘います。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト アーノルド・ローベル作品 小2国語2015.xlsx
キーワード1 音読 キーワード2 劇 キーワード3 手紙 授業計画・指導案等 『音楽劇をしよう「お手紙」』指導案 小2国語2015.pdf 児童・生徒の作品 授業者 寺前孝子教諭 授業者コメント 「お手紙」の単元導入にあたり、「ふたりはともだち」の中の「はるがきた」の読み聞かせを行った。かえるくんとがまくんの関係が「お手紙」に出てくる二人と似通っていること、また、会話文が多いことから、この本を選択した。一度目は普通に、二度目は音読劇風に読み聞かせを行った。比較することによって「音読劇とは?」という話し合い活動につながった。授業では、人物の気持ちを考え、会話文の読みの練習を随時行った。物語の読み取りの後には、音読劇の練習に取り組み、一年生への音読劇発表を行った。最後に子ども達が書いた人物へのお手紙(感想)から、学習を通して、子ども達はかえるくんとがまくんが大好きになったことがうかがえる。 教室には、アーノルド=ローベルのお話を集め、並行読書を推進した。教室においておくことによって、友達同士で一緒に読んだり、薦めあったりと本に親しむことができた。休み時間などに読書することはもちろん、単元学習後も図書室でアーノルド=ローベルの本を借りる姿が見られた。 司書・司書教諭コメント アーノルド・ローベル作品『ふたりはともだち』の「お手紙」は、ふたりの思いやりの深さが伝わる作品です。児童には、お話が素直に心に響くと思います。作者が、子どもの視点で楽しいことやうれしいことを表現している点が、感情移入がしやすい部分かと思います。「お手紙」以外にも、今回紹介した『ふたりはきょうも』の「あしたするよ」や、『ふたりはいっしょ』に掲載されている「よていひょう」は、子どもたちの実生活につながりやすいので、アニマシオンやクイズ形式でブックトークするには最適な作品だと考えます。
次回は、短編一つ一つに繋がりがある点を吟味した上で、児童に紹介したいと思います。
また、本校にはブックリストの通り、アーノルド・ローベル作品の蔵書数が多く紹介しやすいので、他の機会にも、取り上げて紹介したいと思います。
情報提供校 熊本市立川上小学校 事例作成日 事例作成2016年1月19日 /授業実践2015年10月5日 事例作成者氏名 司書補助業務員 松本ゆかり
記入者:中山(主担)
カウンタ
3863441 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0251 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 音読劇をしよう「お手紙」 |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 読み聞かせ、ブックトーク、アニマシオン |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | アーノルド・ローベル作品をできるだけたくさん読ませたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | アーノルド・ローベル作品が児童一人ひとりに行き渡る冊数を準備する。なかでも「がまくんとかえるくん」が登場する『ふたりは・・・』シリーズの理解を深めさせたいので複数冊読ませたい。 |
| 提示資料 | アーノルド・ローベル作品の中でも構成の異なるものを選びました。 |
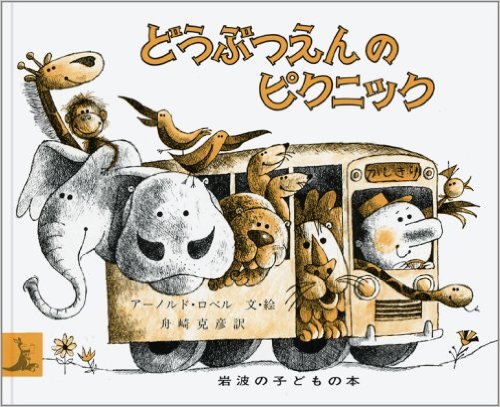 | アーノルド・ローベル『どうぶつえんのピクニック』舟越克彦訳 岩波書店 1992年 運動不足で、風邪気味の動物たちにやさしいマスターさんが、 海へピクニックに連れていってくれます。 途中で遊園地に立ち寄ったところ、動物たちは大はしゃぎになりました。 マスターさんが何と言おうが、動物たちには聞こえません。 そこでマスターさんは特製のバスを作ります。 みんなが楽しく過ごせるように考えてくれたマスターさん。 その後、動物たちはマスターさんと無事に動物園へと戻るのでした。 |
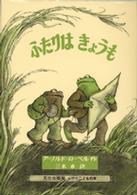 | アーノルド・ローベル『ふたりはきょうも』三木卓訳 文化出版局 1980年 5話あるお話の中から「あしたするよ」をアニマシオンで紹介しました。 がまくんは、家の中を片付けな久手はいけないのに、いつまでもベッドにもぐりこんでいます。そのうえ、変えるくんが何を言っても「あしたかたづけるよ。」と、答えます。それでも、やさしく落ち着いて話しかけるかえるくんのおかげで、がまくんは、一つ一つ家の片付けを済ませることができました。 そして、がまくんは「あしたほんとうにしたいことのためにあけておけるよ。」というのでした。そして、本当にしたいことである「のんびりする」ために、おふとんをかぶってねてしまうのでした。 |
 | アーノルド・ローベル『おはなしばんざい』三木卓訳 文化出版局 1978年 ネズミとイタチのおはなしです。 イタチに捕まえられたネズミが、今にもスープにされようとした時に、スープに入れるとおいしくなる4つのお話をします。イタチはその4つのお話を実践しようとして、散々な目に合ってしまいます。ネズミは危機一髪で逃げだすことができました。 4つの話は1話ずつ完結していて、笑いを誘います。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | アーノルド・ローベル作品 小2国語2015.xlsx |
| キーワード1 | 音読 |
| キーワード2 | 劇 |
| キーワード3 | 手紙 |
| 授業計画・指導案等 | 『音楽劇をしよう「お手紙」』指導案 小2国語2015.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 寺前孝子教諭 |
| 授業者コメント | 「お手紙」の単元導入にあたり、「ふたりはともだち」の中の「はるがきた」の読み聞かせを行った。かえるくんとがまくんの関係が「お手紙」に出てくる二人と似通っていること、また、会話文が多いことから、この本を選択した。一度目は普通に、二度目は音読劇風に読み聞かせを行った。比較することによって「音読劇とは?」という話し合い活動につながった。授業では、人物の気持ちを考え、会話文の読みの練習を随時行った。物語の読み取りの後には、音読劇の練習に取り組み、一年生への音読劇発表を行った。最後に子ども達が書いた人物へのお手紙(感想)から、学習を通して、子ども達はかえるくんとがまくんが大好きになったことがうかがえる。 教室には、アーノルド=ローベルのお話を集め、並行読書を推進した。教室においておくことによって、友達同士で一緒に読んだり、薦めあったりと本に親しむことができた。休み時間などに読書することはもちろん、単元学習後も図書室でアーノルド=ローベルの本を借りる姿が見られた。 |
| 司書・司書教諭コメント | アーノルド・ローベル作品『ふたりはともだち』の「お手紙」は、ふたりの思いやりの深さが伝わる作品です。児童には、お話が素直に心に響くと思います。作者が、子どもの視点で楽しいことやうれしいことを表現している点が、感情移入がしやすい部分かと思います。「お手紙」以外にも、今回紹介した『ふたりはきょうも』の「あしたするよ」や、『ふたりはいっしょ』に掲載されている「よていひょう」は、子どもたちの実生活につながりやすいので、アニマシオンやクイズ形式でブックトークするには最適な作品だと考えます。 次回は、短編一つ一つに繋がりがある点を吟味した上で、児童に紹介したいと思います。 また、本校にはブックリストの通り、アーノルド・ローベル作品の蔵書数が多く紹介しやすいので、他の機会にも、取り上げて紹介したいと思います。 |
| 情報提供校 | 熊本市立川上小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成2016年1月19日 /授業実践2015年10月5日 |
| 事例作成者氏名 | 司書補助業務員 松本ゆかり |
記入者:中山(主担)

























