お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0260 校種 小学校 教科・領域等 外国語 単元 お話を聞いたり読んだりしてみよう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 英語での読み聞かせに適した絵本を探している。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ・耳で聞いてわかりやすく、くり返しの表現があるとよい。
・児童が日本語でも知っているような昔話もあるとよい。
提示資料 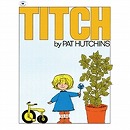
Pat Hutchins "Titch" Aladdin Books c1971
邦訳『ティッチ』 パット・ハッチンスさく・え いしいももこやく 福音館書店 1975年
※メイン教材として使用した本。
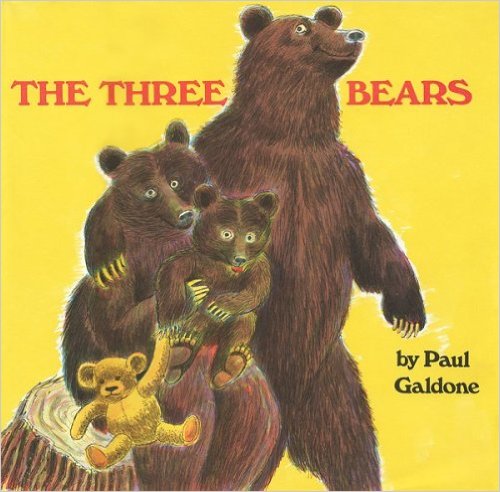
Paul Galdone "The three bears" World's Work c1973
邦訳『3びきのくま』 ポール・ガルドン作 ただひろみやく ほるぷ出版 1978年
※特定の単語や表現を身につけさせるための教材としてはやや難しかった。英語の音に親しませる、英語を楽しむことを目的として読み聞かせをした。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 英語 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 絵本 授業計画・指導案等 「お話を聞いたり読んだりしてみよう」小6 英語 2016.jpg 児童・生徒の作品 授業者 山本剛久,Susannah Howard(ALT),吉川啓史(ALT) 授業者コメント "Titch"は、児童のinput のために、非常に優れている教材である。以下の理由から、児童の教育用の絵本として工夫された絵本なのではないかと推察する。
①絵と言葉を結び付けて、具体的に子どもたちに伝えられる教材であること。
②主人公が小さな子どもで、児童の生活体験と重なる部分が大きいこと。
③3兄弟についてくり返される記述の最後が主人公のTitch に関する記述で、そこには変化(「落ち」のようなもの)があり、興味をもちやすいものであること。
④楽器や工具などが登場する場面があり、Do you have~? Can you play the~?などを用いて話を広げることができること。
⑤3兄弟を比較しながら伝えており、bigger などの比較表現が用いられていること。
⑥above が使われている部分があり、位置関係を表す言葉について扱いやすいこと。
⑦児童が覚えられる程度の分量しかないこと。
⑧登場人物の服などが単色で描かれており、What color is this?のようなやりとりをしやすいこと。
本実践では、児童は大変意欲的に聞いており、言えるところは単語でつぶやくようになり、だんだんと文でつぶやくようになり、本全体を覚えるようになっていった。本校の英語教育では、良質かつ多量のinputと自然なoutputを目指している。これまでは、身につけさせたい単語や文をinputするための活動を考えていた。しかし、本教材のように、母語を獲得する過程で行っている日常の活動から、inputしたい単語や文を設定していった方がよいのではないかと感じた。今回は、司書に目的をある程度伝えてから、複数の本を用意してもらい、その中から選択した。その際、複数ある本の中から特によいと感じた本は、司書と教諭で共通していた。英語が得意でない教員にも扱いやすい優れた一冊である。(山本教諭) 司書・司書教諭コメント 最近、英語の教材として適した絵本を尋ねられることが増えてきている。今回は英語に親しむために、読み聞かせに適した本を紹介してほしいというものであった。
日本語を母語とする子どもたちが、幼いときから絵本を読んでもらうことで、日本語のひびきやリズム、たくさんのことばにふれながら自然と日本語を身につけていくように、外国語を学習する際も同様に、長く読み継がれてきた絵本を読み聞かせることが有効であると考えて選書した。山本教諭が指摘している「くり返しの表現と構成」「絵と文のバランス」「題材は日常的な生活体験」という3点は、幼い子どもたちのために日本語の絵本を選ぶ際の評価基準とも重なる。司書として絵本を“教材”という目で見ることは少ないものの、日頃の経験から養われてきた絵本の選択眼が、教員が希望する絵本の条件と一致していたため、適切な資料を提供することができたのだと思う。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 事例作成 2016年7月25日 / 授業実践 2016年6月11日 事例作成者氏名 司書 小野寺愛美
記入者:小野寺(主担)
カウンタ
3863446 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0260 校種 小学校 教科・領域等 外国語 単元 お話を聞いたり読んだりしてみよう 対象学年 高学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 英語での読み聞かせに適した絵本を探している。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ・耳で聞いてわかりやすく、くり返しの表現があるとよい。
・児童が日本語でも知っているような昔話もあるとよい。
提示資料 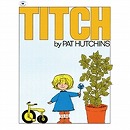
Pat Hutchins "Titch" Aladdin Books c1971
邦訳『ティッチ』 パット・ハッチンスさく・え いしいももこやく 福音館書店 1975年
※メイン教材として使用した本。
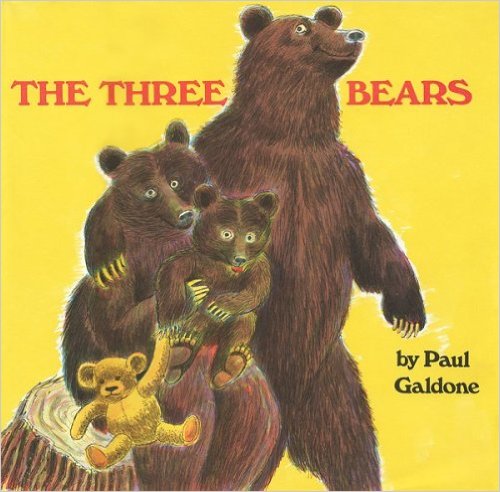
Paul Galdone "The three bears" World's Work c1973
邦訳『3びきのくま』 ポール・ガルドン作 ただひろみやく ほるぷ出版 1978年
※特定の単語や表現を身につけさせるための教材としてはやや難しかった。英語の音に親しませる、英語を楽しむことを目的として読み聞かせをした。

参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 英語 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 絵本 授業計画・指導案等 「お話を聞いたり読んだりしてみよう」小6 英語 2016.jpg 児童・生徒の作品 授業者 山本剛久,Susannah Howard(ALT),吉川啓史(ALT) 授業者コメント "Titch"は、児童のinput のために、非常に優れている教材である。以下の理由から、児童の教育用の絵本として工夫された絵本なのではないかと推察する。
①絵と言葉を結び付けて、具体的に子どもたちに伝えられる教材であること。
②主人公が小さな子どもで、児童の生活体験と重なる部分が大きいこと。
③3兄弟についてくり返される記述の最後が主人公のTitch に関する記述で、そこには変化(「落ち」のようなもの)があり、興味をもちやすいものであること。
④楽器や工具などが登場する場面があり、Do you have~? Can you play the~?などを用いて話を広げることができること。
⑤3兄弟を比較しながら伝えており、bigger などの比較表現が用いられていること。
⑥above が使われている部分があり、位置関係を表す言葉について扱いやすいこと。
⑦児童が覚えられる程度の分量しかないこと。
⑧登場人物の服などが単色で描かれており、What color is this?のようなやりとりをしやすいこと。
本実践では、児童は大変意欲的に聞いており、言えるところは単語でつぶやくようになり、だんだんと文でつぶやくようになり、本全体を覚えるようになっていった。本校の英語教育では、良質かつ多量のinputと自然なoutputを目指している。これまでは、身につけさせたい単語や文をinputするための活動を考えていた。しかし、本教材のように、母語を獲得する過程で行っている日常の活動から、inputしたい単語や文を設定していった方がよいのではないかと感じた。今回は、司書に目的をある程度伝えてから、複数の本を用意してもらい、その中から選択した。その際、複数ある本の中から特によいと感じた本は、司書と教諭で共通していた。英語が得意でない教員にも扱いやすい優れた一冊である。(山本教諭) 司書・司書教諭コメント 最近、英語の教材として適した絵本を尋ねられることが増えてきている。今回は英語に親しむために、読み聞かせに適した本を紹介してほしいというものであった。
日本語を母語とする子どもたちが、幼いときから絵本を読んでもらうことで、日本語のひびきやリズム、たくさんのことばにふれながら自然と日本語を身につけていくように、外国語を学習する際も同様に、長く読み継がれてきた絵本を読み聞かせることが有効であると考えて選書した。山本教諭が指摘している「くり返しの表現と構成」「絵と文のバランス」「題材は日常的な生活体験」という3点は、幼い子どもたちのために日本語の絵本を選ぶ際の評価基準とも重なる。司書として絵本を“教材”という目で見ることは少ないものの、日頃の経験から養われてきた絵本の選択眼が、教員が希望する絵本の条件と一致していたため、適切な資料を提供することができたのだと思う。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 事例作成 2016年7月25日 / 授業実践 2016年6月11日 事例作成者氏名 司書 小野寺愛美
記入者:小野寺(主担)
カウンタ
3863446 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0260 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 外国語 |
| 単元 | お話を聞いたり読んだりしてみよう |
| 対象学年 | 高学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 英語での読み聞かせに適した絵本を探している。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ・耳で聞いてわかりやすく、くり返しの表現があるとよい。 ・児童が日本語でも知っているような昔話もあるとよい。 |
| 提示資料 | |
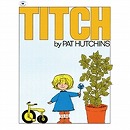 | Pat Hutchins "Titch" Aladdin Books c1971 邦訳『ティッチ』 パット・ハッチンスさく・え いしいももこやく 福音館書店 1975年 ※メイン教材として使用した本。 |
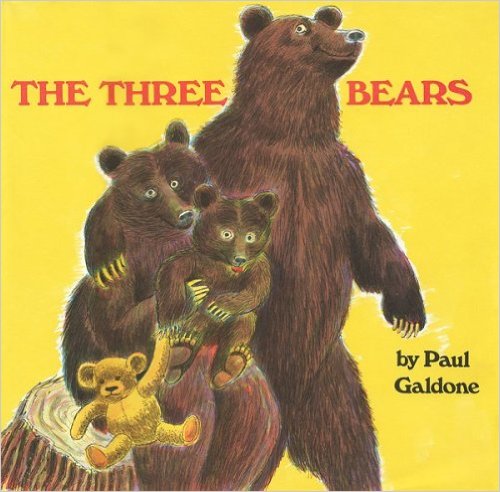 | Paul Galdone "The three bears" World's Work c1973 邦訳『3びきのくま』 ポール・ガルドン作 ただひろみやく ほるぷ出版 1978年 ※特定の単語や表現を身につけさせるための教材としてはやや難しかった。英語の音に親しませる、英語を楽しむことを目的として読み聞かせをした。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 英語 |
| キーワード2 | 読み聞かせ |
| キーワード3 | 絵本 |
| 授業計画・指導案等 | 「お話を聞いたり読んだりしてみよう」小6 英語 2016.jpg |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 山本剛久,Susannah Howard(ALT),吉川啓史(ALT) |
| 授業者コメント | "Titch"は、児童のinput のために、非常に優れている教材である。以下の理由から、児童の教育用の絵本として工夫された絵本なのではないかと推察する。 ①絵と言葉を結び付けて、具体的に子どもたちに伝えられる教材であること。 ②主人公が小さな子どもで、児童の生活体験と重なる部分が大きいこと。 ③3兄弟についてくり返される記述の最後が主人公のTitch に関する記述で、そこには変化(「落ち」のようなもの)があり、興味をもちやすいものであること。 ④楽器や工具などが登場する場面があり、Do you have~? Can you play the~?などを用いて話を広げることができること。 ⑤3兄弟を比較しながら伝えており、bigger などの比較表現が用いられていること。 ⑥above が使われている部分があり、位置関係を表す言葉について扱いやすいこと。 ⑦児童が覚えられる程度の分量しかないこと。 ⑧登場人物の服などが単色で描かれており、What color is this?のようなやりとりをしやすいこと。 本実践では、児童は大変意欲的に聞いており、言えるところは単語でつぶやくようになり、だんだんと文でつぶやくようになり、本全体を覚えるようになっていった。本校の英語教育では、良質かつ多量のinputと自然なoutputを目指している。これまでは、身につけさせたい単語や文をinputするための活動を考えていた。しかし、本教材のように、母語を獲得する過程で行っている日常の活動から、inputしたい単語や文を設定していった方がよいのではないかと感じた。今回は、司書に目的をある程度伝えてから、複数の本を用意してもらい、その中から選択した。その際、複数ある本の中から特によいと感じた本は、司書と教諭で共通していた。英語が得意でない教員にも扱いやすい優れた一冊である。(山本教諭) |
| 司書・司書教諭コメント | 最近、英語の教材として適した絵本を尋ねられることが増えてきている。今回は英語に親しむために、読み聞かせに適した本を紹介してほしいというものであった。 日本語を母語とする子どもたちが、幼いときから絵本を読んでもらうことで、日本語のひびきやリズム、たくさんのことばにふれながら自然と日本語を身につけていくように、外国語を学習する際も同様に、長く読み継がれてきた絵本を読み聞かせることが有効であると考えて選書した。山本教諭が指摘している「くり返しの表現と構成」「絵と文のバランス」「題材は日常的な生活体験」という3点は、幼い子どもたちのために日本語の絵本を選ぶ際の評価基準とも重なる。司書として絵本を“教材”という目で見ることは少ないものの、日頃の経験から養われてきた絵本の選択眼が、教員が希望する絵本の条件と一致していたため、適切な資料を提供することができたのだと思う。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属大泉小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2016年7月25日 / 授業実践 2016年6月11日 |
| 事例作成者氏名 | 司書 小野寺愛美 |
記入者:小野寺(主担)

























