お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0293 校種 中学校 教科・領域等 理科 単元 科学偉人伝レポート 対象学年 中2 活用・支援の種類 課題の設定と発表方法を一緒に考える 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 図書館の蔵書、『科学感動物語』学研 を理科の学びに活かしてほしい。(図書館側からの要望) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 全12巻を120の冊子にしたので、生徒一人一人が、興味関心を持てる人物・事項に関する冊子を手にとってもらい、夏休みの課題としてレポートにする。さらにグループ内で、3分程度、その科学者や事柄について話をしてもらう。
提示資料 『科学感動物語』は全12冊だが、それぞれのテーマに分かれている。特に中学生に人気だったものを3冊あげた。 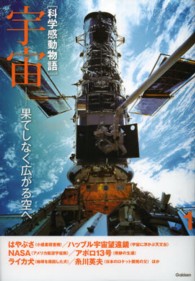
『科学感動物語1 宇宙』 学研 2013
宇宙の発達に貢献した人々や事柄を扱っているが、中学生には、知らない人も多い。誰もが知っていたのは、「はやぶさ」のみ。しかし、話を聞いて、もっと知りたくなったと答えた生徒が多かった。 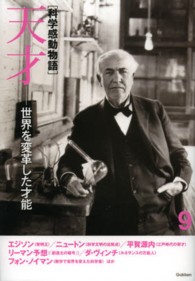
『科学感動物語9 天才』学研 2013
図書館にやってきて、我先に選びたがったのが、知名度の高い人たち。天才の中には、そういう人が多かったせいなのか?でも、安東博や、ジョン・フォン・ノイマンなど中学生が知らない天才も。そして知らない人の感動的な話に、興味をそそられたようだ。 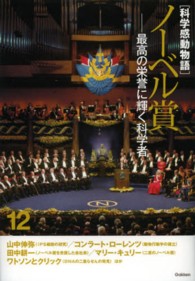
『科学感動物語12 ノーベル賞』学研 2013
ノーベル賞といっても、ノーベルや山中伸哉の名前は知っていても、少しさかのぼると知名度はぐっと下がる。キュリー夫人を知らないと答えた生徒も。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 科学者 キーワード2 レポート キーワード3 プレゼンテーション 授業計画・指導案等 科学偉人伝レポート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 高田太樹 授業者コメント 現在の中学生は「伝記」と呼ばれるものをどれほど読んでいるだろうか。多くの中学生は、授業中に出てくる「ニュートン」「ファラデー」「パスカル」などについては、名前は聞いたことあるけれど、何をやったかまでは知らない。教科書にもコラムとして取り上げられている場合もあるが、ほとんど授業で扱われることがない。よって、理科の授業で習う現象・実験や日常生活にあふれている電子機器・情報の一つ一つが過去の偉人たちの成果によるものであることは、教師も生徒も見逃しがちである。そこで、これからの未来を歩んでいく中学生にむけて、過去に生きた人の人生を振り返り、感動・尊敬・感謝の気持ちをもって欲しいと思い、司書の先生と授業を考えた。
何よりも、今まで誰も見ていなかった世界を初めて見た人や誰も理解できなかった理論を初めて理解した人の話は、大変面白い。そこには、血のにじむような努力があり、奇跡のような出会いがあり、誰もが想像できなかったヒラメキがある。心が強く引き付けられるような魅力的な人生を自分の人生と重ね合わせた中学生は、その後の自分の人生に大きな影響を受けたに違いない。
伝記を読んだ生徒にレポートを書かせた。レポートには印象的な言葉を紹介するように課題を出した。ある生徒は、ファインマンの「まず目の前の問題を楽しもう」を選び、何かにつまずいた時でも、小さいことから楽しもうとする気持ちに共感できたと感想を書いていた。数時間の授業や何日もかけた読書よりも、今まで全く知らなかった人の一言の方が、中学生に響くことがある。 司書・司書教諭コメント 良い本だと思い蔵書にしたものの、なかなか読まれない本を思い切って冊子にしての取組だったが、理科の先生に課題を考えていただけて、とてもよかった。10分もあれば読める薄い冊子だが、そこから興味・関心を抱き、しっかり調べてレポートにしている生徒が多かった。しかも、授業時間で自分が調べた人について伝え合ったことで、少なくとも自分が調べた人物についてはどのような人かを記憶にとどめることができたのではないか。偉大な科学者も、中学生には知られていないということも、よくわかった。(この活動の様子は、2017年10月の「今月の学校図書館」でも記したので、そちらも参照ください。) 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2017.11.21 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863514 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0293 校種 中学校 教科・領域等 理科 単元 科学偉人伝レポート 対象学年 中2 活用・支援の種類 課題の設定と発表方法を一緒に考える 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 図書館の蔵書、『科学感動物語』学研 を理科の学びに活かしてほしい。(図書館側からの要望) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 全12巻を120の冊子にしたので、生徒一人一人が、興味関心を持てる人物・事項に関する冊子を手にとってもらい、夏休みの課題としてレポートにする。さらにグループ内で、3分程度、その科学者や事柄について話をしてもらう。
提示資料 『科学感動物語』は全12冊だが、それぞれのテーマに分かれている。特に中学生に人気だったものを3冊あげた。 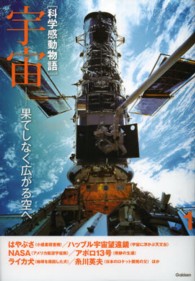
『科学感動物語1 宇宙』 学研 2013
宇宙の発達に貢献した人々や事柄を扱っているが、中学生には、知らない人も多い。誰もが知っていたのは、「はやぶさ」のみ。しかし、話を聞いて、もっと知りたくなったと答えた生徒が多かった。 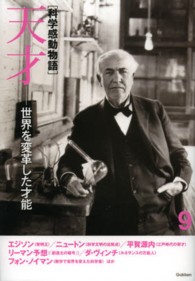
『科学感動物語9 天才』学研 2013
図書館にやってきて、我先に選びたがったのが、知名度の高い人たち。天才の中には、そういう人が多かったせいなのか?でも、安東博や、ジョン・フォン・ノイマンなど中学生が知らない天才も。そして知らない人の感動的な話に、興味をそそられたようだ。 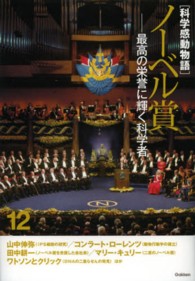
『科学感動物語12 ノーベル賞』学研 2013
ノーベル賞といっても、ノーベルや山中伸哉の名前は知っていても、少しさかのぼると知名度はぐっと下がる。キュリー夫人を知らないと答えた生徒も。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 科学者 キーワード2 レポート キーワード3 プレゼンテーション 授業計画・指導案等 科学偉人伝レポート.pdf 児童・生徒の作品 授業者 高田太樹 授業者コメント 現在の中学生は「伝記」と呼ばれるものをどれほど読んでいるだろうか。多くの中学生は、授業中に出てくる「ニュートン」「ファラデー」「パスカル」などについては、名前は聞いたことあるけれど、何をやったかまでは知らない。教科書にもコラムとして取り上げられている場合もあるが、ほとんど授業で扱われることがない。よって、理科の授業で習う現象・実験や日常生活にあふれている電子機器・情報の一つ一つが過去の偉人たちの成果によるものであることは、教師も生徒も見逃しがちである。そこで、これからの未来を歩んでいく中学生にむけて、過去に生きた人の人生を振り返り、感動・尊敬・感謝の気持ちをもって欲しいと思い、司書の先生と授業を考えた。
何よりも、今まで誰も見ていなかった世界を初めて見た人や誰も理解できなかった理論を初めて理解した人の話は、大変面白い。そこには、血のにじむような努力があり、奇跡のような出会いがあり、誰もが想像できなかったヒラメキがある。心が強く引き付けられるような魅力的な人生を自分の人生と重ね合わせた中学生は、その後の自分の人生に大きな影響を受けたに違いない。
伝記を読んだ生徒にレポートを書かせた。レポートには印象的な言葉を紹介するように課題を出した。ある生徒は、ファインマンの「まず目の前の問題を楽しもう」を選び、何かにつまずいた時でも、小さいことから楽しもうとする気持ちに共感できたと感想を書いていた。数時間の授業や何日もかけた読書よりも、今まで全く知らなかった人の一言の方が、中学生に響くことがある。 司書・司書教諭コメント 良い本だと思い蔵書にしたものの、なかなか読まれない本を思い切って冊子にしての取組だったが、理科の先生に課題を考えていただけて、とてもよかった。10分もあれば読める薄い冊子だが、そこから興味・関心を抱き、しっかり調べてレポートにしている生徒が多かった。しかも、授業時間で自分が調べた人について伝え合ったことで、少なくとも自分が調べた人物についてはどのような人かを記憶にとどめることができたのではないか。偉大な科学者も、中学生には知られていないということも、よくわかった。(この活動の様子は、2017年10月の「今月の学校図書館」でも記したので、そちらも参照ください。) 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2017.11.21 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863514 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0293 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 理科 |
| 単元 | 科学偉人伝レポート |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 課題の設定と発表方法を一緒に考える |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 図書館の蔵書、『科学感動物語』学研 を理科の学びに活かしてほしい。(図書館側からの要望) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 全12巻を120の冊子にしたので、生徒一人一人が、興味関心を持てる人物・事項に関する冊子を手にとってもらい、夏休みの課題としてレポートにする。さらにグループ内で、3分程度、その科学者や事柄について話をしてもらう。 |
| 提示資料 | 『科学感動物語』は全12冊だが、それぞれのテーマに分かれている。特に中学生に人気だったものを3冊あげた。 |
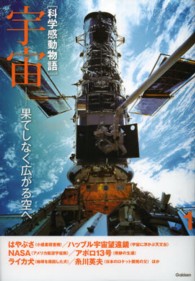 | 『科学感動物語1 宇宙』 学研 2013 宇宙の発達に貢献した人々や事柄を扱っているが、中学生には、知らない人も多い。誰もが知っていたのは、「はやぶさ」のみ。しかし、話を聞いて、もっと知りたくなったと答えた生徒が多かった。 |
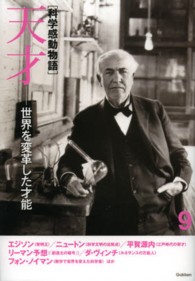 | 『科学感動物語9 天才』学研 2013 図書館にやってきて、我先に選びたがったのが、知名度の高い人たち。天才の中には、そういう人が多かったせいなのか?でも、安東博や、ジョン・フォン・ノイマンなど中学生が知らない天才も。そして知らない人の感動的な話に、興味をそそられたようだ。 |
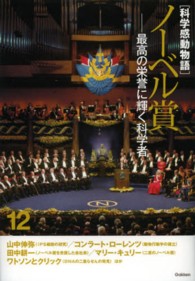 | 『科学感動物語12 ノーベル賞』学研 2013 ノーベル賞といっても、ノーベルや山中伸哉の名前は知っていても、少しさかのぼると知名度はぐっと下がる。キュリー夫人を知らないと答えた生徒も。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 科学者 |
| キーワード2 | レポート |
| キーワード3 | プレゼンテーション |
| 授業計画・指導案等 | 科学偉人伝レポート.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 高田太樹 |
| 授業者コメント | 現在の中学生は「伝記」と呼ばれるものをどれほど読んでいるだろうか。多くの中学生は、授業中に出てくる「ニュートン」「ファラデー」「パスカル」などについては、名前は聞いたことあるけれど、何をやったかまでは知らない。教科書にもコラムとして取り上げられている場合もあるが、ほとんど授業で扱われることがない。よって、理科の授業で習う現象・実験や日常生活にあふれている電子機器・情報の一つ一つが過去の偉人たちの成果によるものであることは、教師も生徒も見逃しがちである。そこで、これからの未来を歩んでいく中学生にむけて、過去に生きた人の人生を振り返り、感動・尊敬・感謝の気持ちをもって欲しいと思い、司書の先生と授業を考えた。 何よりも、今まで誰も見ていなかった世界を初めて見た人や誰も理解できなかった理論を初めて理解した人の話は、大変面白い。そこには、血のにじむような努力があり、奇跡のような出会いがあり、誰もが想像できなかったヒラメキがある。心が強く引き付けられるような魅力的な人生を自分の人生と重ね合わせた中学生は、その後の自分の人生に大きな影響を受けたに違いない。 伝記を読んだ生徒にレポートを書かせた。レポートには印象的な言葉を紹介するように課題を出した。ある生徒は、ファインマンの「まず目の前の問題を楽しもう」を選び、何かにつまずいた時でも、小さいことから楽しもうとする気持ちに共感できたと感想を書いていた。数時間の授業や何日もかけた読書よりも、今まで全く知らなかった人の一言の方が、中学生に響くことがある。 |
| 司書・司書教諭コメント | 良い本だと思い蔵書にしたものの、なかなか読まれない本を思い切って冊子にしての取組だったが、理科の先生に課題を考えていただけて、とてもよかった。10分もあれば読める薄い冊子だが、そこから興味・関心を抱き、しっかり調べてレポートにしている生徒が多かった。しかも、授業時間で自分が調べた人について伝え合ったことで、少なくとも自分が調べた人物についてはどのような人かを記憶にとどめることができたのではないか。偉大な科学者も、中学生には知られていないということも、よくわかった。(この活動の様子は、2017年10月の「今月の学校図書館」でも記したので、そちらも参照ください。) |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2017.11.21 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























