お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0317 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書会(ブックカフェ) 対象学年 中2 活用・支援の種類 読書会課題本の選定、話し合うテーマの絞り込み 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 読書会(ブックカフェ)を授業で行うので、一緒に本を選んでほしい(中1・中2・中3で実施予定) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 中1(2016年)中学1年生が無理なく読める本から上級向けまで、日本文学と外国文学、ファンタジーとリアリズムなど多様に、かつ読書が苦手な男子が、思わず手に取りそうな本も選ぶ。文庫本に限る。
中2(2017年) 昨年度よりもバージョンアップした本
中3(2018年) 生き方について考える本
本は教員個人の研究費で複本で購入(5~20冊)
提示資料 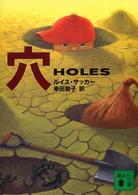
『穴 HOLES』ルイス・サッカー 幸田敦子訳 講談社 2006
ISBN 9784062755870
紹介文
無実の罪で矯正キャンプに送られたスタンリーは、他の少年たちとともに、ひたすら地面に穴を掘らされる。いったい何の目的で?運から見放されたスタンリーに起死回生のチャンスはあるのか。伏線が多く、大どんでん返しの結末が待っている。
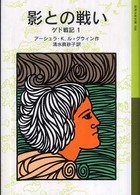
『影との戦い ゲド戦記Ⅰ』アーシュラ・K.ル=グウィン 清水真砂子訳 岩波書店 2009
ISBN 9784001145885
紹介文
真の魔法使いになるために、学院に入ったゲドは、おごりとねたみの心から禁じられた魔法で、死の国から自らの影を呼び出してしまう。影に追われることになったゲドは、逃げずに影と対決することを選ぶ。非日常の言葉、オジオンのたたずまい、真の名などに生徒は魅了された。
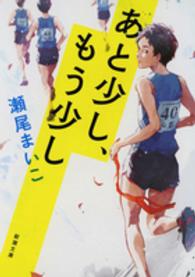
『あと少し、もう少し』瀬尾まいこ 新潮社 2015
ISBN 9784101297736
紹介文
中学生の駅伝チームの出場選手決めから大会当日までを部長の桝井を中心とした6人の奮闘を描く。6章は語り手が変わって、同じ場面を各人の視点から描いている。その手法が、読みなれていない生徒にもわかりやすいと好評だった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト コピー読書会 課題図書リスト.xls
キーワード1 読書会 キーワード2 ブックカフェ キーワード3 課題本 授業計画・指導案等 お茶中ブックカフェ資料 3.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邉光輝教諭 授業者コメント 1年時にはじめて取り組んだときは、グループ編成、話し合うテーマなどをすべて生徒に丸投げ状態で取り組ませたために、話し合いが十分に深まらないグループがあった。
その反省を生かし、2年時にはグループは四人以内に調整し、話し合う前に基本的な設定の確認を済ませておくようにした。また、2回の読書会で必ず触れる話題(レギュラーメニュー)も決め、その上で、各グループで話し合いたいテーマを「スペシャルメニュー」として深められるようにした。(参考資料参照)
このように、話し合う土台の地ならしを丁寧に行った結果、話し合いが上手く絡み合い、活発に読書会での交流に取り組むことができるようになった。また、司会者、記録者を輪番し、「司会のワザカード」などで支援しながら、どの生徒も話し合いに参加できるように配慮することができた。
読書会で一番のカギとなるのはなんと言っても課題本の選択だ。やはり深まる本と、なかなか深まりにくい本がある。年齢や発達段階の兼ね合いも大きい。司書と一緒に課題本を選ぶことはとても大変だったが、うまく生徒に受け入れられ、楽しんで読んでもらえると、とても嬉しかった。 司書・司書教諭コメント 国語の授業でクラス全員が1冊の同じ本を読んで読書会を行う事例は他に実践があるだろう。本校の実践は、読書会の本を、約8種の本から各自の希望で選べるところに特色がある。
一人の読書では、1冊の本の深くて広い世界を充分味わうことは難しい。同じ本を読んでも、感銘を受ける部分が違ったり、感じるところはそれぞれ違うと、読書会で気づけたところが素晴らしい。それが読書の醍醐味だと思う。
なかなか手に取られない『影との戦い』も課題本にしたところ、各クラス数人が読んだ。そして、シリーズに手を伸ばす生徒がいて、「ゲド戦記」が読まれたことは司書としてとても嬉しいことだった。
授業のブックカフェを経験した生徒が数人、放課後のブックカフェ(司書担当)に参加してくれたのも思いがけない成果であった。 情報提供校 お茶の水女子大学附属中学校 事例作成日 事例作成 2018年9月20日 /授業実践 2017年 2月、2017年10月、2018年10月 事例作成者氏名 司書 奥山文子
記入者:村上
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0317 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書会(ブックカフェ) 対象学年 中2 活用・支援の種類 読書会課題本の選定、話し合うテーマの絞り込み 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 読書会(ブックカフェ)を授業で行うので、一緒に本を選んでほしい(中1・中2・中3で実施予定) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 中1(2016年)中学1年生が無理なく読める本から上級向けまで、日本文学と外国文学、ファンタジーとリアリズムなど多様に、かつ読書が苦手な男子が、思わず手に取りそうな本も選ぶ。文庫本に限る。
中2(2017年) 昨年度よりもバージョンアップした本
中3(2018年) 生き方について考える本
本は教員個人の研究費で複本で購入(5~20冊)
提示資料 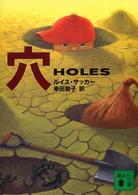
『穴 HOLES』ルイス・サッカー 幸田敦子訳 講談社 2006
ISBN 9784062755870
紹介文
無実の罪で矯正キャンプに送られたスタンリーは、他の少年たちとともに、ひたすら地面に穴を掘らされる。いったい何の目的で?運から見放されたスタンリーに起死回生のチャンスはあるのか。伏線が多く、大どんでん返しの結末が待っている。
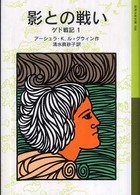
『影との戦い ゲド戦記Ⅰ』アーシュラ・K.ル=グウィン 清水真砂子訳 岩波書店 2009
ISBN 9784001145885
紹介文
真の魔法使いになるために、学院に入ったゲドは、おごりとねたみの心から禁じられた魔法で、死の国から自らの影を呼び出してしまう。影に追われることになったゲドは、逃げずに影と対決することを選ぶ。非日常の言葉、オジオンのたたずまい、真の名などに生徒は魅了された。
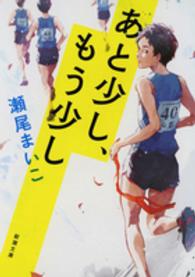
『あと少し、もう少し』瀬尾まいこ 新潮社 2015
ISBN 9784101297736
紹介文
中学生の駅伝チームの出場選手決めから大会当日までを部長の桝井を中心とした6人の奮闘を描く。6章は語り手が変わって、同じ場面を各人の視点から描いている。その手法が、読みなれていない生徒にもわかりやすいと好評だった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト コピー読書会 課題図書リスト.xls
キーワード1 読書会 キーワード2 ブックカフェ キーワード3 課題本 授業計画・指導案等 お茶中ブックカフェ資料 3.pdf 児童・生徒の作品 授業者 渡邉光輝教諭 授業者コメント 1年時にはじめて取り組んだときは、グループ編成、話し合うテーマなどをすべて生徒に丸投げ状態で取り組ませたために、話し合いが十分に深まらないグループがあった。
その反省を生かし、2年時にはグループは四人以内に調整し、話し合う前に基本的な設定の確認を済ませておくようにした。また、2回の読書会で必ず触れる話題(レギュラーメニュー)も決め、その上で、各グループで話し合いたいテーマを「スペシャルメニュー」として深められるようにした。(参考資料参照)
このように、話し合う土台の地ならしを丁寧に行った結果、話し合いが上手く絡み合い、活発に読書会での交流に取り組むことができるようになった。また、司会者、記録者を輪番し、「司会のワザカード」などで支援しながら、どの生徒も話し合いに参加できるように配慮することができた。
読書会で一番のカギとなるのはなんと言っても課題本の選択だ。やはり深まる本と、なかなか深まりにくい本がある。年齢や発達段階の兼ね合いも大きい。司書と一緒に課題本を選ぶことはとても大変だったが、うまく生徒に受け入れられ、楽しんで読んでもらえると、とても嬉しかった。 司書・司書教諭コメント 国語の授業でクラス全員が1冊の同じ本を読んで読書会を行う事例は他に実践があるだろう。本校の実践は、読書会の本を、約8種の本から各自の希望で選べるところに特色がある。
一人の読書では、1冊の本の深くて広い世界を充分味わうことは難しい。同じ本を読んでも、感銘を受ける部分が違ったり、感じるところはそれぞれ違うと、読書会で気づけたところが素晴らしい。それが読書の醍醐味だと思う。
なかなか手に取られない『影との戦い』も課題本にしたところ、各クラス数人が読んだ。そして、シリーズに手を伸ばす生徒がいて、「ゲド戦記」が読まれたことは司書としてとても嬉しいことだった。
授業のブックカフェを経験した生徒が数人、放課後のブックカフェ(司書担当)に参加してくれたのも思いがけない成果であった。 情報提供校 お茶の水女子大学附属中学校 事例作成日 事例作成 2018年9月20日 /授業実践 2017年 2月、2017年10月、2018年10月 事例作成者氏名 司書 奥山文子
記入者:村上
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0317 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 読書会(ブックカフェ) |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 読書会課題本の選定、話し合うテーマの絞り込み |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 読書会(ブックカフェ)を授業で行うので、一緒に本を選んでほしい(中1・中2・中3で実施予定) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 中1(2016年)中学1年生が無理なく読める本から上級向けまで、日本文学と外国文学、ファンタジーとリアリズムなど多様に、かつ読書が苦手な男子が、思わず手に取りそうな本も選ぶ。文庫本に限る。 中2(2017年) 昨年度よりもバージョンアップした本 中3(2018年) 生き方について考える本 本は教員個人の研究費で複本で購入(5~20冊) |
| 提示資料 | |
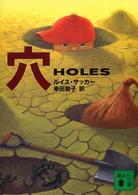 | 『穴 HOLES』ルイス・サッカー 幸田敦子訳 講談社 2006 ISBN 9784062755870 紹介文 無実の罪で矯正キャンプに送られたスタンリーは、他の少年たちとともに、ひたすら地面に穴を掘らされる。いったい何の目的で?運から見放されたスタンリーに起死回生のチャンスはあるのか。伏線が多く、大どんでん返しの結末が待っている。 |
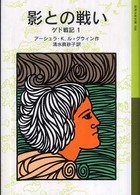 | 『影との戦い ゲド戦記Ⅰ』アーシュラ・K.ル=グウィン 清水真砂子訳 岩波書店 2009 ISBN 9784001145885 紹介文 真の魔法使いになるために、学院に入ったゲドは、おごりとねたみの心から禁じられた魔法で、死の国から自らの影を呼び出してしまう。影に追われることになったゲドは、逃げずに影と対決することを選ぶ。非日常の言葉、オジオンのたたずまい、真の名などに生徒は魅了された。 |
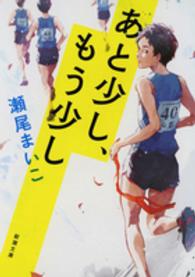 | 『あと少し、もう少し』瀬尾まいこ 新潮社 2015 ISBN 9784101297736 紹介文 中学生の駅伝チームの出場選手決めから大会当日までを部長の桝井を中心とした6人の奮闘を描く。6章は語り手が変わって、同じ場面を各人の視点から描いている。その手法が、読みなれていない生徒にもわかりやすいと好評だった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | コピー読書会 課題図書リスト.xls |
| キーワード1 | 読書会 |
| キーワード2 | ブックカフェ |
| キーワード3 | 課題本 |
| 授業計画・指導案等 | お茶中ブックカフェ資料 3.pdf |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 渡邉光輝教諭 |
| 授業者コメント | 1年時にはじめて取り組んだときは、グループ編成、話し合うテーマなどをすべて生徒に丸投げ状態で取り組ませたために、話し合いが十分に深まらないグループがあった。 その反省を生かし、2年時にはグループは四人以内に調整し、話し合う前に基本的な設定の確認を済ませておくようにした。また、2回の読書会で必ず触れる話題(レギュラーメニュー)も決め、その上で、各グループで話し合いたいテーマを「スペシャルメニュー」として深められるようにした。(参考資料参照) このように、話し合う土台の地ならしを丁寧に行った結果、話し合いが上手く絡み合い、活発に読書会での交流に取り組むことができるようになった。また、司会者、記録者を輪番し、「司会のワザカード」などで支援しながら、どの生徒も話し合いに参加できるように配慮することができた。 読書会で一番のカギとなるのはなんと言っても課題本の選択だ。やはり深まる本と、なかなか深まりにくい本がある。年齢や発達段階の兼ね合いも大きい。司書と一緒に課題本を選ぶことはとても大変だったが、うまく生徒に受け入れられ、楽しんで読んでもらえると、とても嬉しかった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 国語の授業でクラス全員が1冊の同じ本を読んで読書会を行う事例は他に実践があるだろう。本校の実践は、読書会の本を、約8種の本から各自の希望で選べるところに特色がある。 一人の読書では、1冊の本の深くて広い世界を充分味わうことは難しい。同じ本を読んでも、感銘を受ける部分が違ったり、感じるところはそれぞれ違うと、読書会で気づけたところが素晴らしい。それが読書の醍醐味だと思う。 なかなか手に取られない『影との戦い』も課題本にしたところ、各クラス数人が読んだ。そして、シリーズに手を伸ばす生徒がいて、「ゲド戦記」が読まれたことは司書としてとても嬉しいことだった。 授業のブックカフェを経験した生徒が数人、放課後のブックカフェ(司書担当)に参加してくれたのも思いがけない成果であった。 |
| 情報提供校 | お茶の水女子大学附属中学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2018年9月20日 /授業実践 2017年 2月、2017年10月、2018年10月 |
| 事例作成者氏名 | 司書 奥山文子 |
記入者:村上

























