お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0337 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 「本はともだち」としょかんをつくろう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもたちが楽しむ絵本の交換ゲームをしたいので、貸出を1冊増やしてください。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ◎友達と絵本の交換ゲームを通して、読書の幅を広げ、色々な絵本を読んだり、読み聞かせてもらったりする。
〇絵本の絵や題名などを手掛かりにして、自分が面白いと思えるような絵本を選ぶことができるようになる。
提示資料 「よかったねネッドくん」
レミー・シャーリップ(作)八木田宜子(訳)偕成社 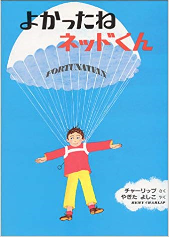
「おたすけこびと」
なかがわちひと(文)コヨセ・ジュンジ(絵)徳間書店
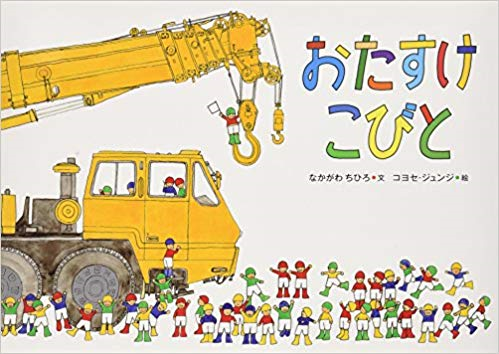
「もっとかんがえるカエルくん」
いわむらかずお(作)福音館書店 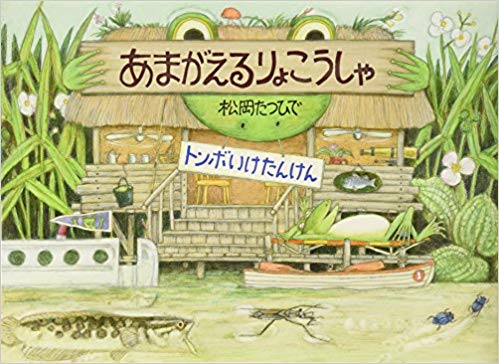
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 ともだちとしょかん.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=892#_1330 授業者 授業者コメント 本単元での子どもたちの目的は、子どもたちが自分たちで絵本を選び、それらを集めて『ほんはともだちとしょかん』というミニ図書館をつくることである。自分たちで好きな絵本を集めて、それらを置くことでも、それはつくることが可能であるが、そこに、「友だちとの絵本の交換」という活動をいれた。この活動をいれたことによって、「友だちが選んだ絵本を読む機会」「自分では選ばない絵本を読む機会」という二つの機会が増えるとともに、自然と絵本を読む時間が増えることになった。 司書・司書教諭コメント 1年生は、一学期中は、絵本1冊の貸し出しにしています。低学年の時にたっぷりと絵本に親しんでほしいと考えているからです。担任の申し出により、このクラスは、一人2冊の絵本を貸し出しました。
この実践は、1学期に行われたものですが、この時期に改めて掲載したのは、子どもたちが絵本をたっぷり楽しんだ成果が三学期に顕著になって来たからです。
この学校では、読んだ本の読書記録を書いています。日を重ねるにつれ、記録が豊かになってきています。絵本を楽しんでいる様子が見られるうえに、それが力になっているんだなあと感じたので、改めて事例に上げさせていただきました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 事例作成 2019年 3月 15日 /授業実践 2018年 5月 事例作成者氏名 福田 淳佑
記入者:金澤(主担)
カウンタ
3863421 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0337 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 「本はともだち」としょかんをつくろう 対象学年 低学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもたちが楽しむ絵本の交換ゲームをしたいので、貸出を1冊増やしてください。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 ◎友達と絵本の交換ゲームを通して、読書の幅を広げ、色々な絵本を読んだり、読み聞かせてもらったりする。
〇絵本の絵や題名などを手掛かりにして、自分が面白いと思えるような絵本を選ぶことができるようになる。
提示資料 「よかったねネッドくん」
レミー・シャーリップ(作)八木田宜子(訳)偕成社 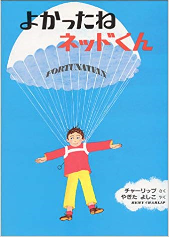
「おたすけこびと」
なかがわちひと(文)コヨセ・ジュンジ(絵)徳間書店
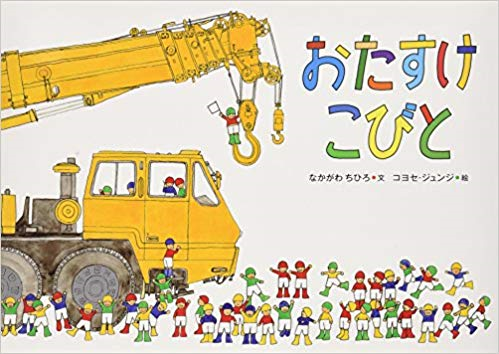
「もっとかんがえるカエルくん」
いわむらかずお(作)福音館書店 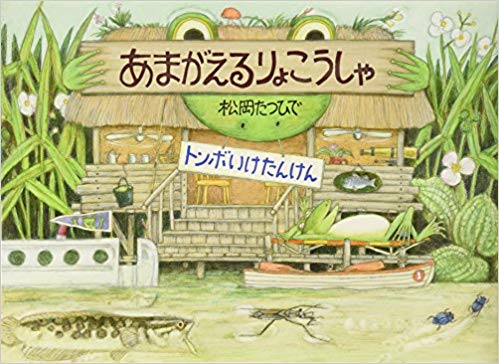
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 キーワード3 授業計画・指導案等 ともだちとしょかん.pdf 児童・生徒の作品 http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=892#_1330 授業者 授業者コメント 本単元での子どもたちの目的は、子どもたちが自分たちで絵本を選び、それらを集めて『ほんはともだちとしょかん』というミニ図書館をつくることである。自分たちで好きな絵本を集めて、それらを置くことでも、それはつくることが可能であるが、そこに、「友だちとの絵本の交換」という活動をいれた。この活動をいれたことによって、「友だちが選んだ絵本を読む機会」「自分では選ばない絵本を読む機会」という二つの機会が増えるとともに、自然と絵本を読む時間が増えることになった。 司書・司書教諭コメント 1年生は、一学期中は、絵本1冊の貸し出しにしています。低学年の時にたっぷりと絵本に親しんでほしいと考えているからです。担任の申し出により、このクラスは、一人2冊の絵本を貸し出しました。
この実践は、1学期に行われたものですが、この時期に改めて掲載したのは、子どもたちが絵本をたっぷり楽しんだ成果が三学期に顕著になって来たからです。
この学校では、読んだ本の読書記録を書いています。日を重ねるにつれ、記録が豊かになってきています。絵本を楽しんでいる様子が見られるうえに、それが力になっているんだなあと感じたので、改めて事例に上げさせていただきました。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷小学校 事例作成日 事例作成 2019年 3月 15日 /授業実践 2018年 5月 事例作成者氏名 福田 淳佑
記入者:金澤(主担)
カウンタ
3863421 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0337 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | その他 |
| 単元 | 「本はともだち」としょかんをつくろう |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 子どもたちが楽しむ絵本の交換ゲームをしたいので、貸出を1冊増やしてください。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | ◎友達と絵本の交換ゲームを通して、読書の幅を広げ、色々な絵本を読んだり、読み聞かせてもらったりする。 〇絵本の絵や題名などを手掛かりにして、自分が面白いと思えるような絵本を選ぶことができるようになる。 |
| 提示資料 | 「よかったねネッドくん」 レミー・シャーリップ(作)八木田宜子(訳)偕成社 |
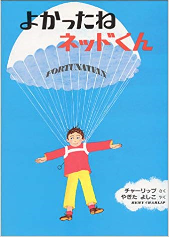 | 「おたすけこびと」 なかがわちひと(文)コヨセ・ジュンジ(絵)徳間書店 |
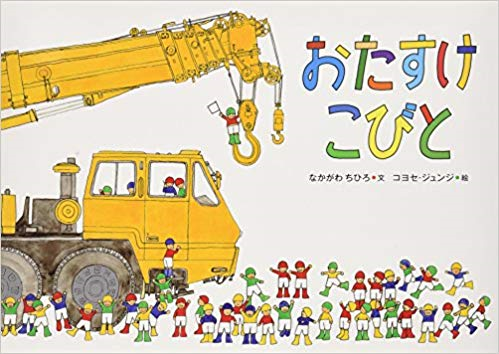 | 「もっとかんがえるカエルくん」 いわむらかずお(作)福音館書店 |
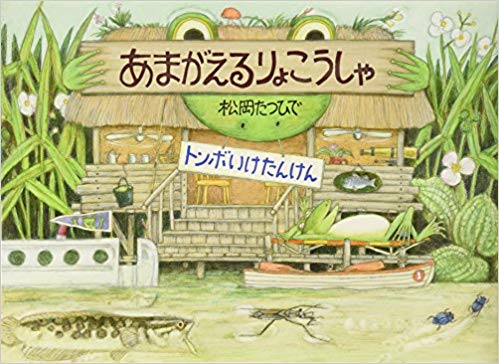 | |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 絵本 |
| キーワード2 | |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | ともだちとしょかん.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http://www.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/index.php?action=pages_view_main&block_id=1330&active_action=journal_view_main_detail&post_id=892#_1330 |
| 授業者 | |
| 授業者コメント | 本単元での子どもたちの目的は、子どもたちが自分たちで絵本を選び、それらを集めて『ほんはともだちとしょかん』というミニ図書館をつくることである。自分たちで好きな絵本を集めて、それらを置くことでも、それはつくることが可能であるが、そこに、「友だちとの絵本の交換」という活動をいれた。この活動をいれたことによって、「友だちが選んだ絵本を読む機会」「自分では選ばない絵本を読む機会」という二つの機会が増えるとともに、自然と絵本を読む時間が増えることになった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 1年生は、一学期中は、絵本1冊の貸し出しにしています。低学年の時にたっぷりと絵本に親しんでほしいと考えているからです。担任の申し出により、このクラスは、一人2冊の絵本を貸し出しました。 この実践は、1学期に行われたものですが、この時期に改めて掲載したのは、子どもたちが絵本をたっぷり楽しんだ成果が三学期に顕著になって来たからです。 この学校では、読んだ本の読書記録を書いています。日を重ねるにつれ、記録が豊かになってきています。絵本を楽しんでいる様子が見られるうえに、それが力になっているんだなあと感じたので、改めて事例に上げさせていただきました。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2019年 3月 15日 /授業実践 2018年 5月 |
| 事例作成者氏名 | 福田 淳佑 |
記入者:金澤(主担)

























