お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0368 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 絵画から物語の読みを深める―『伊勢物語』とその文化的背景― 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供、グループワーク時の生徒支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 『伊勢物語』の文化的背景の理解に役立つ書籍や絵画資料が欲しい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 授業の目標を共有することが重要であるので、高校生が『伊勢物語』を学ぶ意味や国語科として達成したいことについて聞き取りをした。また探究型学習に取り組むにあたり、パフォーマンス課題を授業デザインに組み込むことが有効であると考え、課題づくりに関する議論をした。
提示資料 司書教諭から提示された資料のうち、生徒にも紹介したものはブックリストにある27冊。その中でも特に役立ったのが、次の3冊である。 
『恋の王朝絵巻 伊勢物語』 岡野弘彦 淡交社 2008
絵画紹介はないが、『伊勢物語』の有名な章段について、歴史的・文化的背景を踏まえた解説がなされている。各章段のつながりも解説されており、作品全体の理解につながりやすい。 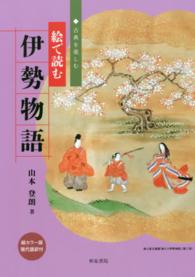
『絵で読む 伊勢物語』 山本登朗 和泉書院 2016
『伊勢物語』の絵画資料として著名な「嵯峨本」を踏襲した物語絵と、高校生にも分かりやすい解説文が収録されており、文化的背景を踏まえた作品鑑賞の手助けとなる。 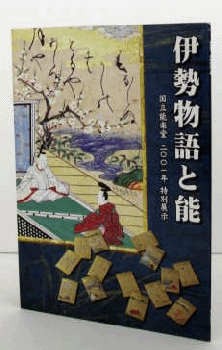
『国立能楽堂特別展示 伊勢物語と能』 国立能楽堂調査養成課調査資料係編 日本芸術文化振興会 2001
『伊勢物語』「筒井筒」絵の大多数は、子ども二人が井戸の中を覗く構図をとっている。原文にはそのような記述がないのに、なぜこの構図が一般的になったのか、能「井筒」の物語を紹介しながら説明している。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 ブックリスト 『伊勢物語』ブックリスト.xlsx
キーワード1 伊勢物語 キーワード2 協同学習 キーワード3 パフォーマンス課題 授業計画・指導案等 『伊勢物語』指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 秋長幸依・梶木尚美 授業者コメント 古文教材を文章だけで鑑賞するのではなく、絵画資料等も用いることで、作品そのものへの興味関心がわいたり、作品解釈が広まり深まったりした。また、当時の風習や人々の考え方、現代に至るまでに作品がどのように伝わってきたのか、などを生徒自身が多くの資料をもちに探究することで、古文教材への関心が深まったようであった。 授業の詳細は、添付PDFおよび次のURLを参照されたい。
秋長幸依「絵画から物語の読みを深める :『伊勢物語』とその文化的背景」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月, 1-11. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 司書・司書教諭コメント 平安時代に書かれた物語を高校生なりに読み解くためには、生徒が興味を持つこと、物語についてもっと知りたいと思うことが大切である。絵画というビジュアル資料は、文字資料よりも生徒にとっては取り組みやすく、探究的な問いを持つことが楽になる。パフォーマンス課題に導かれるようにして、生徒たちが『伊勢物語』の世界を探究していった姿が印象的であった。司書教諭の立場として課題になるのは、評価である。教科の学習目標を共有して学習活動をサポートした一人として、どのように評価に関わるのかという点が不明確なままである。今後の課題としたい。 梶木尚美「『伊勢物語』を探求する授業 :国語科教員と学校図書館員の対話による授業デザイン」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月,13-20. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030598 情報提供校 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 事例作成日 事例作成 2020年 4月 8日 /授業実践 2016年11~12月 事例作成者氏名 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 教諭 秋長幸依、学校図書館司書教諭 梶木尚美
記入者:村上
カウンタ
3863432 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0368 校種 高校 教科・領域等 国語 単元 絵画から物語の読みを深める―『伊勢物語』とその文化的背景― 対象学年 高1 活用・支援の種類 資料提供、グループワーク時の生徒支援 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 『伊勢物語』の文化的背景の理解に役立つ書籍や絵画資料が欲しい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 授業の目標を共有することが重要であるので、高校生が『伊勢物語』を学ぶ意味や国語科として達成したいことについて聞き取りをした。また探究型学習に取り組むにあたり、パフォーマンス課題を授業デザインに組み込むことが有効であると考え、課題づくりに関する議論をした。
提示資料 司書教諭から提示された資料のうち、生徒にも紹介したものはブックリストにある27冊。その中でも特に役立ったのが、次の3冊である。 
『恋の王朝絵巻 伊勢物語』 岡野弘彦 淡交社 2008
絵画紹介はないが、『伊勢物語』の有名な章段について、歴史的・文化的背景を踏まえた解説がなされている。各章段のつながりも解説されており、作品全体の理解につながりやすい。 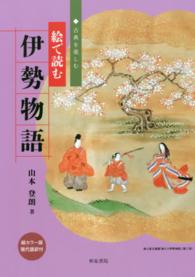
『絵で読む 伊勢物語』 山本登朗 和泉書院 2016
『伊勢物語』の絵画資料として著名な「嵯峨本」を踏襲した物語絵と、高校生にも分かりやすい解説文が収録されており、文化的背景を踏まえた作品鑑賞の手助けとなる。 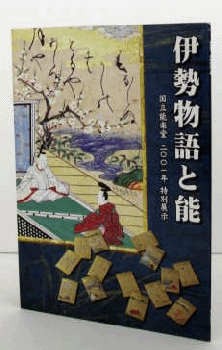
『国立能楽堂特別展示 伊勢物語と能』 国立能楽堂調査養成課調査資料係編 日本芸術文化振興会 2001
『伊勢物語』「筒井筒」絵の大多数は、子ども二人が井戸の中を覗く構図をとっている。原文にはそのような記述がないのに、なぜこの構図が一般的になったのか、能「井筒」の物語を紹介しながら説明している。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 ブックリスト 『伊勢物語』ブックリスト.xlsx
キーワード1 伊勢物語 キーワード2 協同学習 キーワード3 パフォーマンス課題 授業計画・指導案等 『伊勢物語』指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 秋長幸依・梶木尚美 授業者コメント 古文教材を文章だけで鑑賞するのではなく、絵画資料等も用いることで、作品そのものへの興味関心がわいたり、作品解釈が広まり深まったりした。また、当時の風習や人々の考え方、現代に至るまでに作品がどのように伝わってきたのか、などを生徒自身が多くの資料をもちに探究することで、古文教材への関心が深まったようであった。 授業の詳細は、添付PDFおよび次のURLを参照されたい。
秋長幸依「絵画から物語の読みを深める :『伊勢物語』とその文化的背景」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月, 1-11. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 司書・司書教諭コメント 平安時代に書かれた物語を高校生なりに読み解くためには、生徒が興味を持つこと、物語についてもっと知りたいと思うことが大切である。絵画というビジュアル資料は、文字資料よりも生徒にとっては取り組みやすく、探究的な問いを持つことが楽になる。パフォーマンス課題に導かれるようにして、生徒たちが『伊勢物語』の世界を探究していった姿が印象的であった。司書教諭の立場として課題になるのは、評価である。教科の学習目標を共有して学習活動をサポートした一人として、どのように評価に関わるのかという点が不明確なままである。今後の課題としたい。 梶木尚美「『伊勢物語』を探求する授業 :国語科教員と学校図書館員の対話による授業デザイン」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月,13-20. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030598 情報提供校 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 事例作成日 事例作成 2020年 4月 8日 /授業実践 2016年11~12月 事例作成者氏名 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 教諭 秋長幸依、学校図書館司書教諭 梶木尚美
記入者:村上
カウンタ
3863432 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0368 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 絵画から物語の読みを深める―『伊勢物語』とその文化的背景― |
| 対象学年 | 高1 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供、グループワーク時の生徒支援 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 『伊勢物語』の文化的背景の理解に役立つ書籍や絵画資料が欲しい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 授業の目標を共有することが重要であるので、高校生が『伊勢物語』を学ぶ意味や国語科として達成したいことについて聞き取りをした。また探究型学習に取り組むにあたり、パフォーマンス課題を授業デザインに組み込むことが有効であると考え、課題づくりに関する議論をした。 |
| 提示資料 | 司書教諭から提示された資料のうち、生徒にも紹介したものはブックリストにある27冊。その中でも特に役立ったのが、次の3冊である。 |
 | 『恋の王朝絵巻 伊勢物語』 岡野弘彦 淡交社 2008 絵画紹介はないが、『伊勢物語』の有名な章段について、歴史的・文化的背景を踏まえた解説がなされている。各章段のつながりも解説されており、作品全体の理解につながりやすい。 |
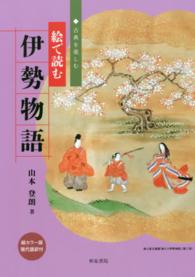 | 『絵で読む 伊勢物語』 山本登朗 和泉書院 2016 『伊勢物語』の絵画資料として著名な「嵯峨本」を踏襲した物語絵と、高校生にも分かりやすい解説文が収録されており、文化的背景を踏まえた作品鑑賞の手助けとなる。 |
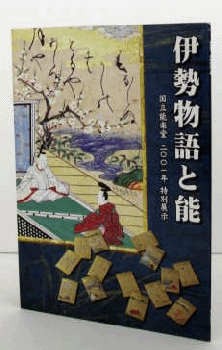 | 『国立能楽堂特別展示 伊勢物語と能』 国立能楽堂調査養成課調査資料係編 日本芸術文化振興会 2001 『伊勢物語』「筒井筒」絵の大多数は、子ども二人が井戸の中を覗く構図をとっている。原文にはそのような記述がないのに、なぜこの構図が一般的になったのか、能「井筒」の物語を紹介しながら説明している。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 |
| ブックリスト | 『伊勢物語』ブックリスト.xlsx |
| キーワード1 | 伊勢物語 |
| キーワード2 | 協同学習 |
| キーワード3 | パフォーマンス課題 |
| 授業計画・指導案等 | 『伊勢物語』指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 秋長幸依・梶木尚美 |
| 授業者コメント | 古文教材を文章だけで鑑賞するのではなく、絵画資料等も用いることで、作品そのものへの興味関心がわいたり、作品解釈が広まり深まったりした。また、当時の風習や人々の考え方、現代に至るまでに作品がどのように伝わってきたのか、などを生徒自身が多くの資料をもちに探究することで、古文教材への関心が深まったようであった。 授業の詳細は、添付PDFおよび次のURLを参照されたい。 秋長幸依「絵画から物語の読みを深める :『伊勢物語』とその文化的背景」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月, 1-11. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030597 |
| 司書・司書教諭コメント | 平安時代に書かれた物語を高校生なりに読み解くためには、生徒が興味を持つこと、物語についてもっと知りたいと思うことが大切である。絵画というビジュアル資料は、文字資料よりも生徒にとっては取り組みやすく、探究的な問いを持つことが楽になる。パフォーマンス課題に導かれるようにして、生徒たちが『伊勢物語』の世界を探究していった姿が印象的であった。司書教諭の立場として課題になるのは、評価である。教科の学習目標を共有して学習活動をサポートした一人として、どのように評価に関わるのかという点が不明確なままである。今後の課題としたい。 梶木尚美「『伊勢物語』を探求する授業 :国語科教員と学校図書館員の対話による授業デザイン」『研究紀要(大阪教育大学附属高等学校池田校舎)』50(1), 2018年.2月,13-20. https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00030598 |
| 情報提供校 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
| 事例作成日 | 事例作成 2020年 4月 8日 /授業実践 2016年11~12月 |
| 事例作成者氏名 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 教諭 秋長幸依、学校図書館司書教諭 梶木尚美 |
記入者:村上

























