お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0362 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 私たちと政治 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料相談・資料提供・ブックリスト作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 国会のしくみを学ぶために擬擬委員会を実施したいので、教員の設定した6つのテーマに関する資料を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 テーマは以下の6つ。
①グローバル化「オーバーツーリズムについて」
②少子高齢化「高齢者ドライバーについて」
③情報化「中学生スマートフォン所持について」
④伝統文化「伝統文化継承について」
⑤両性の平等「政治家の女性人数について」
⑥自己決定権「尊厳死・安楽死について」
提示資料 テーマに関連して用意した資料のなかから、特に中学生に手にとってもらいたい本として選んだ3冊。 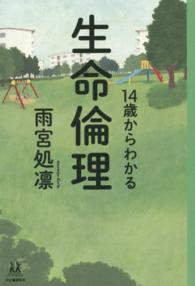
『14歳からわかる生命倫理(14歳の世渡り術)』雨宮 処凛 河出書房新社 '14.5.30 発 ISBN: 9784309616858
生命倫理について、幅広くとりあげているが、そのなかに、今回のテーマ、安楽死・尊厳死についても触れている。14歳の世渡り術シリーズの1冊だけに、中学生にもわかりやすい言葉で書かれている。授業のあとに、この本を借りる生徒がいた。 
『男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える』(岩波ジュニア新書)山下泰子 矢澤澄子 岩波書店 2018/06 発行 ISBN: 9784005008742
1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効した女性差別撤廃条約。日本は1985年に締結している。条約の条文に照らしながら、身近な事例をあげて、現状考察している。
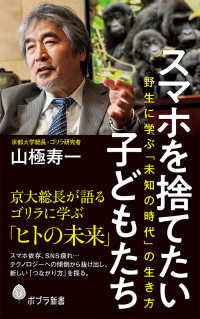
『スマホを捨てたい子どもたち―野生に学ぶ「未知の時代」の生き方(ポプラ新書)』山極 寿一【著】ポプラ社 '20.6.8 発行 ISBN: 9784591166130
この本が、「中学生スマートフォン所持について」 というテーマに直結して、役立ったのかはわからないが、このタイトルだけでもインパクトがあると思う。いろいろな角度から、物事を考える一助になればと、資料に入れ込んだ一冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 模擬委員会用ブックリスト.xlsx
キーワード1 国会 キーワード2 模擬委員会 キーワード3 法律 授業計画・指導案等 模擬委員会指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 金城和秀 授業者コメント ・生徒は主体的に法律案の作成に取り組み、独自で条文をつくってくる生徒や昼休みまで議論を続けているクラスも見られ、とても有意義な実践授業だった。それ故、すべての班の法律案を模擬委員会にかけることができなかったのが残念だった。時間的な制約があるが、今後はできればすべての班の法律案を模擬委員会にかけることができるように工夫したい。
・調べ学習では、学校司書と打ち合わせを行い、必要な図書、資料、新聞記事を用意してもらった。ICT機器もあるが、はじめは紙ベースでの情報収集を意図的にねらいとして、ICT機器は調べ学習の2時間目からの解禁とした。調べる手段が多数あることで、グループでの話し合いも活発になったと思う。中には、ICT機器を使い、尊厳死についての動画を班で見て、基本的な学習をしている班も見られた。
司書・司書教諭コメント 先生からは、余裕をもった段階で、声をかけていただけたので、授業の内容を理解したうえで、資料を準備することができた。今日的テーマなので、自校の資料では足りず、新たに買ったり、公共図書館や附属学校からも借りて準備した。本があまりないものは、使えそうな論文や、新聞記事も用意したので、生徒もこれからやるべきことがある程度イメージできたのではないかと思う。
今後ICT機器の導入がますます進むなかで、今回のように、デジタルな情報とアナログな情報をうまく使い分けながら、学びを深めていってほしいと思う。
その後の模擬委員会の様子を見学させてもらったり、このデータベースに事例を載せてもらうために、担当の先生と話ができたこともよかった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 授業実践 2020年11月 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0362 校種 中学校 教科・領域等 社会 単元 私たちと政治 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料相談・資料提供・ブックリスト作成 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 国会のしくみを学ぶために擬擬委員会を実施したいので、教員の設定した6つのテーマに関する資料を集めてほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 テーマは以下の6つ。
①グローバル化「オーバーツーリズムについて」
②少子高齢化「高齢者ドライバーについて」
③情報化「中学生スマートフォン所持について」
④伝統文化「伝統文化継承について」
⑤両性の平等「政治家の女性人数について」
⑥自己決定権「尊厳死・安楽死について」
提示資料 テーマに関連して用意した資料のなかから、特に中学生に手にとってもらいたい本として選んだ3冊。 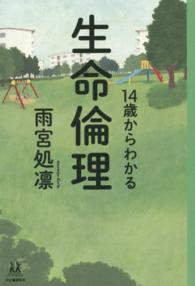
『14歳からわかる生命倫理(14歳の世渡り術)』雨宮 処凛 河出書房新社 '14.5.30 発 ISBN: 9784309616858
生命倫理について、幅広くとりあげているが、そのなかに、今回のテーマ、安楽死・尊厳死についても触れている。14歳の世渡り術シリーズの1冊だけに、中学生にもわかりやすい言葉で書かれている。授業のあとに、この本を借りる生徒がいた。 
『男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える』(岩波ジュニア新書)山下泰子 矢澤澄子 岩波書店 2018/06 発行 ISBN: 9784005008742
1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効した女性差別撤廃条約。日本は1985年に締結している。条約の条文に照らしながら、身近な事例をあげて、現状考察している。
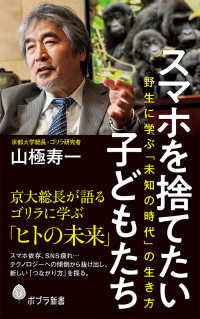
『スマホを捨てたい子どもたち―野生に学ぶ「未知の時代」の生き方(ポプラ新書)』山極 寿一【著】ポプラ社 '20.6.8 発行 ISBN: 9784591166130
この本が、「中学生スマートフォン所持について」 というテーマに直結して、役立ったのかはわからないが、このタイトルだけでもインパクトがあると思う。いろいろな角度から、物事を考える一助になればと、資料に入れ込んだ一冊。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 模擬委員会用ブックリスト.xlsx
キーワード1 国会 キーワード2 模擬委員会 キーワード3 法律 授業計画・指導案等 模擬委員会指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 金城和秀 授業者コメント ・生徒は主体的に法律案の作成に取り組み、独自で条文をつくってくる生徒や昼休みまで議論を続けているクラスも見られ、とても有意義な実践授業だった。それ故、すべての班の法律案を模擬委員会にかけることができなかったのが残念だった。時間的な制約があるが、今後はできればすべての班の法律案を模擬委員会にかけることができるように工夫したい。
・調べ学習では、学校司書と打ち合わせを行い、必要な図書、資料、新聞記事を用意してもらった。ICT機器もあるが、はじめは紙ベースでの情報収集を意図的にねらいとして、ICT機器は調べ学習の2時間目からの解禁とした。調べる手段が多数あることで、グループでの話し合いも活発になったと思う。中には、ICT機器を使い、尊厳死についての動画を班で見て、基本的な学習をしている班も見られた。
司書・司書教諭コメント 先生からは、余裕をもった段階で、声をかけていただけたので、授業の内容を理解したうえで、資料を準備することができた。今日的テーマなので、自校の資料では足りず、新たに買ったり、公共図書館や附属学校からも借りて準備した。本があまりないものは、使えそうな論文や、新聞記事も用意したので、生徒もこれからやるべきことがある程度イメージできたのではないかと思う。
今後ICT機器の導入がますます進むなかで、今回のように、デジタルな情報とアナログな情報をうまく使い分けながら、学びを深めていってほしいと思う。
その後の模擬委員会の様子を見学させてもらったり、このデータベースに事例を載せてもらうために、担当の先生と話ができたこともよかった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 授業実践 2020年11月 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863457 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0362 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 社会 |
| 単元 | 私たちと政治 |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料相談・資料提供・ブックリスト作成 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 国会のしくみを学ぶために擬擬委員会を実施したいので、教員の設定した6つのテーマに関する資料を集めてほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | テーマは以下の6つ。 ①グローバル化「オーバーツーリズムについて」 ②少子高齢化「高齢者ドライバーについて」 ③情報化「中学生スマートフォン所持について」 ④伝統文化「伝統文化継承について」 ⑤両性の平等「政治家の女性人数について」 ⑥自己決定権「尊厳死・安楽死について」 |
| 提示資料 | テーマに関連して用意した資料のなかから、特に中学生に手にとってもらいたい本として選んだ3冊。 |
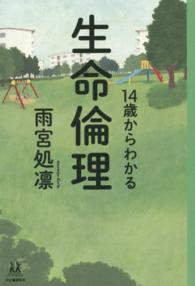 | 『14歳からわかる生命倫理(14歳の世渡り術)』雨宮 処凛 河出書房新社 '14.5.30 発 ISBN: 9784309616858 生命倫理について、幅広くとりあげているが、そのなかに、今回のテーマ、安楽死・尊厳死についても触れている。14歳の世渡り術シリーズの1冊だけに、中学生にもわかりやすい言葉で書かれている。授業のあとに、この本を借りる生徒がいた。 |
 | 『男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える』(岩波ジュニア新書)山下泰子 矢澤澄子 岩波書店 2018/06 発行 ISBN: 9784005008742 1979年の第34回国連総会において採択され、1981年に発効した女性差別撤廃条約。日本は1985年に締結している。条約の条文に照らしながら、身近な事例をあげて、現状考察している。 |
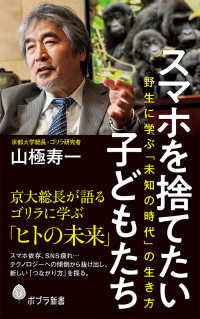 | 『スマホを捨てたい子どもたち―野生に学ぶ「未知の時代」の生き方(ポプラ新書)』山極 寿一【著】ポプラ社 '20.6.8 発行 ISBN: 9784591166130 この本が、「中学生スマートフォン所持について」 というテーマに直結して、役立ったのかはわからないが、このタイトルだけでもインパクトがあると思う。いろいろな角度から、物事を考える一助になればと、資料に入れ込んだ一冊。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 模擬委員会用ブックリスト.xlsx |
| キーワード1 | 国会 |
| キーワード2 | 模擬委員会 |
| キーワード3 | 法律 |
| 授業計画・指導案等 | 模擬委員会指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 金城和秀 |
| 授業者コメント | ・生徒は主体的に法律案の作成に取り組み、独自で条文をつくってくる生徒や昼休みまで議論を続けているクラスも見られ、とても有意義な実践授業だった。それ故、すべての班の法律案を模擬委員会にかけることができなかったのが残念だった。時間的な制約があるが、今後はできればすべての班の法律案を模擬委員会にかけることができるように工夫したい。 ・調べ学習では、学校司書と打ち合わせを行い、必要な図書、資料、新聞記事を用意してもらった。ICT機器もあるが、はじめは紙ベースでの情報収集を意図的にねらいとして、ICT機器は調べ学習の2時間目からの解禁とした。調べる手段が多数あることで、グループでの話し合いも活発になったと思う。中には、ICT機器を使い、尊厳死についての動画を班で見て、基本的な学習をしている班も見られた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 先生からは、余裕をもった段階で、声をかけていただけたので、授業の内容を理解したうえで、資料を準備することができた。今日的テーマなので、自校の資料では足りず、新たに買ったり、公共図書館や附属学校からも借りて準備した。本があまりないものは、使えそうな論文や、新聞記事も用意したので、生徒もこれからやるべきことがある程度イメージできたのではないかと思う。 今後ICT機器の導入がますます進むなかで、今回のように、デジタルな情報とアナログな情報をうまく使い分けながら、学びを深めていってほしいと思う。 その後の模擬委員会の様子を見学させてもらったり、このデータベースに事例を載せてもらうために、担当の先生と話ができたこともよかった。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 授業実践 2020年11月 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























