お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0379 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 たねのふしぎ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 単元の導入として、普段見慣れている野菜や果物のたねに興味を持てる絵本を紹介してほしい。またタネの運ばれ方などを児童が調べて確認できる資料を提供してほしい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 (大田区立清水窪小学校の教科:サイエンスコミュニケーション科の授業で)読み聞かせをしたあと、実際に生活科で育てた野菜を切って、たねの有無や数を確認する。紹介してもらう本に断面図などが載っていると、児童が「この野菜ならたねはきっとあそこにある。」など想像しやすく、仮説をたてられそうである。
提示資料 「たねのさくせん」を確認する過程で提供した資料から抜粋。
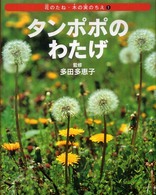
『花のたね・木の実のちえ① タンポポのわたげ』 多田多恵子監修 偕成社 2008年 シリーズ全5巻。タンポポ・スミレとアリ・モミジ・ドングリとリス・オナモミなどの植物が、たねを遠くに運んでもらうための工夫を写真と共に紹介しています。文字も大きく、ルビもあるので、2年生でも1人で読む事ができます。 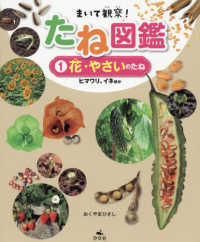
『まいて観察!たね図鑑』 おくやまひさし著 汐文社 2018年 シリーズ全3巻。様々なたねについて、たねの作られ方や本当の大きさなども載っているので、まとめるワークなどの時間に活用できます。
ルビあり。 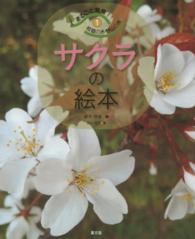
まるごと発見!校庭の木・野山の木 ①サクラの絵本』 勝木俊雄・編 森谷明子・絵 農山漁村文化協会 2015年 シリーズ全8巻。木の生き方・種類についてだけではなく、木の文化や歴史などにも触れています。
情報量が多いので、目次と索引を活用して欲しい情報を探すようにフォローが必要な場合もあります。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.shinga-farm.com/study/ota-science-school/ ブックリスト タネのふしぎ提供資料リスト.xlsx
キーワード1 タネ キーワード2 植物 キーワード3 授業計画・指導案等 2年SC科「たねのふしぎ」 最終指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 宮田知恵 沼田瑞樹 授業者コメント ・SC科「たねのふしぎ」の学習と生活科の学習を繋ぐための役割として野呂先生に協力をしていただいた。生活科で野菜を育てたけれど、たねはどこにあるのか、野菜のなかにあるあのつぶつぶは、何だったんのか疑問に思うきっかけをつくってもらった。絵本なので、クイズ形式で楽しくきっかけをつかめた。
・学習を進め、自分達で学校の中の好きな木や草花を決め、調べ学習をするのに、野呂先生が用意してくれた本のセレクトがよく、子供たちがとてもよく活用していた。野呂先生が、事前に担任へどんな本がよいか、また、学校の中にどんな木があるかをリサーチしてくれたおかげだと思っている。
・わからないことがあれば、本を見れば分かると子供たちが感じるようになった。
・道をあるいていても、いろいろなたねを拾ってくるようになった。
・家で眠っていたであろう「花」「植物」などの辞典を学校に持ってきて調べ学習に使っている児童が何人かいた。きっと家の人がためになるからと買ったものだと思う。 司書・司書教諭コメント 普段から見慣れている野菜や果物も、「やさいのおなか」「くだものなんだ」を読む中で改めて「あれは、タネなのかな。」と疑問に感じている児童も多かった。
「タネのさくせん」を実際に本で確認したり、調べる過程では、事前に図鑑の使い方を指導する時間を図書の時間で取れていたことが良かったように思う。
また2年生の図書の時間や図書だよりなどで、「わんぱくだんのどんぐりまつり」や「どんぐりむら」シリーズ、エリック・カールの「ちいさなタネ」などを紹介、また設置したことで、こうした木の実などが登場する読み物に手を出す子も多くいた。 情報提供校 大田区立清水窪小学校 事例作成日 事例作成 2021年2月19日 /授業実践 2020年10月28日 事例作成者氏名 大田区立清水窪小学校 読書学習司書 野呂 昭子
記入者:村上
カウンタ
3863504 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0379 校種 小学校 教科・領域等 その他 単元 たねのふしぎ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 読み聞かせ・資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 単元の導入として、普段見慣れている野菜や果物のたねに興味を持てる絵本を紹介してほしい。またタネの運ばれ方などを児童が調べて確認できる資料を提供してほしい。
授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 (大田区立清水窪小学校の教科:サイエンスコミュニケーション科の授業で)読み聞かせをしたあと、実際に生活科で育てた野菜を切って、たねの有無や数を確認する。紹介してもらう本に断面図などが載っていると、児童が「この野菜ならたねはきっとあそこにある。」など想像しやすく、仮説をたてられそうである。
提示資料 「たねのさくせん」を確認する過程で提供した資料から抜粋。
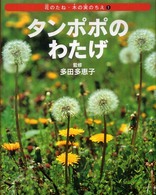
『花のたね・木の実のちえ① タンポポのわたげ』 多田多恵子監修 偕成社 2008年 シリーズ全5巻。タンポポ・スミレとアリ・モミジ・ドングリとリス・オナモミなどの植物が、たねを遠くに運んでもらうための工夫を写真と共に紹介しています。文字も大きく、ルビもあるので、2年生でも1人で読む事ができます。 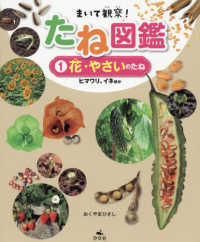
『まいて観察!たね図鑑』 おくやまひさし著 汐文社 2018年 シリーズ全3巻。様々なたねについて、たねの作られ方や本当の大きさなども載っているので、まとめるワークなどの時間に活用できます。
ルビあり。 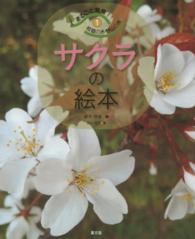
まるごと発見!校庭の木・野山の木 ①サクラの絵本』 勝木俊雄・編 森谷明子・絵 農山漁村文化協会 2015年 シリーズ全8巻。木の生き方・種類についてだけではなく、木の文化や歴史などにも触れています。
情報量が多いので、目次と索引を活用して欲しい情報を探すようにフォローが必要な場合もあります。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.shinga-farm.com/study/ota-science-school/ ブックリスト タネのふしぎ提供資料リスト.xlsx
キーワード1 タネ キーワード2 植物 キーワード3 授業計画・指導案等 2年SC科「たねのふしぎ」 最終指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 宮田知恵 沼田瑞樹 授業者コメント ・SC科「たねのふしぎ」の学習と生活科の学習を繋ぐための役割として野呂先生に協力をしていただいた。生活科で野菜を育てたけれど、たねはどこにあるのか、野菜のなかにあるあのつぶつぶは、何だったんのか疑問に思うきっかけをつくってもらった。絵本なので、クイズ形式で楽しくきっかけをつかめた。
・学習を進め、自分達で学校の中の好きな木や草花を決め、調べ学習をするのに、野呂先生が用意してくれた本のセレクトがよく、子供たちがとてもよく活用していた。野呂先生が、事前に担任へどんな本がよいか、また、学校の中にどんな木があるかをリサーチしてくれたおかげだと思っている。
・わからないことがあれば、本を見れば分かると子供たちが感じるようになった。
・道をあるいていても、いろいろなたねを拾ってくるようになった。
・家で眠っていたであろう「花」「植物」などの辞典を学校に持ってきて調べ学習に使っている児童が何人かいた。きっと家の人がためになるからと買ったものだと思う。 司書・司書教諭コメント 普段から見慣れている野菜や果物も、「やさいのおなか」「くだものなんだ」を読む中で改めて「あれは、タネなのかな。」と疑問に感じている児童も多かった。
「タネのさくせん」を実際に本で確認したり、調べる過程では、事前に図鑑の使い方を指導する時間を図書の時間で取れていたことが良かったように思う。
また2年生の図書の時間や図書だよりなどで、「わんぱくだんのどんぐりまつり」や「どんぐりむら」シリーズ、エリック・カールの「ちいさなタネ」などを紹介、また設置したことで、こうした木の実などが登場する読み物に手を出す子も多くいた。 情報提供校 大田区立清水窪小学校 事例作成日 事例作成 2021年2月19日 /授業実践 2020年10月28日 事例作成者氏名 大田区立清水窪小学校 読書学習司書 野呂 昭子
記入者:村上
カウンタ
3863504 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0379 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | その他 |
| 単元 | たねのふしぎ |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 読み聞かせ・資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 単元の導入として、普段見慣れている野菜や果物のたねに興味を持てる絵本を紹介してほしい。またタネの運ばれ方などを児童が調べて確認できる資料を提供してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | (大田区立清水窪小学校の教科:サイエンスコミュニケーション科の授業で)読み聞かせをしたあと、実際に生活科で育てた野菜を切って、たねの有無や数を確認する。紹介してもらう本に断面図などが載っていると、児童が「この野菜ならたねはきっとあそこにある。」など想像しやすく、仮説をたてられそうである。 |
| 提示資料 | 「たねのさくせん」を確認する過程で提供した資料から抜粋。 |
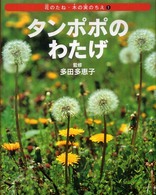 | 『花のたね・木の実のちえ① タンポポのわたげ』 多田多恵子監修 偕成社 2008年 シリーズ全5巻。タンポポ・スミレとアリ・モミジ・ドングリとリス・オナモミなどの植物が、たねを遠くに運んでもらうための工夫を写真と共に紹介しています。文字も大きく、ルビもあるので、2年生でも1人で読む事ができます。 |
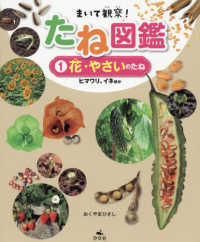 | 『まいて観察!たね図鑑』 おくやまひさし著 汐文社 2018年 シリーズ全3巻。様々なたねについて、たねの作られ方や本当の大きさなども載っているので、まとめるワークなどの時間に活用できます。 ルビあり。 |
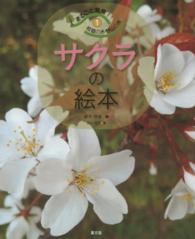 | まるごと発見!校庭の木・野山の木 ①サクラの絵本』 勝木俊雄・編 森谷明子・絵 農山漁村文化協会 2015年 シリーズ全8巻。木の生き方・種類についてだけではなく、木の文化や歴史などにも触れています。 情報量が多いので、目次と索引を活用して欲しい情報を探すようにフォローが必要な場合もあります。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https://www.shinga-farm.com/study/ota-science-school/ |
| ブックリスト | タネのふしぎ提供資料リスト.xlsx |
| キーワード1 | タネ |
| キーワード2 | 植物 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | 2年SC科「たねのふしぎ」 最終指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 宮田知恵 沼田瑞樹 |
| 授業者コメント | ・SC科「たねのふしぎ」の学習と生活科の学習を繋ぐための役割として野呂先生に協力をしていただいた。生活科で野菜を育てたけれど、たねはどこにあるのか、野菜のなかにあるあのつぶつぶは、何だったんのか疑問に思うきっかけをつくってもらった。絵本なので、クイズ形式で楽しくきっかけをつかめた。 ・学習を進め、自分達で学校の中の好きな木や草花を決め、調べ学習をするのに、野呂先生が用意してくれた本のセレクトがよく、子供たちがとてもよく活用していた。野呂先生が、事前に担任へどんな本がよいか、また、学校の中にどんな木があるかをリサーチしてくれたおかげだと思っている。 ・わからないことがあれば、本を見れば分かると子供たちが感じるようになった。 ・道をあるいていても、いろいろなたねを拾ってくるようになった。 ・家で眠っていたであろう「花」「植物」などの辞典を学校に持ってきて調べ学習に使っている児童が何人かいた。きっと家の人がためになるからと買ったものだと思う。 |
| 司書・司書教諭コメント | 普段から見慣れている野菜や果物も、「やさいのおなか」「くだものなんだ」を読む中で改めて「あれは、タネなのかな。」と疑問に感じている児童も多かった。 「タネのさくせん」を実際に本で確認したり、調べる過程では、事前に図鑑の使い方を指導する時間を図書の時間で取れていたことが良かったように思う。 また2年生の図書の時間や図書だよりなどで、「わんぱくだんのどんぐりまつり」や「どんぐりむら」シリーズ、エリック・カールの「ちいさなタネ」などを紹介、また設置したことで、こうした木の実などが登場する読み物に手を出す子も多くいた。 |
| 情報提供校 | 大田区立清水窪小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成 2021年2月19日 /授業実践 2020年10月28日 |
| 事例作成者氏名 | 大田区立清水窪小学校 読書学習司書 野呂 昭子 |
記入者:村上

























