お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0385 校種 高校 教科・領域等 家庭 単元 子どもの生活習慣 対象学年 高2 活用・支援の種類 絵本についてのレクチャー、資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもの発達と絵本の関りについて話をしてほしい。また、学習期間を通しての継続的資料提供及び生徒への読み聞かせのアドバイスをお願いしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 2学期から、授業の初めに生徒に一人ずつ読み聞かせをさせたいと考えている。絵本の読み聞かせをするに当たり、絵本と子どもの発達との関わりや絵本の特徴、読み聞かせのコツなどを紹介してもらいたい。手法はお任せする。
提示資料 特に生徒に伝えたいと司書が考えた3冊をピックアップ。 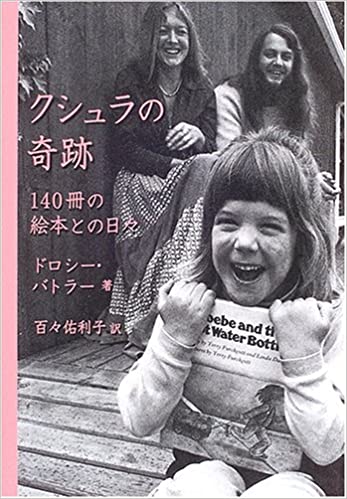
『クシュラの奇跡』 ドロシー・バトラー著 百々祐利子訳 のら書房 2006
本書は、染色体の異常により複雑で重い障害を抱えたクシュラの成長の記録です。腎臓や心臓、視力などの多重障害をもって生まれたクシュラをケアする両親は、発作に苦しみ眠ることさえままならない我が子の辛い時間を少しでも緩和できるようにとの思いで生後4か月ごろから絵本の読み聞かせを始めます。その結果、知的障害も疑われていたにも関わらずクシュラの知的水準は平均を上回る発達をします。原著は研究論文として執筆されたものですが、この本は普及版として読みやすくなっています。子どもの発達に絵本がいかに大きな力をもつかを実証している本です。将来保育園や幼稚園の先生になりたいと考えている人には必ず読んでもらいたい1冊です。 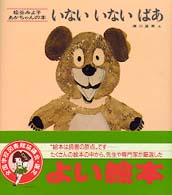
『いないないばあ』 松谷みよ子文 瀬川康夫 絵 童心社 1967
いろんな作家さんが「ないいないばぁ」の仕掛け絵本を描いていますがこの本はその中でも1967年発行のロングセラーで発行部数680万部を超える、日本で一番売れている絵本です。(トーハンミリオンブック2020調べ) 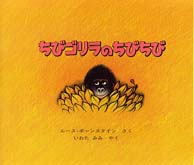
『ちびゴリラのちびちび』 ルース・ボーンスタイン 作 いわたみみ 訳 ほるぷ出版 1978
ジャングルに生まれたゴリラは、仲間の動物たちみんなに好かれています。カバ、ライオン、キリン、ヘビ……森の動物たちとちびゴリラの交遊をユーモラスに描いています。(出版社HPより)どのぺージも「大好きだよ!」という気持ちが伝わってくる絵本です。お父さん、お母さんになったらぜひわが子に読んであげて欲しい1冊です。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.bookstart.or.jp/ ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 ブックスタート 授業計画・指導案等 子どもの発達と保育資料.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 遠藤里子教諭 授業者コメント 子どもの基本的習慣や社会的習慣の中での絵本の果たす役割や関りについて理解を深めることを目的に、今回の授業を構想した。
生徒は子どもの発達と絵本とも密接な関りについて、本の専門家である司書に話をしてもらうことで、改めて認識できたと思う。特に『ちびゴリラのちびちび』の実体験の話は感動した。やはり実体験は説得力が違う。次年度は4月に行い、年間を通して生徒が読み聞かせに携われるようにしたい。 司書・司書教諭コメント 教員には、本の特徴に加え、自治体のブックスタートで話をしていた内容で、絵本が子どもの発達にどのような影響を耐えるのか、その良さを紹介し、その後ブックトークするのはどうかと提案した。ブックトークの内容は、与えられた時間にあわせて調整をするので、1コマの中でどのくらい時間を使えるか。また、紹介する絵本について発達段階により絞る必要があれば、紹介を希望する年齢層を知りたいと、伝えた。
実際の授業では、絵本の特徴だけでなく、発達段階に応じた読み聞かせについて、ブックスタートなどの取り組み事例をからめて紹介した。資料は配付するだけでなく、ホワイトボードに掲示できればよかった。今回依頼をうけたのが1週間前だったため、準備不足が否めなかった。 情報提供校 群馬県立利根実業高等学校 事例作成日 事例作成30年10月18日 /授業実践 平成27年10月16日 事例作成者氏名 学校司書 近藤信子
記入者:村上
カウンタ
3863461 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0385 校種 高校 教科・領域等 家庭 単元 子どもの生活習慣 対象学年 高2 活用・支援の種類 絵本についてのレクチャー、資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 子どもの発達と絵本の関りについて話をしてほしい。また、学習期間を通しての継続的資料提供及び生徒への読み聞かせのアドバイスをお願いしたい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 2学期から、授業の初めに生徒に一人ずつ読み聞かせをさせたいと考えている。絵本の読み聞かせをするに当たり、絵本と子どもの発達との関わりや絵本の特徴、読み聞かせのコツなどを紹介してもらいたい。手法はお任せする。
提示資料 特に生徒に伝えたいと司書が考えた3冊をピックアップ。 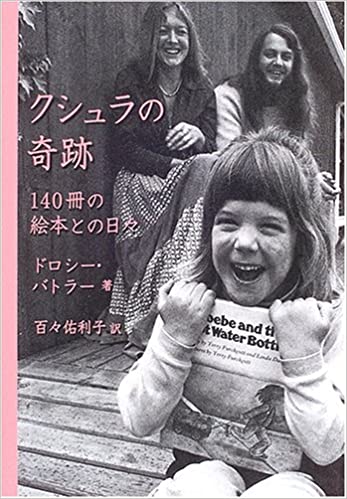
『クシュラの奇跡』 ドロシー・バトラー著 百々祐利子訳 のら書房 2006
本書は、染色体の異常により複雑で重い障害を抱えたクシュラの成長の記録です。腎臓や心臓、視力などの多重障害をもって生まれたクシュラをケアする両親は、発作に苦しみ眠ることさえままならない我が子の辛い時間を少しでも緩和できるようにとの思いで生後4か月ごろから絵本の読み聞かせを始めます。その結果、知的障害も疑われていたにも関わらずクシュラの知的水準は平均を上回る発達をします。原著は研究論文として執筆されたものですが、この本は普及版として読みやすくなっています。子どもの発達に絵本がいかに大きな力をもつかを実証している本です。将来保育園や幼稚園の先生になりたいと考えている人には必ず読んでもらいたい1冊です。 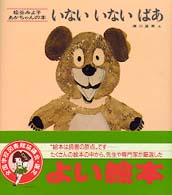
『いないないばあ』 松谷みよ子文 瀬川康夫 絵 童心社 1967
いろんな作家さんが「ないいないばぁ」の仕掛け絵本を描いていますがこの本はその中でも1967年発行のロングセラーで発行部数680万部を超える、日本で一番売れている絵本です。(トーハンミリオンブック2020調べ) 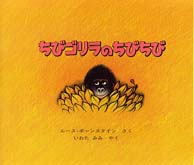
『ちびゴリラのちびちび』 ルース・ボーンスタイン 作 いわたみみ 訳 ほるぷ出版 1978
ジャングルに生まれたゴリラは、仲間の動物たちみんなに好かれています。カバ、ライオン、キリン、ヘビ……森の動物たちとちびゴリラの交遊をユーモラスに描いています。(出版社HPより)どのぺージも「大好きだよ!」という気持ちが伝わってくる絵本です。お父さん、お母さんになったらぜひわが子に読んであげて欲しい1冊です。 参考資料(含HP) 参考資料リンク https://www.bookstart.or.jp/ ブックリスト
キーワード1 絵本 キーワード2 読み聞かせ キーワード3 ブックスタート 授業計画・指導案等 子どもの発達と保育資料.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 遠藤里子教諭 授業者コメント 子どもの基本的習慣や社会的習慣の中での絵本の果たす役割や関りについて理解を深めることを目的に、今回の授業を構想した。
生徒は子どもの発達と絵本とも密接な関りについて、本の専門家である司書に話をしてもらうことで、改めて認識できたと思う。特に『ちびゴリラのちびちび』の実体験の話は感動した。やはり実体験は説得力が違う。次年度は4月に行い、年間を通して生徒が読み聞かせに携われるようにしたい。 司書・司書教諭コメント 教員には、本の特徴に加え、自治体のブックスタートで話をしていた内容で、絵本が子どもの発達にどのような影響を耐えるのか、その良さを紹介し、その後ブックトークするのはどうかと提案した。ブックトークの内容は、与えられた時間にあわせて調整をするので、1コマの中でどのくらい時間を使えるか。また、紹介する絵本について発達段階により絞る必要があれば、紹介を希望する年齢層を知りたいと、伝えた。
実際の授業では、絵本の特徴だけでなく、発達段階に応じた読み聞かせについて、ブックスタートなどの取り組み事例をからめて紹介した。資料は配付するだけでなく、ホワイトボードに掲示できればよかった。今回依頼をうけたのが1週間前だったため、準備不足が否めなかった。 情報提供校 群馬県立利根実業高等学校 事例作成日 事例作成30年10月18日 /授業実践 平成27年10月16日 事例作成者氏名 学校司書 近藤信子
記入者:村上
カウンタ
3863461 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0385 |
|---|---|
| 校種 | 高校 |
| 教科・領域等 | 家庭 |
| 単元 | 子どもの生活習慣 |
| 対象学年 | 高2 |
| 活用・支援の種類 | 絵本についてのレクチャー、資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 子どもの発達と絵本の関りについて話をしてほしい。また、学習期間を通しての継続的資料提供及び生徒への読み聞かせのアドバイスをお願いしたい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 2学期から、授業の初めに生徒に一人ずつ読み聞かせをさせたいと考えている。絵本の読み聞かせをするに当たり、絵本と子どもの発達との関わりや絵本の特徴、読み聞かせのコツなどを紹介してもらいたい。手法はお任せする。 |
| 提示資料 | 特に生徒に伝えたいと司書が考えた3冊をピックアップ。 |
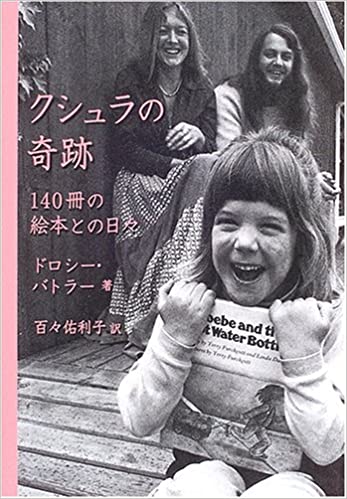 | 『クシュラの奇跡』 ドロシー・バトラー著 百々祐利子訳 のら書房 2006 本書は、染色体の異常により複雑で重い障害を抱えたクシュラの成長の記録です。腎臓や心臓、視力などの多重障害をもって生まれたクシュラをケアする両親は、発作に苦しみ眠ることさえままならない我が子の辛い時間を少しでも緩和できるようにとの思いで生後4か月ごろから絵本の読み聞かせを始めます。その結果、知的障害も疑われていたにも関わらずクシュラの知的水準は平均を上回る発達をします。原著は研究論文として執筆されたものですが、この本は普及版として読みやすくなっています。子どもの発達に絵本がいかに大きな力をもつかを実証している本です。将来保育園や幼稚園の先生になりたいと考えている人には必ず読んでもらいたい1冊です。 |
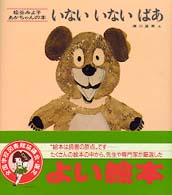 | 『いないないばあ』 松谷みよ子文 瀬川康夫 絵 童心社 1967 いろんな作家さんが「ないいないばぁ」の仕掛け絵本を描いていますがこの本はその中でも1967年発行のロングセラーで発行部数680万部を超える、日本で一番売れている絵本です。(トーハンミリオンブック2020調べ) |
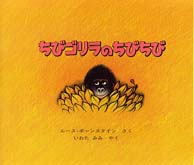 | 『ちびゴリラのちびちび』 ルース・ボーンスタイン 作 いわたみみ 訳 ほるぷ出版 1978 ジャングルに生まれたゴリラは、仲間の動物たちみんなに好かれています。カバ、ライオン、キリン、ヘビ……森の動物たちとちびゴリラの交遊をユーモラスに描いています。(出版社HPより)どのぺージも「大好きだよ!」という気持ちが伝わってくる絵本です。お父さん、お母さんになったらぜひわが子に読んであげて欲しい1冊です。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | https://www.bookstart.or.jp/ |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 絵本 |
| キーワード2 | 読み聞かせ |
| キーワード3 | ブックスタート |
| 授業計画・指導案等 | 子どもの発達と保育資料.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 遠藤里子教諭 |
| 授業者コメント | 子どもの基本的習慣や社会的習慣の中での絵本の果たす役割や関りについて理解を深めることを目的に、今回の授業を構想した。 生徒は子どもの発達と絵本とも密接な関りについて、本の専門家である司書に話をしてもらうことで、改めて認識できたと思う。特に『ちびゴリラのちびちび』の実体験の話は感動した。やはり実体験は説得力が違う。次年度は4月に行い、年間を通して生徒が読み聞かせに携われるようにしたい。 |
| 司書・司書教諭コメント | 教員には、本の特徴に加え、自治体のブックスタートで話をしていた内容で、絵本が子どもの発達にどのような影響を耐えるのか、その良さを紹介し、その後ブックトークするのはどうかと提案した。ブックトークの内容は、与えられた時間にあわせて調整をするので、1コマの中でどのくらい時間を使えるか。また、紹介する絵本について発達段階により絞る必要があれば、紹介を希望する年齢層を知りたいと、伝えた。 実際の授業では、絵本の特徴だけでなく、発達段階に応じた読み聞かせについて、ブックスタートなどの取り組み事例をからめて紹介した。資料は配付するだけでなく、ホワイトボードに掲示できればよかった。今回依頼をうけたのが1週間前だったため、準備不足が否めなかった。 |
| 情報提供校 | 群馬県立利根実業高等学校 |
| 事例作成日 | 事例作成30年10月18日 /授業実践 平成27年10月16日 |
| 事例作成者氏名 | 学校司書 近藤信子 |
記入者:村上

























