お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0392 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書課題 対象学年 中2 活用・支援の種類 授業提案、授業内容の相談、ブックリストの提供と本の紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 春休み中に、戦争に関する資料を一冊選んで、その本が誰の視点で書かれているかを意識して読み、教員の設定した課題に、答える。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 司書としては、図書館にある様々なタイプの戦争に関する本を読んでもらう機会にしたいと考え、提案してみた。国語科としては、どうやってその資料にいきついたか、その本の特徴や戦争に関する本を読むときに留意するべきことは何か、また戦争に関する本のタイトルの特徴などを考えさせる課題を設定し、これから20世紀の大戦を学ぶ社会科との連携も意識した。
提示資料 図書館で実際に資料を選ぶ時間を設けたが、その時に使った資料や、司書が紹介した本から3冊を選んだ。 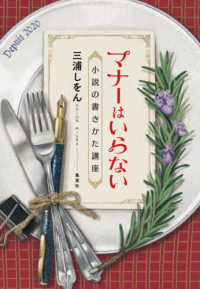
『マナーはいらない;小説の書き方講座』 三浦しをん著 この本は、副題にもあるように小説を書きたい人のための指南書である。今回そのなかに、人称について取り上げているページがあったため、教員と相談してその部分のみ複製して授業内で配布して読んでもらった。 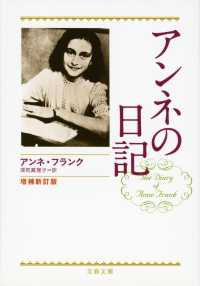
『新装版 アンネの日記」 アンネ・フランク著 文春文庫 リストにあげた本のなかから数冊紹介したが、そのうちの1冊。ちょうど同じ年齢ということもあり、よく聞いてくれた。収容所を生き延びたアンネの父が、存命中は公表されていなかった箇所も、現在はすべて掲載されていることなども伝えた。この本も含め、アンネに関する本を選んだ生徒が12人もいたことから、アンネ・フランクの存在の大きさを感じた。 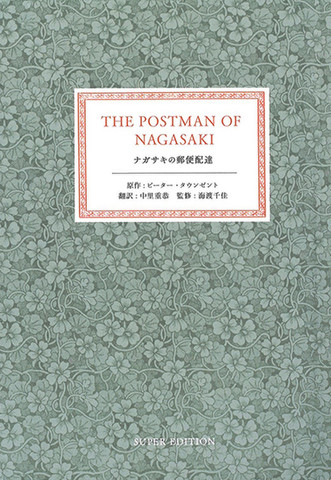
『ナガサキの郵便配達』ピーター・タウンゼント原作 中里重恭訳 海渡千佳監修 ナガサキの郵便配達プロジェクト制作 2018
主人公、谷口稜曄さんは、16歳の時、郵便配達の仕事中に被爆し、熱線で背中一面に重い火傷を負う。奇跡的に命を取り留めたとはいえ、うつぶせのまま身動きひとつできず、激しい痛みと闘う壮絶な日々を過ごす。40歳を過ぎ、少年だった自分の焼けだたれた背中を映し出す映像の存在を知り、以後被爆体験を語り始めたのだった。この本の存在を知ったのは昨年のこと。ブックトークで紹介したところ、読んでくれた生徒がいて嬉しかった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 73回生が選んだ戦争関連書籍.xlsx
キーワード1 戦争 キーワード2 人称 キーワード3 タイトル 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 渡邉裕 授業者コメント この取り組みのまえに、文学作品の「虚構性」と語りや人称について考える単元を行っている。今回の取り組みでは、それを踏まえ選択した本とその内容についてのとらえ方について、人称に関連付けた分析があった点が、この授業を通じて具体化して把握することができた、子どもたちに根付いたものである。
例えば、エッセイやノンフィクションというジャンルが持つ「事実」について、「一人称」ということを結びつけ、その「切り取られたものの可能性」についても自分たちで気づき、言及していく様子が見られた。またここから、選択の幅を持つテーマ設定を行い、読書活動と授業を連動させる取り組みを行えたことで、ジャンルの特性も自分たちの力で把握していくことにもつなげることができた。これには、それを可能にしてもらえる蔵書の蓄積(授業での活用という点での「学校図書館の体力」のような)ということの重要性を再確認した。
入り口は課題読書というオーソドックスなものであるが、テーマ設定について学校図書館からの提案を生かし既習事項との結びつきを作れた点、社会科の先生と情報共有したことで、このあと社会科のスピーチの取り組みでも活用してもらえる可能性を提示できた点、またこのようような取り組みを行えたことで、課題読書を介しての他教科との連携の可能性といった、今後の可能性や気づきといったものも一つの成果であると考える。 司書・司書教諭コメント 3学期最後の国語の授業を図書館で行い、生徒には図書館に所蔵してある戦争関連のブックリストを配布し、司書から短いブックトークを行った。読む本は図書館の本にこだわらず選んでもらったが、「選択した本」にどのようにたどりついたかを記述してもらった。リストから読みたい本を絞り込む生徒、実際にコーナーにある本を見て決める生徒、書店や図書館の棚をめぐる生徒、PCで検索してさらに情報を得る生徒、家の蔵書から選ぶ生徒など、さまざまだったが、皆適当に選ぶのではなく、それぞれに何らかの意味付けがあって選んでいることがわかる。読書課題に選択の余地があることは大切だと感じた。また、今回、ノンフィクション、国内外の小説、絵本といった多様なジャンルの戦争に関する本を読んでもらえる機会となった。どのような視点から書かれた本なのかまでを考えて、コメントを書き込んでいる様子に、中学3年生の成長を感じる。社会科の授業で、さらに深く学んでいくことで、また違った本にも手をのばしてもらえるのではないだろうか。今回の課題の提出は、Microsoft teamsのFormsを利用したため、司書も生徒の提出した課題を共有できたこともよかった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2021.10.10 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863523 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0392 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 読書課題 対象学年 中2 活用・支援の種類 授業提案、授業内容の相談、ブックリストの提供と本の紹介 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 春休み中に、戦争に関する資料を一冊選んで、その本が誰の視点で書かれているかを意識して読み、教員の設定した課題に、答える。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 司書としては、図書館にある様々なタイプの戦争に関する本を読んでもらう機会にしたいと考え、提案してみた。国語科としては、どうやってその資料にいきついたか、その本の特徴や戦争に関する本を読むときに留意するべきことは何か、また戦争に関する本のタイトルの特徴などを考えさせる課題を設定し、これから20世紀の大戦を学ぶ社会科との連携も意識した。
提示資料 図書館で実際に資料を選ぶ時間を設けたが、その時に使った資料や、司書が紹介した本から3冊を選んだ。 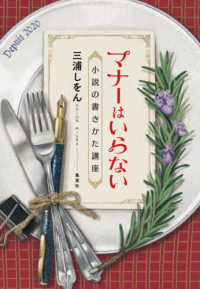
『マナーはいらない;小説の書き方講座』 三浦しをん著 この本は、副題にもあるように小説を書きたい人のための指南書である。今回そのなかに、人称について取り上げているページがあったため、教員と相談してその部分のみ複製して授業内で配布して読んでもらった。 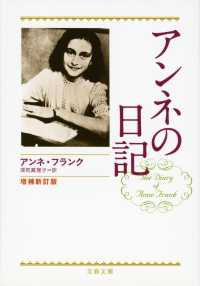
『新装版 アンネの日記」 アンネ・フランク著 文春文庫 リストにあげた本のなかから数冊紹介したが、そのうちの1冊。ちょうど同じ年齢ということもあり、よく聞いてくれた。収容所を生き延びたアンネの父が、存命中は公表されていなかった箇所も、現在はすべて掲載されていることなども伝えた。この本も含め、アンネに関する本を選んだ生徒が12人もいたことから、アンネ・フランクの存在の大きさを感じた。 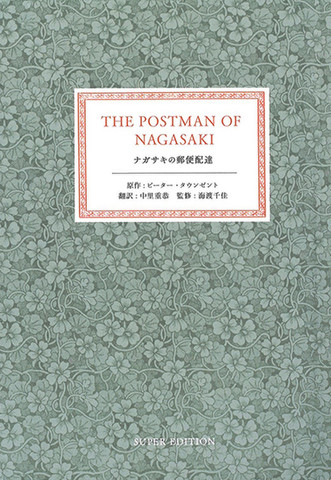
『ナガサキの郵便配達』ピーター・タウンゼント原作 中里重恭訳 海渡千佳監修 ナガサキの郵便配達プロジェクト制作 2018
主人公、谷口稜曄さんは、16歳の時、郵便配達の仕事中に被爆し、熱線で背中一面に重い火傷を負う。奇跡的に命を取り留めたとはいえ、うつぶせのまま身動きひとつできず、激しい痛みと闘う壮絶な日々を過ごす。40歳を過ぎ、少年だった自分の焼けだたれた背中を映し出す映像の存在を知り、以後被爆体験を語り始めたのだった。この本の存在を知ったのは昨年のこと。ブックトークで紹介したところ、読んでくれた生徒がいて嬉しかった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 73回生が選んだ戦争関連書籍.xlsx
キーワード1 戦争 キーワード2 人称 キーワード3 タイトル 授業計画・指導案等 児童・生徒の作品 http:// 授業者 渡邉裕 授業者コメント この取り組みのまえに、文学作品の「虚構性」と語りや人称について考える単元を行っている。今回の取り組みでは、それを踏まえ選択した本とその内容についてのとらえ方について、人称に関連付けた分析があった点が、この授業を通じて具体化して把握することができた、子どもたちに根付いたものである。
例えば、エッセイやノンフィクションというジャンルが持つ「事実」について、「一人称」ということを結びつけ、その「切り取られたものの可能性」についても自分たちで気づき、言及していく様子が見られた。またここから、選択の幅を持つテーマ設定を行い、読書活動と授業を連動させる取り組みを行えたことで、ジャンルの特性も自分たちの力で把握していくことにもつなげることができた。これには、それを可能にしてもらえる蔵書の蓄積(授業での活用という点での「学校図書館の体力」のような)ということの重要性を再確認した。
入り口は課題読書というオーソドックスなものであるが、テーマ設定について学校図書館からの提案を生かし既習事項との結びつきを作れた点、社会科の先生と情報共有したことで、このあと社会科のスピーチの取り組みでも活用してもらえる可能性を提示できた点、またこのようような取り組みを行えたことで、課題読書を介しての他教科との連携の可能性といった、今後の可能性や気づきといったものも一つの成果であると考える。 司書・司書教諭コメント 3学期最後の国語の授業を図書館で行い、生徒には図書館に所蔵してある戦争関連のブックリストを配布し、司書から短いブックトークを行った。読む本は図書館の本にこだわらず選んでもらったが、「選択した本」にどのようにたどりついたかを記述してもらった。リストから読みたい本を絞り込む生徒、実際にコーナーにある本を見て決める生徒、書店や図書館の棚をめぐる生徒、PCで検索してさらに情報を得る生徒、家の蔵書から選ぶ生徒など、さまざまだったが、皆適当に選ぶのではなく、それぞれに何らかの意味付けがあって選んでいることがわかる。読書課題に選択の余地があることは大切だと感じた。また、今回、ノンフィクション、国内外の小説、絵本といった多様なジャンルの戦争に関する本を読んでもらえる機会となった。どのような視点から書かれた本なのかまでを考えて、コメントを書き込んでいる様子に、中学3年生の成長を感じる。社会科の授業で、さらに深く学んでいくことで、また違った本にも手をのばしてもらえるのではないだろうか。今回の課題の提出は、Microsoft teamsのFormsを利用したため、司書も生徒の提出した課題を共有できたこともよかった。 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2021.10.10 事例作成者氏名 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863523 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0392 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 読書課題 |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 授業提案、授業内容の相談、ブックリストの提供と本の紹介 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 春休み中に、戦争に関する資料を一冊選んで、その本が誰の視点で書かれているかを意識して読み、教員の設定した課題に、答える。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 司書としては、図書館にある様々なタイプの戦争に関する本を読んでもらう機会にしたいと考え、提案してみた。国語科としては、どうやってその資料にいきついたか、その本の特徴や戦争に関する本を読むときに留意するべきことは何か、また戦争に関する本のタイトルの特徴などを考えさせる課題を設定し、これから20世紀の大戦を学ぶ社会科との連携も意識した。 |
| 提示資料 | 図書館で実際に資料を選ぶ時間を設けたが、その時に使った資料や、司書が紹介した本から3冊を選んだ。 |
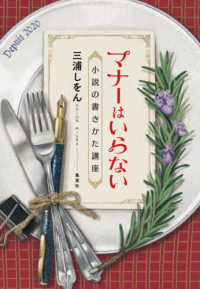 | 『マナーはいらない;小説の書き方講座』 三浦しをん著 この本は、副題にもあるように小説を書きたい人のための指南書である。今回そのなかに、人称について取り上げているページがあったため、教員と相談してその部分のみ複製して授業内で配布して読んでもらった。 |
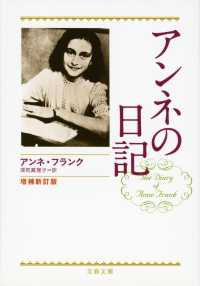 | 『新装版 アンネの日記」 アンネ・フランク著 文春文庫 リストにあげた本のなかから数冊紹介したが、そのうちの1冊。ちょうど同じ年齢ということもあり、よく聞いてくれた。収容所を生き延びたアンネの父が、存命中は公表されていなかった箇所も、現在はすべて掲載されていることなども伝えた。この本も含め、アンネに関する本を選んだ生徒が12人もいたことから、アンネ・フランクの存在の大きさを感じた。 |
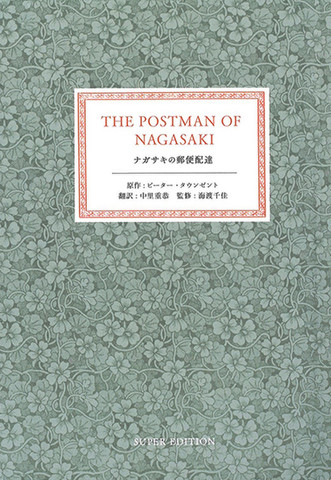 | 『ナガサキの郵便配達』ピーター・タウンゼント原作 中里重恭訳 海渡千佳監修 ナガサキの郵便配達プロジェクト制作 2018 主人公、谷口稜曄さんは、16歳の時、郵便配達の仕事中に被爆し、熱線で背中一面に重い火傷を負う。奇跡的に命を取り留めたとはいえ、うつぶせのまま身動きひとつできず、激しい痛みと闘う壮絶な日々を過ごす。40歳を過ぎ、少年だった自分の焼けだたれた背中を映し出す映像の存在を知り、以後被爆体験を語り始めたのだった。この本の存在を知ったのは昨年のこと。ブックトークで紹介したところ、読んでくれた生徒がいて嬉しかった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 73回生が選んだ戦争関連書籍.xlsx |
| キーワード1 | 戦争 |
| キーワード2 | 人称 |
| キーワード3 | タイトル |
| 授業計画・指導案等 | |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 渡邉裕 |
| 授業者コメント | この取り組みのまえに、文学作品の「虚構性」と語りや人称について考える単元を行っている。今回の取り組みでは、それを踏まえ選択した本とその内容についてのとらえ方について、人称に関連付けた分析があった点が、この授業を通じて具体化して把握することができた、子どもたちに根付いたものである。 例えば、エッセイやノンフィクションというジャンルが持つ「事実」について、「一人称」ということを結びつけ、その「切り取られたものの可能性」についても自分たちで気づき、言及していく様子が見られた。またここから、選択の幅を持つテーマ設定を行い、読書活動と授業を連動させる取り組みを行えたことで、ジャンルの特性も自分たちの力で把握していくことにもつなげることができた。これには、それを可能にしてもらえる蔵書の蓄積(授業での活用という点での「学校図書館の体力」のような)ということの重要性を再確認した。 入り口は課題読書というオーソドックスなものであるが、テーマ設定について学校図書館からの提案を生かし既習事項との結びつきを作れた点、社会科の先生と情報共有したことで、このあと社会科のスピーチの取り組みでも活用してもらえる可能性を提示できた点、またこのようような取り組みを行えたことで、課題読書を介しての他教科との連携の可能性といった、今後の可能性や気づきといったものも一つの成果であると考える。 |
| 司書・司書教諭コメント | 3学期最後の国語の授業を図書館で行い、生徒には図書館に所蔵してある戦争関連のブックリストを配布し、司書から短いブックトークを行った。読む本は図書館の本にこだわらず選んでもらったが、「選択した本」にどのようにたどりついたかを記述してもらった。リストから読みたい本を絞り込む生徒、実際にコーナーにある本を見て決める生徒、書店や図書館の棚をめぐる生徒、PCで検索してさらに情報を得る生徒、家の蔵書から選ぶ生徒など、さまざまだったが、皆適当に選ぶのではなく、それぞれに何らかの意味付けがあって選んでいることがわかる。読書課題に選択の余地があることは大切だと感じた。また、今回、ノンフィクション、国内外の小説、絵本といった多様なジャンルの戦争に関する本を読んでもらえる機会となった。どのような視点から書かれた本なのかまでを考えて、コメントを書き込んでいる様子に、中学3年生の成長を感じる。社会科の授業で、さらに深く学んでいくことで、また違った本にも手をのばしてもらえるのではないだろうか。今回の課題の提出は、Microsoft teamsのFormsを利用したため、司書も生徒の提出した課題を共有できたこともよかった。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2021.10.10 |
| 事例作成者氏名 | 村上恭子 |
記入者:村上

























