お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0030 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 たんぽぽ の くらべよみ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 比べ読み 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) たんぽぽを描いた3冊の絵本があるが、授業で使えないか。(図書館からの提案) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 たんぽぽの生態を表わすのに、全く違ったアプローチをしている絵本2冊を毎年小学校2年生の春に読み聞かせていた。その後、写真絵本も出版された。これらを題材に授業をつくってもらいたかった。
提示資料 たんぽぽ絵本 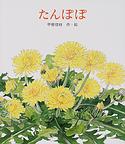
『たんぽぽ』
甲斐信枝 金の星社 1984 ISBN : 4-323-00282-3
たんぽぽが目をさまし、ねむり、おきあがり、とびだす・・・・。擬人法をつかった文学的な表現でたんぽぽの生態を表わす。わた毛が一面にとぶ場面は横に長く開く。 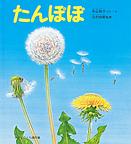
『たんぽぽ』
平山和子 文・絵 北村四郎監修 福音館書店 1992 ISBN : 4-8340-0470-8
たんぽぽが1日のうちに開いたり閉じたりするのは、時間の流れがわかるように絵本のめくりとあわせて左から右へ並べて示され、1つの花は60から240の小さな花の集まりであることを、その小さな花を縦横整列させて数を示す。科学的な解説。
根っこはずっとずっと下まで深く伸びている土の中の様子を縦に長く描いている。

『タンポポのわたげ』(花のたね・木の実のちえ1)
多田多恵子監修 ネイチャー・プロ編集室編著 偕成社 2008 ISBN : 978-4-03-414310-0
子どもたちが日頃目にしているタンポポのについて、日常目にしている風景から、ズームインした写真から花の集まりを表わしたり、綿毛の飛ぶところなど時には叙情的に、写真ならではの伝え方をしている。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 タンポポ キーワード2 比較 キーワード3 授業計画・指導案等 たんぽぽ指導案2009 大塚.jtd 児童・生徒の作品 授業者 大塚健太郎 授業者コメント 情報リテラシーと物語を体感的に読むことの両方を、子どもたちの興味関心のある「たんぽぽ」という素材で狙えるところの価値のある実践になったと考える。甲斐氏の『たんぽぽ』は物語調で書かれており、子どもたちがたんぽぽの一つの花になりきるのに時間はかからなかった。楽しそうに一つの花弁となってたんぽぽの一生を演じ、たんぽぽを体で感じた読書であった。
その後、説明的文章調の平山氏の絵本に出会うと、より細かい数字など情報に探索者としての気持ちが芽生えてくる読書であった。そして、その二人の違いは、ものの見方・表現の違いを感じることになるのである。2冊を比べることで、子どもの好きな文体がはっきりし、また、全く印象のことなる絵本に出会ったことで、調べ物をするときには複数の本にあたることがたいせつであることも感じられた。 司書・司書教諭コメント 3冊の読み比べをした年は、写真は2年生の子どもたちには強い印象を与えすぎるようだった。絵が語ること、絵で表現されていることの読み取りが、しっかりできるようになってから、写真絵本と出会いたいと感じている。甲斐さんはカントウタンポポを描き、平山さんはセイヨウタンポポを描いている。本文には何も書いていないが、たまに知っていて教えてくれる子がいる。実は編集は同じ人。多田さんの写真絵本の巻末では、その違いを教えてくれている。
1つのテーマでいくつかの本を読み比べして欲しいとまとめる。1冊の本ではでていなくても、違う本には出てくる情報もあり、同じ情報でも表現の仕方が違っていることなどをつかんでくれる、よい題材だと思い、ぜひ授業でとりあげてもらいたいと紹介をした。
情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.4.29 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山
カウンタ
3863409 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0030 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 たんぽぽ の くらべよみ 対象学年 低学年 活用・支援の種類 比べ読み 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) たんぽぽを描いた3冊の絵本があるが、授業で使えないか。(図書館からの提案) 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 たんぽぽの生態を表わすのに、全く違ったアプローチをしている絵本2冊を毎年小学校2年生の春に読み聞かせていた。その後、写真絵本も出版された。これらを題材に授業をつくってもらいたかった。
提示資料 たんぽぽ絵本 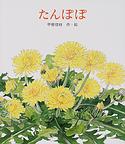
『たんぽぽ』
甲斐信枝 金の星社 1984 ISBN : 4-323-00282-3
たんぽぽが目をさまし、ねむり、おきあがり、とびだす・・・・。擬人法をつかった文学的な表現でたんぽぽの生態を表わす。わた毛が一面にとぶ場面は横に長く開く。 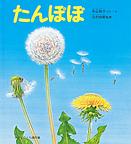
『たんぽぽ』
平山和子 文・絵 北村四郎監修 福音館書店 1992 ISBN : 4-8340-0470-8
たんぽぽが1日のうちに開いたり閉じたりするのは、時間の流れがわかるように絵本のめくりとあわせて左から右へ並べて示され、1つの花は60から240の小さな花の集まりであることを、その小さな花を縦横整列させて数を示す。科学的な解説。
根っこはずっとずっと下まで深く伸びている土の中の様子を縦に長く描いている。

『タンポポのわたげ』(花のたね・木の実のちえ1)
多田多恵子監修 ネイチャー・プロ編集室編著 偕成社 2008 ISBN : 978-4-03-414310-0
子どもたちが日頃目にしているタンポポのについて、日常目にしている風景から、ズームインした写真から花の集まりを表わしたり、綿毛の飛ぶところなど時には叙情的に、写真ならではの伝え方をしている。
参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト
キーワード1 タンポポ キーワード2 比較 キーワード3 授業計画・指導案等 たんぽぽ指導案2009 大塚.jtd 児童・生徒の作品 授業者 大塚健太郎 授業者コメント 情報リテラシーと物語を体感的に読むことの両方を、子どもたちの興味関心のある「たんぽぽ」という素材で狙えるところの価値のある実践になったと考える。甲斐氏の『たんぽぽ』は物語調で書かれており、子どもたちがたんぽぽの一つの花になりきるのに時間はかからなかった。楽しそうに一つの花弁となってたんぽぽの一生を演じ、たんぽぽを体で感じた読書であった。
その後、説明的文章調の平山氏の絵本に出会うと、より細かい数字など情報に探索者としての気持ちが芽生えてくる読書であった。そして、その二人の違いは、ものの見方・表現の違いを感じることになるのである。2冊を比べることで、子どもの好きな文体がはっきりし、また、全く印象のことなる絵本に出会ったことで、調べ物をするときには複数の本にあたることがたいせつであることも感じられた。 司書・司書教諭コメント 3冊の読み比べをした年は、写真は2年生の子どもたちには強い印象を与えすぎるようだった。絵が語ること、絵で表現されていることの読み取りが、しっかりできるようになってから、写真絵本と出会いたいと感じている。甲斐さんはカントウタンポポを描き、平山さんはセイヨウタンポポを描いている。本文には何も書いていないが、たまに知っていて教えてくれる子がいる。実は編集は同じ人。多田さんの写真絵本の巻末では、その違いを教えてくれている。
1つのテーマでいくつかの本を読み比べして欲しいとまとめる。1冊の本ではでていなくても、違う本には出てくる情報もあり、同じ情報でも表現の仕方が違っていることなどをつかんでくれる、よい題材だと思い、ぜひ授業でとりあげてもらいたいと紹介をした。
情報提供校 東京学芸大学附属小金井小学校 事例作成日 2009.4.29 事例作成者氏名 中山美由紀
記入者:中山
カウンタ
3863409 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0030 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | たんぽぽ の くらべよみ |
| 対象学年 | 低学年 |
| 活用・支援の種類 | 比べ読み |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | たんぽぽを描いた3冊の絵本があるが、授業で使えないか。(図書館からの提案) |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | たんぽぽの生態を表わすのに、全く違ったアプローチをしている絵本2冊を毎年小学校2年生の春に読み聞かせていた。その後、写真絵本も出版された。これらを題材に授業をつくってもらいたかった。 |
| 提示資料 | たんぽぽ絵本 |
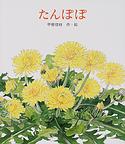 | 『たんぽぽ』 甲斐信枝 金の星社 1984 ISBN : 4-323-00282-3 たんぽぽが目をさまし、ねむり、おきあがり、とびだす・・・・。擬人法をつかった文学的な表現でたんぽぽの生態を表わす。わた毛が一面にとぶ場面は横に長く開く。 |
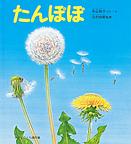 | 『たんぽぽ』 平山和子 文・絵 北村四郎監修 福音館書店 1992 ISBN : 4-8340-0470-8 たんぽぽが1日のうちに開いたり閉じたりするのは、時間の流れがわかるように絵本のめくりとあわせて左から右へ並べて示され、1つの花は60から240の小さな花の集まりであることを、その小さな花を縦横整列させて数を示す。科学的な解説。 根っこはずっとずっと下まで深く伸びている土の中の様子を縦に長く描いている。 |
 | 『タンポポのわたげ』(花のたね・木の実のちえ1) 多田多恵子監修 ネイチャー・プロ編集室編著 偕成社 2008 ISBN : 978-4-03-414310-0 子どもたちが日頃目にしているタンポポのについて、日常目にしている風景から、ズームインした写真から花の集まりを表わしたり、綿毛の飛ぶところなど時には叙情的に、写真ならではの伝え方をしている。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | タンポポ |
| キーワード2 | 比較 |
| キーワード3 | |
| 授業計画・指導案等 | たんぽぽ指導案2009 大塚.jtd |
| 児童・生徒の作品 | |
| 授業者 | 大塚健太郎 |
| 授業者コメント | 情報リテラシーと物語を体感的に読むことの両方を、子どもたちの興味関心のある「たんぽぽ」という素材で狙えるところの価値のある実践になったと考える。甲斐氏の『たんぽぽ』は物語調で書かれており、子どもたちがたんぽぽの一つの花になりきるのに時間はかからなかった。楽しそうに一つの花弁となってたんぽぽの一生を演じ、たんぽぽを体で感じた読書であった。 その後、説明的文章調の平山氏の絵本に出会うと、より細かい数字など情報に探索者としての気持ちが芽生えてくる読書であった。そして、その二人の違いは、ものの見方・表現の違いを感じることになるのである。2冊を比べることで、子どもの好きな文体がはっきりし、また、全く印象のことなる絵本に出会ったことで、調べ物をするときには複数の本にあたることがたいせつであることも感じられた。 |
| 司書・司書教諭コメント | 3冊の読み比べをした年は、写真は2年生の子どもたちには強い印象を与えすぎるようだった。絵が語ること、絵で表現されていることの読み取りが、しっかりできるようになってから、写真絵本と出会いたいと感じている。甲斐さんはカントウタンポポを描き、平山さんはセイヨウタンポポを描いている。本文には何も書いていないが、たまに知っていて教えてくれる子がいる。実は編集は同じ人。多田さんの写真絵本の巻末では、その違いを教えてくれている。 1つのテーマでいくつかの本を読み比べして欲しいとまとめる。1冊の本ではでていなくても、違う本には出てくる情報もあり、同じ情報でも表現の仕方が違っていることなどをつかんでくれる、よい題材だと思い、ぜひ授業でとりあげてもらいたいと紹介をした。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属小金井小学校 |
| 事例作成日 | 2009.4.29 |
| 事例作成者氏名 | 中山美由紀 |
記入者:中山

























