お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0403 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 「翻訳する」って、何をすること? 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 国際学級の児童が翻訳をする授業に使えそうな絵本があれば紹介してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 3~6年生の国際学級(海外帰国児童)が英語の絵本を翻訳して読み合う活動を考えている。児童が興味をもちそうで、日本語に翻訳する上で無理のない難易度の絵本や児童書があれば紹介してほしい。
提示資料 先生にお渡しした本のなかから、導入に使われたものと、児童に選ばれたもので、指導案の具体的な記述に登場する3冊を紹介する。 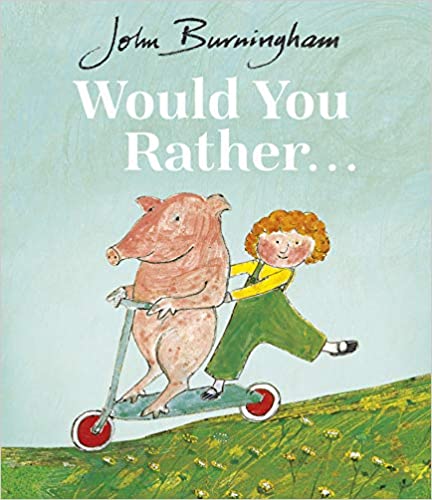
Burningham,John『Would you rather...』Red Fox,1999.
[ジョン・バーニンガムさく『ねえ、どれが いい?』評論社,2010]
1時間目に、授業の導入として使用(指導案参照)。思わず考えこんでしまう「究極の」選択肢から「どれがいい?」と、選ばされる形式の絵本。読み聞かせのおまけ等に取り入れると、子どもたちがとても喜び、盛り上がる。短い問いかけの文章が続くので、あまり身構えず翻訳に取り掛かれるのではないか、と紹介。 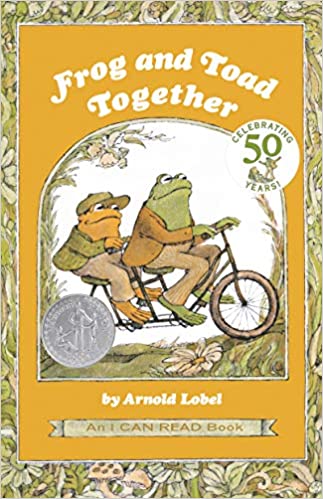
Lobel,Arnold『Frog and Toad Together』HarperCollins,1971、1972.
[アーノルド・ローベル作『ふたりは いっしょ』文化出版局,1972.]
2・4・5時間目の授業についての記述に「The Dream[がまくんの ゆめ]」が登場する(指導案参照)。2年生の国語の教科書にシリーズにあるお話が長年採用されており、本校の児童にとっても非常になじみがある。1冊のなかに、短いお話が5話入っている構成で、一つ一つの文章も短いが、お話全体としては良くまとまっている。
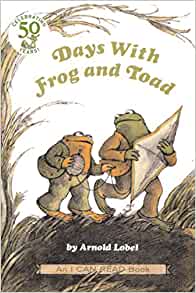
Lobel,Arnold『Days With Frog and Toad 』HarperCollins,1979.
[アーノルド・ローベル作『ふたりは きょうも』文化出版局,1980.]
3時間目の授業についての記述に「Tomorrow[あしたするよ]」が登場する(指導案参照)。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 「『翻訳する』」って何をすること?」ブックリスト.xlsx
キーワード1 翻訳 キーワード2 日本語 キーワード3 英語 授業計画・指導案等 日本語 「「翻訳する」って、何をすること」指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 太田風馬 授業者コメント 導入、プロの翻訳を読んだとき、「それは英語のイメージと違う!」「自分たちの翻訳の方がいい!」という声が聞かれた。全員、英語圏からの帰国児童だったこともあり、自分たちの英語に対する感性を発揮できることが、自信になったようである。翻訳では、必然的に「表現の仕方」に意識がいくため、日本語も上級になり「意味が通じれば良い」と考えていた子たちの日本語の学習として、発展性があった点は成果だと思われる。
反省点として、今回は司書の先生に英語の絵本を予め用意していただいたが、図書室で直接子どもたちに紹介していただいた方がよかったと感じている。特に6年生からは、低中学年向けの絵本ばかりだったこともあり、「この中から選ぶの?」といった声も聞かれ、途中本を変えた子もいた。図書室で授業を行い、実際に翻訳の様子も見ていただきながら、その場でアドバイスをいただける環境づくりをした方がより実態にあった指導につながったと考えている。
司書・司書教諭コメント 本校の蔵書のなかから、英語版と日本語版が両方あるものを選ばなければならなかったので、かなり限られた選択肢しかなかった。学年や言語能力に差がありそうだったので、学年を超えて人気のある、導入として利用できそうな絵本や、短いお話で全体を捉えるのにあまり時間のかからないものを中心にお渡ししたが、先生からのコメントにもあるように、授業を実際に見たり、児童本人から要望の聞き取りができなかったため、特に高学年の児童の実態を掴みきれなかった。本を渡しっぱなしにせず、こちらからもっと状況を尋ねたほうが良かった。「がまくんとかえるくん」のシリーズを、全て展示していたところだったので、『Frog and Toad are Friends[ふたりは ともだち]』は、貸出になっていて提供できなかった。この授業をきっかけに、「ハリー・ポッター」シリーズの英語版を、全巻蔵書に加えた。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 事例作成日 令和4年3月 / 授業実践日 令和3年1月~2月 事例作成者氏名 太田風馬、富澤佳恵子
記入者:富澤
カウンタ
3863468 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0403 校種 小学校 教科・領域等 国語 単元 「翻訳する」って、何をすること? 対象学年 中学年 活用・支援の種類 資料提供 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 国際学級の児童が翻訳をする授業に使えそうな絵本があれば紹介してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 3~6年生の国際学級(海外帰国児童)が英語の絵本を翻訳して読み合う活動を考えている。児童が興味をもちそうで、日本語に翻訳する上で無理のない難易度の絵本や児童書があれば紹介してほしい。
提示資料 先生にお渡しした本のなかから、導入に使われたものと、児童に選ばれたもので、指導案の具体的な記述に登場する3冊を紹介する。 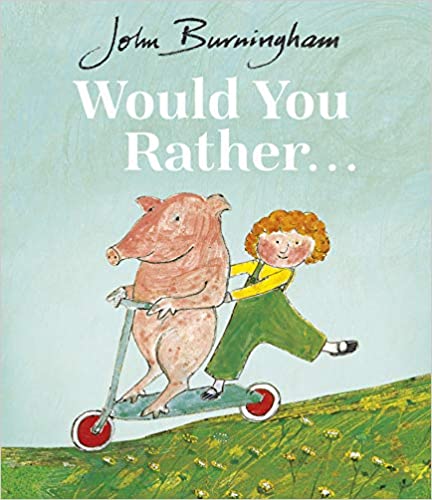
Burningham,John『Would you rather...』Red Fox,1999.
[ジョン・バーニンガムさく『ねえ、どれが いい?』評論社,2010]
1時間目に、授業の導入として使用(指導案参照)。思わず考えこんでしまう「究極の」選択肢から「どれがいい?」と、選ばされる形式の絵本。読み聞かせのおまけ等に取り入れると、子どもたちがとても喜び、盛り上がる。短い問いかけの文章が続くので、あまり身構えず翻訳に取り掛かれるのではないか、と紹介。 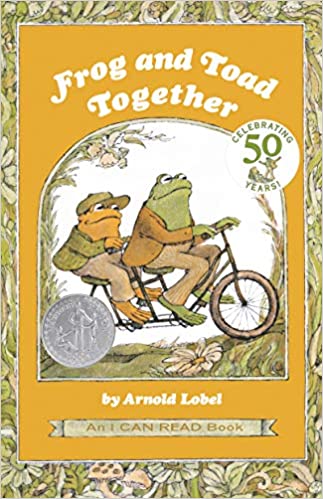
Lobel,Arnold『Frog and Toad Together』HarperCollins,1971、1972.
[アーノルド・ローベル作『ふたりは いっしょ』文化出版局,1972.]
2・4・5時間目の授業についての記述に「The Dream[がまくんの ゆめ]」が登場する(指導案参照)。2年生の国語の教科書にシリーズにあるお話が長年採用されており、本校の児童にとっても非常になじみがある。1冊のなかに、短いお話が5話入っている構成で、一つ一つの文章も短いが、お話全体としては良くまとまっている。
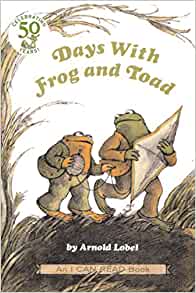
Lobel,Arnold『Days With Frog and Toad 』HarperCollins,1979.
[アーノルド・ローベル作『ふたりは きょうも』文化出版局,1980.]
3時間目の授業についての記述に「Tomorrow[あしたするよ]」が登場する(指導案参照)。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http:// ブックリスト 「『翻訳する』」って何をすること?」ブックリスト.xlsx
キーワード1 翻訳 キーワード2 日本語 キーワード3 英語 授業計画・指導案等 日本語 「「翻訳する」って、何をすること」指導案.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 太田風馬 授業者コメント 導入、プロの翻訳を読んだとき、「それは英語のイメージと違う!」「自分たちの翻訳の方がいい!」という声が聞かれた。全員、英語圏からの帰国児童だったこともあり、自分たちの英語に対する感性を発揮できることが、自信になったようである。翻訳では、必然的に「表現の仕方」に意識がいくため、日本語も上級になり「意味が通じれば良い」と考えていた子たちの日本語の学習として、発展性があった点は成果だと思われる。
反省点として、今回は司書の先生に英語の絵本を予め用意していただいたが、図書室で直接子どもたちに紹介していただいた方がよかったと感じている。特に6年生からは、低中学年向けの絵本ばかりだったこともあり、「この中から選ぶの?」といった声も聞かれ、途中本を変えた子もいた。図書室で授業を行い、実際に翻訳の様子も見ていただきながら、その場でアドバイスをいただける環境づくりをした方がより実態にあった指導につながったと考えている。
司書・司書教諭コメント 本校の蔵書のなかから、英語版と日本語版が両方あるものを選ばなければならなかったので、かなり限られた選択肢しかなかった。学年や言語能力に差がありそうだったので、学年を超えて人気のある、導入として利用できそうな絵本や、短いお話で全体を捉えるのにあまり時間のかからないものを中心にお渡ししたが、先生からのコメントにもあるように、授業を実際に見たり、児童本人から要望の聞き取りができなかったため、特に高学年の児童の実態を掴みきれなかった。本を渡しっぱなしにせず、こちらからもっと状況を尋ねたほうが良かった。「がまくんとかえるくん」のシリーズを、全て展示していたところだったので、『Frog and Toad are Friends[ふたりは ともだち]』は、貸出になっていて提供できなかった。この授業をきっかけに、「ハリー・ポッター」シリーズの英語版を、全巻蔵書に加えた。 情報提供校 東京学芸大学附属大泉小学校 事例作成日 事例作成日 令和4年3月 / 授業実践日 令和3年1月~2月 事例作成者氏名 太田風馬、富澤佳恵子
記入者:富澤
カウンタ
3863468 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0403 |
|---|---|
| 校種 | 小学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 「翻訳する」って、何をすること? |
| 対象学年 | 中学年 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 国際学級の児童が翻訳をする授業に使えそうな絵本があれば紹介してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 3~6年生の国際学級(海外帰国児童)が英語の絵本を翻訳して読み合う活動を考えている。児童が興味をもちそうで、日本語に翻訳する上で無理のない難易度の絵本や児童書があれば紹介してほしい。 |
| 提示資料 | 先生にお渡しした本のなかから、導入に使われたものと、児童に選ばれたもので、指導案の具体的な記述に登場する3冊を紹介する。 |
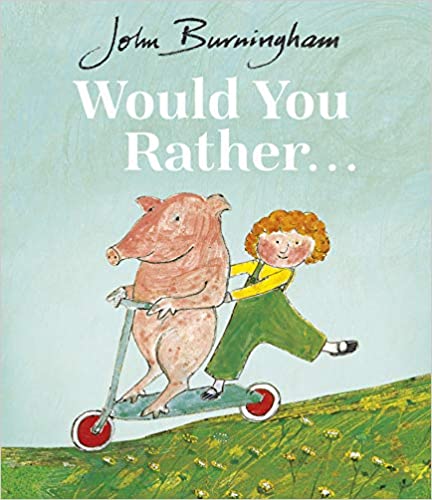 | Burningham,John『Would you rather...』Red Fox,1999. [ジョン・バーニンガムさく『ねえ、どれが いい?』評論社,2010] 1時間目に、授業の導入として使用(指導案参照)。思わず考えこんでしまう「究極の」選択肢から「どれがいい?」と、選ばされる形式の絵本。読み聞かせのおまけ等に取り入れると、子どもたちがとても喜び、盛り上がる。短い問いかけの文章が続くので、あまり身構えず翻訳に取り掛かれるのではないか、と紹介。 |
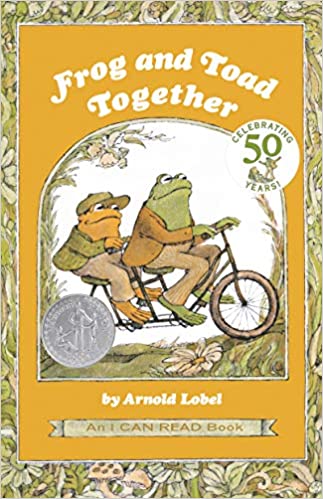 | Lobel,Arnold『Frog and Toad Together』HarperCollins,1971、1972. [アーノルド・ローベル作『ふたりは いっしょ』文化出版局,1972.] 2・4・5時間目の授業についての記述に「The Dream[がまくんの ゆめ]」が登場する(指導案参照)。2年生の国語の教科書にシリーズにあるお話が長年採用されており、本校の児童にとっても非常になじみがある。1冊のなかに、短いお話が5話入っている構成で、一つ一つの文章も短いが、お話全体としては良くまとまっている。 |
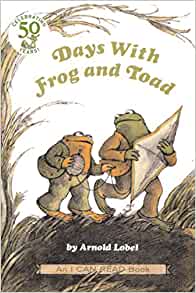 | Lobel,Arnold『Days With Frog and Toad 』HarperCollins,1979. [アーノルド・ローベル作『ふたりは きょうも』文化出版局,1980.] 3時間目の授業についての記述に「Tomorrow[あしたするよ]」が登場する(指導案参照)。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http:// |
| ブックリスト | 「『翻訳する』」って何をすること?」ブックリスト.xlsx |
| キーワード1 | 翻訳 |
| キーワード2 | 日本語 |
| キーワード3 | 英語 |
| 授業計画・指導案等 | 日本語 「「翻訳する」って、何をすること」指導案.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 太田風馬 |
| 授業者コメント | 導入、プロの翻訳を読んだとき、「それは英語のイメージと違う!」「自分たちの翻訳の方がいい!」という声が聞かれた。全員、英語圏からの帰国児童だったこともあり、自分たちの英語に対する感性を発揮できることが、自信になったようである。翻訳では、必然的に「表現の仕方」に意識がいくため、日本語も上級になり「意味が通じれば良い」と考えていた子たちの日本語の学習として、発展性があった点は成果だと思われる。 反省点として、今回は司書の先生に英語の絵本を予め用意していただいたが、図書室で直接子どもたちに紹介していただいた方がよかったと感じている。特に6年生からは、低中学年向けの絵本ばかりだったこともあり、「この中から選ぶの?」といった声も聞かれ、途中本を変えた子もいた。図書室で授業を行い、実際に翻訳の様子も見ていただきながら、その場でアドバイスをいただける環境づくりをした方がより実態にあった指導につながったと考えている。 |
| 司書・司書教諭コメント | 本校の蔵書のなかから、英語版と日本語版が両方あるものを選ばなければならなかったので、かなり限られた選択肢しかなかった。学年や言語能力に差がありそうだったので、学年を超えて人気のある、導入として利用できそうな絵本や、短いお話で全体を捉えるのにあまり時間のかからないものを中心にお渡ししたが、先生からのコメントにもあるように、授業を実際に見たり、児童本人から要望の聞き取りができなかったため、特に高学年の児童の実態を掴みきれなかった。本を渡しっぱなしにせず、こちらからもっと状況を尋ねたほうが良かった。「がまくんとかえるくん」のシリーズを、全て展示していたところだったので、『Frog and Toad are Friends[ふたりは ともだち]』は、貸出になっていて提供できなかった。この授業をきっかけに、「ハリー・ポッター」シリーズの英語版を、全巻蔵書に加えた。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属大泉小学校 |
| 事例作成日 | 事例作成日 令和4年3月 / 授業実践日 令和3年1月~2月 |
| 事例作成者氏名 | 太田風馬、富澤佳恵子 |
記入者:富澤

























