お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0415 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 よりよい住まい方を考える 対象学年 中2 活用・支援の種類 授業相談・資料準備・資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 中学生に、「よりよい住まい方」について考える授業を、学校図書館を活用して行いたいので、協力してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 家族・家庭生活、衣食住の生活、環境と領域を横断させながら、学校図書館やICTを活用した授業を計画した。よりよい家族関係や豊かな住生活に向けて自らの考えを形成し、自分自身の家族関係・住生活を見つめ、課題に気づき、その課題の解決に向けて、考えたことを自らの生活に生かすことをねらいとしている。 約200冊の書籍を入口とし、住まいや住まい方への視野を広げ、「マイファミリーの家づくり」に向け、模擬家族での家族会議を通して互いに意見を出し合ったり、書籍やインターネット上の情報、コンピュータ支援設計ソフトを活用したりする中で、主体的に住まいに参画する生徒の育成と情報活用能力の育成を目指した。
提示資料 
『おとなのための住まい力:知識 経験 リテラシー』住総研編 ドメス出版 2020 学校現場における住領域の学びの変遷やその背景について理解するのに役立つ1冊。また、よりよく住まうとはどういうことなのか、住まいに対する知識やリテラシーを身に着けるうえで、たくさんの示唆に富む1冊だった。 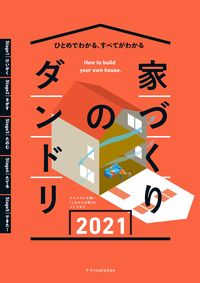
『家づくりのダンドリ 2021』エクスナレッジ 2021 模擬家族で、どのような家を作ればいいかを考えるにあたり、とても役立った資料。ここから必要な情報を抜き出し、生徒に配布することができた。 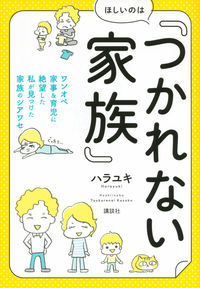
『つかれない家族』ハラユキ著 講談社 2020 ワンオペ育児につかれた筆者が、「つかれない家族」を取材し、その極意はなにかをマンガエッセイにした本。黄色い表紙とめだつタイトルに思わず手が出る本。生徒の関心も高かった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.jusoken.or.jp/ ブックリスト 住まい関連図書リスト(生徒配布用).xlsx
キーワード1 住まい キーワード2 家族 キーワード3 住環境 授業計画・指導案等 よりよい住まい方を考える指導案およびワークシート.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 関野かなえ 授業者コメント 「住まい」は、そこに住まう人の生活と深くかかわっている。生徒に「住まい」をより身近に感じてもらいたいと思い、さまざまな領域と横断させて関連付けて学びをデザインした。
住まいは食品の購入と異なり、気軽に住み替えや改変ができず、実際に生徒が意思決定に参画しにくいことから、大人任せになりかねない。また、住領域の学習の課題として、「複雑な機能を有する住空間を認識することが難しい」、「子どもが体験的に学べる教材等を準備しにくい」等が挙げられる。
生徒の自発的、主体的な学習活動を支援する「読書センター」、「学習・情報センター」としての機能を有する学校図書館を活用し、授業の中で、図書やインターネット上の情報に触れる時間や、グループでの話し合い活動等、計画的に組み込むことで、生徒に「家族」や「住まい」について 自分事として考えさせることができたこと。中でも、学校司書と相談の上、住総研の図書室や横浜市のレファレンスサービスを利用したり、東京学芸大学の教員のおすすめの資料等をうかがったりする中で、住まいや家族に関係する蔵書を収集し、授業の冒頭にて約200冊の書籍を用意したことで、生徒が住まいへの興味関心を高め、自分と他者との興味が異なることに気付くなど、広い視野をもって学習をスタートできたことが大きな収穫であった。 司書・司書教諭コメント 住まいに関する授業をするのは初めてだったため、蔵書が圧倒的に不足していた。そこで少しずつ買い足す一方で、公共図書館、専門図書館、大学教員、附属学校司書にもアドバイスをいただきながら、書籍を揃えて授業臨んだ。たくさんの住居に関する資料を手に取ることで、中学生の「住まい方」に関するイメージを広げることが出来たように思う。
具体的な情報を得る段階では、用意した本にこだわらず、教科書・教員から配布された資料、ネット情報、家族からの聞き取りなど、多様な情報源を想定した。最終的な振り返りでは、これからの住まい方を考えるうえで、情報を適切に取捨選択していくことの重要性に気付いた生徒が多かったのは、図書館という場で授業を行ったことも少なからず関係しているのではないだろうか。
また、新たな単元では、今回のように単元構想の段階から学校司書として関わることで、教員の意図を理解し、より適切な授業支援につなげられるように感じた。
添付したブックリストは、住まいの本をテーマ別に分類したもの。(右側の数字は、クラスでその本を選んだ人数。オレンジの色がついた本は人気があった本。) 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2023年3月6日 事例作成者氏名 学校司書 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0415 校種 中学校 教科・領域等 家庭 単元 よりよい住まい方を考える 対象学年 中2 活用・支援の種類 授業相談・資料準備・資料提供・レファレンス 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 中学生に、「よりよい住まい方」について考える授業を、学校図書館を活用して行いたいので、協力してほしい。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 家族・家庭生活、衣食住の生活、環境と領域を横断させながら、学校図書館やICTを活用した授業を計画した。よりよい家族関係や豊かな住生活に向けて自らの考えを形成し、自分自身の家族関係・住生活を見つめ、課題に気づき、その課題の解決に向けて、考えたことを自らの生活に生かすことをねらいとしている。 約200冊の書籍を入口とし、住まいや住まい方への視野を広げ、「マイファミリーの家づくり」に向け、模擬家族での家族会議を通して互いに意見を出し合ったり、書籍やインターネット上の情報、コンピュータ支援設計ソフトを活用したりする中で、主体的に住まいに参画する生徒の育成と情報活用能力の育成を目指した。
提示資料 
『おとなのための住まい力:知識 経験 リテラシー』住総研編 ドメス出版 2020 学校現場における住領域の学びの変遷やその背景について理解するのに役立つ1冊。また、よりよく住まうとはどういうことなのか、住まいに対する知識やリテラシーを身に着けるうえで、たくさんの示唆に富む1冊だった。 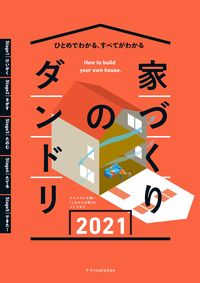
『家づくりのダンドリ 2021』エクスナレッジ 2021 模擬家族で、どのような家を作ればいいかを考えるにあたり、とても役立った資料。ここから必要な情報を抜き出し、生徒に配布することができた。 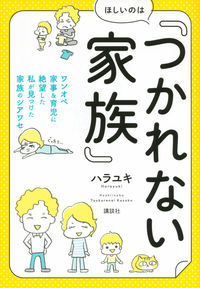
『つかれない家族』ハラユキ著 講談社 2020 ワンオペ育児につかれた筆者が、「つかれない家族」を取材し、その極意はなにかをマンガエッセイにした本。黄色い表紙とめだつタイトルに思わず手が出る本。生徒の関心も高かった。 参考資料(含HP) 参考資料リンク http://www.jusoken.or.jp/ ブックリスト 住まい関連図書リスト(生徒配布用).xlsx
キーワード1 住まい キーワード2 家族 キーワード3 住環境 授業計画・指導案等 よりよい住まい方を考える指導案およびワークシート.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 関野かなえ 授業者コメント 「住まい」は、そこに住まう人の生活と深くかかわっている。生徒に「住まい」をより身近に感じてもらいたいと思い、さまざまな領域と横断させて関連付けて学びをデザインした。
住まいは食品の購入と異なり、気軽に住み替えや改変ができず、実際に生徒が意思決定に参画しにくいことから、大人任せになりかねない。また、住領域の学習の課題として、「複雑な機能を有する住空間を認識することが難しい」、「子どもが体験的に学べる教材等を準備しにくい」等が挙げられる。
生徒の自発的、主体的な学習活動を支援する「読書センター」、「学習・情報センター」としての機能を有する学校図書館を活用し、授業の中で、図書やインターネット上の情報に触れる時間や、グループでの話し合い活動等、計画的に組み込むことで、生徒に「家族」や「住まい」について 自分事として考えさせることができたこと。中でも、学校司書と相談の上、住総研の図書室や横浜市のレファレンスサービスを利用したり、東京学芸大学の教員のおすすめの資料等をうかがったりする中で、住まいや家族に関係する蔵書を収集し、授業の冒頭にて約200冊の書籍を用意したことで、生徒が住まいへの興味関心を高め、自分と他者との興味が異なることに気付くなど、広い視野をもって学習をスタートできたことが大きな収穫であった。 司書・司書教諭コメント 住まいに関する授業をするのは初めてだったため、蔵書が圧倒的に不足していた。そこで少しずつ買い足す一方で、公共図書館、専門図書館、大学教員、附属学校司書にもアドバイスをいただきながら、書籍を揃えて授業臨んだ。たくさんの住居に関する資料を手に取ることで、中学生の「住まい方」に関するイメージを広げることが出来たように思う。
具体的な情報を得る段階では、用意した本にこだわらず、教科書・教員から配布された資料、ネット情報、家族からの聞き取りなど、多様な情報源を想定した。最終的な振り返りでは、これからの住まい方を考えるうえで、情報を適切に取捨選択していくことの重要性に気付いた生徒が多かったのは、図書館という場で授業を行ったことも少なからず関係しているのではないだろうか。
また、新たな単元では、今回のように単元構想の段階から学校司書として関わることで、教員の意図を理解し、より適切な授業支援につなげられるように感じた。
添付したブックリストは、住まいの本をテーマ別に分類したもの。(右側の数字は、クラスでその本を選んだ人数。オレンジの色がついた本は人気があった本。) 情報提供校 東京学芸大学附属世田谷中学校 事例作成日 2023年3月6日 事例作成者氏名 学校司書 村上恭子
記入者:村上
カウンタ
3863371 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0415 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 家庭 |
| 単元 | よりよい住まい方を考える |
| 対象学年 | 中2 |
| 活用・支援の種類 | 授業相談・資料準備・資料提供・レファレンス |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 中学生に、「よりよい住まい方」について考える授業を、学校図書館を活用して行いたいので、協力してほしい。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 家族・家庭生活、衣食住の生活、環境と領域を横断させながら、学校図書館やICTを活用した授業を計画した。よりよい家族関係や豊かな住生活に向けて自らの考えを形成し、自分自身の家族関係・住生活を見つめ、課題に気づき、その課題の解決に向けて、考えたことを自らの生活に生かすことをねらいとしている。 約200冊の書籍を入口とし、住まいや住まい方への視野を広げ、「マイファミリーの家づくり」に向け、模擬家族での家族会議を通して互いに意見を出し合ったり、書籍やインターネット上の情報、コンピュータ支援設計ソフトを活用したりする中で、主体的に住まいに参画する生徒の育成と情報活用能力の育成を目指した。 |
| 提示資料 | |
 | 『おとなのための住まい力:知識 経験 リテラシー』住総研編 ドメス出版 2020 学校現場における住領域の学びの変遷やその背景について理解するのに役立つ1冊。また、よりよく住まうとはどういうことなのか、住まいに対する知識やリテラシーを身に着けるうえで、たくさんの示唆に富む1冊だった。 |
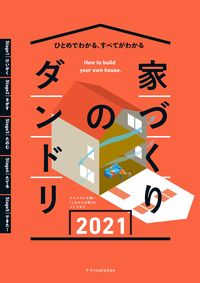 | 『家づくりのダンドリ 2021』エクスナレッジ 2021 模擬家族で、どのような家を作ればいいかを考えるにあたり、とても役立った資料。ここから必要な情報を抜き出し、生徒に配布することができた。 |
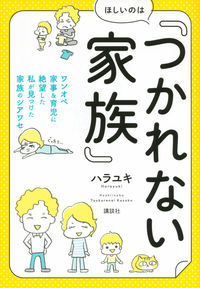 | 『つかれない家族』ハラユキ著 講談社 2020 ワンオペ育児につかれた筆者が、「つかれない家族」を取材し、その極意はなにかをマンガエッセイにした本。黄色い表紙とめだつタイトルに思わず手が出る本。生徒の関心も高かった。 |
| 参考資料(含HP) | |
| 参考資料リンク | http://www.jusoken.or.jp/ |
| ブックリスト | 住まい関連図書リスト(生徒配布用).xlsx |
| キーワード1 | 住まい |
| キーワード2 | 家族 |
| キーワード3 | 住環境 |
| 授業計画・指導案等 | よりよい住まい方を考える指導案およびワークシート.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 関野かなえ |
| 授業者コメント | 「住まい」は、そこに住まう人の生活と深くかかわっている。生徒に「住まい」をより身近に感じてもらいたいと思い、さまざまな領域と横断させて関連付けて学びをデザインした。 住まいは食品の購入と異なり、気軽に住み替えや改変ができず、実際に生徒が意思決定に参画しにくいことから、大人任せになりかねない。また、住領域の学習の課題として、「複雑な機能を有する住空間を認識することが難しい」、「子どもが体験的に学べる教材等を準備しにくい」等が挙げられる。 生徒の自発的、主体的な学習活動を支援する「読書センター」、「学習・情報センター」としての機能を有する学校図書館を活用し、授業の中で、図書やインターネット上の情報に触れる時間や、グループでの話し合い活動等、計画的に組み込むことで、生徒に「家族」や「住まい」について 自分事として考えさせることができたこと。中でも、学校司書と相談の上、住総研の図書室や横浜市のレファレンスサービスを利用したり、東京学芸大学の教員のおすすめの資料等をうかがったりする中で、住まいや家族に関係する蔵書を収集し、授業の冒頭にて約200冊の書籍を用意したことで、生徒が住まいへの興味関心を高め、自分と他者との興味が異なることに気付くなど、広い視野をもって学習をスタートできたことが大きな収穫であった。 |
| 司書・司書教諭コメント | 住まいに関する授業をするのは初めてだったため、蔵書が圧倒的に不足していた。そこで少しずつ買い足す一方で、公共図書館、専門図書館、大学教員、附属学校司書にもアドバイスをいただきながら、書籍を揃えて授業臨んだ。たくさんの住居に関する資料を手に取ることで、中学生の「住まい方」に関するイメージを広げることが出来たように思う。 具体的な情報を得る段階では、用意した本にこだわらず、教科書・教員から配布された資料、ネット情報、家族からの聞き取りなど、多様な情報源を想定した。最終的な振り返りでは、これからの住まい方を考えるうえで、情報を適切に取捨選択していくことの重要性に気付いた生徒が多かったのは、図書館という場で授業を行ったことも少なからず関係しているのではないだろうか。 また、新たな単元では、今回のように単元構想の段階から学校司書として関わることで、教員の意図を理解し、より適切な授業支援につなげられるように感じた。 添付したブックリストは、住まいの本をテーマ別に分類したもの。(右側の数字は、クラスでその本を選んだ人数。オレンジの色がついた本は人気があった本。) |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
| 事例作成日 | 2023年3月6日 |
| 事例作成者氏名 | 学校司書 村上恭子 |
記入者:村上

























