お知らせ
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
新着案内
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0429 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 古典発展学習 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・パスファインダー作成・著作権指導 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 書籍とデジタルコンテンツを活用して古典作品を紹介し合うので、原文が掲載された図書資料やデジタルアーカイブを図書館から案内する。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 様々な古典作品に触れ、深く知り相手意識を持って紹介することで、この先の上級学校での授業に繋げたい。図書館は関連図書資料を揃えるとともに、参考となるウェブサイトをまとめてパスファインダーを作成。さらにデジタル資料の検索や活用に関して、著作権の観点から指導をおこなった。大学図書館とも連携し、大学所蔵のデジタルコンテンツを検索するためのタグ付けをしてもらった。
作品の発表にはパワーポイントを使用したが、必ず原典にあたることと、デジタルコンテンツを活用することを必須条件とした。附属の大学図書館や他機関のデジタルアーカイブを活用する際に必要な著作権についても説明した。授業のねらいについては指導案に詳しく記述している。
提示資料 ●原文や口語訳を含む基本的な図書資料
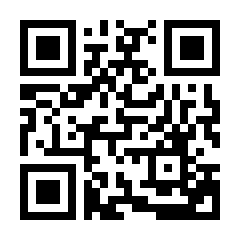
▲国立国会図書館『ジャパンサーチ』https://jpsearch.go.jp/
日本の様々な分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できる
プラットフォーム。
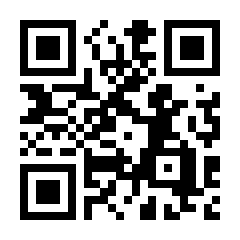
▲(有)ウィリング『アンドラデジタルアーカイブリンク』https://andla.jp/da/
大学や公共図書館、官公庁などが運営・公開しているデジタルアーカイブのウェブページを検索できる。 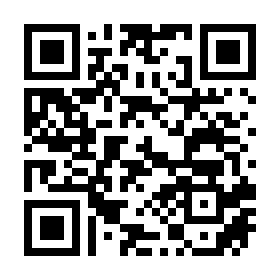
▲東京学芸大学『東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ』https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/
東京学芸大学の教育・研究活動成果としてのデジタル資源を収集・公開。 参考資料(含HP) ●古典関連のデジタルアーカイブサイトをまとめたパスファインダー 参考資料リンク https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=11643 ブックリスト
キーワード1 古典 キーワード2 プレゼンテーション キーワード3 デジタルアーカイブ 授業計画・指導案等 古典指導案・授業の様子.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 菊地圭子(国語科) 授業者コメント 生徒たちには3年間を通して、古典を含めて、暗唱マラソンに取り組み、古典を暗唱することを通して、古典に親しむようにした。司書教諭、及び大学図書館には、多くの古典作品を紹介する活動に合わせてデジタルコンテンツを整えていただいたり、パスファインダーを作成していただいたりした。相手意識をもって作品を発表するように指導したが、パワーポイントの作成に夢中になるあまり、出典などの著作権の問題をすべてクリアすることは難しかった。自分たちが作品を紹介することを念頭に置いていたので、問題意識をもって取り組んだり、作品に興味を持ってもらえるような工夫を行ったりして、創意工夫する姿が見られた。ここで互いに学び合った古典作品が、上級学校での学習への導入となり、さらには生涯学習での古典作品との出会いのきっかけになる機会を持つ学習過程として単元を構成した。 司書・司書教諭コメント 公開研究会での発表もあったので、メディアリテラシーについて学習前に時間をかけて説明したつもりだが、出来上がった作品を見ると無意識の著作権侵害が非常に多く、改めて日頃から丁寧に著作権について説明していくことの大切さを痛感した。一方でデジタルコンテンツを活用することで、言葉だけでは想像しづらい古典の世界観がよく伝わり、生徒の興味関心を大いに惹きつけたように思う。授業で扱わない多くの作品を味わえた経験を、この先の上級学校での学習に繋げてほしい。 情報提供校 東京学芸大学附属竹早中学校 事例作成日 2023年3月23日(2023年10~11月実践) 事例作成者氏名 中村誠子(学校司書)
記入者:中村(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
「文科省事業報告会 みんなで使おう!学校図書館 Vol.17」の視聴をご希望の方は、こちらから申し込みください。自動返信で視聴URLが送られます。迷惑メールに紛れることもあるので、お気をつけください。視聴後は、参加アンケートへのご協力もよろしくお願いいたします。当日いただいたご質問への回答、公開できる資料は、司書のまなびページに掲載しました。
2025年3月21日(土) 13時半より、東京学芸大学附属世田谷中学校図書館に於いて、現職研修セミナー「明日から活用できる学校図書館Vol.5」を開催します。
2025年3月25日(水)13時半より、「10代にとっての『海外文学の魅力』を考える」と題して、オンライン研修を企画しました。特別ゲストは、『ソリアを森へ』の翻訳者杉田七重氏と、ハコブネ×ブックス主宰きむらともお氏です。詳細・申し込みはトピックスから。
2025年9月6日(土) のオンライン講座 「小学校の読書教育の現状と課題」 が I Dig Edu から視聴できます。司書のまなびもご覧ください。
「ここは図書館だよ。なんでおしゃべりしないの?」(2024年8月21日のオンラインイベント 筑波大学教授 吉田右子氏と前みんなの森メディアコスモス総合プロデューサー 吉成信夫氏との対談です。必見!)
過去の文科省事業報告会は、司書の学び から視聴申し込みができます。
「10代がえらぶ海外文学大賞」結果が発表されました!サイトをクリックしてくださいね!
「使い方動画」をリニューアルしました。時間も短くなりました(約5分)。
「今月の学校図書館」は大分県九重町立ここのえ緑陽中学校です。
授業実践事例:教科別目次
授業に役立つ学校図書館活用データベース:事例検索
コンテンツ詳細
管理番号 A0429 校種 中学校 教科・領域等 国語 単元 古典発展学習 対象学年 中3 活用・支援の種類 資料提供・パスファインダー作成・著作権指導 図書館とのかかわり
(レファレンスを含む) 書籍とデジタルコンテンツを活用して古典作品を紹介し合うので、原文が掲載された図書資料やデジタルアーカイブを図書館から案内する。 授業のねらい・協働に
あたっての確認事項 様々な古典作品に触れ、深く知り相手意識を持って紹介することで、この先の上級学校での授業に繋げたい。図書館は関連図書資料を揃えるとともに、参考となるウェブサイトをまとめてパスファインダーを作成。さらにデジタル資料の検索や活用に関して、著作権の観点から指導をおこなった。大学図書館とも連携し、大学所蔵のデジタルコンテンツを検索するためのタグ付けをしてもらった。
作品の発表にはパワーポイントを使用したが、必ず原典にあたることと、デジタルコンテンツを活用することを必須条件とした。附属の大学図書館や他機関のデジタルアーカイブを活用する際に必要な著作権についても説明した。授業のねらいについては指導案に詳しく記述している。
提示資料 ●原文や口語訳を含む基本的な図書資料
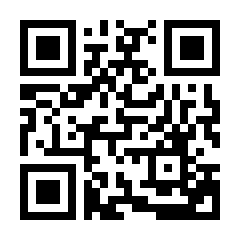
▲国立国会図書館『ジャパンサーチ』https://jpsearch.go.jp/
日本の様々な分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できる
プラットフォーム。
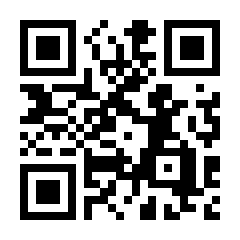
▲(有)ウィリング『アンドラデジタルアーカイブリンク』https://andla.jp/da/
大学や公共図書館、官公庁などが運営・公開しているデジタルアーカイブのウェブページを検索できる。 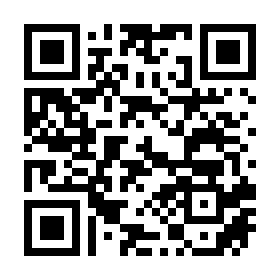
▲東京学芸大学『東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ』https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/
東京学芸大学の教育・研究活動成果としてのデジタル資源を収集・公開。 参考資料(含HP) ●古典関連のデジタルアーカイブサイトをまとめたパスファインダー 参考資料リンク https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=11643 ブックリスト
キーワード1 古典 キーワード2 プレゼンテーション キーワード3 デジタルアーカイブ 授業計画・指導案等 古典指導案・授業の様子.pdf 児童・生徒の作品 http:// 授業者 菊地圭子(国語科) 授業者コメント 生徒たちには3年間を通して、古典を含めて、暗唱マラソンに取り組み、古典を暗唱することを通して、古典に親しむようにした。司書教諭、及び大学図書館には、多くの古典作品を紹介する活動に合わせてデジタルコンテンツを整えていただいたり、パスファインダーを作成していただいたりした。相手意識をもって作品を発表するように指導したが、パワーポイントの作成に夢中になるあまり、出典などの著作権の問題をすべてクリアすることは難しかった。自分たちが作品を紹介することを念頭に置いていたので、問題意識をもって取り組んだり、作品に興味を持ってもらえるような工夫を行ったりして、創意工夫する姿が見られた。ここで互いに学び合った古典作品が、上級学校での学習への導入となり、さらには生涯学習での古典作品との出会いのきっかけになる機会を持つ学習過程として単元を構成した。 司書・司書教諭コメント 公開研究会での発表もあったので、メディアリテラシーについて学習前に時間をかけて説明したつもりだが、出来上がった作品を見ると無意識の著作権侵害が非常に多く、改めて日頃から丁寧に著作権について説明していくことの大切さを痛感した。一方でデジタルコンテンツを活用することで、言葉だけでは想像しづらい古典の世界観がよく伝わり、生徒の興味関心を大いに惹きつけたように思う。授業で扱わない多くの作品を味わえた経験を、この先の上級学校での学習に繋げてほしい。 情報提供校 東京学芸大学附属竹早中学校 事例作成日 2023年3月23日(2023年10~11月実践) 事例作成者氏名 中村誠子(学校司書)
記入者:中村(主担)
カウンタ
3863490 : 2010年9月14日より
コンテンツ詳細
| 管理番号 | A0429 |
|---|---|
| 校種 | 中学校 |
| 教科・領域等 | 国語 |
| 単元 | 古典発展学習 |
| 対象学年 | 中3 |
| 活用・支援の種類 | 資料提供・パスファインダー作成・著作権指導 |
| 図書館とのかかわり (レファレンスを含む) | 書籍とデジタルコンテンツを活用して古典作品を紹介し合うので、原文が掲載された図書資料やデジタルアーカイブを図書館から案内する。 |
| 授業のねらい・協働に あたっての確認事項 | 様々な古典作品に触れ、深く知り相手意識を持って紹介することで、この先の上級学校での授業に繋げたい。図書館は関連図書資料を揃えるとともに、参考となるウェブサイトをまとめてパスファインダーを作成。さらにデジタル資料の検索や活用に関して、著作権の観点から指導をおこなった。大学図書館とも連携し、大学所蔵のデジタルコンテンツを検索するためのタグ付けをしてもらった。 作品の発表にはパワーポイントを使用したが、必ず原典にあたることと、デジタルコンテンツを活用することを必須条件とした。附属の大学図書館や他機関のデジタルアーカイブを活用する際に必要な著作権についても説明した。授業のねらいについては指導案に詳しく記述している。 |
| 提示資料 | ●原文や口語訳を含む基本的な図書資料 |
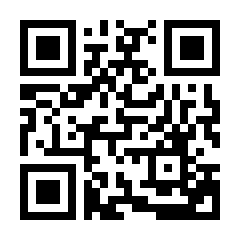 | ▲国立国会図書館『ジャパンサーチ』https://jpsearch.go.jp/ 日本の様々な分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できる プラットフォーム。 |
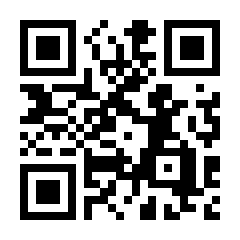 | ▲(有)ウィリング『アンドラデジタルアーカイブリンク』https://andla.jp/da/ 大学や公共図書館、官公庁などが運営・公開しているデジタルアーカイブのウェブページを検索できる。 |
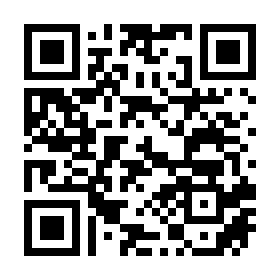 | ▲東京学芸大学『東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ』https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/ 東京学芸大学の教育・研究活動成果としてのデジタル資源を収集・公開。 |
| 参考資料(含HP) | ●古典関連のデジタルアーカイブサイトをまとめたパスファインダー |
| 参考資料リンク | https://www2.u-gakugei.ac.jp/~schoolib/htdocs/?action=common_download_main&upload_id=11643 |
| ブックリスト | |
| キーワード1 | 古典 |
| キーワード2 | プレゼンテーション |
| キーワード3 | デジタルアーカイブ |
| 授業計画・指導案等 | 古典指導案・授業の様子.pdf |
| 児童・生徒の作品 | http:// |
| 授業者 | 菊地圭子(国語科) |
| 授業者コメント | 生徒たちには3年間を通して、古典を含めて、暗唱マラソンに取り組み、古典を暗唱することを通して、古典に親しむようにした。司書教諭、及び大学図書館には、多くの古典作品を紹介する活動に合わせてデジタルコンテンツを整えていただいたり、パスファインダーを作成していただいたりした。相手意識をもって作品を発表するように指導したが、パワーポイントの作成に夢中になるあまり、出典などの著作権の問題をすべてクリアすることは難しかった。自分たちが作品を紹介することを念頭に置いていたので、問題意識をもって取り組んだり、作品に興味を持ってもらえるような工夫を行ったりして、創意工夫する姿が見られた。ここで互いに学び合った古典作品が、上級学校での学習への導入となり、さらには生涯学習での古典作品との出会いのきっかけになる機会を持つ学習過程として単元を構成した。 |
| 司書・司書教諭コメント | 公開研究会での発表もあったので、メディアリテラシーについて学習前に時間をかけて説明したつもりだが、出来上がった作品を見ると無意識の著作権侵害が非常に多く、改めて日頃から丁寧に著作権について説明していくことの大切さを痛感した。一方でデジタルコンテンツを活用することで、言葉だけでは想像しづらい古典の世界観がよく伝わり、生徒の興味関心を大いに惹きつけたように思う。授業で扱わない多くの作品を味わえた経験を、この先の上級学校での学習に繋げてほしい。 |
| 情報提供校 | 東京学芸大学附属竹早中学校 |
| 事例作成日 | 2023年3月23日(2023年10~11月実践) |
| 事例作成者氏名 | 中村誠子(学校司書) |
記入者:中村(主担)

























